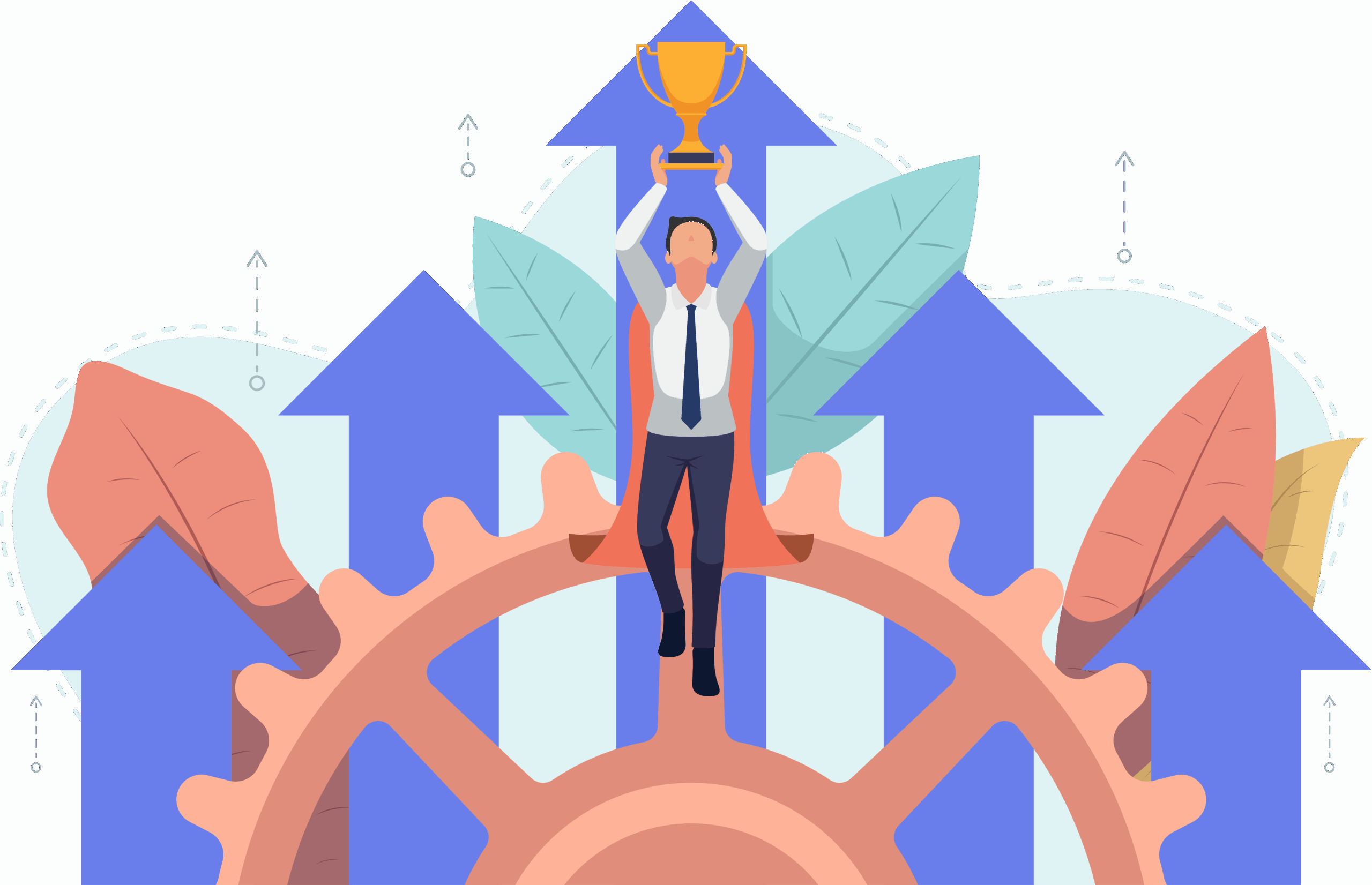なぜ、日本では“失敗した経営者”に冷たいのか?
挑戦をためらうあなたへ。これは、もう一度立ち上がるための問いです。
こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
あなたは、“これから挑戦したい人”ですか? それとも、“再び立ち上がろうとしている人”ですか?
先日、起業を目指すある20代の男性から、こんな相談を受けました。
彼は、ビジネスプランもしっかりしていて、資金の目処も立っていた。だけど、顔には曇りがありました。
「もし、失敗したら……その時、自分のことを責めるのは、社会の空気じゃないかって思ってしまって」
そう言った彼の目は、不安ではなく、“諦め”のようなものを宿していました。
私は一瞬、返す言葉に詰まりました。彼が恐れていたのは、借金でも、倒産でも、人生設計のやり直しでもなかったんです。
——失敗したあと、「ああ、やっぱりダメだったね」と周囲から“そっと距離を取られる”あの感覚。
「支援を受けたくても、もう信用がないから…」と自ら社会との接続を断たねばならないような、あの独特な孤独。
たしかに、日本には「失敗を祝福する文化」は、まだ根づいていないのかもしれません。
「どうせうまくいかない」「最初からやらない方が傷つかない」——そんな無言の圧力が、起業家の最初の一歩を封じ込めているとしたら。
私は、そこに“構造としての無関心”が存在しているように思えてなりません。
今回は、あえてこのテーマに踏み込んでみたいと思います。
「なぜ、日本では“失敗した経営者”に冷たいのか?」
ひょっとしたらこの“空気”は、誰かのせいではなく、私たち一人ひとりの沈黙から生まれているのかもしれません。
それは、個人の責任ではなく、私たち社会全体が向き合うべき課題ではないでしょうか。
そして——あなたなら、彼の悲痛な問いにどう応えますか?
なぜ、日本社会は「失敗」を罪のように扱うのか?
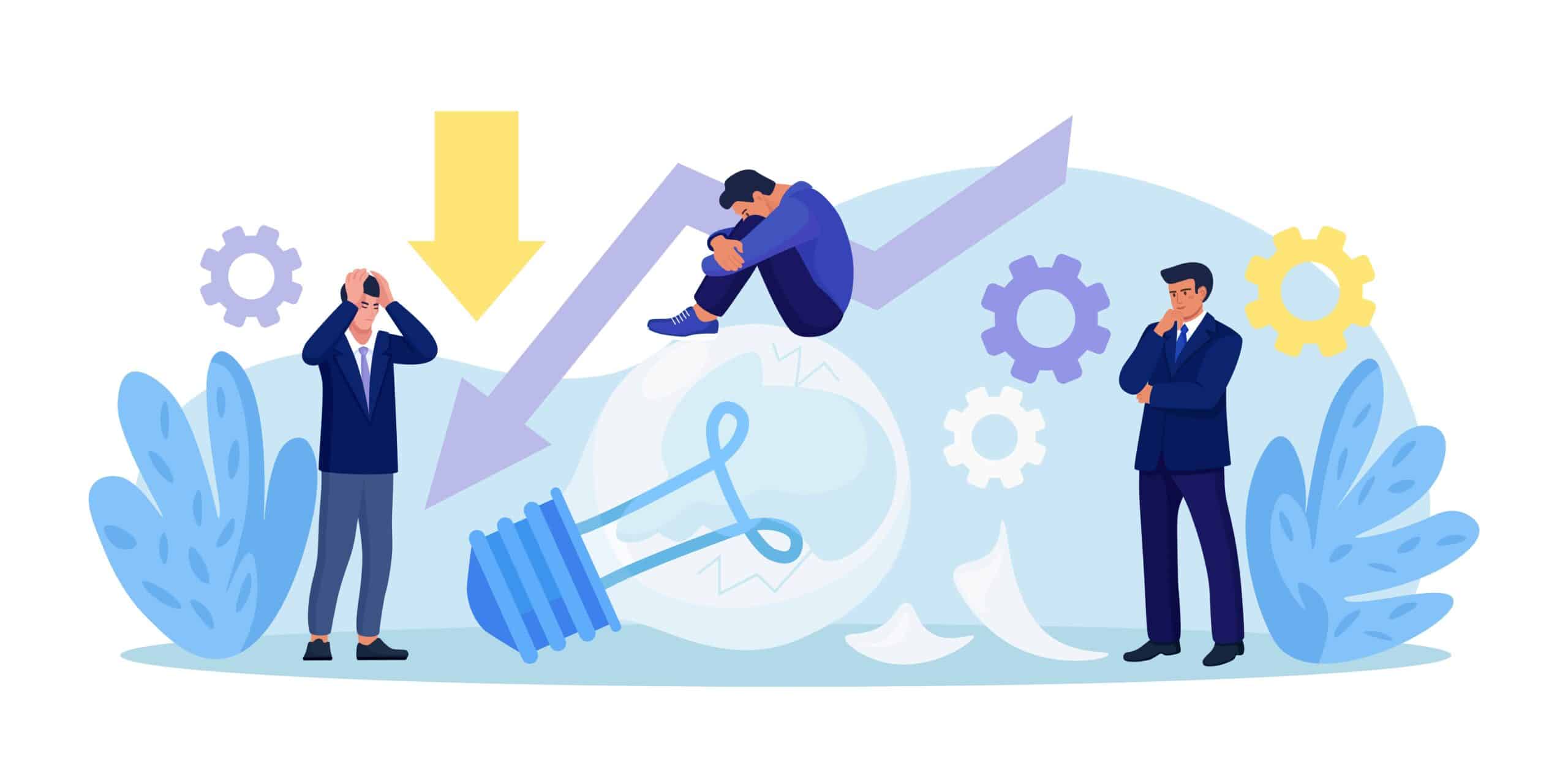
「一度でも失敗したら終わり」——そう口にする人は、経営者に限りません。就職活動をする学生、転職を考える社会人、子育てに悩む親…
日本ではあらゆる場面で、「失敗」に対する過剰な恐れと、“敗者”としてのレッテル貼りが繰り返されています。
この背景には、単なる個人の価値観ではなく、歴史と構造があります。
江戸時代以降に根づいた「連帯責任」文化では、個人のミスが“家族”や“組織”全体の恥とされてきました。
この感覚は、現代の学校や企業文化にも静かに引き継がれています。
たとえば学校では、間違えることは恥とされ、減点方式で評価されることが一般的です。
間違えない=優秀、という前提のもとに育った子どもたちは、やがて大人になっても「正解を出すこと」ばかりに意識が向くようになります。かくいう私も、学生時代“間違えたら恥ずかしい”と手を挙げられなかったひとりでした。
特に中学時代、数学のテストで1問だけ間違えた際に、先生から「あれだけ言ったのに…」と言われたことで、以来授業中に発言することが怖くなった経験があります。
会社でも似たような構造が見られます。
プロジェクトの失敗は「誰の責任か?」を追求する方向に流れやすく、失敗の原因を探るよりも「二度と失敗しないこと」が優先される。
このような空気の中で育った人が、経営という“挑戦”に立ったとき、果たして“失敗してもいい”と本気で思えるでしょうか。
海外に目を向けると、その対比は鮮明です。
アメリカでは「失敗歴=バッジ(勲章)」という言葉があるほど、過去の挑戦が評価されます。
起業経験者に対して「一度会社を潰した人ほど、次に成功する確率が高い」というデータもあるほどです。
Harvard Business Reviewによれば、起業家の成功確率は初回22%、2回目で34%、3回目以降で50%近くにまで上がるとされています。
つまり、“挑戦したこと”そのものが、資産としてカウントされているということなのです。
一方、日本ではどうでしょうか?
倒産すれば銀行の信用を失い、再起業に向けた融資も下りにくくなる。
「一度失敗した経営者」という経歴は、あらゆる場面で“見えない足かせ”として付きまとう。
しかもこの構造には、「失敗=他人に迷惑をかけた」という“空気の罪”が潜んでいます。
誰かが倒れたとき、それを支えるよりも、距離を置くことが“常識的な対応”になってしまう社会。
しかし、本来“失敗”とは、個人の不注意や怠慢ではなく、新しい未来に本気で挑んだ結果として起こる不可避な一時的挫折ではないでしょうか?
その余白が残されない社会こそが、本当の損失を抱えるのだと、私は感じています。
“失敗”と“詐欺”を混同する日本人
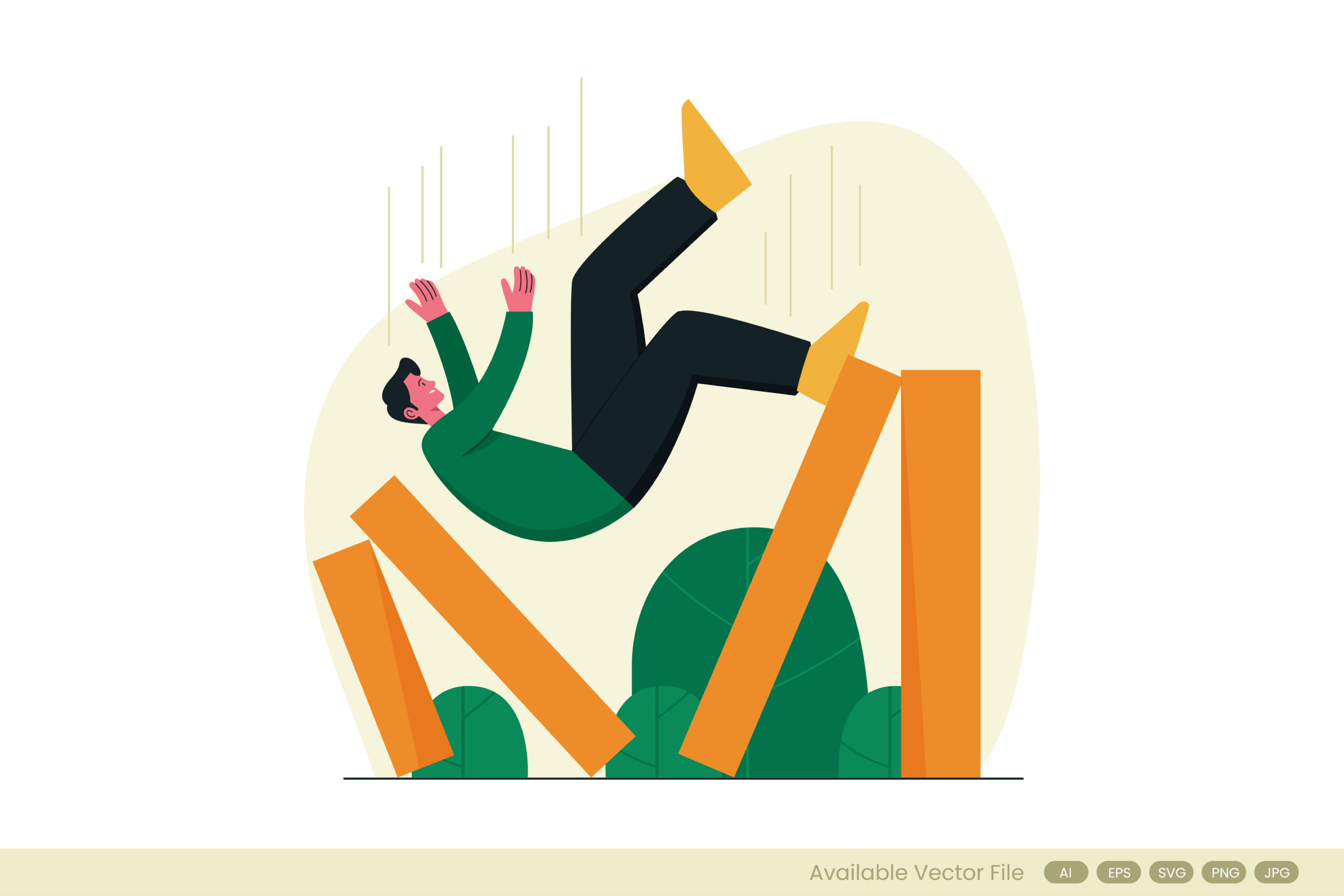
近年、経営破綻や倒産が報じられるたびに、SNSのタイムラインには決まってこんな言葉が並びます。
「やっぱり怪しいと思ってた」「あれ、結局詐欺だったんでしょ?」
——何の根拠もないまま、“倒れた人”を「加害者」として裁く空気が漂い始めます。
これは、極めて危険な現象です。
もちろん、意図的に資金を詐取した悪質なケースが存在するのは事実です。
クラウドファンディング詐欺、無許可投資事業、融資持ち逃げ……ビジネスの皮を被った詐欺行為はたしかにある。
しかし、それと“真摯に挑戦した末に倒産した経営者”を、同じ土俵で語ることに、私は強い違和感を覚えます。
現実には、誠実な経営者であっても、資金繰りの悪化や外部環境の変化、取引先の不渡りなど、不可抗力に近い形で破綻に至ることは珍しくありません。
なのに、「お金を集めて失敗した」=「人を騙した」という短絡的な解釈がなされ、“詐欺と失敗の境界線”が溶けてしまっている。
これは、日本社会における「結果至上主義」と「感情ベースの断罪」が結びついた、いわば構造的混同です。
特にSNSという“即断即決の言論空間”では、文脈も事情も無視され、「倒産=悪」と単純化されがちです。
一度バズれば、謝罪しても訂正しても、汚名だけがデジタルの海に永遠に残り続ける。
失敗した経営者は、社会的に抹消され、信用が“再発行不能”になる。
実際、中小企業庁の調査(2022年)によると、再挑戦経験者のうち52.4%が「再挑戦で最も苦労したのは“社会的評価の回復”」と答えています。
そして最も恐ろしいのは、そうした光景を見た若い挑戦者たちが、無意識に「挑まないこと」を選ぶという点です。
——「こんなリスクを背負うくらいなら、起業なんてやめておこう」
結果として、日本社会全体の「挑戦総量」が下がり、可能性の芽が摘まれていく。
この構造に対して、私たちはもっと敏感でなければなりません。
失敗者を詐欺師と同列に扱うことは、未来の挑戦者を“静かに殺す”行為なのです。
必要なのは、線引きです。
悪質な詐欺行為は厳しく罰すべき。
でも、誠実に挑んだ結果の失敗には、問いの痕跡と再起の余地を残しておかなければならない。
社会に必要なのは、処刑人ではなく、“失敗の物語を聴く耳”なのだと私は思います。
「失敗」とは問いを残したという証

「失敗とは、問いを残す行為である」——私は、そう捉えています。
多くの人が「失敗=無意味な結末」と考えます。
でも、本当にそうでしょうか?
倒産した事業、採用の失敗、計画倒れのプロジェクト……
どれもその裏には、「なぜうまくいかなかったのか?」「どうすればよかったのか?」という問いが残ります。
その問いこそが、次の誰かにとっての“道しるべ”になるのです。
完璧に成功した人の話よりも、一度倒れて、それでも問いを手放さなかった人の言葉の方が、私たちの胸に深く届くことはないでしょうか?
なぜなら、問いは“これからの道を自分で探す”ための灯になるからです。
たとえば、会社を潰した経験者が、その理由を真正面から言語化しようとする時。
その言葉は、“こうすれば成功する”という正解ではなく、「ここで私はつまずいた」というリアルな地図になります。
それを受け取った誰かが、同じ場所で踏みとどまるかもしれない。
あるいは、その痕跡を見て、自分の中に別の問いを育てるかもしれない。
「なんで潰れたのか、いまだによく分からない」
そう語った元経営者の言葉に、私は深く耳を傾けました。
その人は、数字にも人にも誠実でした。それでも破綻した。
最後に彼が語ったのは——
「人間関係を“想定変数”に入れてなかったんだ」
このひと言が、若い起業家の思考を変えました。
その後彼は、“人との設計”を最優先にしたビジネスモデルで再挑戦し、初年度黒字を達成します。
問いは、未来のどこかで必ず“応答”される。
それが、失敗の持つ“贈与の力”なのです。
私は思います。
すでに正解を持っている人よりも、自分の問いを差し出せる人のほうが、世界に対して優しいと。
だからこそ、もしあなたが失敗したとしても。
問いを語る勇気さえあれば、それは誰かの希望になりうる。
そしてその誰かが、あなたの問いに応えるようにして歩き出した時——
それはもう、「失敗」ではなく、「物語の継承」になっているのです。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 会社が倒産したら、もう起業はできませんか?
いいえ、可能です。過去に倒産経験がある経営者が再起業して成功した事例も多数あります。信用回復には時間がかかるかもしれませんが、事業計画や人との信頼構築で十分挽回できます。
- Q2. 失敗した時、どこに相談すればいいですか?
公的支援では「日本政策金融公庫」や「中小企業再生支援協議会」、地方自治体の起業相談窓口などがあります。民間では信用保証協会や専門家ネットワークも活用可能です。
- Q3. 再挑戦したいけれど、家族や周囲の反応が怖いです。
まずは“問い”を共有するところから始めてみましょう。「なぜやりたいのか」を言葉にできれば、必ず理解者が現れます。孤独は“語れない”ことで強まります。
- Q4. どんな支援制度がありますか?
記事下部の外部リンクを参考にしてください(中小企業庁・起業支援・再挑戦プログラムなど)
これらの制度は、月末や四半期で受付枠・予算上限が変わることもあるため、少しでも気になった時点で早めに相談することをおすすめします。
再挑戦は“制度”でも応援されている時代へ
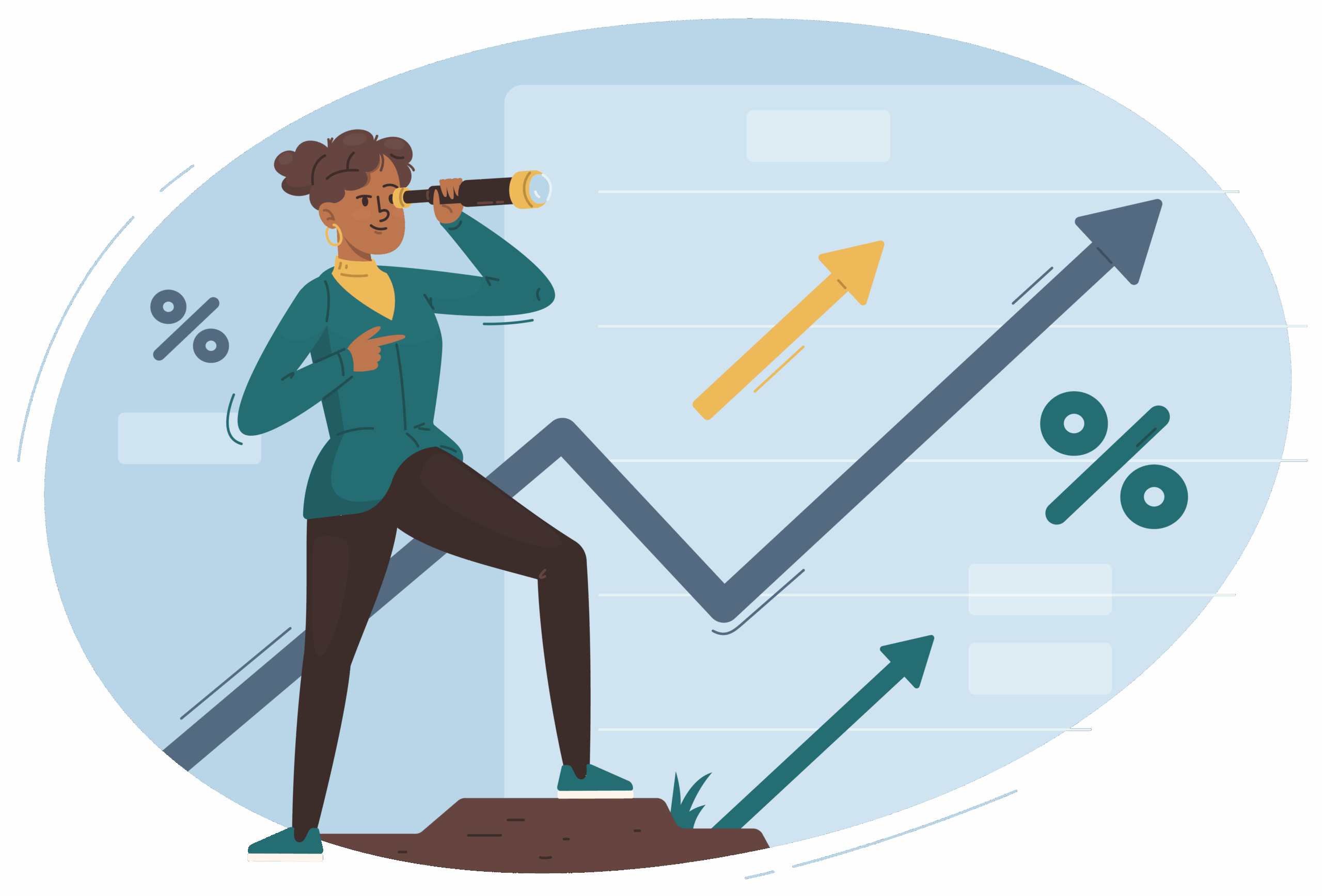
起業や経営の失敗を乗り越えるための公的支援は、近年着実に整備されてきています。
たとえば「日本政策金融公庫」では、再挑戦支援資金(通称:リスタート融資)という制度があり、倒産や廃業を経験した経営者でも、一定の条件を満たせば再度資金調達が可能です。
『再挑戦支援資金』は、日本政策金融公庫(JFC)の地域支店、または「創業支援センター」等から直接申請・相談が可能です。
必要書類は主に「過去の事業概要」「現在の資金状況」「再挑戦に関する事業計画書」の3点です。
オンライン申請も一部自治体でスタートしています。
また、中小企業再生支援協議会では、事業継続が困難な中小企業に対し、弁護士や会計士などの専門家チームが「再生計画」を共に立て、再出発をサポートしています。
他にも、2024年度から始まった「再挑戦特別保証制度」では、信用保証協会の保証付きで最大2,000万円の資金借入が可能になっています(※一部地域限定)。
つまり、“失敗しても立ち上がれる制度的な余白”は、確実に整いつつあるということです。
大切なのは、こうした制度を「失敗の証明」としてではなく、「もう一度問う権利」として使う視点です。
たとえ1度つまずいたとしても、それを“制度が肯定する時代”に私たちは立っているのです。
中小企業庁の「2023年度白書」によれば、廃業を経験した経営者のうち約24.6%が5年以内に再起業を果たしています。
また、再起業者のうち68%が「過去の失敗経験が今の経営に活きている」と回答しています(※中小企業庁『再挑戦支援調査報告書』より)。
海外と比較すると、日本では「倒産後の信用回復期間」が長く、再挑戦を制度的に後押しする仕組みが乏しいと言われていますが、2024年からは「再起業支援融資」や「セーフティネット保証制度」の柔軟化も始まっています。
つまり、“失敗=終わり”という認識は制度的にも徐々に変わりつつあるのです。
それでも、あなたが挑む理由は何ですか?
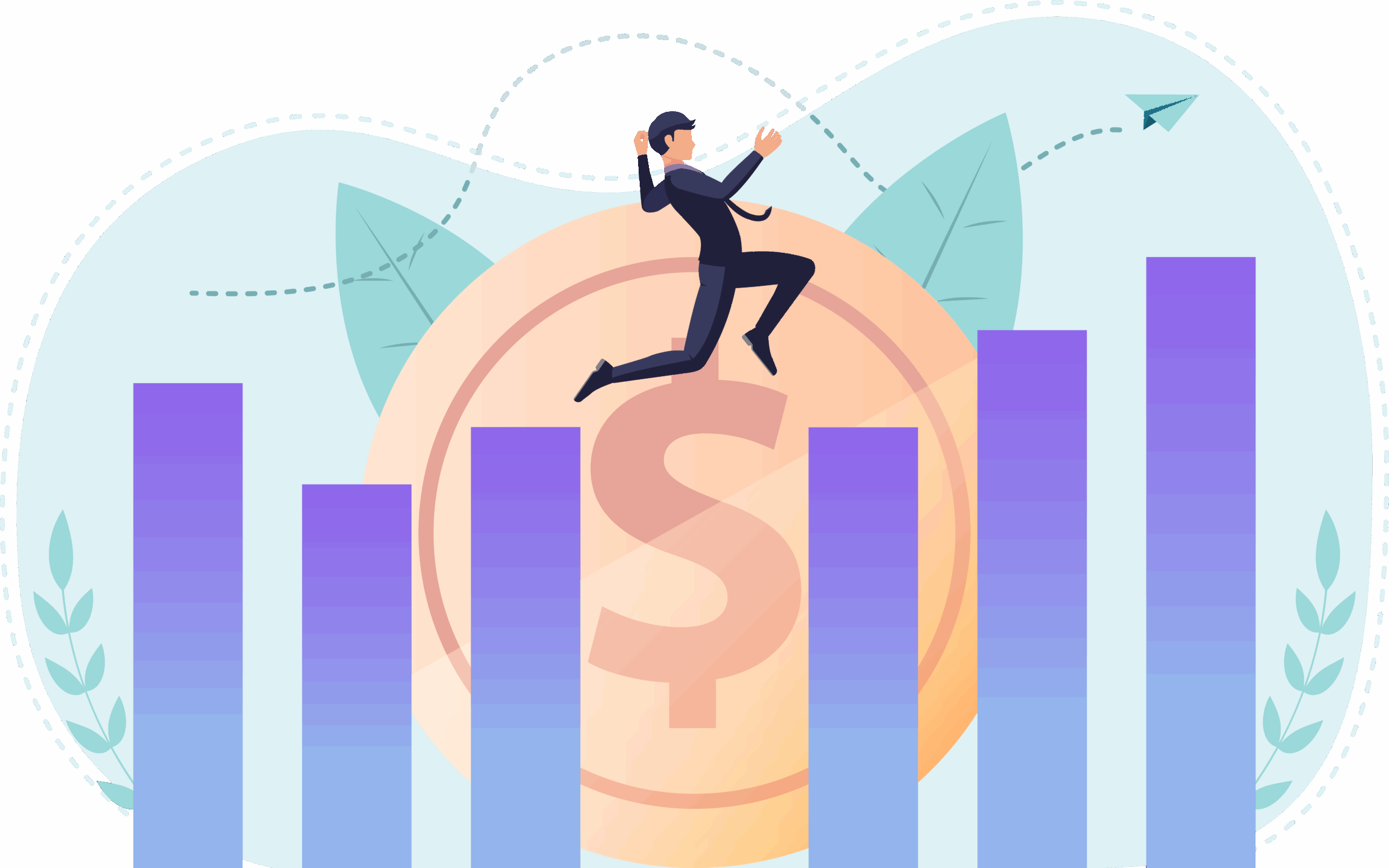
ここまで読んでくださったあなたに、私はひとつだけ、問いを贈りたいと思います。
「それでも、あなたが挑む理由は何ですか?」
資金が尽きるかもしれない。仲間が去るかもしれない。
アイデアが形にならないかもしれない。
それでも、あなたは今、このページにたどり着いた。
もしかしたら、世間の目が怖くて、起業に踏み切れないでいるのかもしれない。
過去の失敗が尾を引いて、「もう一度」は怖いと感じているのかもしれない。
それとも、まだ誰にも言えない“小さな願い”を、胸の内で密かに抱えているだけかもしれない。
それでも、私は信じています。
あなたがその一歩を踏み出すのは、「勝ちたい」からでも「成功したい」からでもない。
あなたの中に、“贈りたい問い”が眠っているからです。
問いとは、誰かの役に立つために自分を差し出すことです。
「これって変じゃない?」「もっとこうできないかな?」「誰か、これを必要としているかもしれない」
そんな違和感や願いが、あなたを静かに突き動かしている。
起業とは、問いを世の中に投げる行為です。
投げたその問いが、誰かの人生に届き、響き、形を変えて戻ってくる。
たとえ結果が思うようにいかなくても、あなたの問いは確かに誰かの中に残ります。
だから私は、あなたが挑戦することそのものに、もう“意味”はあると思っています。
そして、もうひとつ信じていることがあります。
もしあなたが、その問いを誰かに贈ることができたなら——
きっと、あなたにも、誰かからの問いが届くはずです。
そうしてつながっていく小さな照応が、社会をあたたかく変えていくのだと、私は願っています。
さあ、今あらためて、静かに自分に問いかけてみてください。
「それでも、あなたが挑む理由は、何ですか?」
まとめ ~それでも、進む価値がある。
- 日本では“失敗”が社会的なスティグマとして扱われやすい構造がある
- しかし「失敗」は、未来へ贈られる“問い”として価値を持つ
- あなたが挑戦する理由には、まだ言葉にならない願いが宿っている
失敗とは、何かが終わることではありません。
それは、まだ解かれていない問いを世界に投げかけたという「痕跡」です。
あなたがもし、これから何かに挑もうとしているのなら、結果よりも、その“問いの純度”を信じてください。
問いを残せる人は、まだ終わっていません。
そして、その問いを誰かが受け取ったとき、それはもう失敗ではなく、誰かの道しるべになります。
挑戦するということは、孤独ではありません。
あなたのその一歩は、必ず誰かの“応答”を呼ぶからです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
どんな問いでも、あなたの内側に灯りがある限り、きっと誰かとつながれます。
また次回のコラムでお会いできるのを楽しみにしています。
- ノート1ページに「なぜ挑戦したいのか?」を書いてみる
書くことで“問い”が輪郭を持ち始めます。それは、まだ小さくても確かな起点です。 - 信頼できる1人に「実はやってみたいことがある」と話してみる
共鳴は、共有から生まれます。ひとりで完璧を目指す必要はありません。 - 倒産経験者や起業家のインタビュー記事を3本読む
他者の“問い”に触れることは、自分の問いを深める最短ルートです。 - 「自分が応援したい人」をひとりイメージしてみる
応援されたい時は、まず応援したい誰かを想像してみる。問いの“受け手”を感じる練習です。