こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
最近、AIに関する相談が経営者のもとにも少しずつ届くようになってきました。
ChatGPTや生成AIの存在は“なんとなく知っている”という方も多い中、ある日、社員からこう言われたとします。
「業務でAI、試してみたいんです」
一見、前向きな申し出のように聞こえます。
「お、やる気があるな」「時代に乗ってるな」
しかし、どこかで引っかかりを感じたことはないでしょうか?
「うちでそんなの使って本当に大丈夫か?」
「勝手に進めて、情報が外部に漏れたりしないか?」
「そもそも、自分がよくわかってないのに許可してもいいのか?」
結論から言えば、「問い返すこと」こそが、経営者に求められる最善の応答です。
社員のAI提案に即OK/NOを出すのではなく、「なぜ?」「何を変えたい?」と問い返すことで、信頼・文化・学びが芽吹きます。
社員からの“AI活用提案”は、単なる業務効率化の話ではありません。
それは経営者の「問い返す力」が試されるサインであり、組織文化の入口が少し開きかけた瞬間でもあります。
今、AI導入を検討する経営者にとって最も重要なのは、「やるか、やらないか」ではなく、
“その声が、なぜ今、どの立場から出てきたのか”を見極める姿勢です。
本記事では、社員からのAI提案にどう応えるべきかを軸に、
「AI導入 経営者」「社員 AI 提案」という視点で、問い返しの力とその効果を実践的に掘り下げていきます。
社員からのAI提案の本質とは?

現場の社員が「AIを使ってみたい」と言ってきたとき、それを“ただの業務提案”として処理してしまうのは、あまりにももったいない対応です。
実はこの一言には、組織の変化の芽が含まれています。
そもそも通常、業務改善や新しいツールの導入は“上”から降りてくるものであり、それに対して“現場が応答する”というのが一般的な企業の構造です。
そこへ、“現場からの発案”が飛び込んでくる――これは現場が“受け身”を脱し、組織の思考に関与し始めた兆しと捉えることができます。
また、この申し出には必ず背景があります。
「業務が遅れていて何とかしたい」
「繰り返し作業に疑問を感じている」
「他社と比較して、自社の非効率さが気になっている」
こうした“違和感”の積み重ねが、AIというツールを通じて言語化された形なのです。
重要なのは、提案そのものよりも、そこに含まれる“問いの芽”に気づけるかどうか。
「どうせ試しても大したことはできないよ」
「うちはそんなに大きな会社じゃないし」
──そうした無意識の“組織規模バイアス”が、せっかくの提案を潰してしまうことがあります。
✔ 効率化の願望だけでなく、「働き方そのものを変えたい」という奥行きがある
✔ 他社の動向への危機感と、自社での可能性の模索が含まれている
✔ 現場のストレスを“技術”で救えるかという希望が宿っている
実際に、AI提案が“共通テーマ化”され、1チーム内での活用検討ミーティングが定例化した企業では、半年でプロジェクト稼働件数が+25%に増加したという事例もあります[1]。
つまりこの一言は、ただの機能提案ではなく、「会社をどうしたいのか」「自分の仕事をどう変えたいのか」というビジョンの端緒なのです。
経営者がそれを“やっていい/やめておけ”の二択で終わらせてしまえば、組織は変わりません。
この問いをどう育てるかが、“学び合える組織”への第一歩になります。
経営者の不安の3つの正体

社員のAI提案に対し、ためらいや違和感を抱く経営者は少なくありません。
それは“古い”とか“否定的”ということではなく、むしろごく自然な経営的反応です。
なぜならAIというテーマは、単なるツール選定ではなく、リスク・統制・信頼・責任といった経営の根幹を揺さぶる構造を持っているからです。
1. 「リスクが見えにくい」不安
社員が勝手に外部サービスに情報を入れてしまったら?
生成されたアウトプットに誤りがあって、それが顧客との取引に使われてしまったら?
AIの“ブラックボックス性”が、予測不能なリスク感覚を生んでいます。
2. 「社内統制が崩れるかも」への不安
ひとりが使い始め、あちこちで“独自ルール”のAI活用が進み、気づいたら現場がバラバラに……
この「見えない拡散」が、経営の可視性を失わせる不安につながります。
3. 「自分がよく分かっていない」ことへの戸惑い
「部下より自分の方が分かってないのでは?」という引け目。
「分からないのに承認するのは無責任では?」というブレーキ。
これは経営者の誠実さゆえの“ためらい”とも言えます。
このような不安は、決して“導入反対”を意味しません。
むしろ、その不安をどう言語化し、構造的に整理するかが経営者の本質です。
✔ リスク:使用可能なAIツールのガイドラインを社内で簡潔にまとめる
✔ 統制:試験導入は“1部署・1テーマ・1ヶ月”など条件を明確化
✔ 理解不足:自ら「何がわからないのか」を言語化し、社員と共有する
“やらない理由”ではなく“やれる条件”を言語化することが、リーダーの本質です。
ピーター・ドラッカーは言いました。
「最も重要なことは、正しい問いを持つことである」[2]。
AI導入において、経営者の“問い方”は組織の方向を決めるコンパスとなるのです。
問い返す経営の力
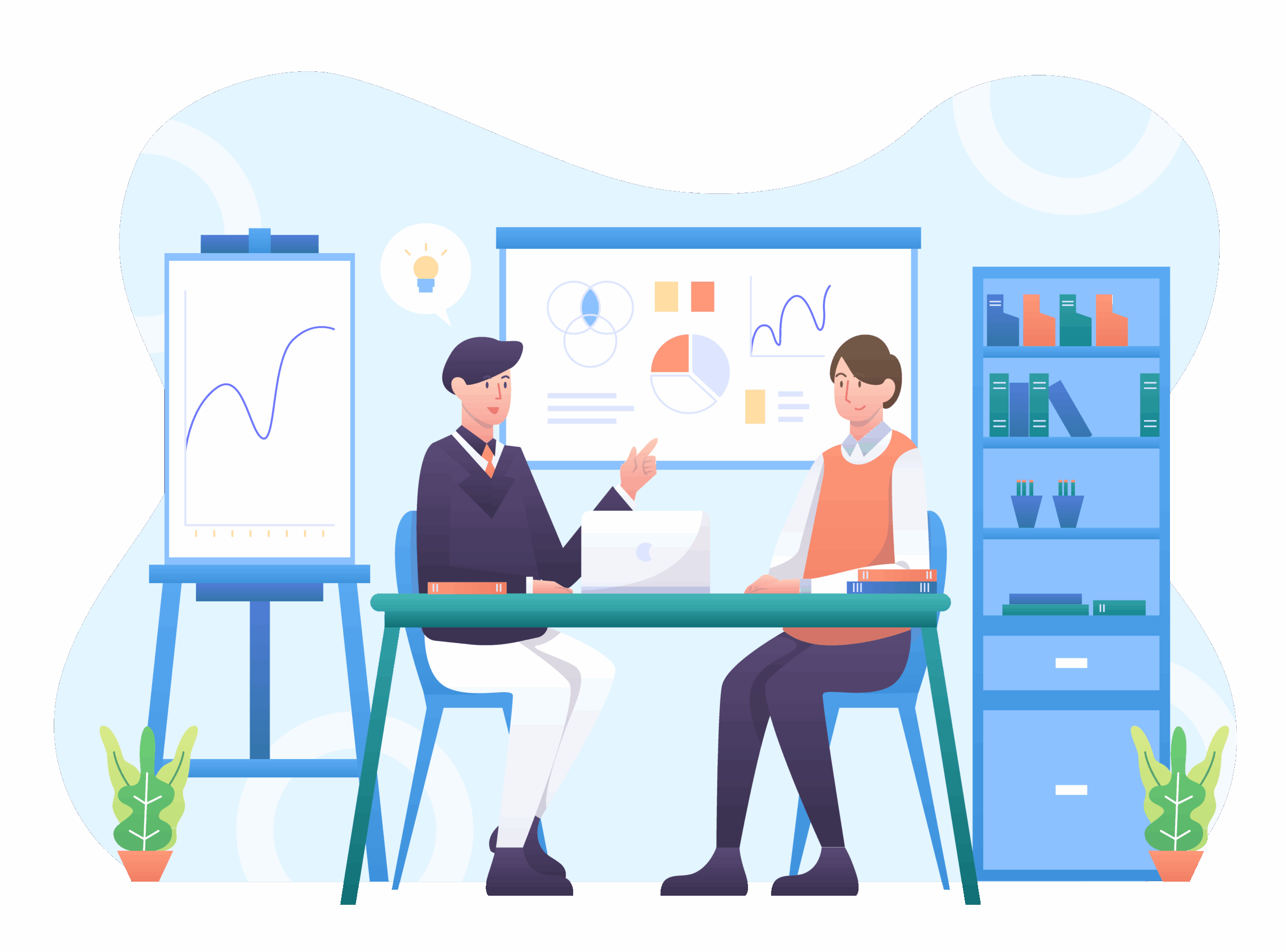
社員が「AIを使ってみたい」と申し出てきたとき、経営者の反応が“YES”か“NO”の即答になってしまうのは惜しい瞬間です。
実はその問いには、単なる許可・不許可以上の価値が詰まっています。
経営者が「問い返す」ことで、その声は“文化”へと変換される可能性を持っているからです。
たとえば、「それって何に使いたいと思った?」と聞く。
「どんな効果があると感じた?」と問いかける。
こうした対話を通じて、社員の中にある“ぼんやりとした直感”が言語化され、組織共有可能な知見へと育っていきます。
また、問い返しは“責任の所在”を明確にすることにもつながります。
「好きにやってみて」では責任の主体が曖昧になりますが、「一緒に考えてみよう」と言えば、その取り組みは“共創”の性質を帯びていくのです。
そしてもう一つ、問い返すことは、経営者が“わかっていない”ことを許容する姿勢にもなります。
完璧に理解していないからこそ、問いを持つ。
この姿勢が、社員に安心と“探究の自由”を与えます。
✔「そのAI活用で、今の仕事の何が変わると思った?」
✔「それは1人でできそう?チームにも広げられそう?」
✔「小さく試すとしたら、どこから始める?」
これらの問いは、“使っていいよ”よりも深い、「あなたの考えに本気で関わるよ」というメッセージになります。
AI活用において、最も重要なのはツールそのものの性能ではなく、それを通じた“対話の起点”をどう育てるかです。
「使う/使わせる」という構図から抜け出し、「ともに問い、試し、育てる」という姿勢こそが、これからの経営を支える土台となるでしょう。
AIを文化に変えるには
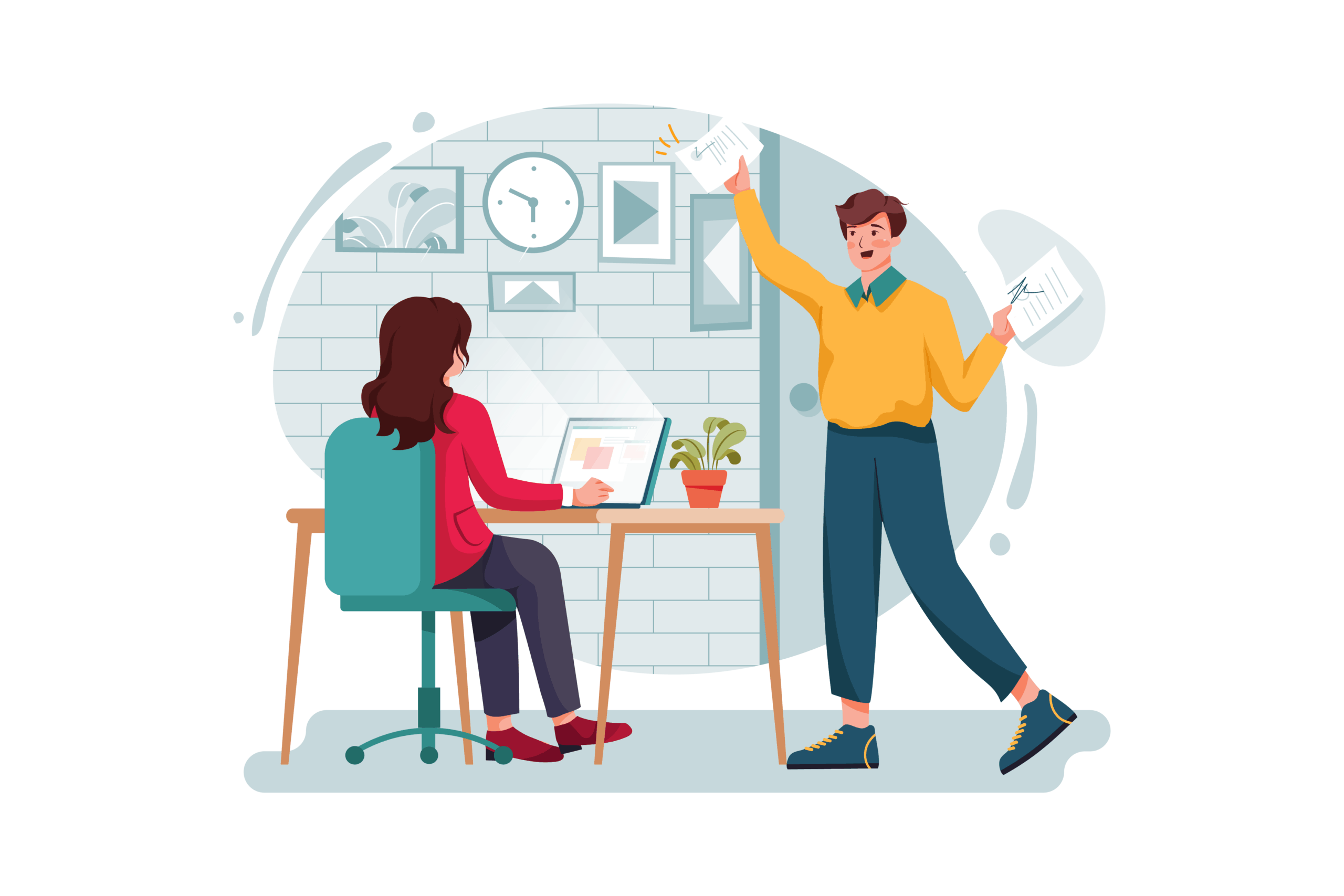
「AI使ってもいいですよ」──この一言をもらって、社員が意気揚々と取り組んだ。
けれど、数週間後には何の音もなく、話題にもならず、忘れられていく…。
そんな光景を、すでに経験された経営者もいるかもしれません。
AI導入が“取り組み”で終わってしまう企業と、“文化”へと根づく企業の違いは、「その後の問いかけの有無」にあります。
導入したあと、「どうだった?」と聞かれなければ、現場はそこで止まります。
結果や変化のフィードバックが求められなければ、学びも共有されず、組織知としての蓄積もされません。
だからこそ、経営者には“使わせるかどうか”ではなく“使った後をどう受け取るか”を設計する視点が求められます。
まずは小さな導入単位を設定するのが有効です。
たとえば「1部署1人、1週間だけ試してみる」──この“48時間以内に試す”という明確な開始タイミングを設けるだけで、組織の空気は変わります。
そして、その“結果の共有”が場として保証されていることが大切です。
週1の5分共有でもいい。
「試した内容・つまずいた点・気づいた効果」などを、安心して語れる場をつくることで、AI活用は組織に静かに根づいていきます。
✔ 経営者自身が“わからなさ”を可視化する:「自分も試してみて驚いた」と語る
✔ 形式化する:「導入→検証→共有」の3ステップをルールとして明文化する
✔ 評価制度に反映:「AI活用レポート」などを業務評価の補足資料とする
文化とは、「何をしてもいい」自由ではなく、「やっていいと言われなくても、やれる」空気のことです。
経営者の“問い返し”や“場づくり”の姿勢は、その空気を静かに変えていきます。
AIを入れるかどうかよりも、“問う力”があるかどうか。
それが、変化に強い組織をつくる本当の経営判断です。
まとめ~社員の「やりたい」にどう応えるか?
- 社員の「AI使いたい」は、業務提案ではなく“問いかけ”である。
- 経営者の“問い返し”が、信頼と学習文化の土壌を育てる。
- AI導入の核心は「ツール」ではなく、「関わり方」にある。
結論:経営者が問い返すだけで、AI提案は“文化の起点”になる。
AIという言葉が日常になりつつある今、社員から「使ってみたい」という声が上がることは決して珍しくなくなりました。
しかし、そこに応答する経営者の姿勢次第で、その組織の未来は大きく変わっていきます。
単に“やらせる”か“やめさせるか”ではなく、その間にある「問い返しの時間」こそが、最も深い経営判断です。
問い返すことで、社員の思考が深まり、責任の所在が共有され、組織に“信頼の余白”が生まれます。
それは単なる業務改善ではなく、文化の起点となり得る行為です。
「まずはやってみろ」ではなく、「何を見たいと思ったのか、聞かせてくれるか?」
そんな問いが、これからの組織に必要とされるリーダーシップの姿なのかもしれません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
経営判断とは、答えることではなく、問われること。
そして、問われたときに、どう返すかで文化が育ちます。























