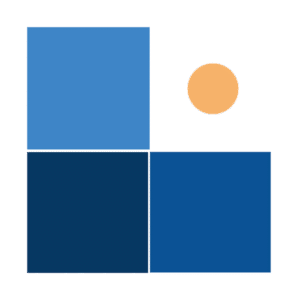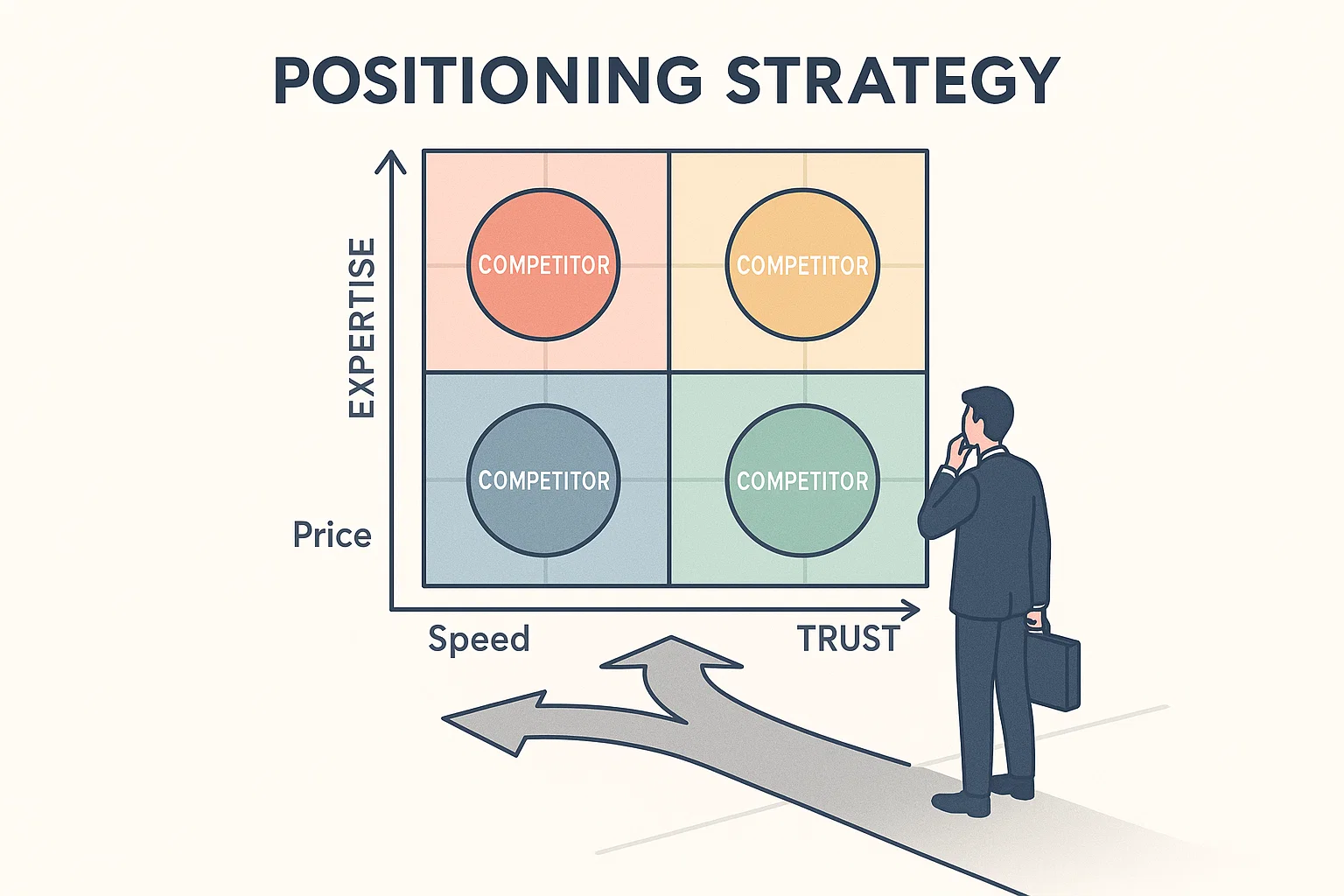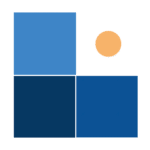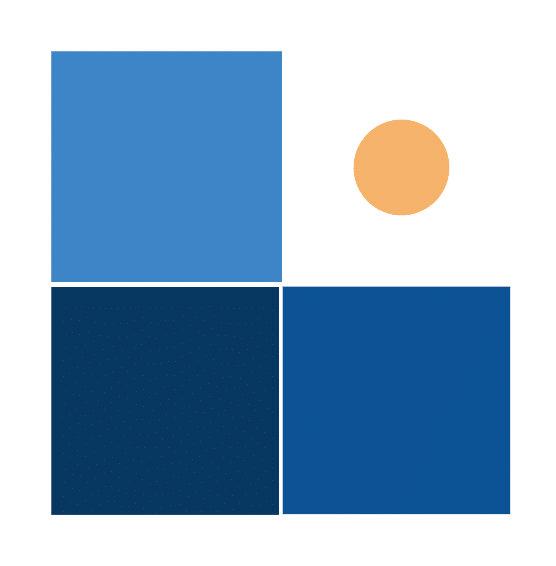ChatGPTを使う社員が怖い?経営者が乗り越える“逆デジタル・ディバイド”戦略
こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
社員がChatGPTを使ってメールを作成していた。議事録を自動生成していた。
そんな場面を見て、「便利そうだな」よりも「ちょっと怖いな」と感じたことはありませんか?
自分がまだ試してもいないのに、若手社員はすでにツールを使いこなしている。
その姿に、どこか焦りや不安を感じてしまう──それは決して珍しいことではありません。
その感情は、バカにされるべきものではなく、むしろ“学ぶ機会を奪われてきた構造の副作用”かもしれません。
今、静かに広がっているのは“逆デジタル・ディバイド”。
つまり、若手ではなく“上の世代・上の立場”のほうが、学びの機会や安全な失敗の場を失ってきたという現象です。
これは単に「デジタルに弱い」という話ではありません。
経営者が安心して学ぶ文化が育っていないという、構造の問題なのです。
この記事では、ChatGPTを使う社員に“怖さ”を感じる背景をひも解きながら、経営者自身が問い直すべき「学びのあり方」を考えていきます。
“怖さ”の奥にあるのは、まだ使ったことがない「問い」の可能性かもしれません。
ChatGPTを使う社員に“なぜか怖さ”を感じてしまうのはなぜ?
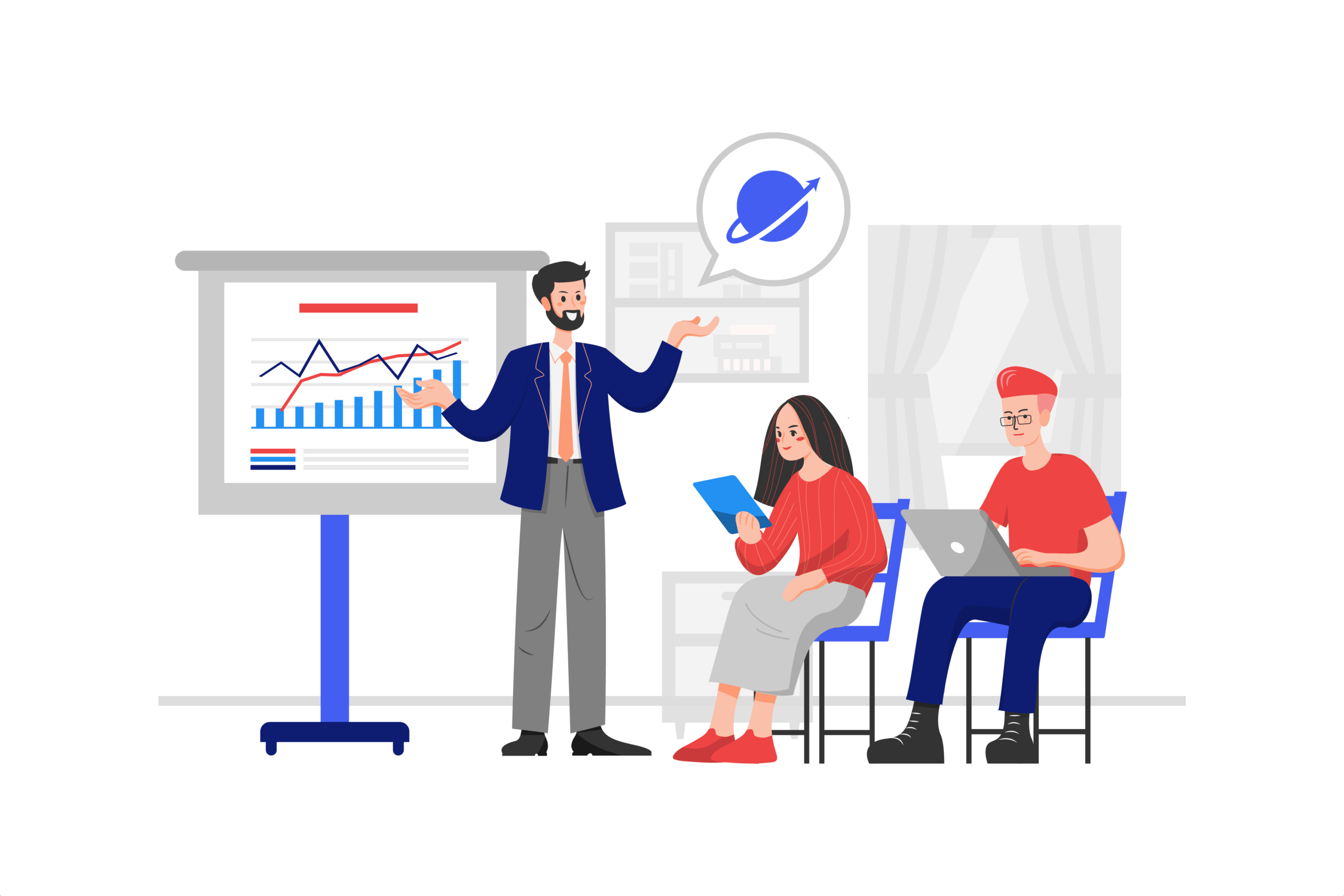
ChatGPTに限らず、社員が“自分の知らない技術”を使いこなしている姿に、どこかざわつきを覚えたことはありませんか?
その感情を正確に言語化するのは、意外と難しいものです。
でも、その正体はおそらく「置いていかれるかもしれない」という不安です。
知らないうちに自分より速く動いている存在に出会ったとき、人は本能的に警戒心を抱きます。
しかも相手が「自分の部下」であれば、その感情は“権威の揺らぎ”として反応することもあります。
「教える側であるはずなのに、教えられる立場になってしまう」
この逆転が、経営者や管理職にとって無意識に“怖さ”をもたらしているのです。
たとえば、部下がChatGPTで企画案のたたきを作ってきた。
クオリティはそこそこだが、スピードと工数効率は抜群。
その瞬間に「アイデアより効率が重視される会社になったらどうしよう」と、どこかで不安がよぎる──
それが「怖さ」の本質に近い感情です。
そして多くの場合、この感情は「ChatGPTなんて文章ヘンだろ?」「結局、中身が薄いんじゃない?」と“茶化し”の形で処理されてしまいます。
でも、茶化してしまった瞬間に、学びのシャッターは音もなく閉じてしまいます。
✔ 自分が“何に”怖さを感じているのか、3つ挙げてみる
✔ その怖さは「技術」か「立場」か?
✔ もし部下がその言葉を自分に返してきたら、どう感じるか?
ちなみに、ある企業では部下が「実はもう1か月前からChatGPTで議事録作ってます」と正直に打ち明けたとき、
経営者が「正直、それ聞いてちょっと悔しかった。でも、すごいと思う」と返したことで、一気に社内でAI活用が加速したそうです。
感情を否定せず、ただ正直に“そのままの自分”で返す。
怖さを共有できる経営者がいる組織は、強いのです。
「学びにくくなる」のは“年齢”ではなく“立場”のせい
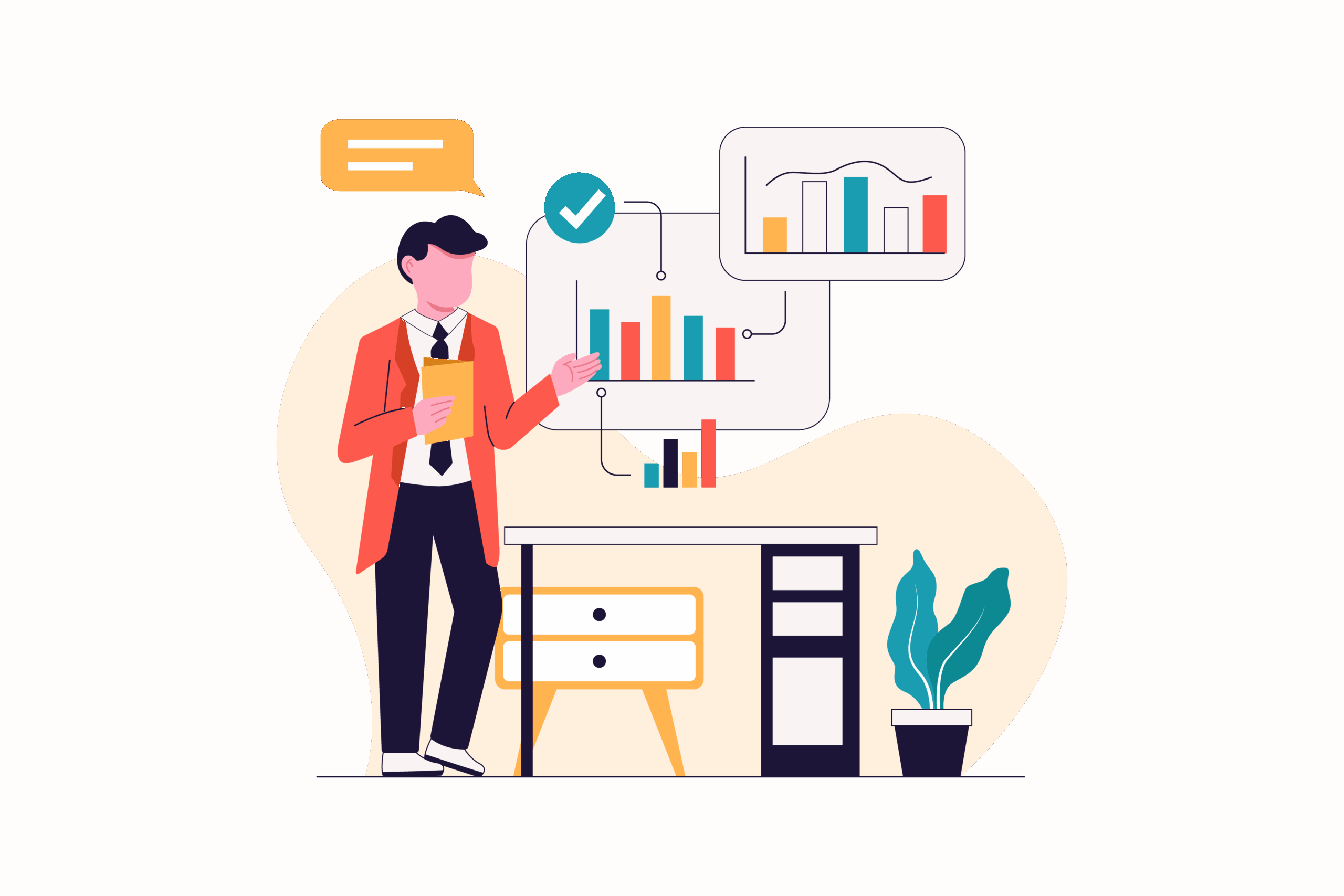
一般的に「高齢者はデジタルに弱い」と語られがちですが、実はそれ以上に深刻なのが、“立場が上がるほど学びにくくなる”という構造的な壁です。
社長や管理職は多忙です。責任も重く、1日の中で「自分が学ぶための時間」を確保するのは至難の業。
その現実がある一方で、問題は“誰も経営者に勉強を促してこない”という点です。
社員ならば、上司や評価制度が「学び続ける」圧力になります。
しかし経営者には、そうした圧力がありません。
つまり“学ばなくても誰にも怒られない”という構造の中に置かれているのです。
加えて、“知らない”ことを社員に聞くのは、意外とハードルが高いものです。
「そんなことも知らないんですか?」と言われるわけではなくても、どこかで“恥”に感じてしまう。
ある経営者はこう語っていました。
「実はChatGPTって、使い方すらよく知らなかった。でも、社員には“知ってて当然”みたいな空気があって、聞けなかったんですよね」
知らないことを“知らない”と言えない空気。それが立場の副作用です。
✔ 学ばないのではなく、“誰も自分に学べと言わない”だけかも
✔ 教えてくれる相手が「自分より下」だと、心理的にブレーキがかかる
✔ でも、そのブレーキは「自分が勝手に踏んでいる」かもしれない
“逆デジタル・ディバイド”とは、デジタルの問題ではありません。
「学び続けられる関係性を持っているか?」という、組織文化の話なのです。
経営者が学ぶことを選びやすい環境を、自ら言葉でつくっていくこと。
その姿勢が、次の“学びたがっている誰か”の背中を押すことになります。
社員は“学び合いたい”と思っている

AIについて語り始めた社員の多くは、ただ「許可がほしい」のではありません。
むしろ、「一緒に考えてほしい」「このことについて誰かと話したい」──そう思っていることの方が多いのです。
「ChatGPT試したんです」
その言葉の裏には、「面白かった」「怖かった」「すごいかも」といった“混ざった感情”が含まれています。
その体験を言語化してみたかった。受け止めてもらいたかった。
そう感じている社員は多いのに、話しかけた相手から「へぇ」で終わってしまったら、もうその感情は二度と外に出てこないかもしれません。
一方で、経営者が「使ってみた」「びっくりした」「わからなかった」といった感情を共有すれば、
社員は「この人も一緒に学ぼうとしているんだ」と受け取り、安心して自分の問いを語れるようになります。
実際、とある中小企業では、経営者が「ChatGPTって怖いくらい返してくるな」と笑いながら語ったことがきっかけで、
週1の“AI雑談ミーティング”が自然発生し、組織全体のリテラシーが目に見えて底上げされたという事例もあります。
その結果、導入から3か月で社内のAI活用報告件数は前年比+25%、
社員1人あたりの残業時間は平均で-8%という効果が見られたそうです。
“語れる場”があるだけで、数字は確かに動きます。
✔「正直、まだよくわからない。でも関心はある」
✔「ちょっと試してみたら、想像以上だったよ」
✔「これ、どう思った?」と聞くのは“信頼”の証
社員は、「知らない自分」よりも「知ろうとする上司」に安心します。
経営者が“わからない”を語れる会社は、強い組織です。
“逆ディバイド”を超える問い直し戦略
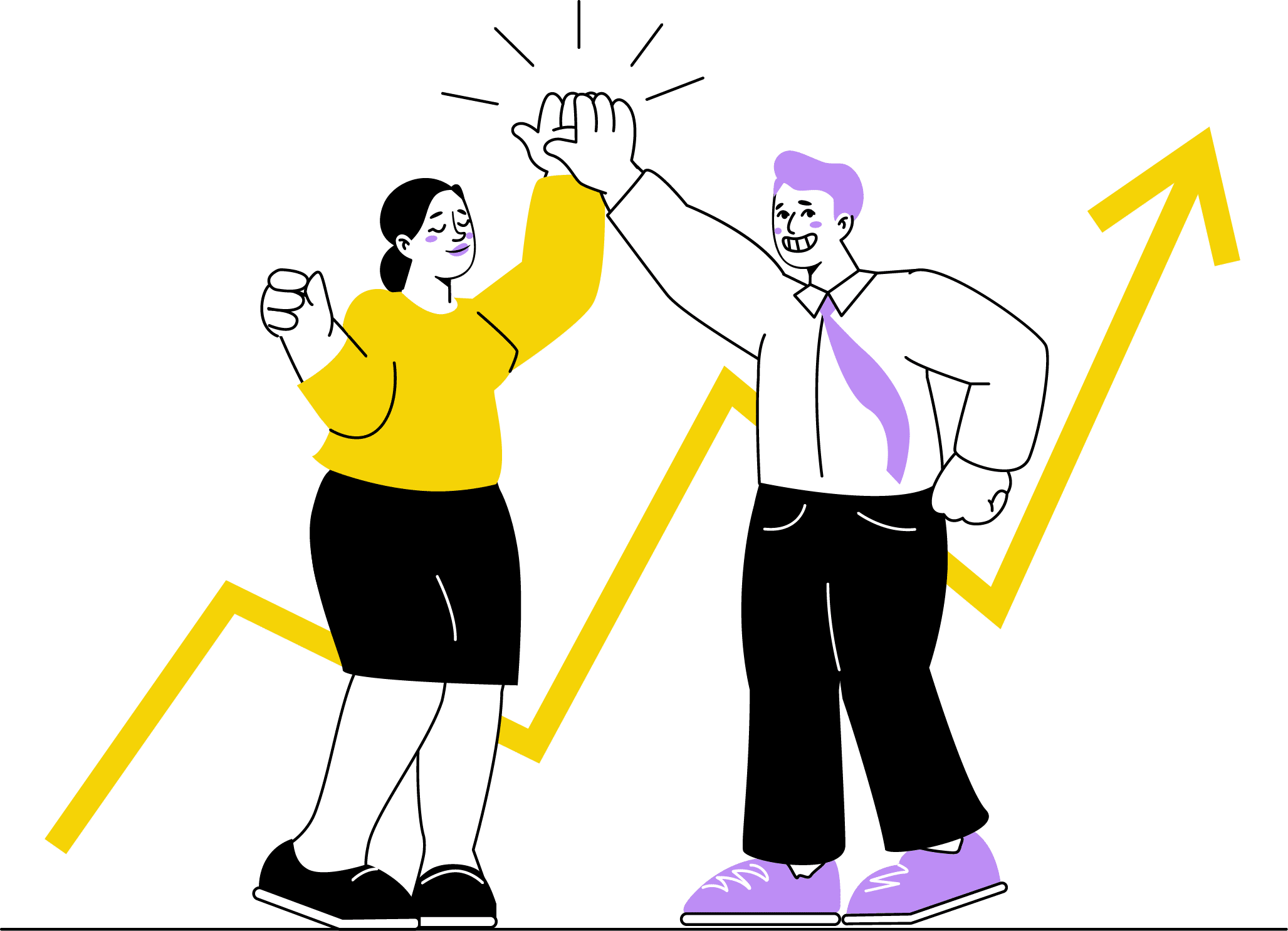
ChatGPTを使う社員が怖い。
その感情に気づいたとき、まずすべきは「自分を責めること」ではありません。
それよりも大切なのは、「なぜ問い返せなかったのか?」を、そっと問い直してみることです。
答えを知らなかったから?
使ったことがなかったから?
もしかしたら“自分に問いを持っていなかった”からかもしれません。
実際、総務省調査によると、20代の生成AI利用率は約64%にのぼる一方で、50代では約21%に留まっています[1]。
使う/使わないの選択が、世代間で“文化的分断”になりつつあるのが現実です。
でも、その分断を乗り越える第一歩は、とても小さな行動から始められます。
ある経営者は、「まずChatGPTに“うちの会社の強みを箇条書きして”と聞いてみた」と言います。
そこで返ってきた答えはたしかに荒削りでしたが、「ああ、社員たちが感じてる“驚き”はこれか」と思ったそうです。
✔ ChatGPTに、自分の業界について質問してみる(たった5分)
✔ 社員に「使ってみてどうだった?」と聞いてみる(15分対話)
✔ 「何がわからないか」を1つ言語化してみる
48時間以内に、ChatGPTで“自社の強み”を1つ質問してみてください。
出力の良し悪しではなく、「自分でも動けた」という感覚が、次の一歩を後押しします。
問いを持つことは、恥ではありません。
問いを手放さないことこそが、学び続ける経営者の証です。
よくある質問:社員にAI活用を聞かれたら?
- Q:社員から「ChatGPT使っていいですか?」と聞かれたら?
A:すぐにYes/Noで答えるのではなく、「どんな使い方を想定してる?」と問い返してみましょう。 - Q:自分が使ったことがなくて不安です…
A:それは自然な反応です。「自分もまだ試したばかりだけど」と正直に共有する姿勢が、信頼につながります。 - Q:使わせたあと、管理が心配です。
A:小さく試す+定期レビューをセットにしましょう。「1テーマ・1人・1週間」から始めるのがおすすめです。
まとめ~「怖さ」を問いに変える経営へ
- ChatGPTを使う社員に“怖さ”を感じるのは、自然なこと。
- 問題は、その感情を茶化し、問い返さずに終えること。
- 「問い直す」姿勢が、経営と組織を“共に学ぶ場”に変える。
経営者だからこそ、知らないことを認めにくくなる。
それはよくあることですし、決して“怠慢”ではありません。
でも、AIが当たり前になりつつある今、「わからないまま、判断し続ける」ことはリスクになります。
「ChatGPT、まだ触ったことない」
「社員が先に進んでいて焦る」
──その感情を、そっと問いに変えることから始めてみてください。
問いとは、恥ではなく、対話の入口。
その一言が、部下の背中を押し、組織の空気を変えます。
そして何よりも、「学び続ける自分でいたい」と思うこと自体が、最も信頼される経営姿勢です。
変化の時代における経営とは、誰よりも多く答えることではなく、
誰よりも深く問い続けること。
その姿勢がある限り、技術の波は決して脅威ではなくなります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
このコラムが、皆様の「次の問い」のきっかけになれば嬉しいです。