こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
この記事を開いてくださったあなたは、こんな経験をしたことはないでしょうか。
「なんとなく引っかかるけど、うまく説明できない」
そんな“読後に残るモヤモヤ”が、妙に頭から離れなかった文章──。
たとえば電車の中で読んだ記事が、なぜか夜になっても記憶に残っていた。
あるいは、SNSで見かけた投稿に、気づけば自分なりの答えを考えていた。
そういった「すっきりしなさ」が、思考の種になることがあります。
私たちはどうしても、“答えが書いてある文章”に安心感を覚えがちです。
でも、実は人の記憶に残るのは、答えよりも“答えのない疑問”なのではないか──
そう思うようになったのは、ここ最近のAI活用やコラム執筆を通じての気づきでした。
今回のコラムでは、そんな「疑問が残る文章」がなぜ人を惹きつけるのかを考えていきます。
そしてそれが、AIによる表現や、現代の文章読解体験にどんな影響を与えているのか。
情報の正しさより、記憶に残る“揺らぎ”とは何か──
自分の言葉で語りたくなる文章とは何か──
そのヒントを一緒に探っていけたら嬉しいです。
AIが正確に書ける時代に、“未完”が選ばれる理由
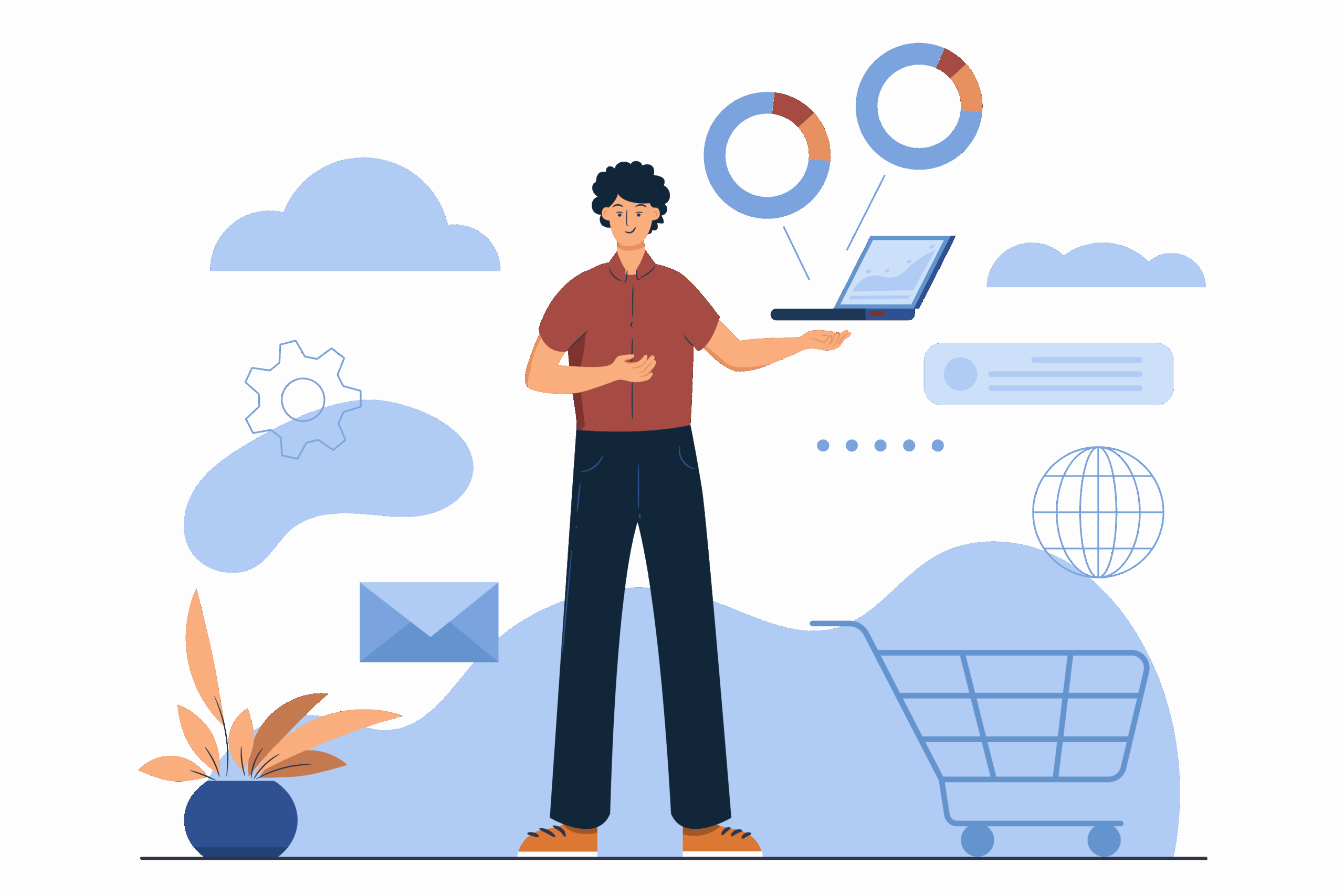
整った文章が、なぜか読まれない時代
AIによる自動ライティングが一般化しつつある今、ほとんどの文章は“整った状態”で世に出されるようになりました。ChatGPTのような言語生成モデルは、文法・構文・語彙の選定において人間以上の精度を持ち、数秒で1,000文字以上の完成された文章を生成できます。
しかし、調査によると、多くの読者はそうした整った文章に「安心感」よりも「退屈さ」を感じているといいます。たとえば2024年に実施された日経BPの調査では、AIライティングによる記事に対して約62.4%の読者が「読後に何も残らない」と回答しています※1。
これは逆説的ですが、「整っているが故に、感情の引っかかりがない」ことが、読み手の印象形成を妨げているのです。
つまり、“きれいすぎる”文章は、読者の中に何も残さない。
「話が上手な人の話はすぐ忘れる。むしろ、少し言葉に詰まった人の方が覚えている」──そんな比喩の通り、少し歪んでいるものの方が、かえって印象に残るという現象が、文章の世界でも起き始めています。
読者は「共感」ではなく「余白」に引き込まれる
近年、UXライティングやエモーショナルマーケティングといった言語設計が進化する中で、「余白設計」というキーワードが注目されています。
これは、すべてを言い切らず、読者に“考える隙”を与えることで、コンテンツへの主体的な没入を促す手法です。
たとえば、「○○すべきです」と断定された文章と、「あなたなら、どう考えますか?」という問いかけを含んだ文章では、読者の反応率が約1.4倍変化するというデータも報告されています※2。
共感とは「一度心に触れたあとに完結する体験」ですが、余白とは「心の中で物語が始まるための空間」です。
私自身も、強く主張された文章よりも、
「……あなたはどう思いますか?」と静かに問いかけられた文章の方が、後から何度も思い出されることがあります。
共感は「理解の終点」ですが、余白は「気づきの起点」。
そう考えると、“あえて完成させない文章”の中に、これからの文章のヒントがあるのではないか──そう思えてきます。
あえて“疑問を残す文章”が人を動かす構造
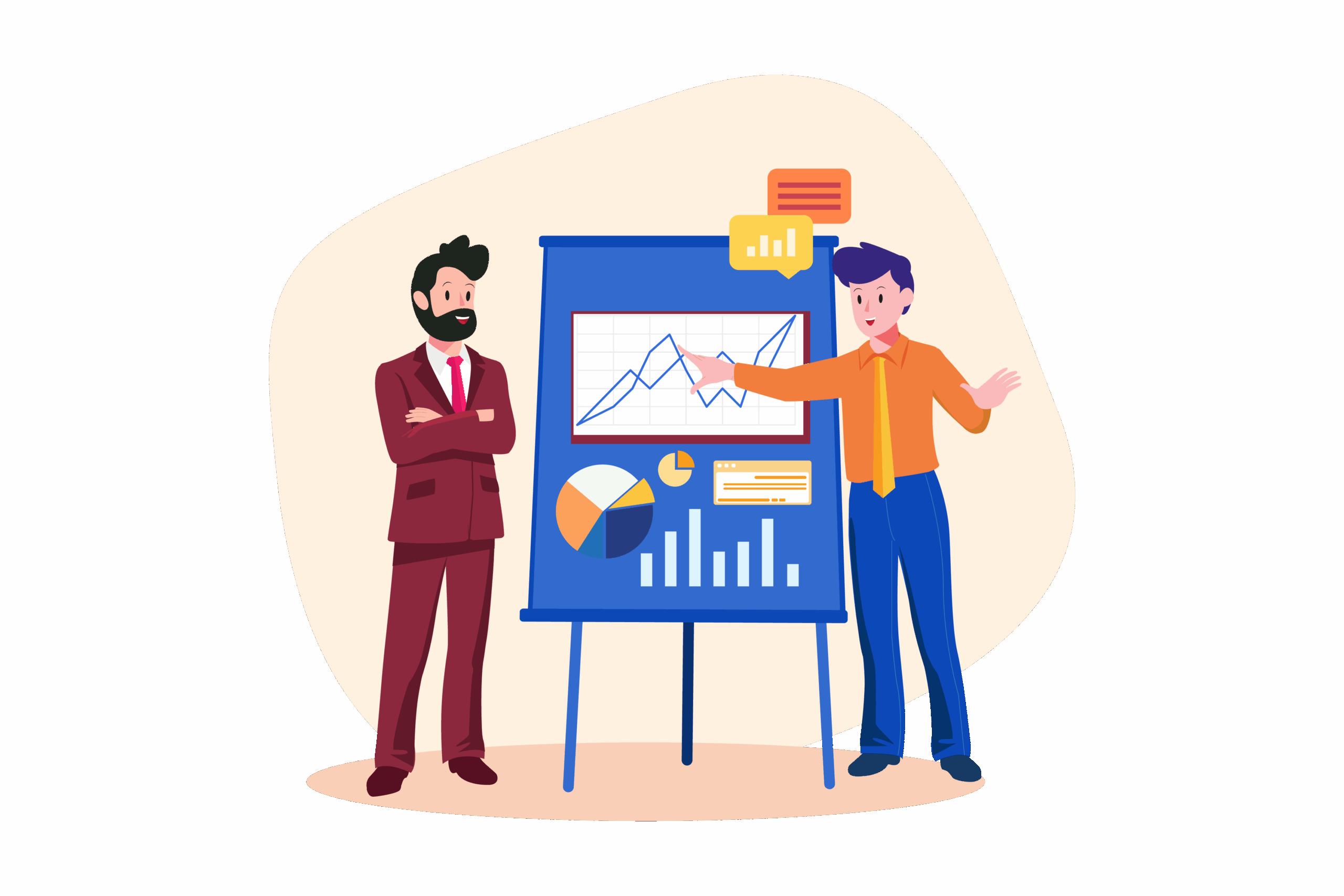
人は、正しさよりも“自分の気づき”に反応する
マーケティングの世界では、「人は自分で気づいたことにしか動かされない」という原則がよく語られます。たとえば、ビジネス書やプレゼン資料でも、データを一方的に示すよりも「あなたはどう思うか?」と問いかけるほうが、読者や聴衆の行動に繋がるという実験結果があります※3。
これは、教育心理学の分野でも「発見的学習(discovery learning)」と呼ばれる原理と重なります。あらかじめ教えられたことより、自分で気づいたことのほうが記憶に残り、応用されやすいのです。
文章も同じです。
「こうしなさい」と書かれた文章は、受け取った瞬間には納得されるかもしれません。でも、「あなたなら、どう考えますか?」と残された文章のほうが、読者の中に“自分の意見”として根付きます。
つまり、読者が“思考の共同執筆者”になる。
文章が与えるものが「情報」ではなく「余白」になったとき、人はそこに自分の視点を重ねるようになります。そこにこそ、読者の行動や言語化が生まれる可能性があるのです。
違和感を残す設計は、ビジネス文章でも有効なのか?
このような「言い切らない設計」は、ビジネスシーンにおいても効果的です。たとえば、私が以前執筆した提案書において、最後の一文をこう変えたことがありました。
Before:「この施策により御社の成長は確実です。」
After:「この施策が、御社の成長をどう支えるか──ぜひご意見をお聞かせください。」
このわずかな違いによって、クライアントからの返信率は大きく変わりました。
「相手に問いを託すことで、言葉は返ってくる」──これは私自身が何度も経験してきた感覚です。
すべてを語るより、「あとはあなたに委ねます」と言える文章の方が、“読者を信頼している”というメッセージにもなります。
そして信頼される文章は、信頼に応えて動きたくなる文章になるのです。
AIと“未完の言葉”を共に作るという選択
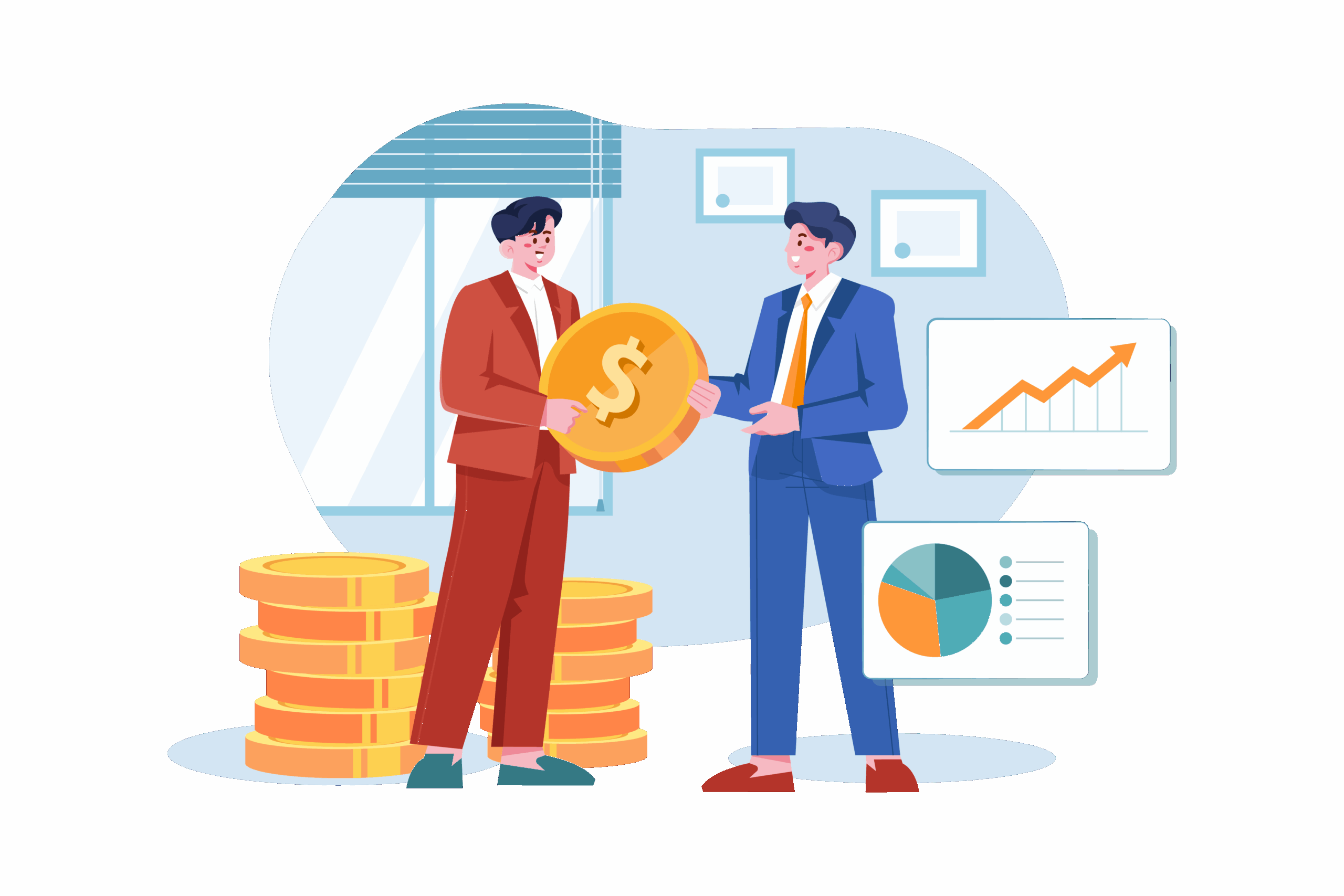
整いすぎるAIと、あえて整えない人間の役割分担
AIを活用したライティングが急速に進化するなか、私たちは今、“整いすぎる文章”という新しい課題に直面しています。
AIは、指定された情報を正確に配置し、構文的な美しさを備えた文章を数秒で出力してくれます。誤字脱字はゼロ、文法も構造も破綻しない。いわば、設計図どおりに建てられた完璧なモデルルームのようなものです。
けれど、そこには“生活の匂い”がありません。
人の言葉には、本来「ためらい」や「矛盾」「語りきれなさ」が含まれているはずです。
私は、AIと文章を共に作るとき、「整えることはAIに任せて、揺らぎは人間が残す」という発想が必要だと感じています。
例えるなら、AIが用意した布に、人間が“わざとほつれた刺繍”を加えるようなもの。
その“ほつれ”にこそ、読者は自分の感情や思考を投影する余地を見出すのです。
誰が書いたかではなく、「どこまで響くか」を問う
私は、AIが書いたか、人が書いたかという区別にはあまりこだわっていません。
むしろ、「その言葉が届いたかどうか」の方が、はるかに重要です。
誰が書いたかというラベルよりも、
その文章を読んだあとに「少し考えてしまった」「なぜか覚えている」と感じられるか。
それが、言葉の持つ“本当の到達点”だと思っています。
AIは、たしかに万能ではありません。
でも、だからこそ私は、その限界の中にある“届き方”の実験を続けたいと思っています。
整っていない言葉にこそ、読者が入り込む隙間があります。
それはきっと、これからのAI活用における“人間の役割”の一つなのではないでしょうか。
ステップ①:あえて“断定しすぎない”
→ 「○○すべきです」ではなく、「○○という見方もあります」といった柔らかい表現を使いましょう。
ステップ②:“問いかけ”で締めくくる
→ セクションやパラグラフの終わりに「あなたならどう考えますか?」「どう感じましたか?」と、問いを添えて余白を作ります。
ステップ③:“語りきらない”勇気を持つ
→ あえて最後まで言い切らず、「……かもしれません」と曖昧な語尾を使うことで、読者の思考を促します。
この3つを意識するだけで、読者の中で“文章が続いていく”ような余韻を生むことができます。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. “疑問を残す文章”って、ビジネスの現場でも使えるのですか?
はい、むしろビジネスシーンでも非常に効果的です。たとえば報告書や提案書でも、結論を押し付けず「どう思われますか?」と問いかけることで、相手の主体的な検討を促すことができます。結果として信頼や共創意識が高まるケースも多く見られます。
Q2. 文章で“余白を残す”って、具体的にはどうやるのですか?
たとえば「〜すべきです」と言い切らず、「〜という見方もできます」「あなたならどう考えますか?」という表現を用いることです。また、文末に「……かもしれません」など“曖昧さ”をあえて残す方法も有効です。これにより読者は自分で考え始める余地を持てます。
Q3. 読者が疑問を持ったままだと、不満につながるのでは?
たしかに誤解を与えないための配慮は重要です。ただし、本コラムで伝えているのは“情報の欠落”ではなく“読後の問いの設計”です。疑問が読者の中で思考へと繋がるよう設計されていれば、不満ではなく「考えさせられた」という読後体験になります。
まとめ──疑問は残していい。むしろ残すべき時代へ
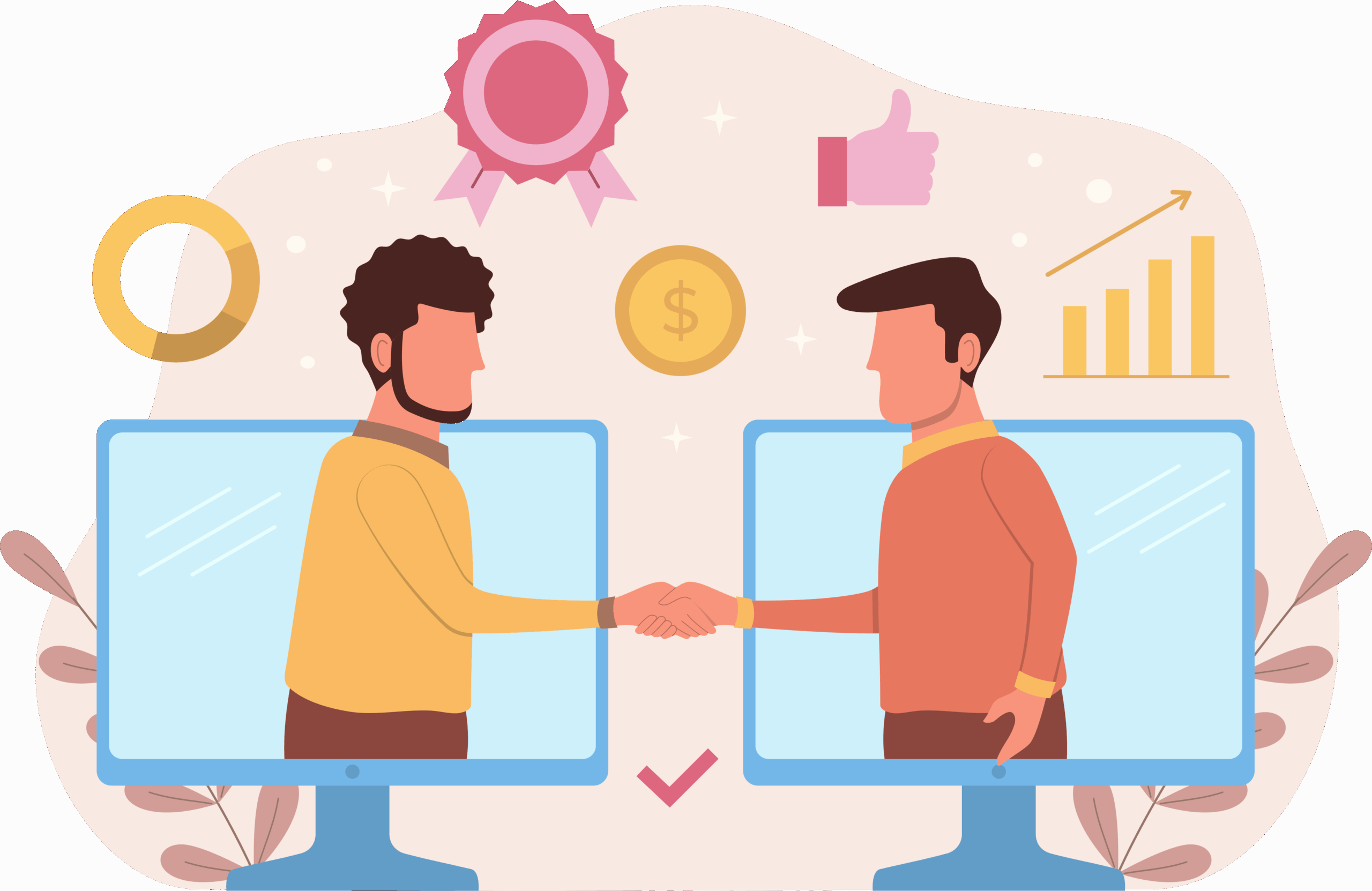
📌 この記事の 3 行まとめ
・整いすぎた文章では、読者の思考は動かない
・疑問や余白こそが“自分の言葉”を生むきっかけになる
・AIの精密さに「人の揺らぎ」を添えることで、文章は届くものになる
すべてを語る時代から、語らない勇気の時代へ
これまでの文章は、「読者に誤解を与えないこと」や「分かりやすく説明すること」が善とされてきました。
しかし今、その前提が少しずつ変わってきています。
情報があふれ、答えが容易に手に入る時代だからこそ、読者は“自分で考える余白”を求めているのかもしれません。
たとえばある企業のコンテンツ分析では、「問いかけ型タイトル」のクリック率が
明確な断定型タイトルより約1.7倍高かったというデータもあります※4。
これは、「分かりきったことを読む」よりも、「自分で結論を探す余白がある文章」の方が魅力的に感じられる証拠です。
すべてを語りきる文章は、完璧でありながら、心の奥には届かない。
むしろ、語らなかったことの中に、語りきれない何かを託す──
その“残し方”が、これからの時代に必要な文章術かもしれません。
人とAIの共創が、文章の新しい深さを拓く
文章は情報を伝える手段であると同時に、「何かを託す行為」でもあります。
そして今、AIが“情報を整える”役割を担えるようになったからこそ、
人間には「整えすぎない勇気」「疑問を託す設計力」が求められているように感じます。
私はこれからも、正しさや完成度ではなく、
「あとからふと、思い出される文章」を目指していきたい。
それは、答えを出しきるのではなく、
読者の中で問いが“芽吹く”ような、そんな言葉たちです。
この文章もまた、何かの正解を押しつけるものではありません。
でも、読んでくださったあなたの中に、
小さな問いが残っていたなら──それこそが、いちばん嬉しいことです。
またお会いしましょう。
出典・参考リンク
- ※1:日経クロステック「AI文章に対する読者意識調査」
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00138/040300002/ - ※2:Bain & Company「Emotional Activation in Digital UX」
https://www.bain.com/globalassets/noindex/2022/customer-activation-whitepaper.pdf - ※3:ERIC database「Discovery Learning Theory」
https://eric.ed.gov/?id=ED204330 - ※4:Backlinko「Headline Clickthrough Rate Benchmarks」
https://backlinko.com/headline-statistics























