こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
「普通でいなきゃ」──
そう思ったことが、一度もない人は、きっといない。
人に合わせる。 場に溶け込む。 目立たないように、ズレないように。
私もそうでした。
「あの人、ちょっと変わってるよね」
そう言われたことがあります。何度も。
はじめは、笑って受け流していました。
でも、どこかで確かに、自分はズレているんだと感じていた。
そのたびに、黙るようになった。
会議でも、空気を読んで発言を引っ込めるようになった。
「普通でいる方が、波風立たない」 ──そんなふうに思うようになったのです。
でも、ある時ふと気づいたんです。
「普通」って……いったい、なんだろう?
よくよく考えると、それは誰かが明確に定義したものじゃなかった。
法律でもなければ、指示されたわけでもない。
「空気」でした。
誰が言ったわけでもないけれど、
“そうするのが当然”というような、無言の圧力。
誰もがその空気を読み合い、 違和感があっても、問いを口にしない。
その空気の中で、私たちは 自分の思考を、 自分の感情を、 少しずつ削っていくのかもしれません。
このコラムでは、
「普通でいよう」として苦しくなってしまった人へ──
あなたの中にある“ズレ”や“違和感”を、 問いへと変える構造について考えていきたいと思います。
「ズレ」は、壊すものではなく、
跳ねるための準備かもしれないから。
「普通であろうとする空気」が問いを止める
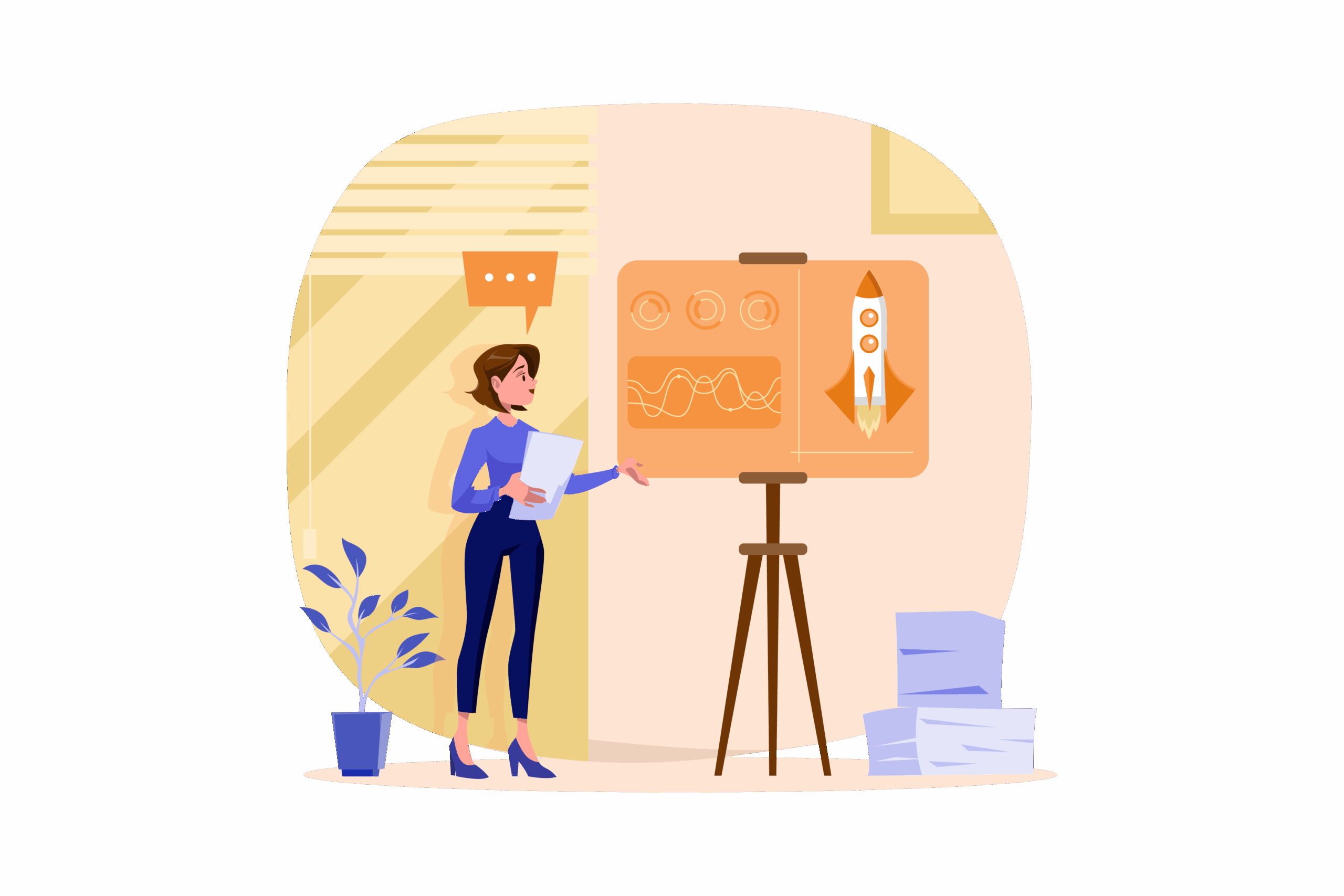
図:職場で問いが出なくなる3つの段階(違和感→沈黙→構造化)
会議中、誰かが当たり障りのない報告をしている。
それに続くように、他の参加者も同じような内容を淡々と話す。
時間は過ぎる。
でも、何も決まらない。
──それでも、誰も「おかしい」とは言わない。
ある調査によれば、 「会議で自分の意見を発言しづらい」と感じる人は全体の6割を超え、 その主な理由は「雰囲気を壊したくないから」であるといいます[1]。
つまり、“問い”を持っていても、 空気がそれを封じてしまうのです。
私の職場でも起きていた、問いの不在
私が以前いた職場でも、何年も続いている定例会議がありました。
発言する人は決まっていて、内容もだいたい似通っていて。
私はその会議に出ながら、ずっとこう思っていました。
「何を決めようとしてるんだろう?」
「これは誰のための時間なんだろう?」
でも、私はその問いを口にしませんでした。
なぜか?
自分の知識が足りないだけかもしれない。
若手が空気を壊すのはよくないかもしれない。
“普通”の大人として、そういう場では黙っておくものだ。
──そう思っていたからです。
数年後、私はその会議を主導する側になりました。
そのとき初めて知ったのです。
あの場にいた全員が、実は分かっていなかったのだと。
- ゴールが明示されていない
- 議論ではなく報告になっている
- 反論を許さない雰囲気がある
- 誰がどう決めるのかが曖昧
──にもかかわらず、
「みんな、普通に進めているから黙っていた」
問いが起きないことが、普通になる
そこには“問いを出さない”ことが、すでに空気化されたルールとして存在していたのです。
問いを出す=空気を壊す=ズレる人になる。
だから皆、黙る。
黙っているのが、善とされる。
これが、普通であろうとする空気が、問いを殺す構造です。
「空気の支配」は、誰も命じない
それは誰かの明示的なルールではありません。
でも、誰もが従ってしまう。
・波風を立てない ・和を乱さない ・ズレないようにする
これらの“普通”を保つことが、 いつしか問いを持たない人間であることに繋がっていく。
そして、組織の中では「思考しないこと」が、 無言の推奨事項になっていくのです。
・全員が“言っていない”けれど“分かっている”
・違和感があっても、「言わないこと」が評価される
・それはルールではなく、“みんなが従っている空気”として支配されている
「ズレている人」が“悪”になる構造
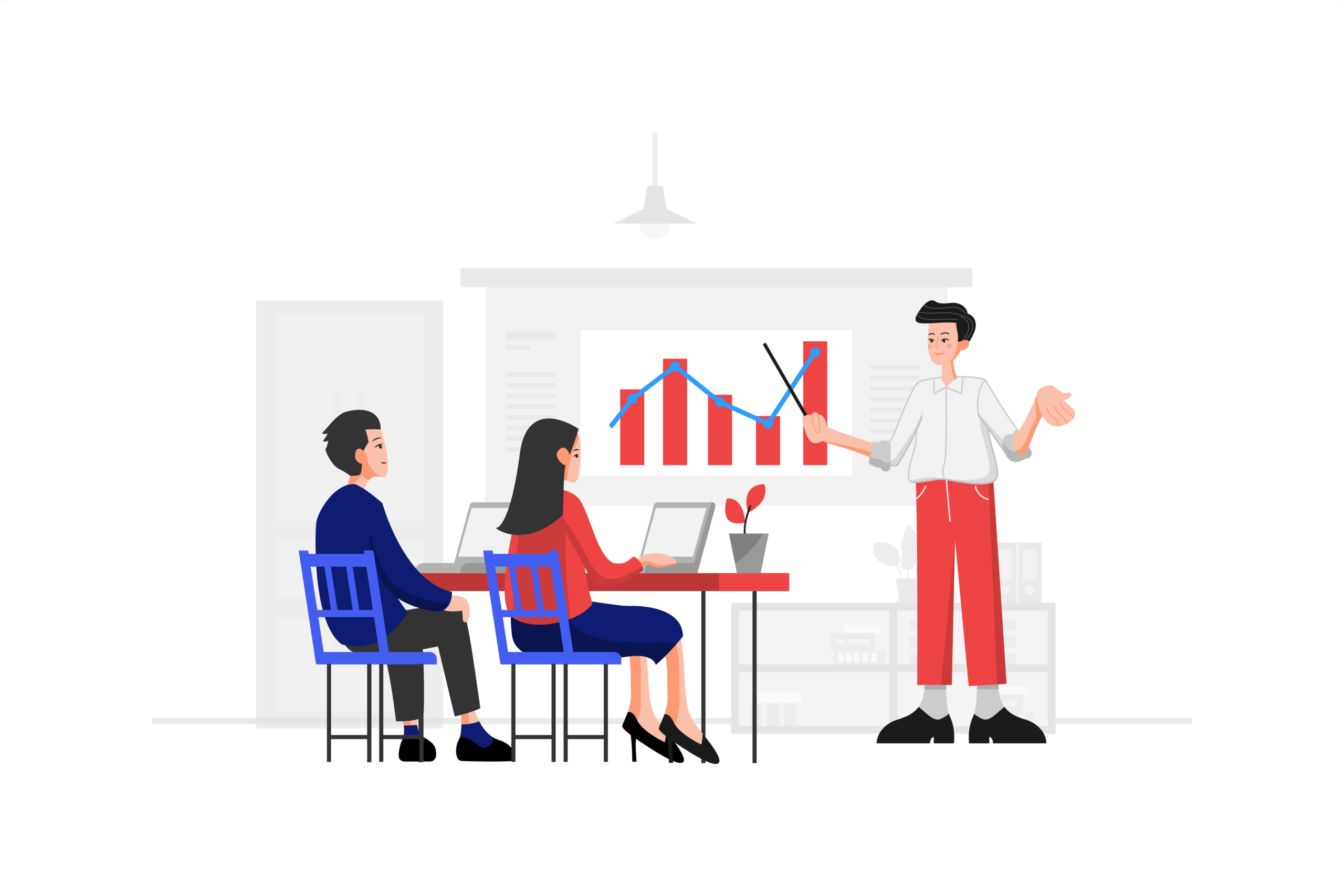
図:ズレている人が“悪”になる構造図解(構造逸脱と空気)
「あの人、ちょっとズレてるよね」
そんなふうに言われたこと、あるでしょうか?
あるいは──誰かに、そう言ったこと。
でも、「ズレている」とは、いったい何からズレているのでしょう?
「普通」の正体は、誰が決めているのか?
「ズレ」とは、基準があってこそ生まれる言葉です。
その基準は、“普通”と呼ばれるもの。
しかし、その「普通」は自然にできたわけではありません。
構造的に、作られてきたものです。
- マクロな普通: 国家・教育・メディア・政策が形づくる“社会通念としての普通”
- ミクロな普通: 組織文化・企業風土・上司の哲学・業界的合意によって形成される“ローカル常識”としての普通
たとえば、企業が「自社に合う人材」を採用し続けた結果、
同じような学歴・思想・生活水準・価値観を持った人々が自然と集まってくる。
その中で形成された「会社の空気」は、 ある意味で“属人的な普通”として機能し始めます。
そこに、異なるバックグラウンドや思考様式を持つ人が加わったとき──
その人は“ズレている”と評価されてしまう。
けれど実際には、
ズレているのは“その人”ではなく、
その場の前提条件と合っていないだけなのです。
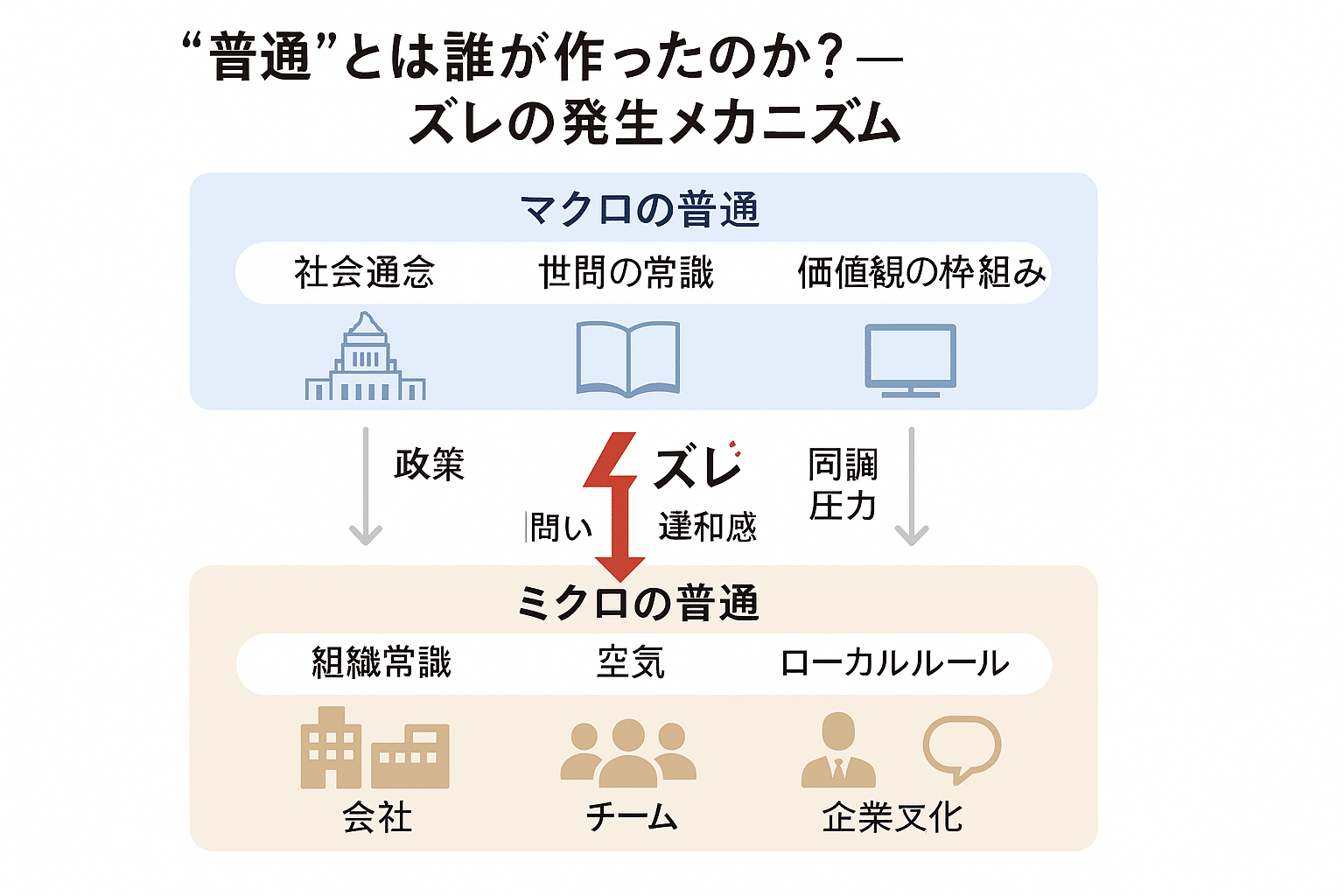
国家や教育、メディアによる「マクロな普通」と、企業や上司による「ミクロな普通」の2層構造を可視化し、ズレが生じる起点を図解化。
「ズレ」は構造との不一致であって、誤りではない
ズレとは、思考力、文化背景、価値観などの“非対称性”によって起きるものであり、 それ自体は間違いでも逸脱でもありません。
ただ、組織が「自分たちにとって快適な普通」を前提に運営されているとき、 そこにフィットしない違和感は“問題”として処理されるのです。
しかもその処理は、明示的ではなく、 空気によって静かに行われる。
「あの人は浮いてるよね」 「ちょっとズレてる感じがする」
その言葉には、問いを持つ者に対する“同調の拒否”が含まれているのです。
ズレは問いの兆し──それを許容しない空気が危うい
ズレる人とは、
「まだ名前のついていない違和感」を最初に感じ取る人です。
問いの種を持っている人。
構造を揺さぶる可能性を秘めている人。
それを排除する場では、問いは起きません。 跳躍も起きません。
人々はズレることを恐れ、自分の違和感を封じ込め、 空気の中で同化していく。
“ズレている人”をどう扱うかが、組織の未来を決める
ズレる人を、排除するか。 それとも、問いの触媒として活かすか。
それを選ぶのは、組織や社会の構造の器です。
ズレが許されない社会では、 誰も違和感を語らなくなる。
そして、思考の停止が「普通」とされていく。
・ズレは“文化的前提条件とのミスマッチ”によって生まれる現象
・構造が固定化された場では、ズレが悪として処理される傾向がある
・ズレを受け入れられる構造だけが、“跳躍”と“問い”を持ちうる
「優しさと模範」が人を押しつぶす
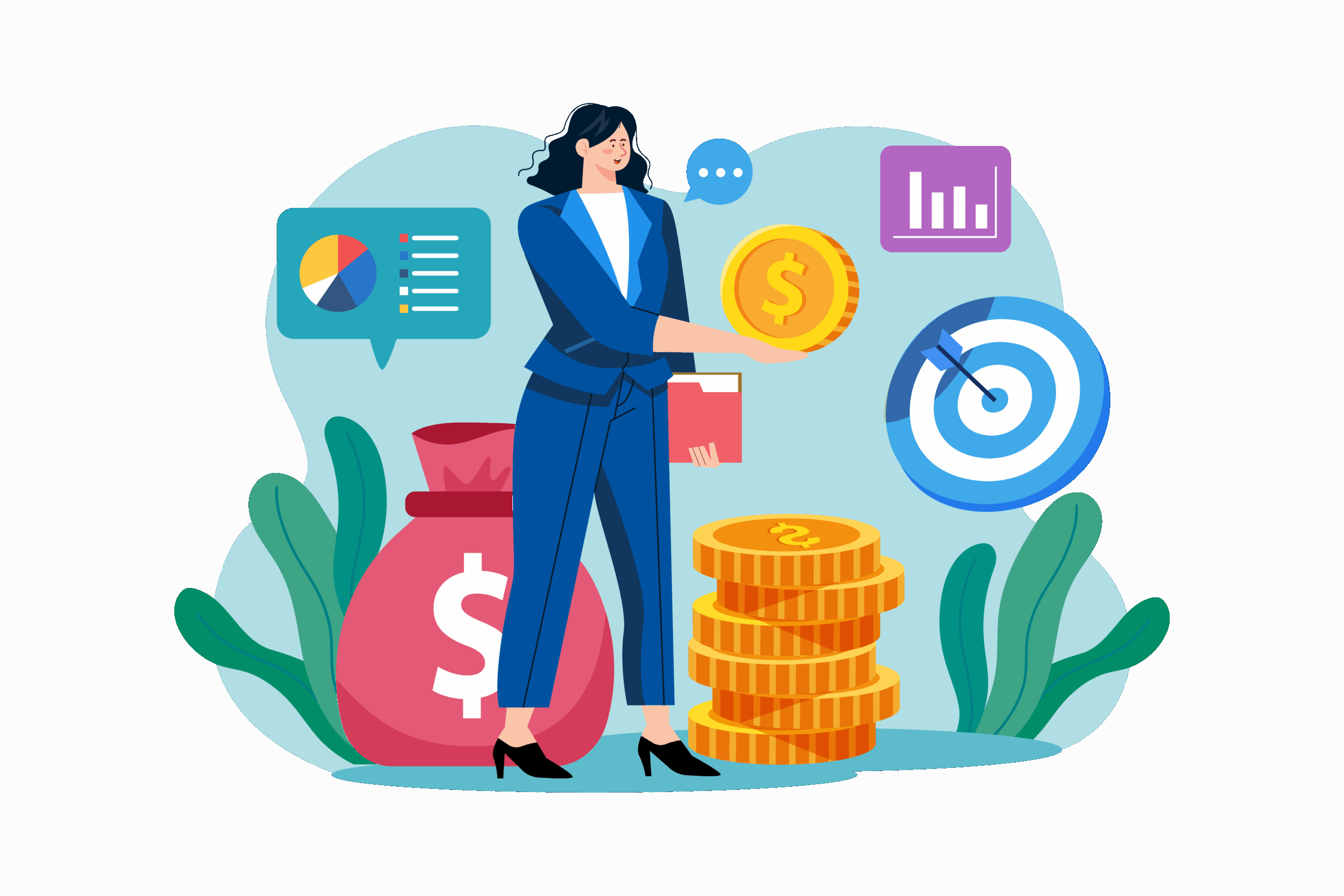
図:優しさと模範が問いを封じる3段階構造
ズレを許容しない空気の中で、人々は“ズレないふり”を始めます。
波風を立てないこと。 誰かを否定しないこと。 みんなと同じように、模範的であること。
──それが「正しさ」として機能しはじめるのです。
「いい人であれ」が内側を静かに壊していく
ズレたときに叩かれた記憶がある人ほど、 次は“ズレないように”と自分を抑えはじめます。
私もそうでした。
職場で「ズレている」と見なされた経験をきっかけに、
次第に私は“模範的な人物”を演じるようになっていきました。
場の空気を読み、怒らず、優しくふるまう。
誰にも指摘されないように振る舞う。
それは「いい人になること」であり、 同時に自分の問いを封じることでもありました。
模範とは、自分を最適化すること。
“ズレないように生きる技術”です。
けれど、その技術は──
人の内側を、静かにすり減らしていきます。
優しさが構造になると、問いは消えていく
もともと優しさとは、感情です。 相手を思いやる、瞬間的な意思です。
でもそれが、「常に優しくあるべきだ」という構造に昇格するとき、
人は“感情”を超えて義務としての模範を演じはじめます。
怒らない。
異論を出さない。
波風を立てない。
そして問いを封じるのです。
「ここではそういうことを言うべきじゃないよね」
「大人なんだから空気読もうよ」
そうやって、場に問いを挿すことそのものが、 “優しくない行為”とされていくのです。
こうして、優しさはいつの間にか問いを排除する空気になっていく。
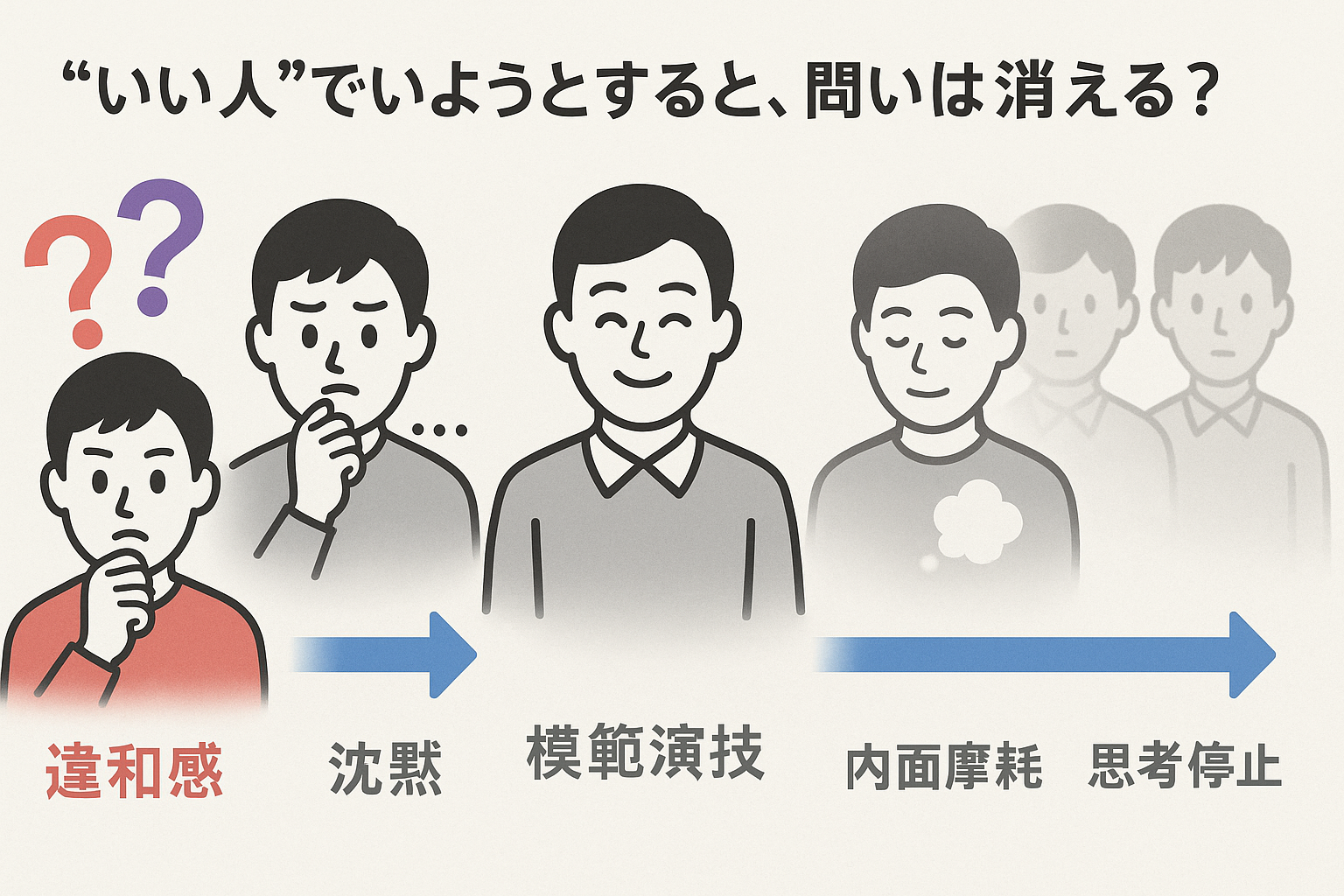
ズレ→沈黙→模範演技→内面摩耗→無風組織 という流れを人物イラストで表現したフローチャート図解。
人には「壊す/設計する/支える」の適性がある
すべての人が、ズレを壊す役割を担えるわけではありません。
誰かが違和感を口にする。 誰かが空気を壊す。 誰かが、問いを拾い、形にする。
その連鎖には、それぞれの適性があります。
- 壊す人: 違和感を恐れずに言葉にする。沈黙を破る役割を引き受ける“初動者”。
- 設計する人: 壊れた空気の中で、問いを構造化し、意味を再構築する“翻訳者”。
- 支える人: 変化によって揺らいだ場に安心を与え、跳躍の揺れを受け止める“地層”。
どれが偉いとか、正しいという話ではありません。
それぞれの型が、問いと跳躍の構造に必要なのです。
問題は、その適性を無視して“模範”を演じること。
私は壊すことにも、模範を演じることにも向いていませんでした。
後から気づいたのは、「構造を見て、言語化して、整理する」こと──
それが、私自身の“設計型”としての適性だったということです。
でも当時は、それを知らなかった。
だから“ズレた人”とされ、“模範”を演じようとした。
そして、その演技は自分自身を静かに壊していったのです。
模範を演じる前に、自分の“違和感”を疑ってみてほしい
問いが出せない場所で、 「いい人でいる」ことは、確かに楽です。
でも、もしその“正しさ”が、 あなた自身の跳躍を押しつぶしているのだとしたら。
模範とは、空気に合わせることではなく── 空気の中に問いの余白を残せる力のことかもしれません。
・模範=最もズレず、空気を壊さない構造維持型の振る舞い
・人には、壊す・設計する・支えるという“構造的適性”がある
・問いが生きる場とは、これらの適性が共存できる空間である
まとめ:ズレを恐れず、“問いの空白”を残せる構造を
「普通でいよう」
その思いは、ときに自分を守る防衛反応になります。
けれどそれが強くなりすぎたとき──
問いは封じられ、 ズレは悪とされ、 模範の中で人は静かに壊れていく。
普通とは、合意と空気によって作られるものであり、 決して“絶対的な正しさ”ではありません。
そしてズレとは、逸脱ではなく、構造と自分の非一致にすぎません。
誰かが問いを持つことで、 ズレが可視化される。
そのズレを「間違い」とするのではなく、 「問いの兆し」として扱える構造を持つこと。
それが、組織にも社会にも、そして自分にも、
跳躍の余白を残してくれるのです。
模範であることに疲れたら、
自分が何に違和感を持っていたかを、もう一度思い出してみてください。
その違和感こそ、あなたが壊れてしまわないための、問いの種かもしれません。
📌 この記事の 3 行まとめ
- “普通であれ”という空気は、問いを封じ、ズレを排除する構造になりうる
- ズレとは逸脱ではなく、構造的な非一致=問いの兆候である
- 模範を演じる前に、自分の“適性と違和感”に耳を澄ませよう
ズレたままでいよう。
それが問いを封じない、自分のかたちだから。
またお会いしましょう。
あわせて読みたい関連記事
よくあるご質問(FAQ)
Q. 普通に合わせるのが“無難”ではありませんか?
A. 一時的には安心につながりますが、問いを封じ続けることで、自分自身が壊れてしまう危険があります。
Q. ズレを口にすると悪者扱いされそうで怖いです。
A. 空気を壊すことは勇気がいりますが、必ずしも正面からぶつかる必要はありません。問いの“形”を選ぶ工夫も大切です。
Q. 自分がどの“適性型”か分かりません。
A. 無理に分類する必要はありません。まずは“違和感をどこで感じるか”に注目してみてください。それが適性のヒントになります。
Q. 模範を演じるのがつらいです。やめてもいいのでしょうか?
A. はい。模範は義務ではありません。構造に問いの余白を残せるあなたのままでも、十分に価値があります。























