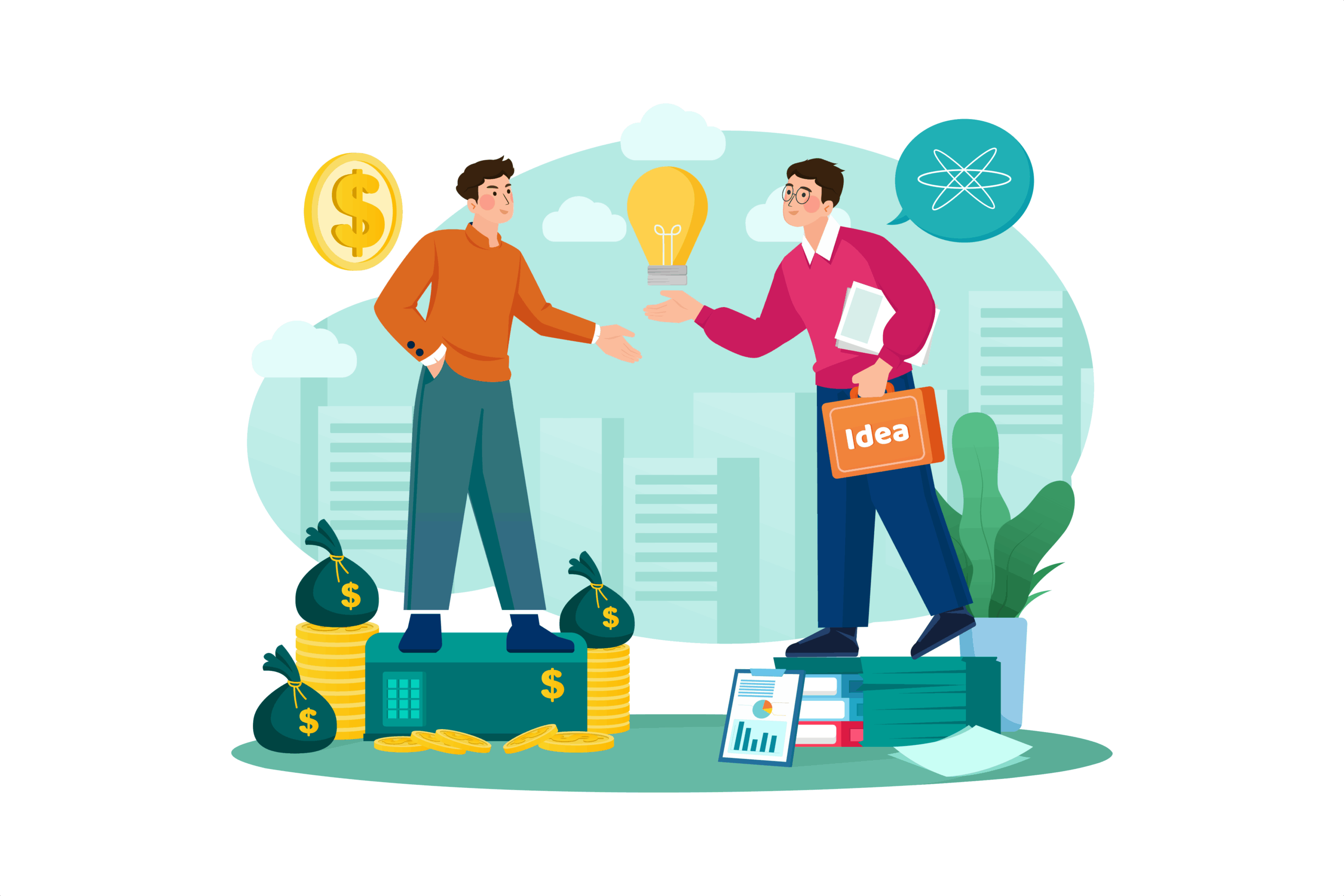パーパス策定ワークショップ:中小企業向け実践ガイド
「そろそろ、うちも理念をちゃんと掲げたほうがいいかもしれない」
そんな声が、社内からも経営者自身からも聞こえてくる──
今、多くの企業で「パーパス」という言葉に再注目が集まっています。
実際、ある時は「AIツール導入は見送ろう」と判断した社長が、
翌月には「今後のために業務自動化を進めよう」と180度方針を変える。
そんな場面は珍しくありません。
意思決定が頻繁に揺れ動く時代。
一貫性を欠いた判断は、社員にとって不安の種になります。
「うちはどこへ向かってるんだろう?」
「この先、この仕事が残る保証はあるのか?」
こうした漠然とした不安が生まれたとき、
掲げられたパーパスが“共通の指針”になっていれば、組織は強くなります。
実際、経済産業省の調査によれば、
Z世代の約7割が「企業の存在意義に共感できないと働きたくない」と回答していることがわかっています[2]。
※出典:経済産業省『未来人材ビジョン』(2022年5月)
……とはいえ、
「パーパスって言われても、何から始めればいいのかわからない」
「正直、カッコいい理念文をつくっても、社内で見向きもされない」
──そんな経営者も多いのではないでしょうか。
この記事では、言葉を整える前にまず、
“会社の中にある感覚”を一緒に見つける──そんな入り口としての
パーパス策定ワークショップの進め方を解説します。
やるべきことは、シンプルです。
「うちらしいな」と思える出来事や判断を、拾い上げていくこと。
社員とともに、それを制度や言語に落とし込んでいくことで、
“自然と納得される理念”が、あとから浮かび上がってきます。
なぜ今、パーパスが必要なのか?
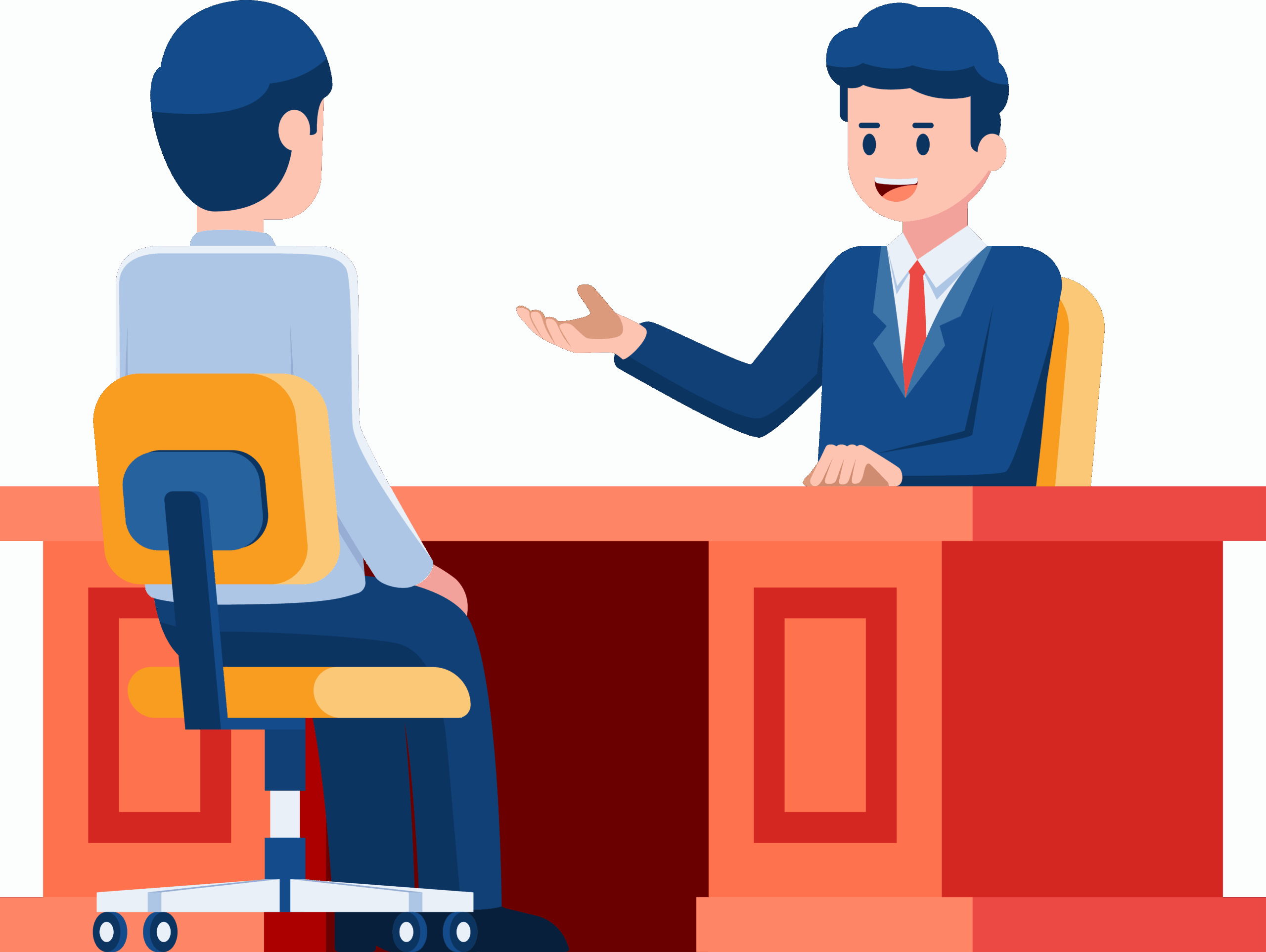
「理念なんて、あってもなくてもいい」──
かつてはそう言い切る経営者も少なくありませんでした。
しかし、変化のスピードが加速し、経営判断の“首尾一貫性”が社員に問われる今、
理念の空洞化=組織の不安定化につながるケースが増えています。
パーパスとは経営の軸を示すもの
たとえば、昨日までは「今は守りだ」と言っていた会社が、
今朝には「やっぱり新規投資だ」と方針を転換する。
それを3度、4度繰り返すと、社員はどう思うでしょうか?
「この会社、大丈夫だろうか?」「自分の仕事は来年もあるのか?」
経営層にとっては合理的判断でも、
現場には“根拠のわからない揺れ”として映ってしまうのです。
こうしたリスクに対し、経営の軸を示すものとして「パーパス」が再注目されています。
ただし、ここで注意すべきなのが、
“言葉ありきのパーパス”は、むしろ逆効果になりかねないということです。
「社員に理念を浸透させよう」と思って立派な文章を作成し、
壁に貼った──
……にもかかわらず、現場では誰も読んでいない。
使われず、語られず、むしろ「白けた空気」が広がってしまった。
こうした事例は、実際に多くの現場で起きています。
実際、HR NOTEの調査では、
“自社のパーパスに共感している従業員は、そうでない人に比べてエンゲージメントが5倍以上高い”という結果が出ています[3]。
※出典:パーパスとエンゲージメントに関する調査結果を発表 | ウォンテッドリー株式会社| HRNOTE”
問題は、「パーパスがあるかどうか」ではなく、
“共感されているかどうか”なのです。
共感されるパーパスのつくり方
では、共感されるパーパスをつくるためには、どうすればいいのか?
答えは明快です。
パーパスとは「つくるもの」ではなく、
会社の中に“すでにある感覚”を言語化する行為であるべきです。
・この会社らしい判断って、どんなときに出ている?
・逆に「うちらしくなかった」と感じた瞬間は?
・新人が入って最初に戸惑うのは、どんなところ?
こうした日常の“ズレ”や“安心”の中にこそ、
その会社の価値観や行動の根拠がにじんでいます。
理念を言語化するなら、まずはそれを拾い上げる。
社員と一緒に、それを確認し、共有する。
それこそが、パーパスを“掲げる”前にやるべき、本当の第一歩です。
言語化しなくてもいいパーパスとは?
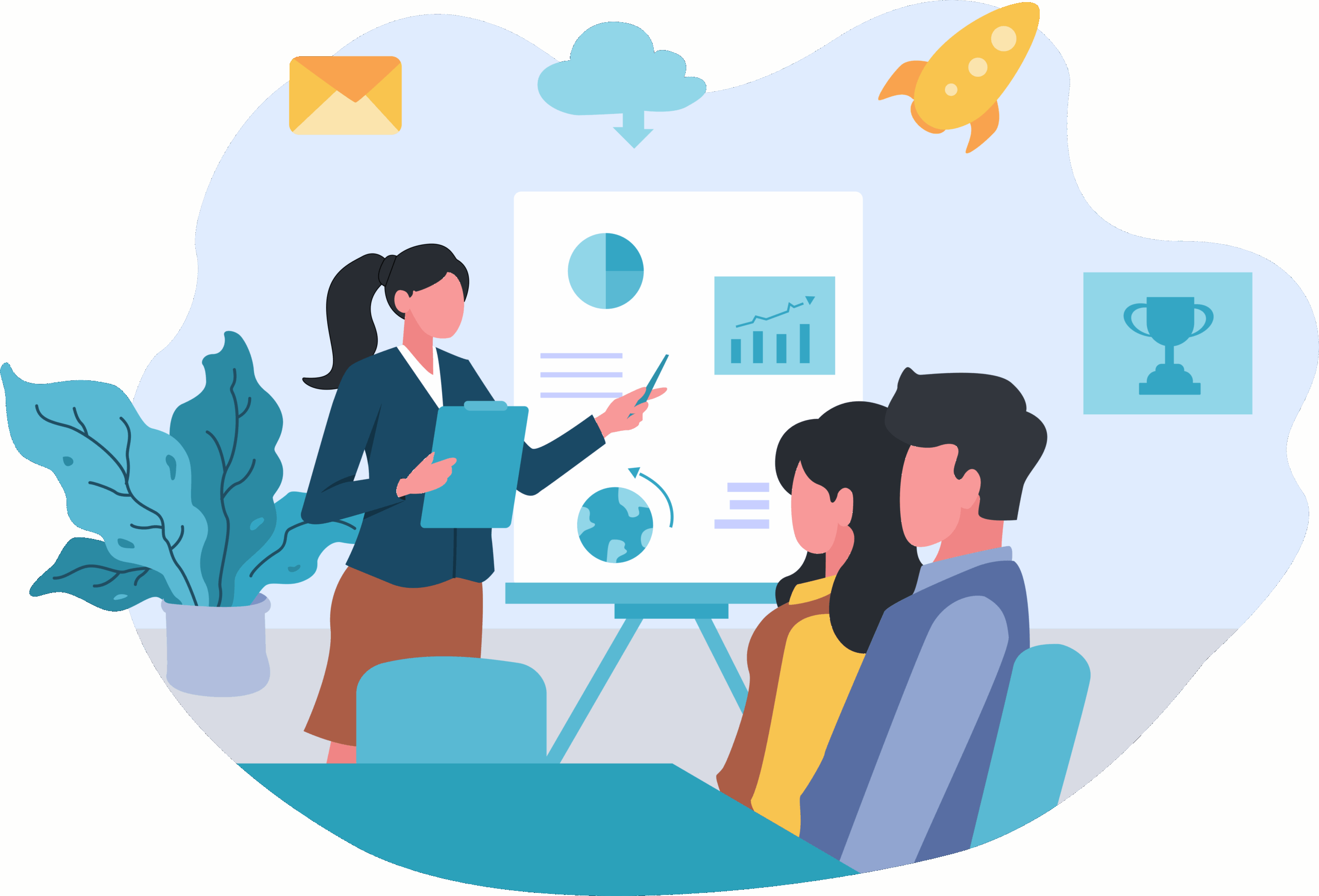
パーパスというと、多くの企業がまず「理念文づくり」に取り組みます。
しかし、「理念を作ったけれど、結局誰も使っていない」という声もまた、多く聞かれます。
理由は明快です。
言葉だけを整えても、それが“社内の感覚”と一致していなければ浸透しないからです。
むしろ、立派な理念ほど、「現場とのズレ」を明確にしてしまうことすらあります。
ではどうすればいいのか?
答えは、パーパスは“つくる”のではなく、“拾う”ものだという視点に立つことです。
具体的には──
- ・「この会社らしいな」と感じる行動や言葉
- ・「これはちょっと違った」と皆が思った瞬間
- ・新人が戸惑った、でも今は慣れてきた“会社特有の文化”
こうした日常の中にある“感覚”を、少しずつすくい上げていく。
それを社員と一緒に「なるほど、そういう空気あるよね」と確認し、
それから必要があれば言語化すればいい。
この順序を守ることが、“共感されるパーパス”の基本構造です。
- テーマ投げかけ:「最近、“うちらしいな”と思った出来事ありますか?」
- エピソード共有: 1人ずつ話す(正解不要)
- 感覚を言い換える:「そのとき、どんな判断が良かったと感じました?」
- 言葉にせず“合意”する: まとめず、「それ、うちっぽい」で終えてOK
目的は言葉を整えることではなく、“感覚の共有”を生み出すことです。
- □ 理念文ではなく「うちらしさ」が社内で語られているか?
- □ 会話の中で「それ、うちっぽい」という言葉が出たことがあるか?
- □ 判断の基準が共有されている瞬間を、実感したことがあるか?
- □ 新人の戸惑いから「らしさ」を見直すきっかけがあったか?
- □ 制度やルールが“感覚”から生まれたことがあるか?
これらが1つでもYESなら、“理念文”より先に、共有の感覚を観察することをおすすめします。
パーパスは、最後に文章にすることが目的ではありません。
社員がその言葉を“自分の言葉として語る”こと──
それを実現するためには、まず社内に流れている感覚を一緒に見つけていくこと。
それが、言語化しないパーパスの出発点です。
ワークショップで“会社らしさ”を拾う方法
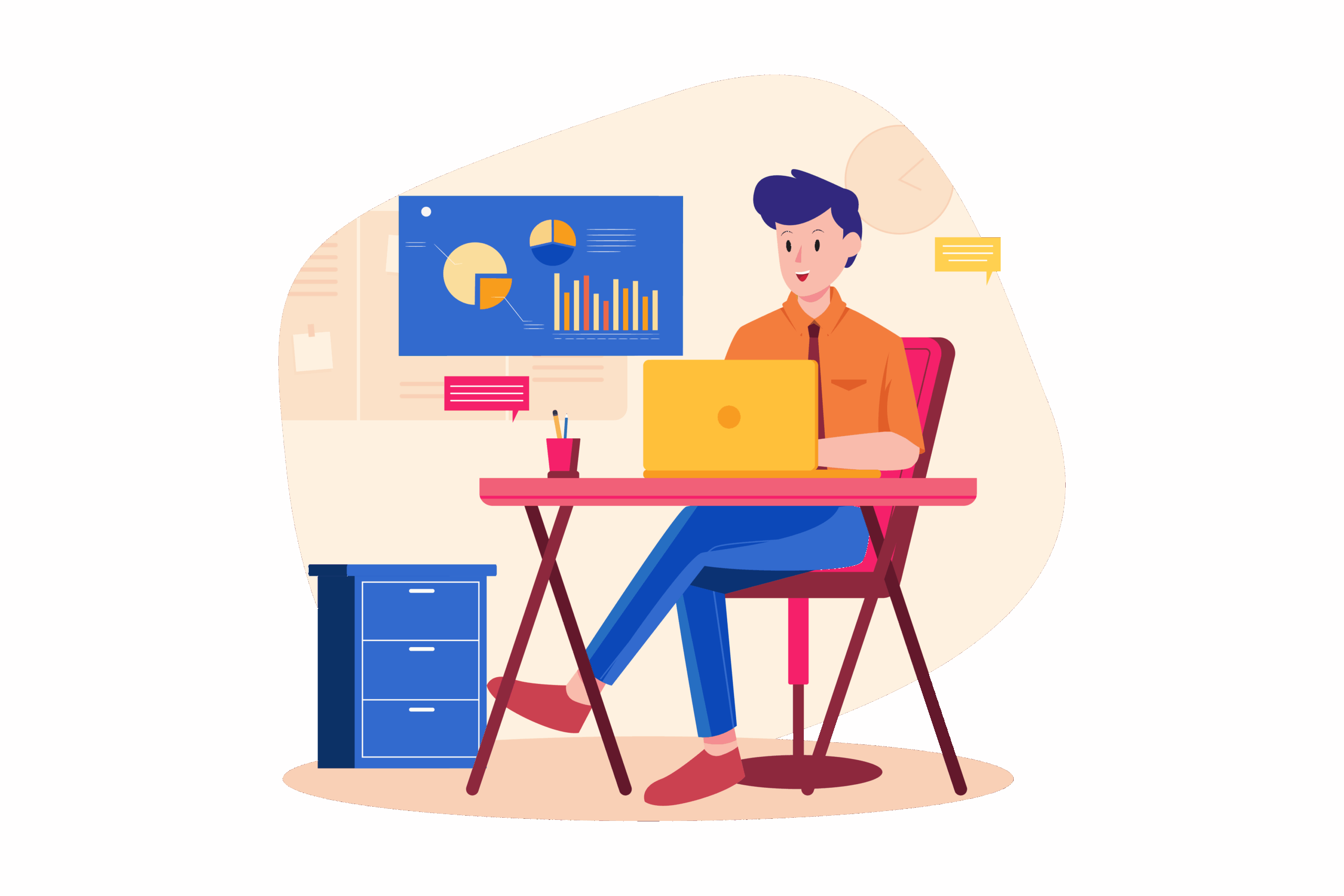
ここからは、実際にパーパス策定ワークショップを行う際に、
「何を問い、どんな場をつくれば、“らしさ”が見えてくるのか」──その具体的な方法をご紹介します。
【STEP①】“感覚を引き出す問い”を準備する
いきなり「うちの存在意義って何だと思う?」と聞いても、
多くの社員は戸惑ってしまいます。
重要なのは、“体験”に紐づいた問いを使うこと。
たとえば:
- ・最近「うちらしいな」と感じた出来事は?
- ・逆に、「それは違う」と思った判断や行動は?
- ・この会社で誇りに思ったこと、家族に話したくなったことは?
- ・新入社員が戸惑いそうな“この会社っぽい空気”って何?
これらは抽象ではなく、日常の中の具体と感情に基づいています。
- □ 答えるのに“役職や正解”が必要ない問いか?
- □ できれば“例え話”で答えたくなるような問いか?
- □ 聞いてすぐ「何となく言えそう」な入り口があるか?
- □ 「誰かの話を思い出す」ような感覚が引き出せるか?
【STEP②】沈黙を怖れず、話せる空気をつくる
良い場には、必ず“沈黙”があります。
「みんな黙ってしまった」──それはむしろ、考えている証拠です。
ファシリテーターは、次のような言葉を使って沈黙を許可してください:
- ・「急がなくて大丈夫ですよ」
- ・「今、ちょっと考えてる時間にしましょう」
- ・「言葉にならなくても、“分かる”ってこと、ありますよね」
正解は必要ありません。
1人の小さなつぶやきや、ため息のような本音から、場が動くこともあります。
【STEP③】言葉ではなく“共通感覚”を持ち帰る
最後にありがちな失敗が、“その場でまとめようとする”ことです。
パーパスワークショップでは、何かを“決める”必要はありません。
おすすめの終わり方は、こんな問いかけです:
- ・「今日の話の中で、“印象に残った一言”はありましたか?」
- ・「今の話を聞いて、“うちっぽいな”と思ったところは?」
この段階では、理念文などなくていい。
むしろ、“共通の納得感”の種が拾えれば、それが一番の収穫です。
- 🗣 正解ではなく、具体的な出来事ベースで話す
- 🧍♀️ 自分の話をしたら、「○○さんはどう?」とバトンをつなぐ
- ✍️ メモは「キーワード+誰が言ったか」を中心に
- 📢 最後は“意見を言う”より、“何かが残ってる感じ”を大切に
「これがうちらしいよね」という“実感”が1つ残っただけで、
そのワークは“パーパスのはじまり”になっています。
そこから少しずつ制度に落ちていけば、
自然と「言葉」が後からついてきます。
制度と行動に“にじませる”設計論
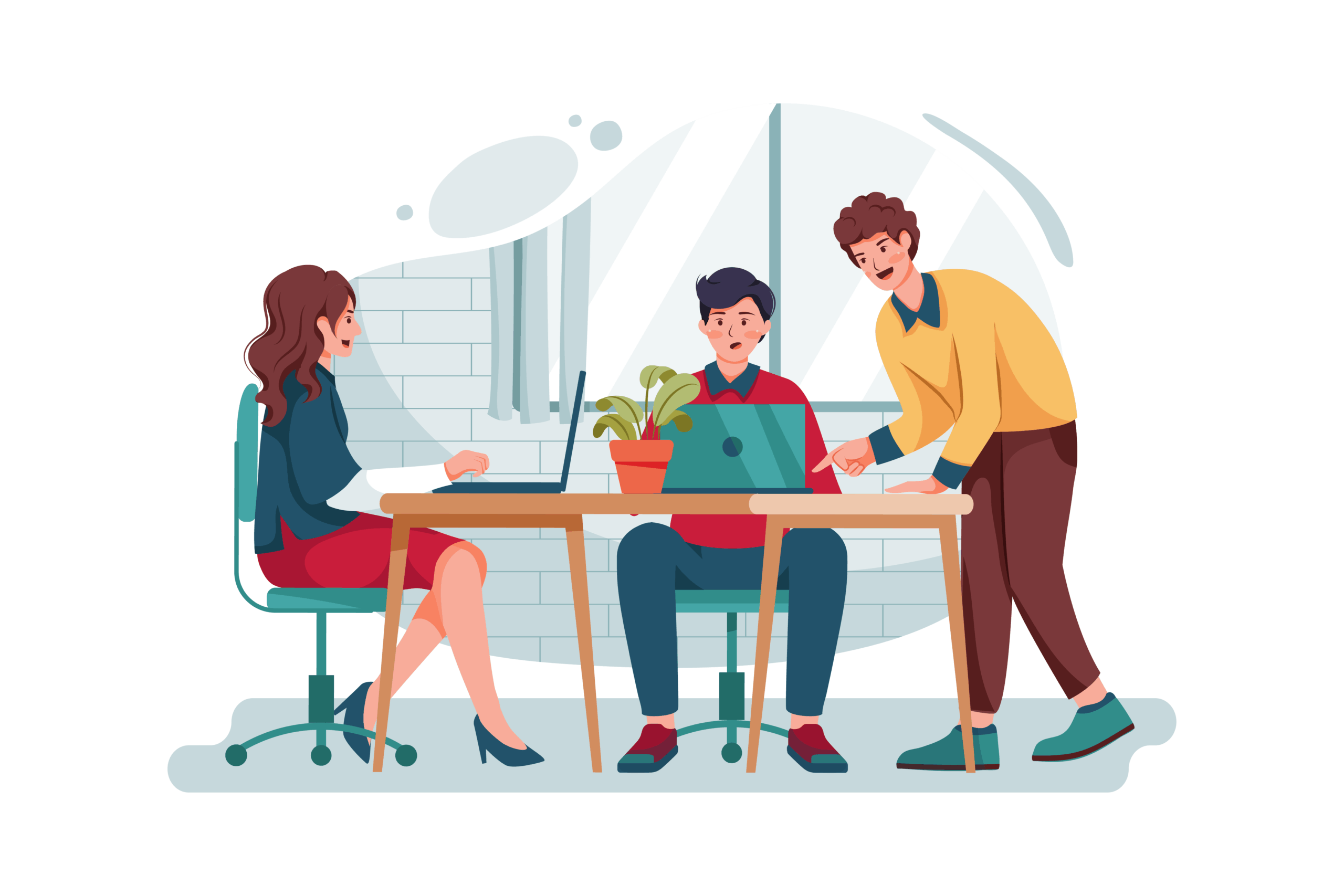
図:“うちらしさ”を行動・制度に翻訳する設計マップ
パーパスがワークショップで浮かび上がったとしても、
それが“制度”や“行動”に落とし込まれなければ、社内には浸透しません。
多くの失敗例では、「理念文はできたけれど、その後何も変わらなかった」
という形で終わってしまっています。
では、どうすれば日常に“にじませる”ことができるのか?
【行動変換の具体例】理念 → 評価 → 日常の言葉へ
- 理念:「誠実であることを大切にする」
- 評価指標:「情報共有の正確性・速度・姿勢」
- 行動支援: Slackで「#丁寧だった対応」タグを導入
- 理念:「スピードを重視する」
- 評価指標:「決断の速さ/改善サイクルの回数」
- 行動支援: 毎週1つ「やってみた報告」を共有
このように、“感覚”だったものを、「どう見えるか」「どう評価できるか」
「どんな支援があれば行動できるか」に分解していきます。
- □ 理念文はなくても「うちらしさ」を語る制度がある
- □ Slackや朝礼など“非公式の場”で判断が語られている
- □ 評価制度に「価値観の実践」を含めている
- □ その行動が「誰でも語れるシーン」で使われている
制度と空気をつなげるのは、“場”と“支援”です。
【注意点】周知ではなく“使われている”ことが大事
パーパスの社内展開で、やりがちな間違いが「発表→浸透」型の一方通行です。
それよりも、「あの話、うちらしいよね」「この判断、合ってたかな?」と
話題に上がること自体が、すでに“共有されている”状態です。
社員の会話の中に、理念の片鱗が出てくるようになったら──
そのとき、パーパスは初めて「浸透した」と言えるのです。
社内で実践するためのパーパスワークショップマニュアル
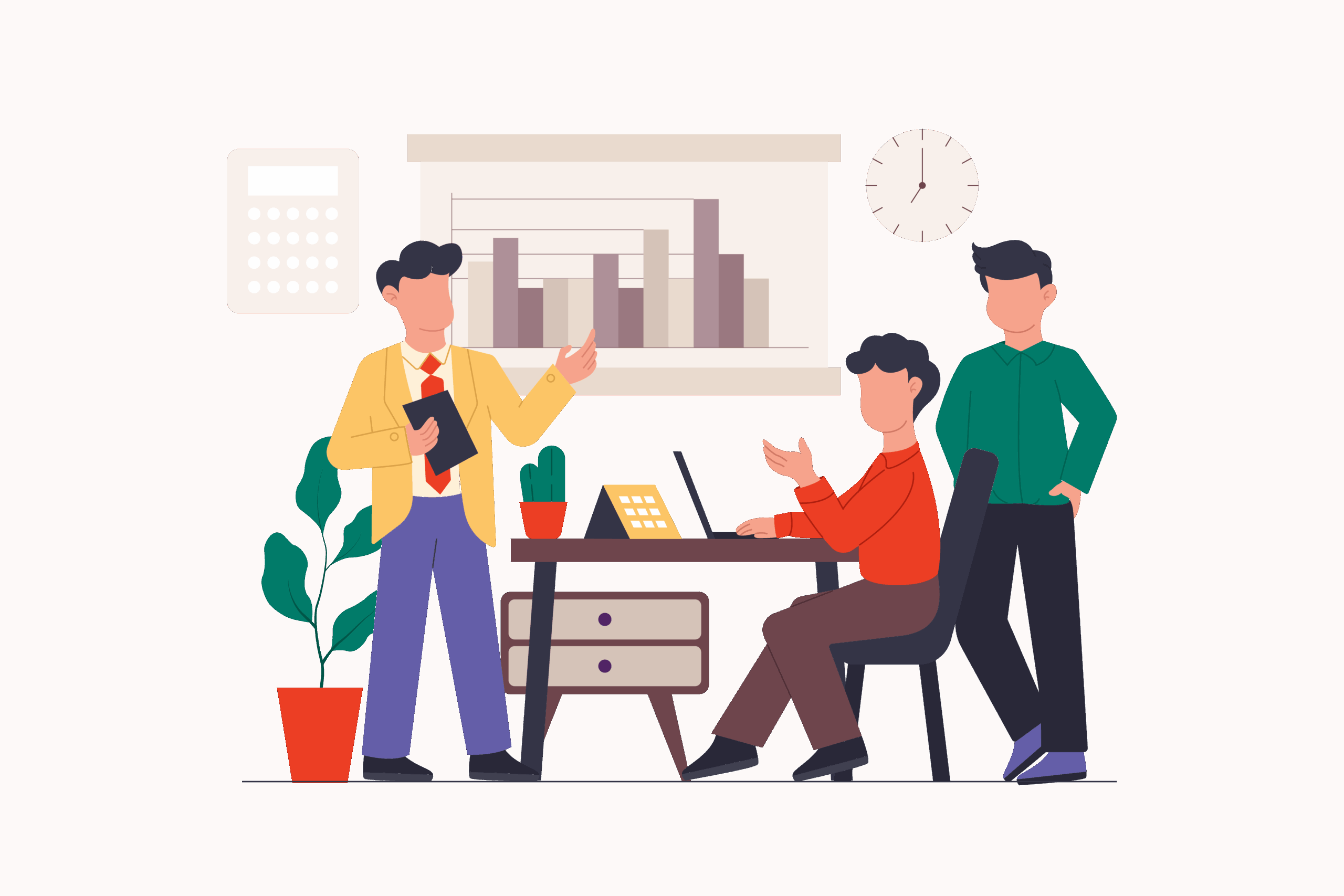
図:ワーク設計・問い・記録を一体化した“にじみ出す”テンプレート構成
ここまで読んで、「やってみたいけど、どう設計すればいいの?」
そう感じた方のために、社内でそのまま使えるワークショップ進め方マニュアルをご用意しました。
どれも実際に支援現場で使用されているもので、
「場を壊さず進める」「無理なく“らしさ”が拾える」ことを第一に設計されています。
特別なスキルやファシリテーション経験がなくても、
“問いを投げるだけ”で共通の感覚が生まれていく──そんなマニュアルに仕上がっています。
本マニュアルを活用することで、「話してよかった」だけで終わらないワークを
社内で無理なく設計することが可能です。
「一度試してみたい」「小さく始めたい」
そんな方は、ぜひ今すぐダウンロードしてみてください。
よくある質問(FAQ)
パーパスとミッション・ビジョンの違いは何ですか?
パーパスは「なぜこの会社が存在するのか?」という根本的な問いへの答えです。ミッション(何をするか)やビジョン(どこを目指すか)とは異なり、判断軸としての土台になります。
ワークショップは外部ファシリテーターが必要ですか?
必須ではありません。社内で信頼されている人が進行できれば効果は十分にあります。ただし、「まとめようとしすぎない」「答えを出させない」空気づくりが大切です。
言語化せずに、制度に落とすだけでも大丈夫ですか?
はい、問題ありません。むしろ最初はその方が“共感が自然に広がる”ケースもあります。言葉にするのはあとからでも可能です。
まとめ:パーパスは“うちっぽさ”の再発見から始まる
「パーパスをつくろう」と思ったとき、
最初にやるべきことは、言葉を整えることではありません。
それよりも、社員と一緒に、
「この会社らしいな」と感じる瞬間を集めてみてください。
その感覚こそが、制度になり、行動になり、
やがて自然に“理念”として語られていきます。
パーパスとは、生まれるものではなく、“残っていたものを見つけ直す”こと。
無理に言語化する必要はありません。
「うちらしさ」が制度や対話の中で語られているなら、それで十分。
共通の実感が残ったとき、
その会社にはもう、ブレない判断の軸が育ち始めているのです。
- 理念づくりの前に、“会社らしさ”を拾う対話が必要。
- パーパスは、日常の判断と制度に“にじませる”もの。
- 言語化は最後でいい。共通の実感が芽生えたら、それが始まり。
理念が“壁の言葉”になっていませんか?
ラプロユアコンサルティングでは、
パーパスを“掲げる理念文”ではなく、“制度と日常の中で自然ににじむ構造”として設計します。
「言葉が社内に響かない」「共感される空気を設計したい」──
そんな悩みを感じたら、まずはお気軽にご相談ください。
参考資料
- [1] Simon Sinek, Start With Why(公式書籍)
- [2] 経済産業省『未来人材ビジョン』(2022年5月)
https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531003/ - [3] “パーパスとエンゲージメントに関する調査結果を発表 | ウォンテッドリー株式会社| HRNOTE”
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/talent/purpose-driven-companies.html