「USPを作りたい。でも“うちの強み”が分からない──」
これは、ある日ぽつりと経営者の方がこぼした言葉です。
セミナーや書籍で「USP=独自の強み」と学んでも、いざ「御社のUSPは?」と問われると、ふと詰まってしまう。
わかる気がしました。私自身、同じように迷ったことがあるからです。
起業したての頃、広告のキャッチコピーを考えていた時期がありました。
いろいろ考えてはみるものの、どれもピンとこない。気づけば、「他と何が違うのか」を言葉にするだけで何時間も悩んでいました。
結局、出てくるのは「丁寧な対応」「迅速なレスポンス」「安心感」──どれも悪くない。でも、“どこかで見たような表現”ばかりでした。
その時ふと思ったんです。
「“私たちらしさ”って、言葉で言えるんだろうか?」
そこから「USPを考える」という作業が、「自分たちの本質と向き合う」時間に変わりました。
本記事では、そんな実感からスタートして
「USPって何?」から、「どう作る?」「なぜ機能しない?」「どう改善すればいい?」まで──
体系的に、でもやわらかく、ひとつずつ紐解いていきます。
USPとは?──あなたを選ぶ“理由の一言”

- USP(Unique Selling Proposition)の本来の意味と定義
- キャッチコピーや強み一覧との違い
- なぜ「USPが言えない」と感じる人が多いのか
USP(Unique Selling Proposition)とは、顧客があなたを選ぶ「明確な理由」のこと。
しかもそれは、企業側が主張する「強み」ではなく、“顧客が実際に語る言葉”として機能するものです。
例えば、あるWeb制作会社は「成果が出るサイト」を謳っていました。
けれど顧客が口にしたのは「初回相談で“数字の話”をしてくれたのがあなただけでした」でした。
USPは、まさにこの“顧客が感じた違い”を言語化したものです。
キャッチコピーと何が違うの?
よく混同されますが、USPとキャッチコピーは役割が異なります。
キャッチコピーは表現であり、USPは戦略の核。前者は見た目や伝え方、後者は存在理由です。
強み一覧とはどう違うの?
「丁寧な対応」「低価格」「品質へのこだわり」……こうした“強みの羅列”は、USPにはなりません。
なぜなら、それらは誰でも言えることであり、「なぜそれがあなた独自なのか」という根拠がないからです。
USPとコア・コンピタンス──“打ち出し方”と“中身の強さ”の関係
USPは「顧客に対して何を約束するか」を示す“外向きの言葉”ですが、その源泉には自社のコア・コンピタンス(本質的な競争力)が存在します。
プラハラードとハメルは1990年の論文で、コア・コンピタンスを「複数市場に応用可能で、顧客に独自価値を届ける源泉」と定義しています。
たとえば、ホンダの「エンジン開発力」は、自動車にもバイクにも芝刈り機にも活かされるコア・コンピタンスです。そこから導かれた「燃費」「耐久性」などが、プロダクトUSPとして言語化されていきます。
USPを考える際に“何を約束するか”に詰まったら、「自社の中にある譲れない強み」に立ち返ること。これが表層コピーで終わらせないための鍵になります。
USPに必要な3つの条件
- 唯一性: 他社と“明確に差がある”ポイントが含まれている
- 顧客視点: 「自分に関係ある」と感じられる文脈になっている
- 一貫性: 言葉だけでなく、実際の提供・導線・営業がそれを体現している
言い換えれば、USPとは── “その一言だけで、顧客が「じゃあ、ここにしよう」と思えるかどうか”に尽きるのです。
USPが機能しない3つの理由──「言ってるのに、伝わらない」その根っこ

「USPをちゃんと考えたはずなのに、売上が動かない」
「“選ばれる理由”を打ち出したのに、問い合わせが増えない」
そんな声を、これまで何度も聞いてきました。
実は、こうした“機能不全”には共通点があります。
多くの場合、それはUSPそのものの言葉選びではなく、構造や運用設計の歪みに原因があります。
現場でのひとこと:
「“安心感”がウリなんです」って言われたとき、ふと思ったんです。
“安心”って、誰にとって? どんな瞬間に? それは何で証明されるのか──。
言葉として通じていても、価値として届いていないことって、意外と多いんです。
1. 月並み化──誰でも言えて、誰の記憶にも残らない
「高品質」「安心対応」「スピード重視」──これらの言葉はたしかに正しい。
けれど、他社も同じように言っているなら、それは差別化ではなく“並列化”です。
USPは“選ばれる理由”です。誰にでも当てはまるものは、「理由」にはなりません。
2. 顧客視点の欠如──「自分ごと化」されていない
自社の努力や実績を語るのは大事。でも、それが顧客の課題や欲求に接続されていなければ──
どれだけ素晴らしくても、伝わりません。
USPは「言いたいこと」ではなく、「言われたいこと」を考える視点から生まれます。
ロッサー・リーブスは著書『Reality in Advertising』の中で、USPの条件を次の3つと定義しています。
- ① 魅力的なベネフィット: 顧客にとって重要な利益を提示すること
- ② 独自性: 競合には提供できない特徴であること
- ③ 証明可能: その主張を実際の製品・サービスで証明できること
3. 実態とズレている──“期待”が裏切られる構造
「即日対応」と謳っていて、実際の納期が3日。
「成果を保証」と言いながら、その定義が曖昧だった──そんなズレが、顧客の信頼を静かに削ります。
USPが機能するためには、それが体験として一貫していることが必要です。
- ① 月並み化: 記憶に残らず、他と比較される
- ② 顧客視点の欠如: 「自分ごと」にならず、響かない
- ③ 実態とのズレ: 言葉と体験が噛み合わず、期待を裏切る
だからこそ、USPは「一文で考える」ものではなく、一貫して実装される“体験構造”として捉える必要があるんです。
フィリップ・コトラーは、差別化戦略の核心を「顧客が競合ではなく自社を選ぶ理由を、明確に提示すること」と定義しています。
これはまさにUSPが果たす役割そのものであり、戦略マーケティングの本質です。
(参考:コトラー公式|ポジショニング戦略)
USPの作り方──5ステップで“伝わる強み”に育てる
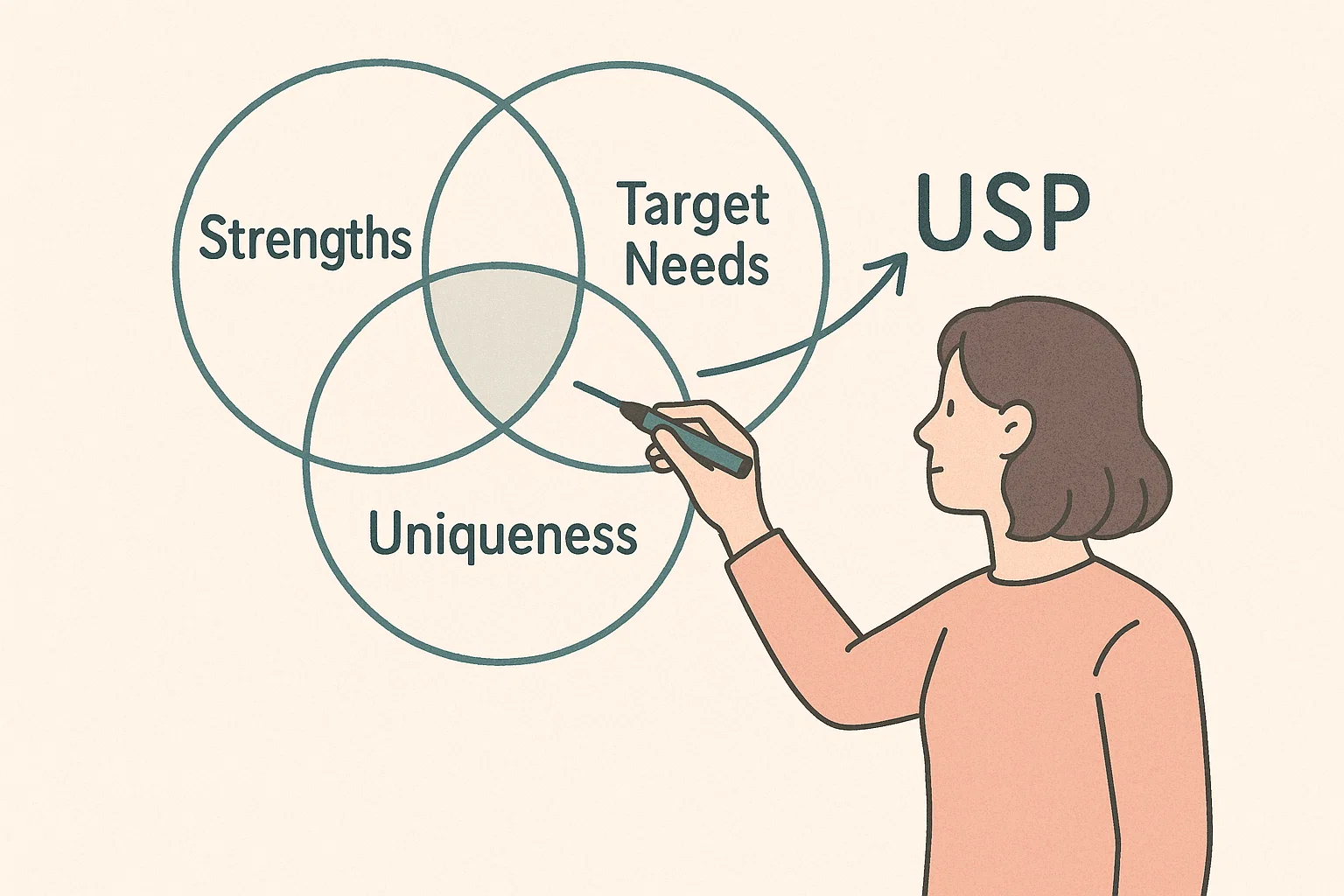
「何を打ち出せばいいかわからない」
「書き出してみても、全部ふわっとしてしまう」
私も、最初はそうでした。強みを語っているつもりなのに、“選ばれる理由”にはならない。そんな違和感だけが残っていて……。
だから、言葉を整える前に“視点の順番”を整えることにしました。
すると、伝わる言葉が生まれやすくなったんです。
以下では、実際に私が使っているワークをベースに、USPが“自然に浮かび上がる構造”をご紹介します。 ぜひ、紙とペンを使いながら一緒に進めてみてください。
- 自社の「選ばれる理由」を言語化できるようになる
- ワークを通じて、現場目線での強みを言葉にできる
- USPを“一文で語れる”レベルにまで仕上げる
Step 1. 顧客の「決め手」を拾う
過去10件の顧客に「なぜ、うちを選びましたか?」と聞いてみてください。
大事なのは、“顧客の言葉そのまま”でメモすること。
たとえば──
「話が分かりやすかった」「初回で道筋が見えた」「他より対応が早かった」など。
これらはすべて、「選ばれた理由」です。
- 顧客1:○○○○(選んだ理由)
- 顧客2:○○○○(選んだ理由)
- 顧客3:○○○○(選んだ理由)
Step 2. 競合と“差がつく切り口”を洗い出す
競合3社のWebサイトや広告を眺めながら、どんな訴求をしているかを書き出してみましょう。
「自社がやっていて、他社がやっていないこと」=空白領域が見えてきます。
- A社:即日対応/価格訴求
- B社:専門性/実績
- C社:地域密着/人柄重視
- 自社:○○○○(まだ語られていない要素)
Step 3. 「自社ならでは」を交差させる
ここで視点を交差させます。
・顧客が決め手にしていること
・他社がやっていないこと
・自社が得意としていること
この3つの重なりに、USPの種があります。
- 決め手(顧客):「話が早かった」
- 自社の強み:「初回相談で具体的なスケジュールを提示」
- 競合がやっていない:「その場で手順まで示せる人がいない」
Step 4. 一文にまとめる
ここまでくると、自然と“言葉のカタチ”が見えてきます。
型は、「誰に|何を約束|どう証明」の3点セット。
たとえば──
「初めて起業する方に、最短3日で開業。実績120社以上、手順書つきで不安ゼロ」
これが、USPです。
・ターゲット:○○さん向けに
・約束する価値:○○を○○します
・証拠:○○という実績・仕組み・声
Step 5. 実装と検証
できあがった一文を、Webサイトのトップや営業トーク、名刺などに使ってみてください。
反応率(CVR)や、成約時の「決め手」にその言葉が出てくれば、機能している証拠です。
ある日の出来事:
作り直したUSPを名刺の裏に載せたあと、ある経営者の方にこう言われました。
「この一文、すごくいいですね。実はこれが決め手でした」
あのときの嬉しさは、今もはっきり覚えています。言葉って、届くときは、一瞬なんですね。
- ① 魅力的なベネフィット: 顧客にとって意味のある利益を提示
- ② 独自の提供: 競合にはない、自社だけのもの
- ③ 証明できる主張: 根拠・体験・証明が可能な内容
- USPは「言いたいこと」ではなく「言われたいこと」
- 顧客の言葉から始め、交差点で磨く
- 「誰に|何を|どう証明」で、言葉に命が宿る
USPは“打ち出し”で終わらない──STP・4P・PTAFとの接続
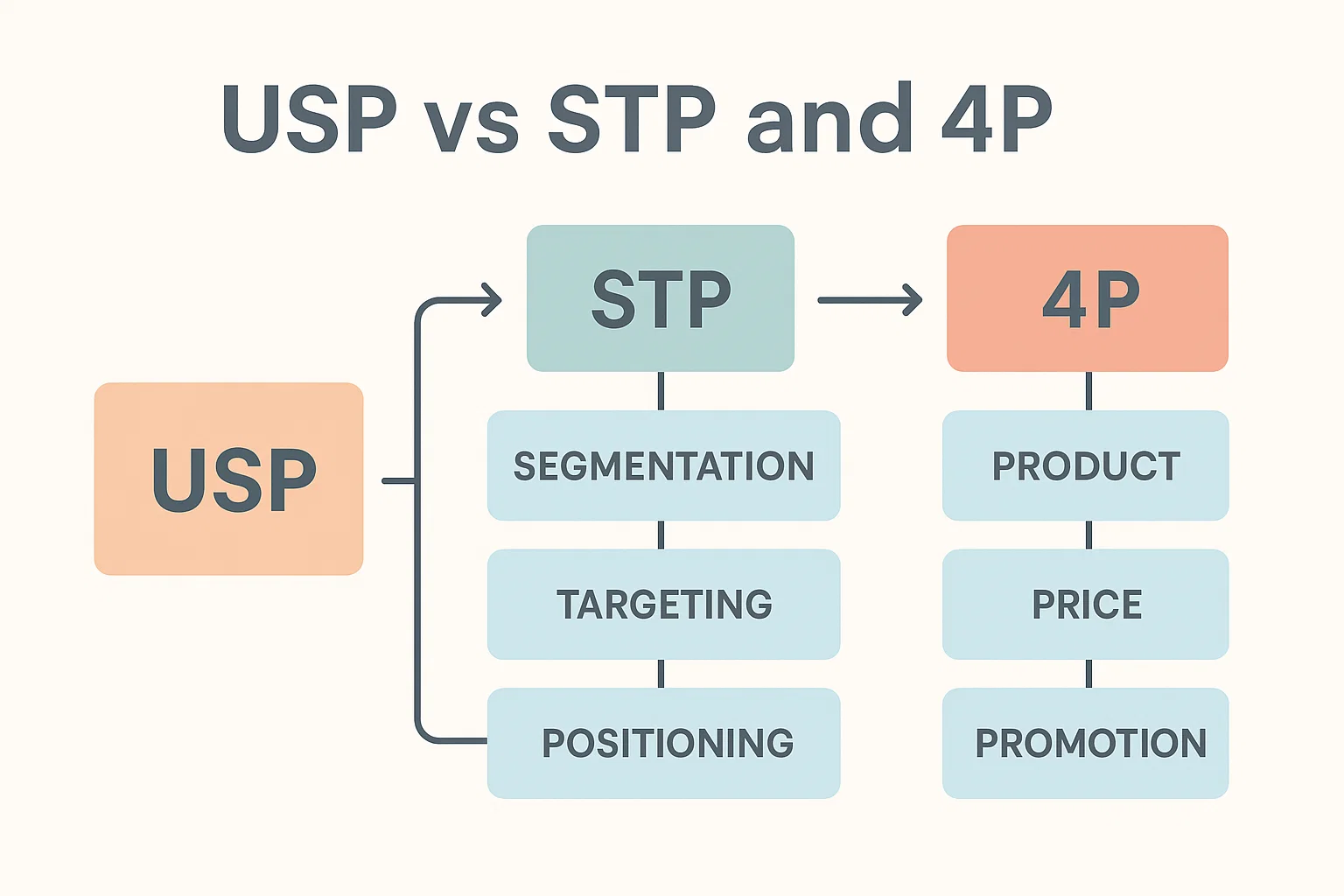
「USPができた。あとは発信するだけ」──そう思っていた時期が、私にもありました。
けれど実際は、打ち出すだけでは成果は出ない。むしろ打ち出した後の構造こそが勝負なのだと、実感する出来事がありました。
あるクライアント企業では、「最短3日納品」をUSPとして掲げていました。
しかし、価格表には納期記載なし、導線のLPでは“品質訴求”が強く、商談では「一週間でOKです」と話す営業もいたんです。
結果、「どれが本当なんですか?」という問い合わせが増え、商談化率も落ちてしまいました。
その時、あらためて確信したんです。
USPとは言葉だけでなく、構造全体に一貫性を持たせなければ意味がないのだと。
- USPは「発信」よりも「整合性」で効いてくる
- 戦略構造(STP・4P)との一貫性が求められる
- 体験に沿って約束が実感されると、信頼に変わる
STP──“誰に対して、何を届けるか”の中核にUSPを
USPは、マーケティングの3要素 STP(セグメンテーション・ターゲティング・ポジショニング)のうち、P=ポジショニングの核に位置します。
つまり、「誰に向けて/どのポジションで/何を約束するのか」を明確にする言葉です。
ターゲットが曖昧なUSPは、誰にも刺さらない。
一方、明確なSTP構造に基づいたUSPは、選ばれる“理由の地図”になります。
HubSpot社の調査によれば、「明確なUSPを打ち出している企業」は、ウェブサイトのCV率が平均で72%高いという結果が出ています。
実際、あるBtoB製造業(中堅部品メーカー)は、「月産10万個×国内即納3日」というUSPを前面に出したことで、見積もり依頼件数が前年比で28.6%増加しました。
競合が納期や規格で横並びだった中、“スピード×信頼性”の組み合わせが効果を発揮した好例です。
4P──言葉と体験が一致しているか
USPが効かない理由のひとつは、言っていることと、実際の体験がズレていることです。
その整合性を点検するために、4P(Product・Price・Place・Promotion)の視点が有効です。
- Product: USPに合った商品設計や特徴があるか
- Price: 価格設定は、期待する価値と一致しているか
- Place: 実際に届ける流通・提供方法に矛盾はないか
- Promotion: 発信している言葉や媒体は、約束とズレていないか
私が見てきた中で、“一番信用を失う瞬間”は、「言ってたことと違う」と気づかれたときです。 USPは、信頼構築の起点でもあるのです。
PTAF──顧客の変化までデザインする
最近では、「顧客が“行動を起こす”構造」として、PTAF(Promise → Trigger → Action → Feedback)というフレームが注目されています。
USPはこの中で、P=Promise(約束)の役割を担います。
・Trigger(きっかけ)は広告や接触機会
・Action(行動)は問い合わせや申込み
・Feedback(評価)は体験後の印象や再購入意欲
そのすべての流れの出発点が、USP=“言葉にされた約束”なんですね。
だからこそ、USPは「書いて終わり」ではなく、 行動と印象を変える“変化設計の第一歩”として機能させる必要があると、私は思っています。
- USPはSTPのポジショニングとして機能する
- 4Pを通じて言葉と体験を一致させると、信頼が生まれる
- PTAFモデルでは、USPは顧客の行動を動かす約束になる
USP成功事例(5社)と、そこに見えた共通構造
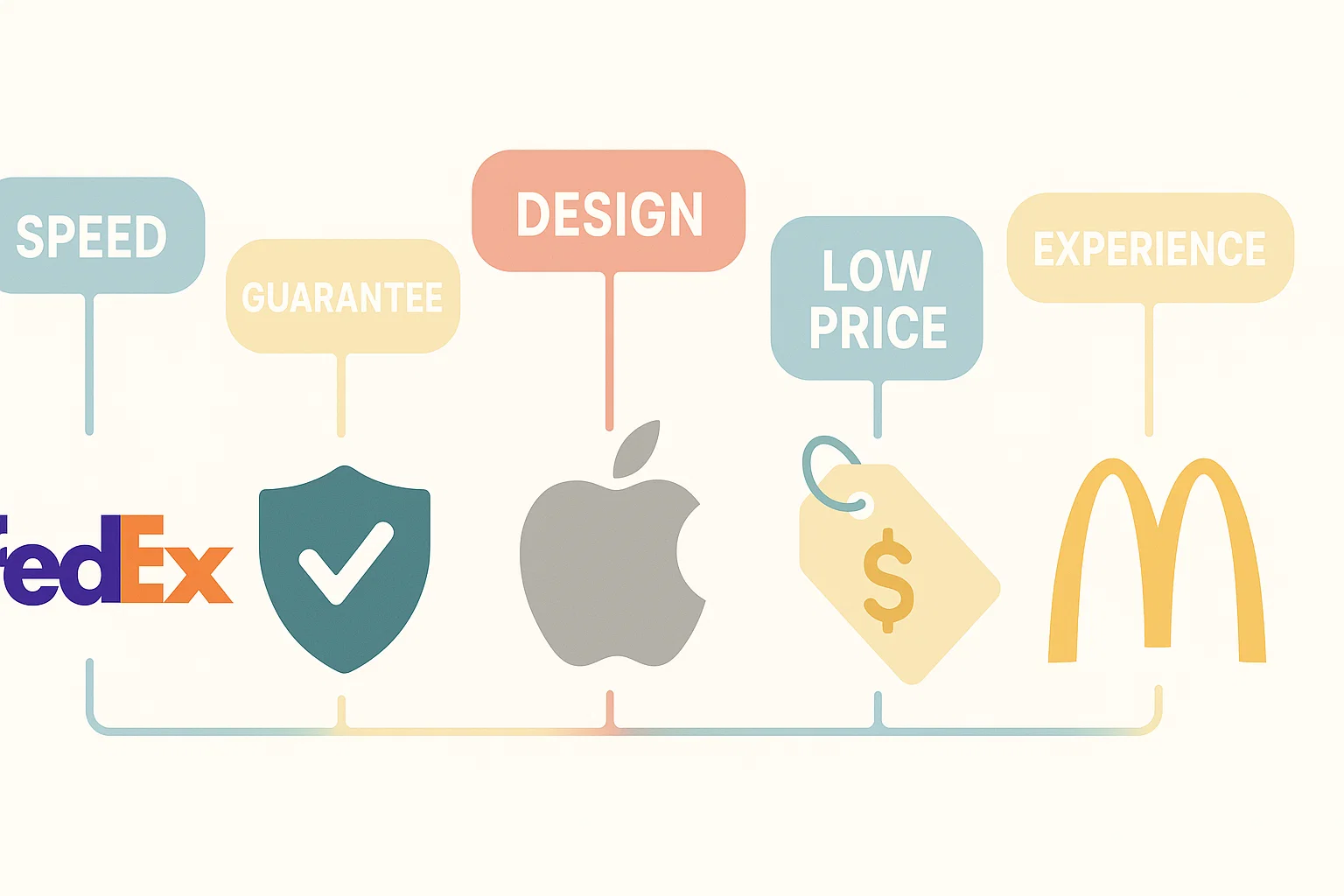
「USPは言葉だけじゃない」──その意味が最も伝わるのは、成功企業の“構造ごと見る”ときかもしれません。
ここでは、明確なUSPによって独自の地位を築いた5社の事例を紹介しながら、実装・体験・差別化の視点で読み解いていきます。
事例1:QBハウス ─ USP「10分の身だしなみ」
顧客ターゲット: 忙しい通勤者・時間効率重視層
差別化要素: 所要時間の短縮+駅ナカ立地
実装KPI: 1店舗あたり1日40〜50名回転/顧客満足度90%以上
「安い・早い・そこそこ」の概念を逆手に取り、“時間こそ価値”というターゲットに絞り込んだ構造。
待ち時間の可視化やチケット制など、体験全体がUSPを裏切らない設計となっています。
事例2:ドミノ・ピザ ─ USP「30分以内で無料」
顧客ターゲット: 宅配ピザで「遅い」に不満を持つ層
差別化要素: 時間保証によるリスク逆転の提供
実装KPI: 宅配平均28分/時間保証適用率2%未満
「遅い」が当たり前だった業界に、“届かなければ無料”という挑発的な約束を提示。 実際にはほとんど無料にはならないが、顧客の不安を逆転させるUSPとして強力に機能しました。
事例3:RIZAP ─ USP「結果にコミットする」
顧客ターゲット: 明確な成果を求めるダイエット層
差別化要素: Before/Afterの視覚証拠+返金保証
実装KPI: 成約率35%→46%(6か月後)/継続率70%超
「痩せたい」ではなく「確実に痩せたい」という層をターゲットに、“結果保証”と“可視化”で信頼を構築。
ビジュアル・返金制度・専属トレーナーという一貫した体験構造が、USPを説得力あるものに仕立てています。
事例4:Dyson ─ USP「他社の3倍の吸引力」
顧客ターゲット: 掃除機の性能にこだわる層
差別化要素: 数値化された性能比較+革新的デザイン
実装KPI: 発売初年度シェア5%→3年で15%
物理的性能である“吸引力”を全面に押し出し、誰もが理解しやすい単一訴求×証明のスタイルを徹底。 「デザイン家電=中身が弱い」という印象を払拭し、プレミアム価格でも納得されるブランドになりました。
事例5:IKEA ─ USP「おしゃれ家具を低価格で」
顧客ターゲット: 若年層・新生活層
差別化要素: DIY組立によるコスト削減+大量仕入れ
実装KPI: 平均客単価12,000円/再訪率60%
「安い家具=ダサい」の常識を壊し、「安くて映える」ラインを確立。
DIY前提の組立/ショールーム体験/倉庫直結など、すべてがコストカットとブランド世界観に直結した設計です。
共通点に見える「USP構築の公式」
こうしたUSP成功企業に共通しているのは、顧客の“記憶に残る違い”を数値や体験で証明している点です。
フィリップ・コトラーは、競争優位の三戦略のひとつに「差別化戦略(Differentiation)」を挙げ、「認知された違いこそが価格ではなく価値で選ばれる根拠になる」と説いています。
まさにUSPとは、その“認知される違い”を言葉・体験・構造で再設計するフレームなのです。
5社の事例には、以下3つの共通構造が見られました。
- ① 尖らせる: 「誰に」「どんな体験を約束するか」を一点集中
- ② 証明できる: 数字/保証/体験フローなど、納得の根拠がある
- ③ 実装されている: 言葉が“現場と一致”しており、顧客がその通りに体感できる
「USPを設計して機能させている企業」は、いずれも“言葉”ではなく“仕組み”で証明しています。
詳細な事例解説や数値データについては、Copyblogger|USP完全ガイドも参考になります。
USPは、言うだけでは信じられません。
一貫した体験構造があって初めて、「あぁ、たしかにそうだ」と腑に落ちる。
そこにこそ、選ばれるブランドの設計力があるのだと感じます。
- USPは「約束」であると同時に「構造」である
- 実例5社はいずれも、体験・数値・仕組みで差別化を実装している
- USPを成功させるには、“言葉と現場”の一致が鍵になる
よくある誤解と間違い──“やってるつもり”が成果を遠ざける

「USPは考えました」「言葉もつくりました」──それでも成果が出ない、という相談は本当に多いです。 原因は、“やっているつもり”の中にある見落としとズレにあります。
ここでは、現場でよく見かける“失敗のパターン”を紹介しながら、 どこでつまずき、何を調整すべきかを一緒に見直していきましょう。
誤解①「USP=キャッチコピー」だと思っている
USPは“言葉の見栄え”ではなく、“事業構造の違い”を伝えるものです。 短くインパクトのあるキャッチを作ることがゴールではなく、 その言葉の背後に「何を」「どうやって」「誰に届けるか」が詰まっている必要があります。
誤解②「強み」をそのままUSPにしてしまう
「うちは技術があります」「創業◯年です」といった自社の特徴は、たしかに大切です。 でも、それが顧客のニーズと接続されていなければ、“伝わるUSP”にはなりません。
強みをUSPに変換するには、「だから何が変わるのか?」「誰がどんなメリットを受けるのか?」まで掘り下げる必要があります。
誤解③「伝えているのに、伝わっている」と思っている
社内では「この言い方で浸透してる」と思っていても、実際のお客様はその文言を見て「よくある表現だな」と流してしまっているかもしれません。
特に多いのが、抽象語だけの表現──「高品質」「安心」「丁寧」など。 顧客は“それをどうやって体験するのか?”が気になっているのに、答えが書かれていないんです。
誤解④ USPは一度作れば終わりだと思っている
市場は動きます。競合も変化します。 一度作ったUSPも、時間が経てば「ありふれた表現」になってしまうこともあります。
USPは、継続的に問い直す言葉。 反応が鈍くなってきたと感じたときこそ、更新・再設計のタイミングなのかもしれません。
- USPは「見栄えのいい言葉」ではなく「構造に根ざした約束」
- 自社の強みを、そのまま言っても伝わらない
- 顧客の体験・視点・言語で再翻訳することが大切
- 一度作って終わりではなく、更新する姿勢が成果を守る
自社のUSPを見直す3つの視点
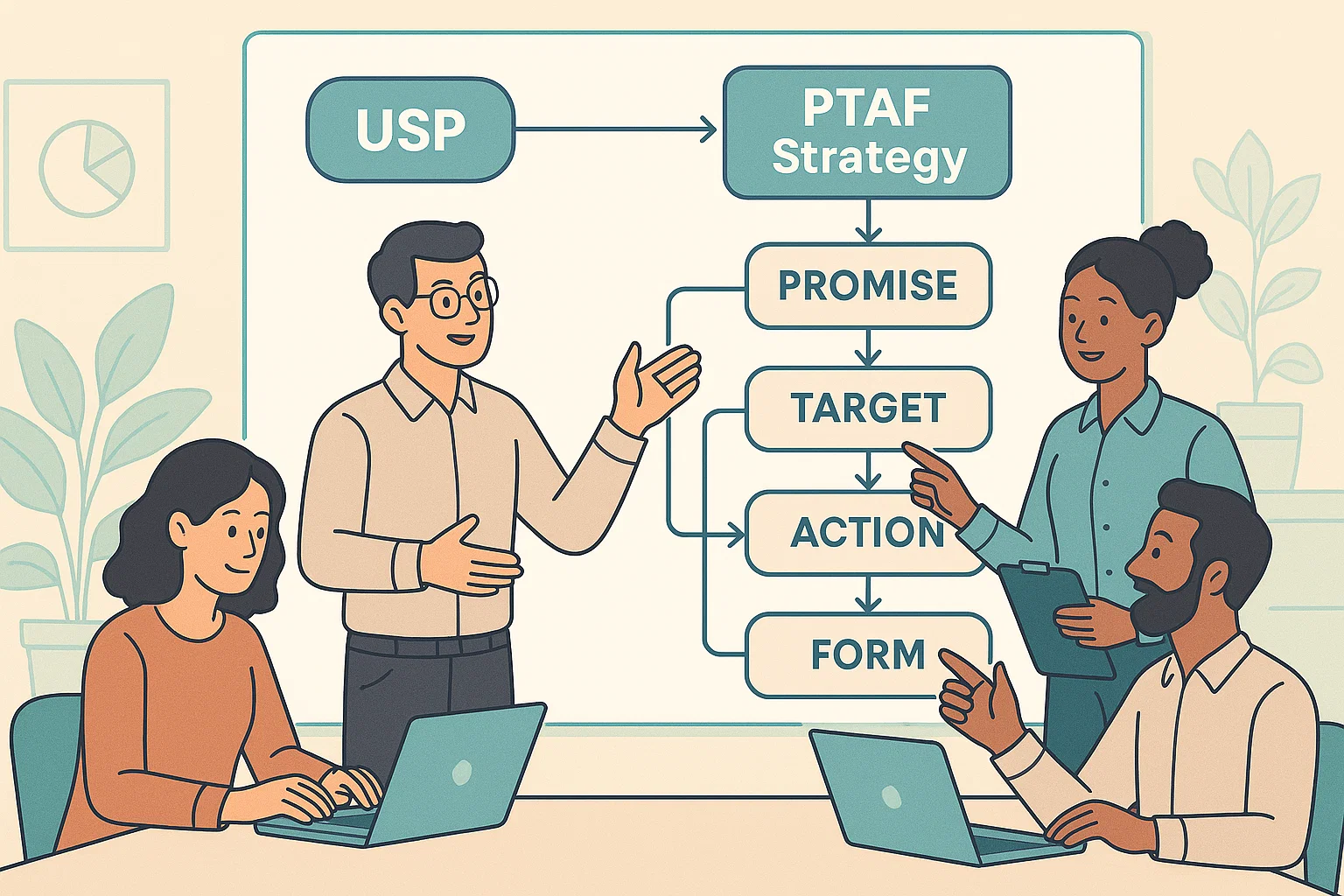
言葉を整えて、戦略につなげて、体験として届ける。 ここまでお読みいただいて、「自社にも使えそうだ」と感じていただけたでしょうか?
最後に、今あるUSPをアップデートするための視点を3つだけ、具体的にお伝えします。 一つでもチェックが入れば、すでに再設計の入口に立っている証です。
視点① 「“誰に向けての約束”か」が明確か?
「うちの強みは○○です」と語るとき、それが誰にとっての“違い”なのかが不明確なことは多くあります。
その価値を「必要としている人」が、具体的に見えているでしょうか?
「このUSPが“1番効く”のは、どんな人?どんな状況?」
→ ペルソナとシチュエーションを1文で言えるか試してみてください。
視点② 「体験で証明できているか?」
そのUSPが、言葉でしか伝わらない状態になっていないか── 顧客は言葉ではなく、体験の中で“違い”を感じて判断します。
「お客さまがその“違い”を初めて感じる瞬間は、どこか?」
→ 商品体験・接客・購入後など、実際のシーンで考えてみてください。
視点③ 「競合と並んだときに一目で伝わるか?」
ウェブサイト、チラシ、営業トーク──
「他社と並べられる場面」で、自社の違いは一瞬で分かるかどうか。
これが明確であれば、比較検討段階でも強くなれます。
自社・競合2〜3社を比較して、パッと見て違いが分かるか?
→ 「誰が見ても違う」と言えるなら、USPは届いている証拠です。
USPとは、「自社の良さを言うこと」ではなく、相手の選択に寄り添う言葉です。 今のUSPを、もう一度“届ける形”に整え直す──その一歩が、ブランド全体の構造を変えていきます。
なお、PTAFモデルでいう「Promise=USP」に相当します。
USPを軸に、Target(誰に)・Action(何を)・Form(どう届けるか)を再構成することで、戦略全体と接続できる設計になります。
USPが言語化されても、ターゲットや行動導線とつながっていなければ、実際の成果にはつながりません。
その点で、STP(誰に)→USP(何を約束)→4P(どう届ける)→PTAF(どう行動へ導く)という全体接続の視点が不可欠です。
- USPは“届ける言葉”であり、構造の起点になる
- 再設計には「ターゲット」「体験」「比較」の3点チェックが有効
- 言葉を変えることで、選ばれ方が変わっていく
よくある質問(FAQ)
USPとは何の略ですか?
USPとは「Unique Selling Proposition(ユニーク・セリング・プロポジション)」の略で、
直訳すると「独自の販売提案」。
つまり「他社にはない、自社だけが提供できる価値や約束」を示す言葉です。
USPはどのように作れば良いですか?
ターゲット・ニーズ・自社の強みの3点を整理し、競合との違いを明確にするのが第一歩です。
「誰に、どんな価値を、どう届けるか?」を問い直すことで自然に形になっていきます。
USPとキャッチコピーの違いは?
キャッチコピーは広告表現としての“見せ方”ですが、USPは“構造の差”そのものです。
USPが土台にあることで、効果的なキャッチコピーが生まれます。
USPが競合とかぶってしまった場合は?
「切り口」をずらすことで差別化できます。
同じ商品特性でも「誰に」「どう響かせるか」を変えれば、十分に独自性を持たせられます。
一度作ったUSPは変更しても良いのですか?
はい、むしろ定期的な見直しが必要です。
市場環境や顧客ニーズが変化すれば、USPもそれに合わせて更新されるべきです。
この記事のまとめと次の一歩
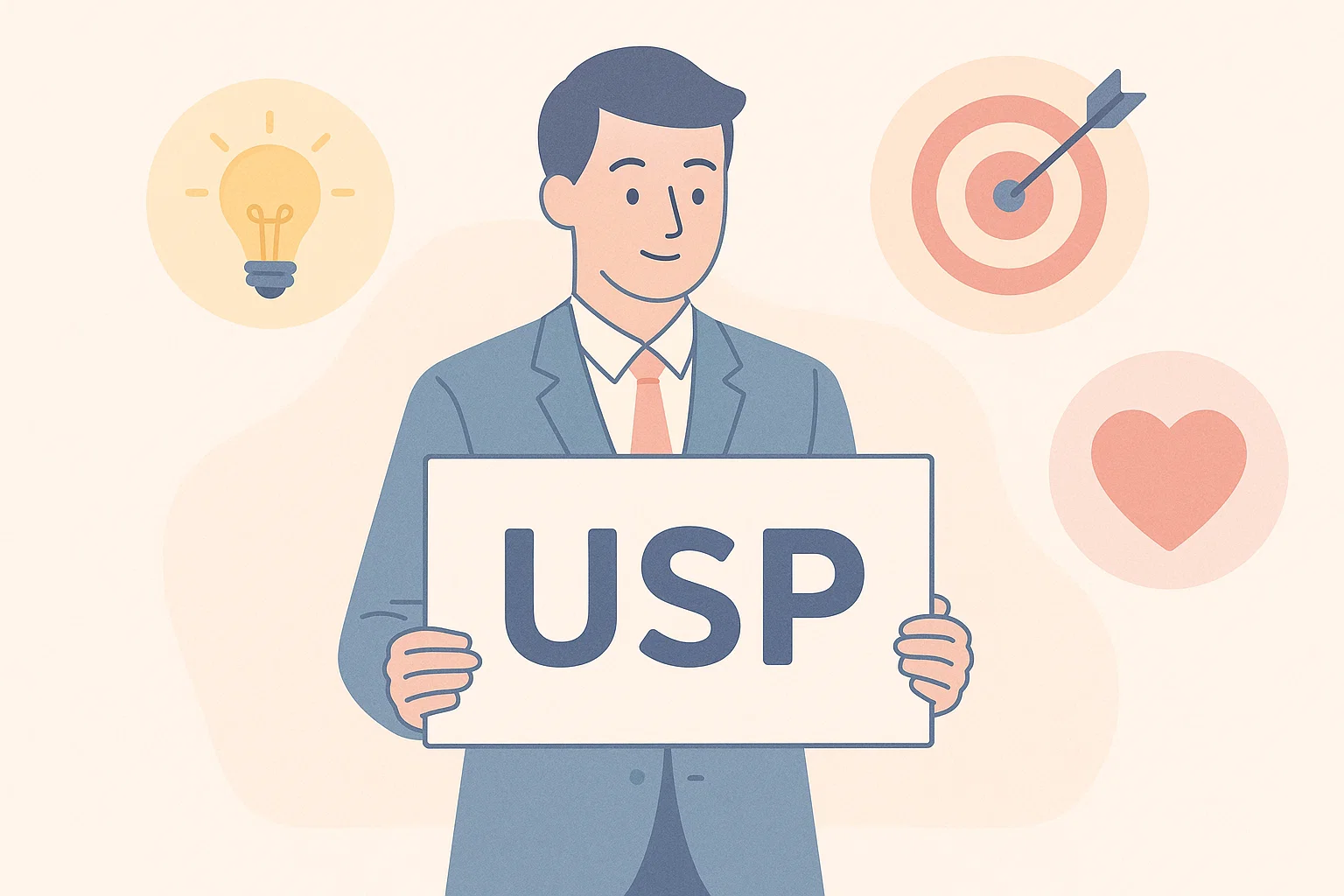

- USPは「言葉」ではなく「構造」に根ざした“選ばれる理由”
- 届ける体験と一致して初めて信頼を生む
- 自社にフィットするUSPは、設計×証明×再翻訳で見つかる
「伝えたいこと」はある。だけど、それが「届いていない」と感じるなら──
きっと、USPの構造にヒントがあるはずです。
言葉を磨くだけではなく、“どう届き、どう体験されるか”まで設計できたとき、
その一文はブランドの軸に変わっていきます。
参考文献・外部リソース
- ▶Prahalad, C. K. and Hamel, G. (1990). “The Core Competence of the Corporation”, Harvard Business Review.
- ▶ コトラー公式|ポジショニングと競争優位
- ▶ Take 15 Minutes to Find Your Winning Difference(Copyblogger)
- ▶ USPとCV率の関係(HubSpot調査)
- ▶ HBR|コトラーの差別化戦略(英語)
- ▶ PTAF×USP接続ワークPDF(無料DL)
本稿はPTAFモデル(©2025 Lapro your Consulting)を基盤とし、その<プロダクト戦略軸>を拡張した概念を解説しています。






















