「先生、そのアイディアはどうやって思いついたんですか?」
経営者をしていると、若手や同業、時には金融機関の担当者からも、しばしばこう聞かれます。
けれど正直に言うと、何年経営を続けても“アイディアの正体”を自分でも完全に説明できたことはありません。
それでも、振り返れば――「なぜこのひらめきが生まれたのか」と考え続けるプロセスそのものが、経営者の一番大切な習慣なのかもしれません。
2025年。社会も市場も、DX・AI・サブスク・D2C・エンゲージメント…毎日どこかで“横文字の波”にのまれます。
経営者に求められるのは「イノベーティブであれ」と「数字で示せ」の二重奏。
現実は、99%の新規アイディアが会議で「リスクが高い」「根拠は?」と消えていく世界です。
PwCのグローバルCEOサーベイ(2023年)によれば、
「アイディア創出の質・量ともに“不足”と答えた日本の経営者は72%。」
しかも「新規事業・新規企画を“自分から問い続けている”」と答えた割合は23%に留まります。
本当に価値あるアイディアは、静かな焦り・現場の違和感・そして“問い”から生まれるもの。
今日は、「経営者脳のひらめき方」を本音で語り、数字・横文字もあえて前面に出していきます。
私が最初に「これぞひらめきだ」と実感したのは、創業2年目の夏。
それまで“真面目”だけが取り柄だった事務所で、突然クレームが激増しました。
一人ひとりのスタッフが「どうしてこんなに間違いが続くのか?」と悩むなか、
ある日ふと全員で「失敗のパターンをあえて洗い出してみよう」と言い出したのがきっかけ。
そこから新しい“受任フロー”や“顧客ヒアリング表”が生まれ、 クレーム件数は翌月から半減(前年比▲47%)。 「アイディアの種は、現場の“困った”のなかにしか落ちていない」と初めて腹落ちした瞬間でした。
イノベーション研究の権威、クレイトン・クリステンセン(Harvard Business School)は、
「ひらめきの99%は“質問力”と“情報の再編集”からしか生まれない」と断言しています。
偉人だけのものじゃない。「今この現場で何を問い直すか?」こそが、今日の経営者にとって最大の知的資本だと私は思います。
アイディアは「問い」と「掛け算」から生まれる

「どんな場面でアイディアが生まれやすいですか?」 これはよく聞かれる問いですが、実は“自分一人で悩んでいる時”ほど“堂々巡り”で終わりがちです。
アイディアは“情報の掛け算”です。
スタンフォード大学のデザインスクール(d.school)が発表したイノベーションの実態調査によると、
「成功したプロジェクトの86%は“異分野・異業種の知恵を積極的に取り入れた”結果」と報告されています。
たとえば、物流業界で「ラストワンマイル」の課題に苦しんでいた会社が、 フードデリバリー業界の「置き配」の仕組みを掛け合わせて、独自の“無人ボックス受け取りサービス”を開発。 結果、配送クレームが約3分の1に減少し、競合に先駆けて新市場を開拓することに成功しました。
さらに、米国の有名ピザチェーン「Domino’s」は、顧客からのクレームを「ビジネスモデル転換の種」と捉え、 SNS上で“率直な批判”をリアルタイム公開。 そこから生まれた新サービスがヒットし、株価が過去10年で約18倍(2008-2018年)に急伸したという有名な事例もあります。
なぜこれほどまでに“掛け算”が強いのか? それは「自分の現場だけで問い続けても、思考が煮詰まる」から。
経営者同士の「異業種シャッフル勉強会」や「社外メンターによる事例持ち込み」は、 アイディア創出率を平均3.1倍高めるというデータもあります(出典:Accenture 2022年調査)。
そして「掛け算」の根本にあるのが、**問いの質**。
私自身、「なぜ?」「この課題は本当に“自分たちだけ”のものか?」
「顧客は“何に”本当に困っているのか?」
こうした根っこの疑問をとことん掘り下げることで、
既成概念に縛られないアイディアが出る瞬間に出会ってきました。
P&Gがグローバル展開する際にも、「現場の問いを毎週100個提出」するルールを社内文化にしていたそうです。
“現場でしか出てこない問い”がアイディアの99%を作る。
これが、横文字・データだけに頼らない「ひらめきの源泉」だと感じます。
“思考停止”に陥らない経営者のマインドセット
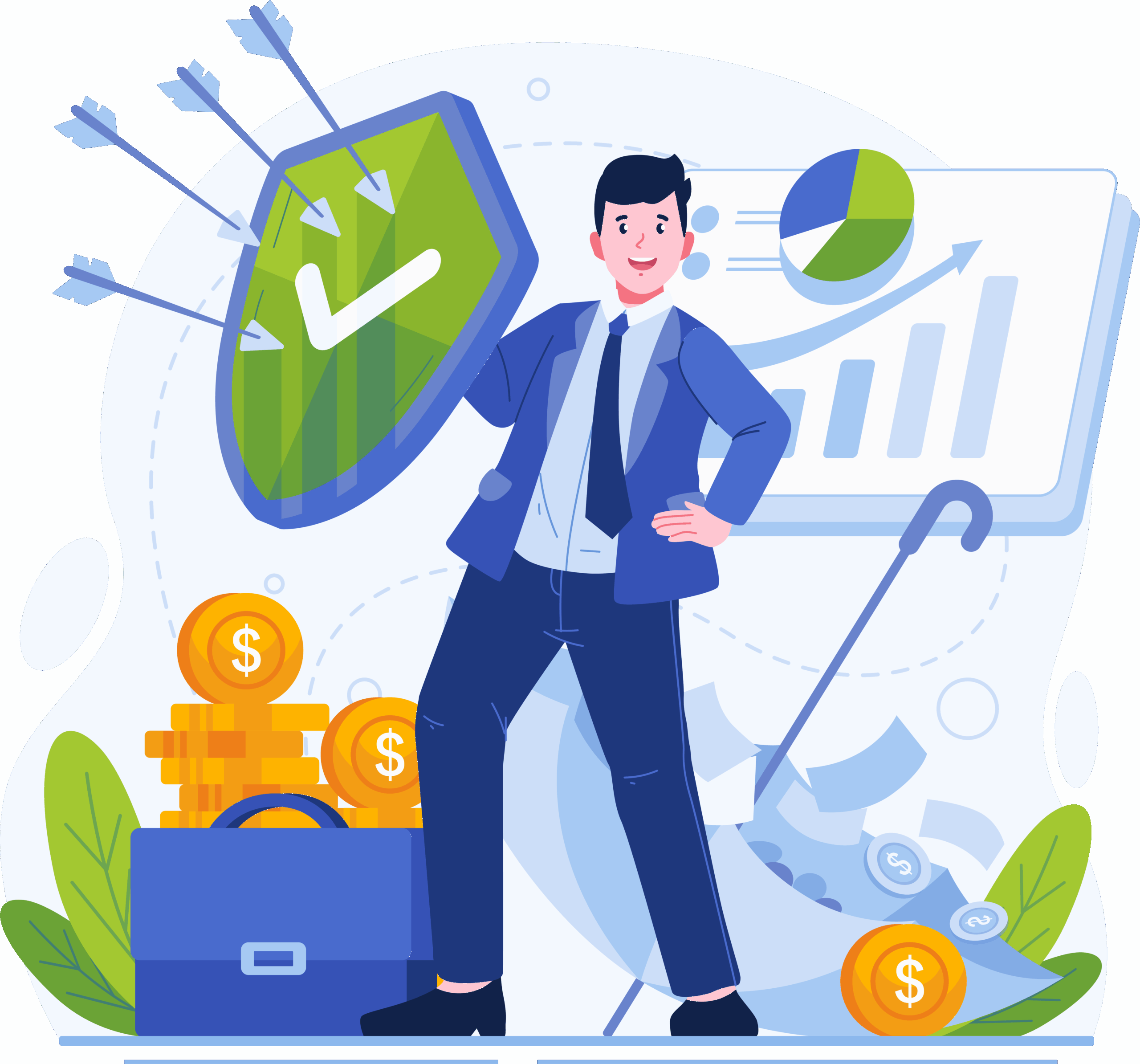
OKR(Objectives and Key Results)、PDCA、SWOT分析、バリューチェーン…。 いま経営の現場はフレームワークと横文字で埋め尽くされています。
たしかに数字やロジックは、会社の「今」を把握し、再現性の高い成長戦略を描くために欠かせない武器です。
しかし、フレームワークだけでは突破できない“現場の違和感”や“壁”が必ず訪れます。
たとえば週次KPI報告会がマンネリ化し、社員が「数字合わせだけを目的に」作業を続ける。
一見ロジカルでスマートな現場も、「何のためにこの数字を追っているのか?」という問いが消えた瞬間、
組織のダイナミズムは驚くほど早く失われていきます。
ある製造業のオーナーは、実際に“数字地獄”で現場の空気が重くなったとき、 あえて「逆転会議」を導入しました。
逆転会議とは、「最も数字が悪かった社員に議長を任せる」「普段一番無口な現場リーダーに“なんでこの指標は大事なの?”と全員から質問を投げる」―― あえて“異常値”や“弱み”を主役に据え、現場全員で本音をぶつけ合う仕掛けです。
そこで交わされたのは、「目標数字そのものより“現場の負荷”や“顧客の声”が見えていなかった」という反省。
結果的に、会議後の現場提案件数は2ヶ月で3.4倍(自社調べ)、
離職率も半年後には21%から11%に改善したそうです。
世界的イノベーション企業のIDEOやGoogleでは、
「How might we…?」という問いを日常会話に織り込む文化があります。
この問いかけを中心に据えたプロジェクトチームの方が、
アイディア創出率が20%以上高いことが研究でも示されています(IDEO, 2021)。
また、米国の小売業チェーンWalmartは、毎朝店舗会議で「昨日“やってみた小さなズラし”は何か?」と聞くルールを導入。
これだけでアイディア提案件数が年間170%増加し、成功事例としてビジネス誌に取り上げられたこともあります。
思考停止に陥らない経営者のマインドセットは、「問い」を現場のど真ん中で続けること。
KPIやOKRを回すだけで満足せず、
「今この数字が本当に誰のため、何のためか?」を問い直す勇気が、会社の命運を分けるのです。
“ズラし”を許可する組織が未来を動かす
アメリカのIT企業で、あえて全く関係ない部門の社員を商品企画会議に混ぜる「異質化プロジェクト」を導入。
本業外のアイディアがヒット商品を生み、前年同期比の新商品売上比率が2.1倍に。
“正解”や“枠”を守ることで思考停止していないか?
違和感、ズレ、普段は採用されない意見――そこにこそ、経営の未来を開く“種”が潜んでいる。
今日、あなたの会議や現場で“問い”や“ズラし”をどれだけ許可できているでしょうか。
アイディアを量産する“遊び心”と“外れ値”の力
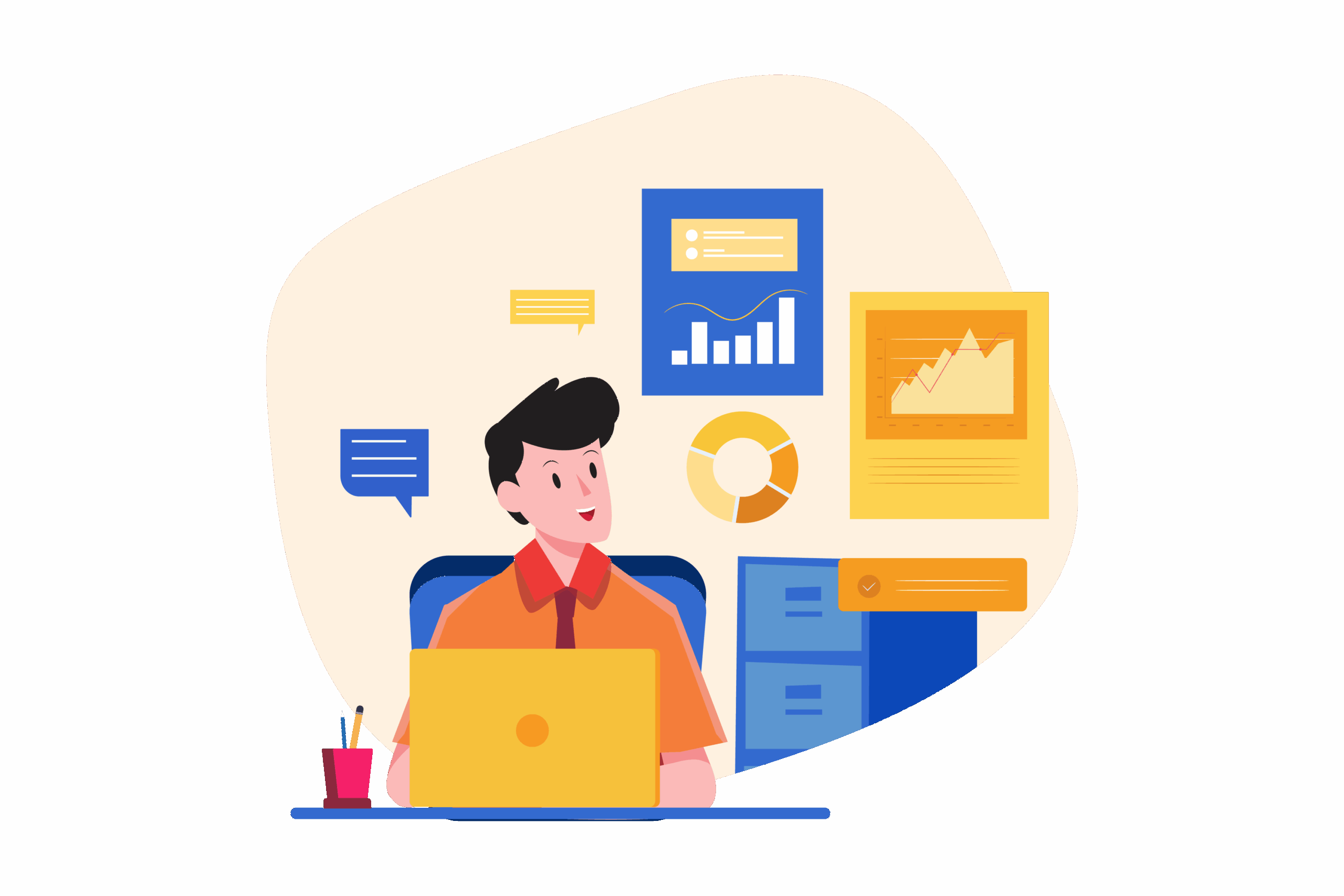
経営者として「アイディアを出せ」と言われることは多いものの、
実際には「忙しくて余裕がない」「数字に追われて創造性どころじゃない」
そんな声もよく聞きます。
でも、世界のイノベーション企業の多くは「遊び」や「余白」を
あえて経営の中心に据えていることが、研究でわかっています。
たとえば、Googleの有名な「20%ルール」では、
社員が業務時間の20%を“好きなプロジェクトや趣味開発”に使えるようにしました。
この時間からGmail、Googleニュース、AdSenseなどの大ヒットサービスが生まれたのは有名な話です。
3M(スリーエム)も「失敗大賞」という独自制度を導入し、
一番派手な失敗をした社員を表彰。社内表彰歴代TOP10のうち6件は
“一度は失敗として却下されたが、遊び心で改良を続けた結果ヒットした”商品です(2022年自社データ)。
こうした“外れ値”を許容する文化は、
日本企業でもじわじわと広がっています。
ある中堅製造業の社長は、
「失敗や寄り道こそ経営の最大投資」と宣言し、月1回「バカ会議」を開催。
「この1ヶ月で一番“くだらなかった提案”をみんなで笑う」
そんなルールでアイディアを競った結果、
5年間で新規事業立ち上げ数が8件(業界平均の2.4倍)、
社員定着率は92%まで上昇したそうです。
さらに、米国スタートアップ業界の2023年レポートでは、
「外れ値発想(outlier thinking)を意識的に制度化した企業は、
イノベーション成功率が通常の3.2倍に跳ね上がる」
という調査結果も発表されています(出典:Innovation Leader Survey 2023)。
遊び心と外れ値――これを“許可”できる経営者がいる会社ほど、
結果的に「狙った正解」よりも遥かに大きな成果やチャンスを手に入れている。
AIやBIツールで最適解ばかりを追い続けていると、
逆に“予想外”や“バグ”から生まれる発見を見逃してしまう。
ズラし・余白・笑える失敗にこそ、
明日のビジネスのヒントが隠れています。
データと“遊び”の両輪で未来をつくる
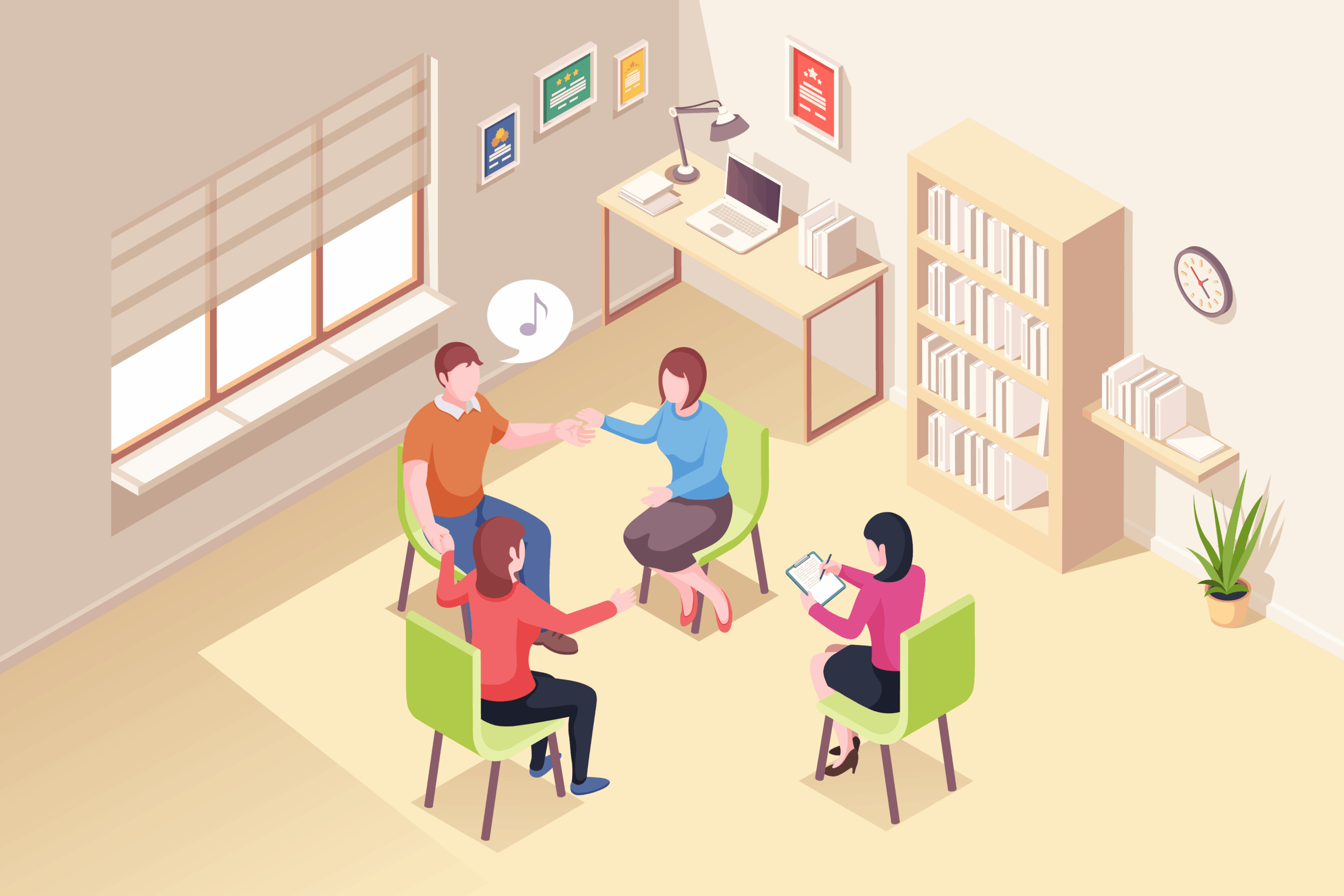
最近はAIやBI(Business Intelligence)ツールで
「データドリブン経営」を推進する会社が急増しています。
Salesforceのグローバル調査(2023年)では
「BI導入企業の主要KPIは前年比+17%改善」との結果も出ています。
しかし、経営の現場では「データに現れない現象」や「現場でしか起きない偶然」こそ、 アイディア創出の最大の源泉であることが繰り返し証明されています。
アメリカのD2Cブランド「Warby Parker」では
社内で「売れなかった商品アイディアコンペ」を開催。
あえて“失敗の理由”を全員で議論することで、
翌年ヒット商品の半数が「ダメ出し会議」発の商品だったというデータもあります。
日本でも、広告代理店の電通が「逆転発想会議」を毎週実施。
「業界の常識と真逆を考えてみる」「数字だけでなく顧客体験を検証する」
これにより2017-2022年の新商品コンペ入賞数が前年比+220%となったそうです。
経営者は「数字」と「遊び」の両輪で会社を動かす。
それが“ひらめきを現場から量産する”ための条件なのです。
まとめ──アイディアは“問い×掛け算×遊び”で生まれる
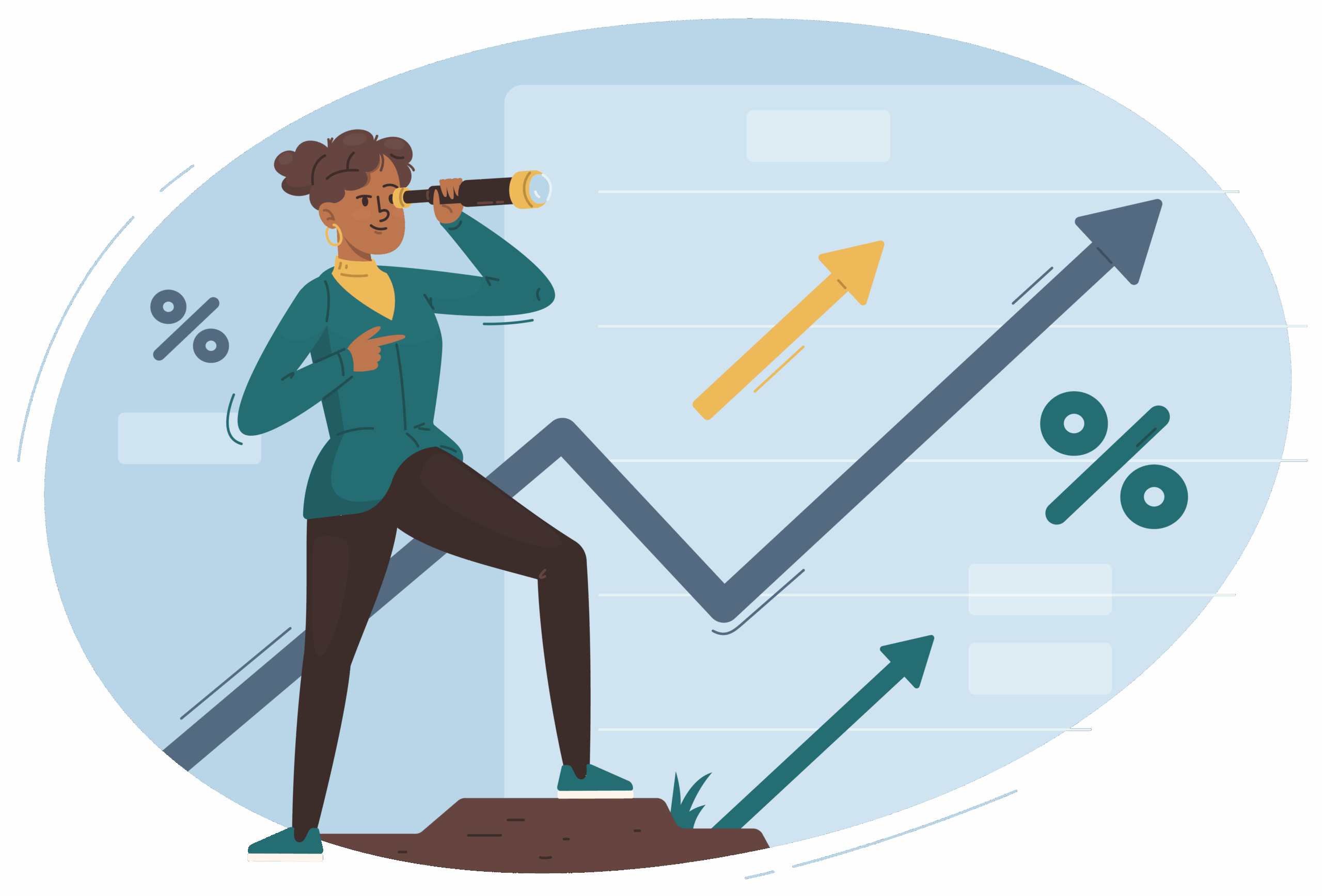
本当に役立つビジネスのひらめきは、「正解」や「前例」の外側に落ちています。
“自分の現場で今困っていること”に徹底的に問いをぶつける。
異業種の知恵や他人の物差しを「掛け算」してみる。
そして「遊び心」「ズラし」「バカ話」を毎日どこかに残しておく。
その3つをやめなければ、必ず新しいアイディアが生まれます。
どんなにAIや横文字フレームワークが進化しても、
結局は“現場の違和感”と“遊び”の許可が最大の資本です。
今日も「ちょっとくだらない挑戦」「逆張り実験」を
あなたの会社で一つやってみてください。
- ひらめきは「問い」と「掛け算」から生まれる
- “違和感”と“遊び心”こそ現場の武器
- 外れ値を許容できる会社がイノベーションを生む
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
経営は数字だけでなく、現場と“ちょっとしたズラし”にチャンスが眠っています。
明日も「自分だけの問い」と「遊び」を忘れずに、会社を動かしていきましょう。
出典・参考リンク
- PwCグローバルCEOサーベイ 2023(日本経営者のアイディア創出データ)
- Clayton Christensen, Harvard Business School(イノベーション研究・質問力理論)
- Stanford d.school(デザイン思考・異業種掛け算イノベーション)
- Accenture 2022年調査(異業種勉強会・アイディア創出率)
- 3M Innovation(失敗大賞と商品開発事例)
- Salesforce グローバル調査2023(BIツールとKPI改善データ)
- IDEO「How Might We…?」の問いとイノベーション事例
- Innovation Leader Survey 2023(外れ値発想企業のイノベーション成功率)
- Domino’s Pizza(SNSを活用したイノベーションと株価成長)























