「会社は誰のものか?」 この問い、令和の時代になってもなぜか答えは一つに収束しません。
資本主義のルールでいえば「株主のもの」。 昔の日本型経営なら「従業員のもの」や「地域のため」と言われてきました。 最近では「社会や未来世代のもの」「地球環境のもの」と答える経営者も増えました。
しかし、現場で経営判断に悩むとき、机上の正論や“きれいごと”だけで答えが出ることはまずありません。 「今日、自分が一番大事にしたい人は誰か?」 本音で迷い続ける経営者が、むしろ増えている――それが現場のリアルです。
ESG経営、ステークホルダー資本主義、パーパス経営―― 新しい横文字と理念が溢れる時代になったものの、 「誰のための会社か?」という問いがこれほど迷走した時代は、歴史的にも稀です。
たとえば、経済産業省2023年調査では、 「経営トップの7割が“理想論”と“現場の幸福”の間で強い違和感を感じている」と回答しています。
最近、経営者仲間と話していても「自分のため?従業員のため?社会のため?みんな正しいけど、誰もが納得できる答えが見つからない」という声をよく耳にします。 経営理念やパーパス経営がどれだけ美しくても、 “現場の心”や“日々の幸福”が伴わなければ、会社は持続しないと痛感しています。
今日は、「会社の所有」と「幸福」の根源的な問いに、 哲学、データ、リアルなエピソード、現場の揺れを重ねて、 “誰のものか”という問いそのものを問い直してみたいと思います。
会社を経営するあなた自身は、今この瞬間「誰のために」意思決定していますか? その問いを一緒に揺らしながら、読んでいきましょう。
“会社は誰のものか”という問いの暴力性――なぜ未だに議論が終わらないのか
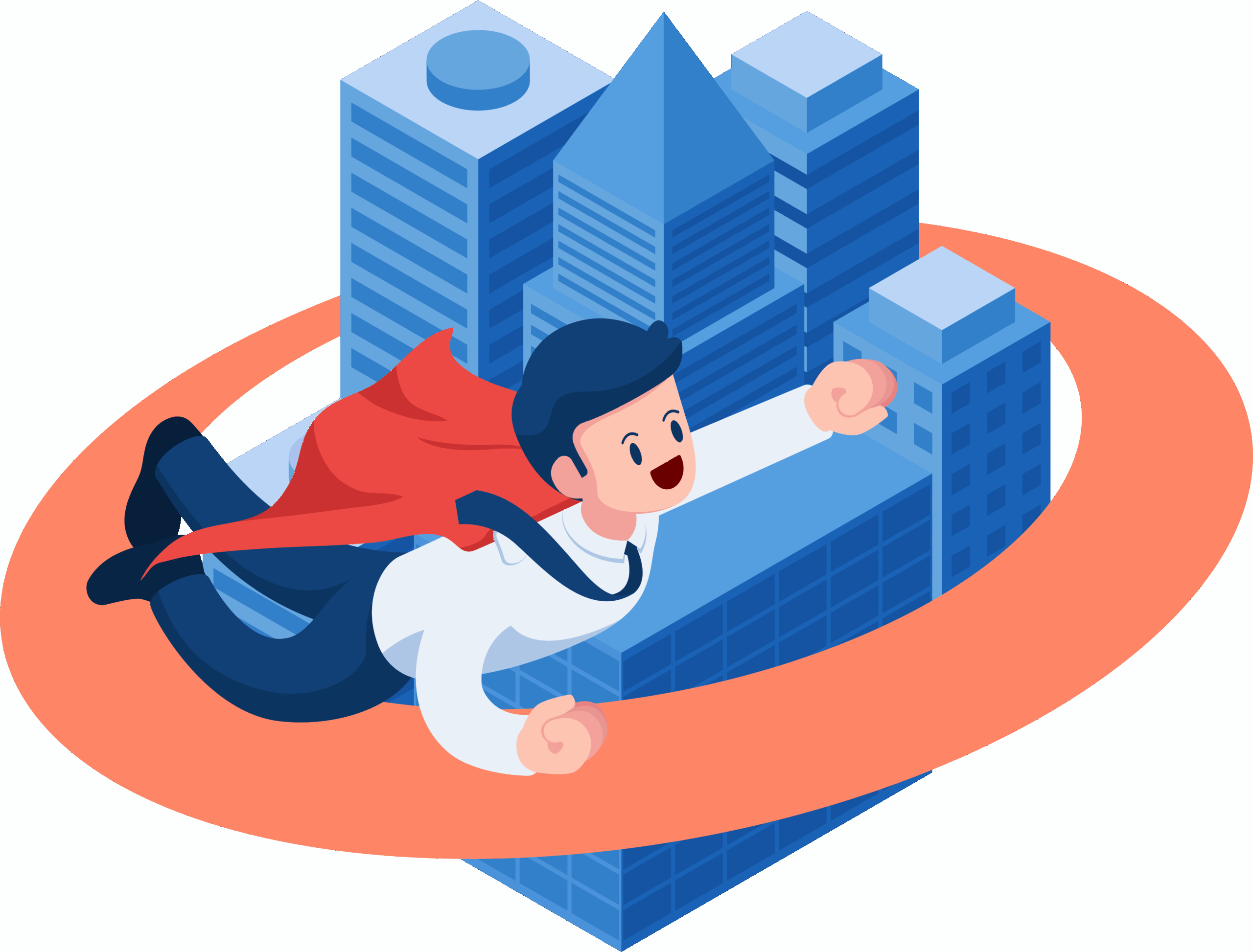
「会社=株主」「会社=従業員」「会社=社会」…。 どの立場から見ても一理あるし、正しいようで、どこか暴力的な違和感も残る問いです。
この議論は100年以上繰り返されてきました。 経営学のバーナードやドラッカー、稲盛和夫も「誰のもの論」に正解を出そうとしてきましたが、 その度に新たな矛盾や現場の反発が生まれています。
たとえば、2023年経済産業省調査では、 「会社の“所有者”を明確に語れない企業は、ESGスコア・従業員満足度・財務パフォーマンス全てで低迷」 という数字が出ています(7割が「理念と現場幸福のズレ」に悩み)。
なぜ“誰のものか”という問いは、これほど現場を迷わせるのでしょうか。
私が実感するのは、所有の定義が「時代・状況・人間関係」によってあっという間に変わってしまうという事実です。 極端な話、「昨日までは従業員第一だったのに、赤字や不正一つで一気に“株主第一”が絶対命令に変わる」現実もありますよね。
かつて、ある上場企業で幹部として働いていた友人は、 「人事評価も株主総会も“今月の所有者”によって真逆の基準が使われた」と振り返っています。 組織の空気が“揺れ動くもの”であることを、現場で実感している経営者は多いはずです。
そして何より厄介なのは、この“問いそのもの”が時に組織を引き裂くナイフになるという事実。 社員同士が「私たちの会社」と言う横で、オーナーが「いや、俺の会社だ」と言い張る。 どちらも正しいが、ぶつかると誰も幸せにならない――そんな泥臭い現場も少なくありません。
最近だと、中居正広さんの件を発端としたフジテレビ騒動(米ダルトン・インベストメンツの要求を巡るフジテレビ経営陣の一連の対応や、フジメディアホールディングスとの対立など)は記憶に新しいところです。
「所有」を言語化するワークのすすめ
経営理念やガバナンス体制の議論で、「現場で一番幸せそうな人は誰か?」を全員で共有しあうワークを導入してみてはどうでしょう。
曖昧な所有論より、幸福な現場の“顔”が見えたとき、方向性が一段階クリアになります。
本当の問いは「誰のものか」ではなく、「今の現場が本当に幸せか」「誰の笑顔が会社を動かしているか」を問い直すことかもしれません。
“所有”という言葉の暴力に振り回されず、“幸福”という実感に軸足を戻せるリーダーが、これからの時代は必要なのだと強く思います。
ステークホルダー資本主義/パーパス経営の“功罪”と現場のリアル
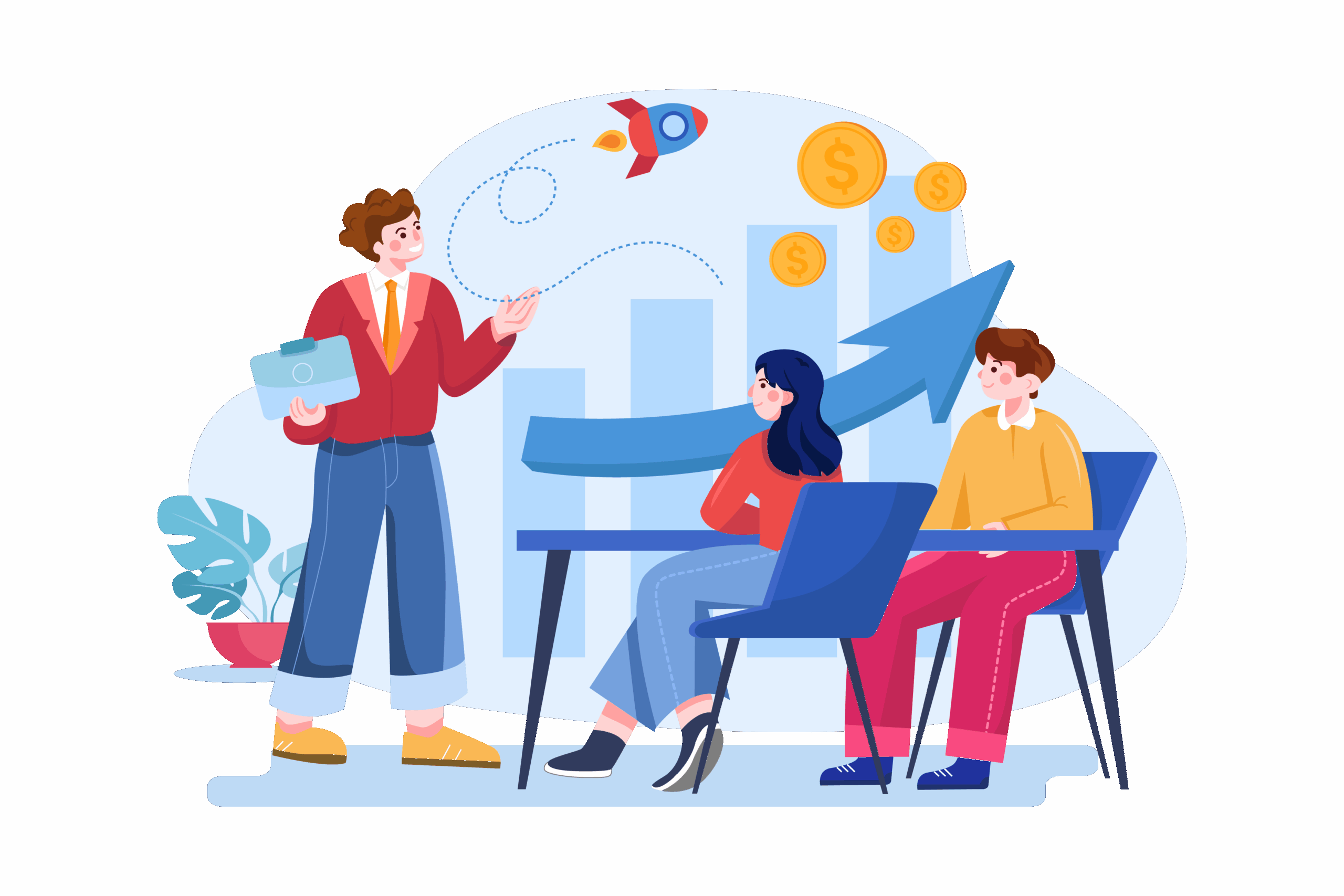
ESG、DEI、パーパス経営…ここ数年のビジネスワードは、まるで「みんなで幸せになろう」と繰り返しているように聞こえます。
たしかに、ステークホルダー資本主義やウェルビーイング経営を導入した会社では、
数字で見ても「社員幸福度」「離職率」「エンゲージメント」が大きく改善したというデータが増えています。
2023年の日経HR調査でも、「従業員幸福度経営」導入企業のうち離職率が前年比50%以上改善した例が全体の29%にのぼると発表されました。
でも、パーパスやESGが“スローガン”で終わっている会社も実際多いのが現場のリアルです。
ある大手メーカーの若手現場リーダーは、「会議では『社会のために』と言うけれど、
日々の仕事は納期とクレームと“無理な数字”ばかり」とぼやいていました。
きれいごとや最新ワードを掲げても、現場の幸福や顧客の心がついてこないなら、それは“ただの理想論”になってしまいます。
一方で、現場の会話や日報に「この仕事は誰のため?」「自分のやっていることがどの幸せにつながるか」を毎日問い直している会社ほど、 顧客満足度・従業員満足度・社会評価の“三冠”を達成しているという分析も出ています(Gallup, 2023)。
ステークホルダー資本主義は「みんなのため」という“理想”を語るほど、現場で「誰のものか」がますます分かりにくくなりがちです。
誰のものでもあり、誰のものでもなくなる――その曖昧さに迷子になるリーダーも多いのではないでしょうか。
パーパス経営は“現場の日常”で測る
トップや経営企画だけでなく、現場の会話・日報に「この会社は何のため?」を繰り返し言語化してください。
理想論だけで終わらず、幸福を「現場の日常語」に落とし込むことでしか、本物のパーパスは根付かない。
幸福度経営やパーパス経営が本当に機能するのは、現場・顧客・社会、どこかひとつでも“本音の幸福”が育っているときだけ。
それが無ければ、どんなに美しいスローガンも現場には届かないのです。
あなたの会社の「パーパス」は、現場や顧客の“日常幸福”と本当に結びついていますか?
その問いこそ、経営者自身が毎朝問い直す価値があるのだと私は考えます。
リーダーが“本当に大切にすべき人”とは誰か――哲学×現場で再定義する
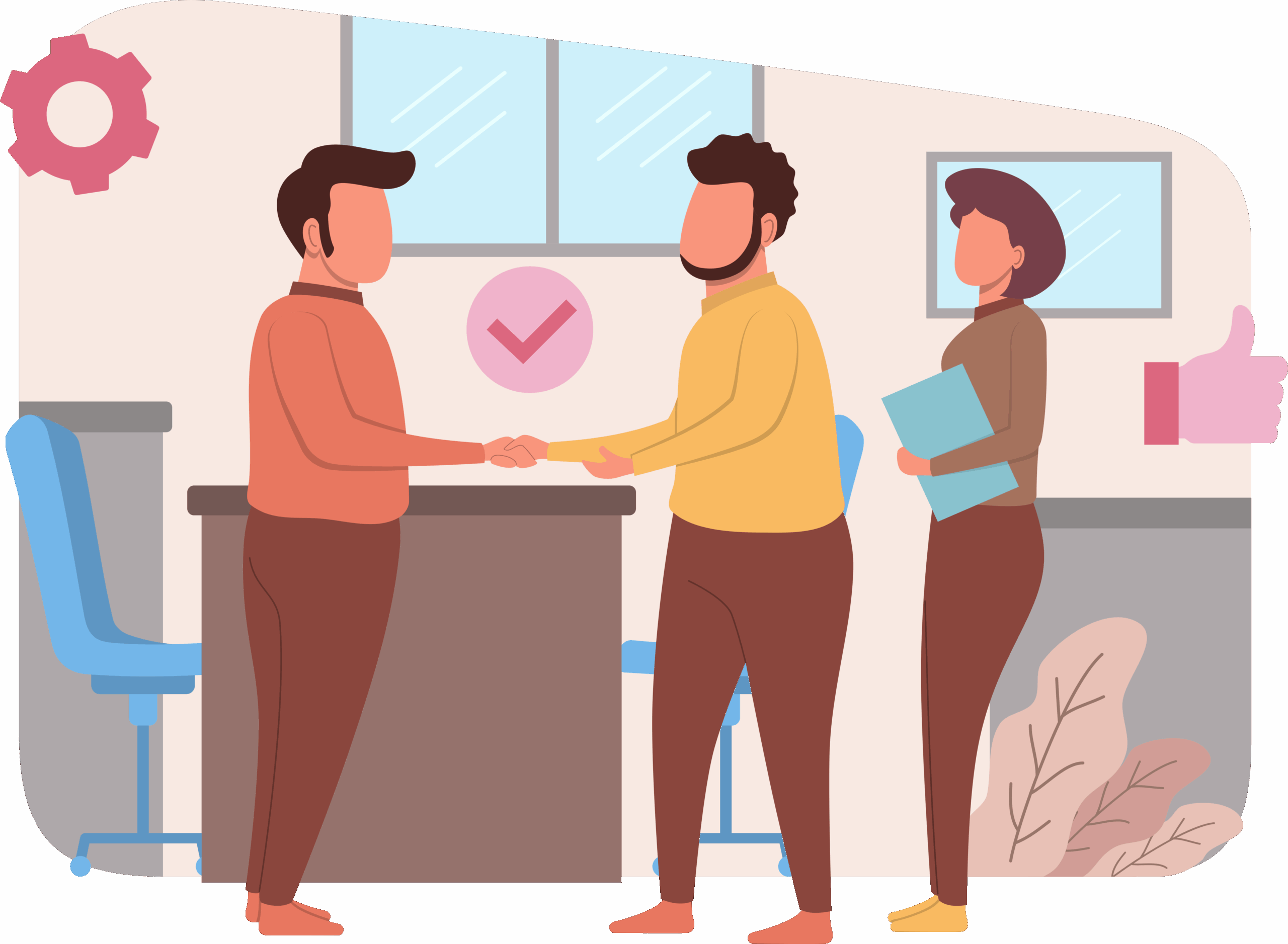
経営者は「誰のために会社をやっているのか」と問われるとき、どこかで言葉に詰まる瞬間があります。
理想論では「みんなのため」と答えがちですが、実際の現場や人生の岐路では、
顧客か、従業員か、家族か、自分自身か――その答えが揺れ続けるのが経営の本音です。
例えばある老舗企業の社長は、長年「従業員第一主義」を貫いてきました。
しかし経営危機の中でやむなくリストラを決断した際、「自分は本当は誰を一番守りたかったのか」を改めて自問せざるを得なかったと語ります。
一方、成長企業の若手創業者は「自分自身や家族の幸福を犠牲にしてまで会社を守る意味が本当にあるのか」と悩み抜き、 あえて一定期間会社を離れて“個人の幸福”を問い直す選択をしたそうです。
リーダーの「大切にすべき人」は、環境や時代、そして自分の成長とともに必ず揺れ動きます。
海外企業の中には、従業員・顧客・社会・株主という4つの“誰のため”を毎年再定義する「価値観アジャイル経営」を導入し、
各年ごとに「今年は従業員中心/来年は社会価値」と“舵の切り直し”をあえて組織文化にしている会社も増えています。
こうした現場の“問い直し”を続けている会社では、エンゲージメントや幸福度、業績だけでなく、 リーダー自身の納得度・幸福感も上がっているという調査も(2023年Gallup)。
大切にすべき“誰か”は、人生や経営の転機ごとに変化して良い。 「絶対的な正解」よりも、「今の自分が本気で誰を一番大切にしたいか」に素直になる勇気が、会社にもリーダー自身にも幸福をもたらすのだと思います。
“一人の幸福”から会社の軸をつくる
パーパス迷子になったときは、「この一週間で最も感謝された出来事」「一人の従業員や顧客を具体的に幸せにした経験」を振り返りましょう。
その積み重ねが“会社=誰のものか”を日々再定義する“現場の軸”になります。
リーダーが「本当に大切にすべき人」は、自分の中で問い続ける価値観と現場の幸福が交差するところに、 その都度アップデートされていくものなのかもしれません。
会社は誰のものか――その問いをやめないリーダーだけが、 時代や変化を超えて“幸福な会社”をつくっていくのだと、私は強く信じています。
まとめ――「会社のものさし」を問い続けよう
- 「会社は誰のものか」の答えは現場と時代ごとに変わる
- きれいごと・スローガンだけでは誰も幸せにできない
- 一人一人の“幸福”から再定義を始めてみる
“会社は誰のものか”という問いは、最初から“正解のない旅”なのかもしれません。 かつては株主のため、従業員のため、社会のため…と一つに答えようとしてきたけれど、 経営の現場ではその答えが時に変わり、迷い、ぶつかり合う現実と向き合わざるを得ませんでした。
でも、「揺れる」ことを恐れず、会社の軸を問い直し続けるリーダーだけが、 本当に“幸福な会社”を生み出していくのだと、私は思います。 パーパスや理念を掲げるだけでなく、現場や日常の小さな行動を“誰のためにやるのか”―― その問いを毎日アップデートできる経営者でありたい。
幸福も所有も、変わることを許せる勇気こそが、これからの時代に問われているリーダーの美学です。 今日も、「会社は誰のものか」を自分の言葉で問い直してみませんか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
会社も社会も、経営者の“問い直し”と“行動”ひとつで未来が変わります。
明日も“あなたらしい幸福”を探す一歩を大切にしてください。
誰のものか――正解がなくていい。この記事を読んだ後、あなた自身が“誰のために決めた一日”が一番幸せだったか、思い出してみてください。あなたが「これだ」と信じられる問いを持つこと、それ自体が経営の価値です。






















