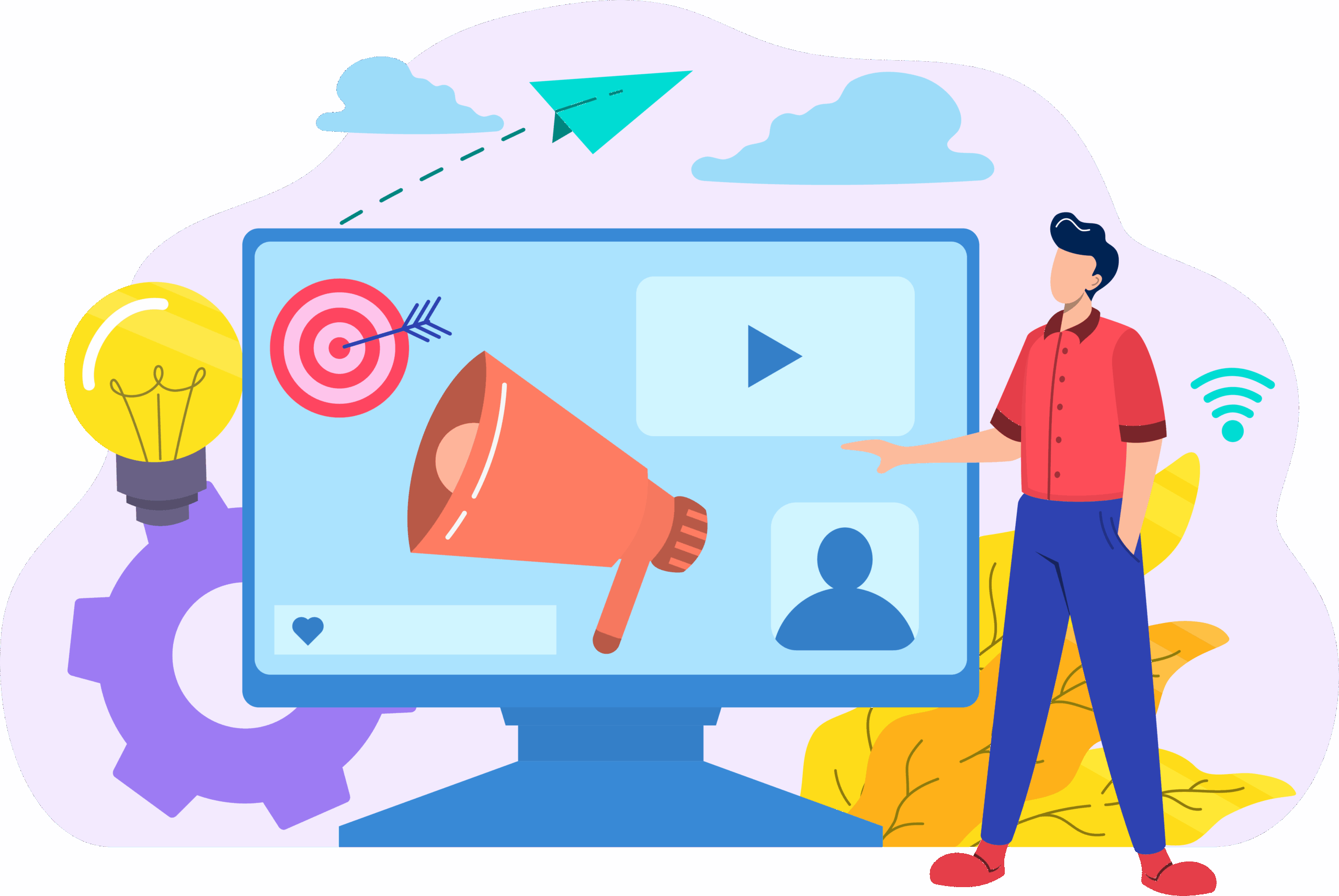通じないのは“中身”じゃない──言葉・文化・ポジションで刺さる場所を設計する方法
こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
何度も練った企画が、「悪くないですね」とだけ言われて終わったこと、ありませんか?
私はあります。 しかも、ひとつやふたつじゃない。
構想には自信があった。
資料も作り込んだし、プレゼンも準備した。
話した相手は真剣に聞いてくれていたし、「面白いですね」と言ってくれた。
でも、そのあとがない。
何も起きない。
まるで“うなずいてもらっただけで終わった”ようなあの手応えのなさ。
ちょっとずつ修正して、言葉を足して、ビジュアルを足して、何度も形を変えた。
それでも、反応は変わらなかった。
最初は、「まだ伝え方が足りないのかもしれない」と思っていました。
でも、あるとき気づいたんです。
それは“何を言ったか”じゃなく、“どこで言ったか”が問題だったのかもしれないと。
届かないのは、言葉じゃなく場所のせい。
思い返せば、あのとき私は、間違った戦場に、良いアイディアを投げていたんです。
アイディアは“戦略”になる前に、“戦場”を選び損ねる
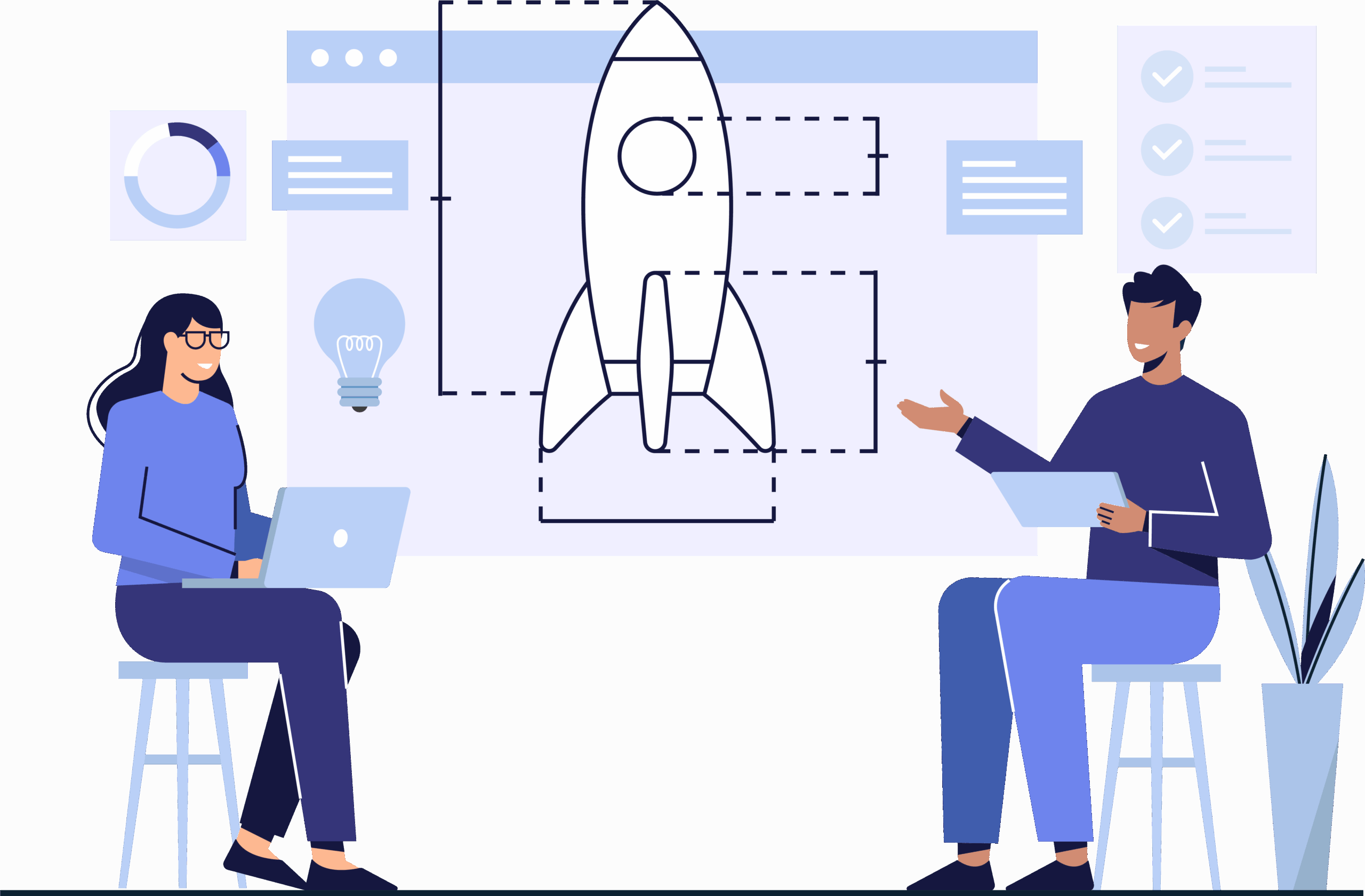
図:同じアイディアでも、投げた場所で結果が変わる
「この企画、よくできてるね」
そう言われて、笑顔で打ち合わせが終わる。
でもその後、メールも来ない。誰にもシェアされない。
そんな“無風”のリアクション、あなたにも心当たりがあるかもしれません。
世の中には、「いいアイディアですね」と言われてそのまま消えていく言葉が山ほどあります。
その理由は、決して“中身が悪かった”からではありません。
多くのアイディアは、“どこで戦うか”を間違えて投げられている。
戦略を練る前に、まず“戦場”を見誤っている。
マーケットは、「何を作ったか」より、 「その言葉を、誰に向けて放ったか」のほうが圧倒的に重要です。
でも私たちは、中身ばかり磨こうとする。
機能を加え、デザインを整え、言葉を洗練する。
その努力は必要です。
でも、“その言葉がどこの文化圏で通じるか”という視点を欠いたまま、私たちは企画を投げてしまう。
たとえば──
- 「ウェルビーイング」を掲げた人事制度を、評価制度重視の部署に提案したとき
- 「哲学的問いベースの研修」を、KPI文化の管理職にプレゼンしたとき
それは、“正しいこと”を、通じない場所に投げただけだった。
戦略とは、「どう勝つか」ではなく「どこで戦うか」から始まるもの。
そして、その“どこ”を間違えると、
どんなによく練られた言葉でも、空中に溶けていくだけなのです。
実際、世界的な調査でも「良いアイディアだったのに刺さらなかった」ケースは非常に多いとされています。
CB Insightsのレポートでは、スタートアップ失敗の理由のうち、56%が「市場のニーズに合っていなかった」という要因によると分析されています。
※出典:CB Insights『The Top 12 Reasons Startups Fail』(2021)
「誰にどう売るか?」という問いと、「どこに投げるか?」という視点。
一見似ているようで、この二つは“思考のスタート地点”がまったく異なります。
「誰にどう売るか」は、相手に合わせて言葉を調整する行為。 ターゲットを設定し、伝わるように表現を最適化していく、“戦略としての届け方”です。
一方で「どこに投げるか」は、そのアイディアが“元の形のままでも通じる文脈”を選ぶという行為。 つまり、“言葉の受け取られ方が保証されている文化や場所”を選ぶ視点です。
もちろん両立は可能です。
ただし、このコラムでは「言葉の内容を変える前に、まず“どこに投げるべきか”を考えること」の重要性に焦点を当てています。
なぜなら、多くのアイディアが“届かない”のは、戦略の練り不足ではなく、戦場選びの誤りだからです。
だから今回は、「何を言うか」より「どこで言うか」に集中して話を進めていきます。
“このアイディア、どこで生きて、どこで殺される?”という視点が抜けていた
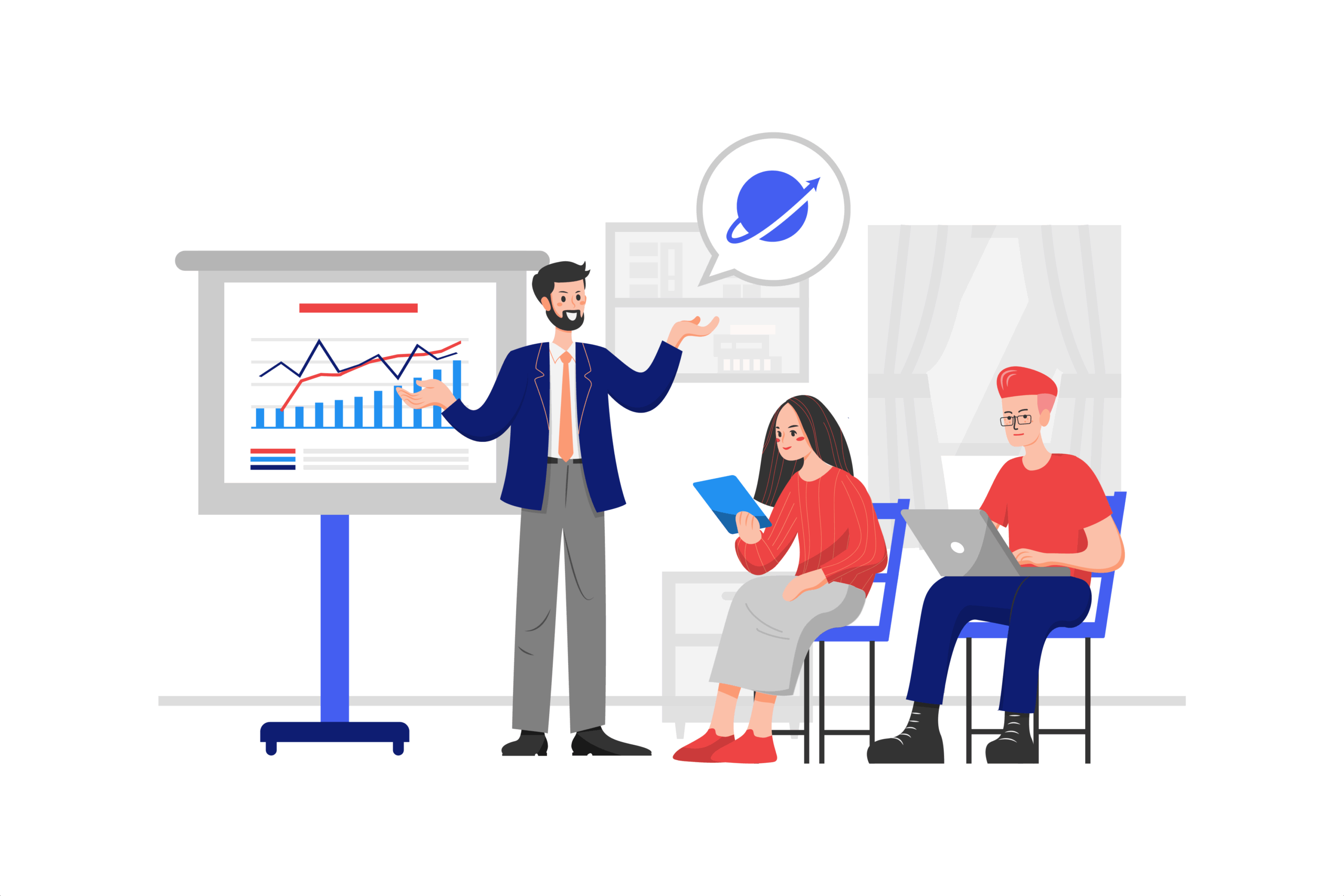
図:同じ言葉でも、場所によって“殺される”ことがある
どんなに優れたアイディアでも、それが通じる場所と、通じない場所がある。
そして恐ろしいのは、通じない場所に投げるとき、それが「潰される」だけではなく、「スルーされて消える」ということです。
私は以前、「感情インサイトに基づいたカスタマーサポート設計」を企業向けに提案したことがありました。
当時の相手は、数字でKPIを評価する文化が強く、情緒的な設計にピクリとも反応しなかった。
むしろ「要は、平均対応時間を減らしたいって話ですよね」と、別の言語に“変換されてしまった”のです。
それは、否定されたわけではない。 でも、伝えたかったことは殺されていた。
別のプロジェクトでは、「問いベースのワークショップ」を教育現場に提案したとき、 「で、それってテストの点数に関係ありますか?」という言葉で即着地されたことがあります。
人は、自分の“馴染みのフレーム”でしかアイディアを評価できない。
つまり、馴染まない言葉は、内容の良し悪し以前に誤読されるか無視されるか、どちらかになる。
私たちが気づくべきなのは、
アイディアには「そのままの姿で受け入れられる場所」が存在する一方で、
「翻訳しなければ伝わらない、あるいは受け取られない場所」も確実に存在するということです。
翻訳ができる人は強い。
でも、それ以前に、“翻訳なしで済む土壌”を探すほうが、ずっと楽に跳べる。
その視点が抜けていた私は、何度もアイディアを殺してしまった。
言葉は、殺されるよりも“無視される”ことで死んでいく。
その死に方は、静かで、気づきにくい。
でも、その静けさに気づけるようになったとき、
初めて私は「このアイディア、どこで生きるのか?」という問いに戻れたのです。
戦場の三層構造──言語戦・文化戦・ポジション戦
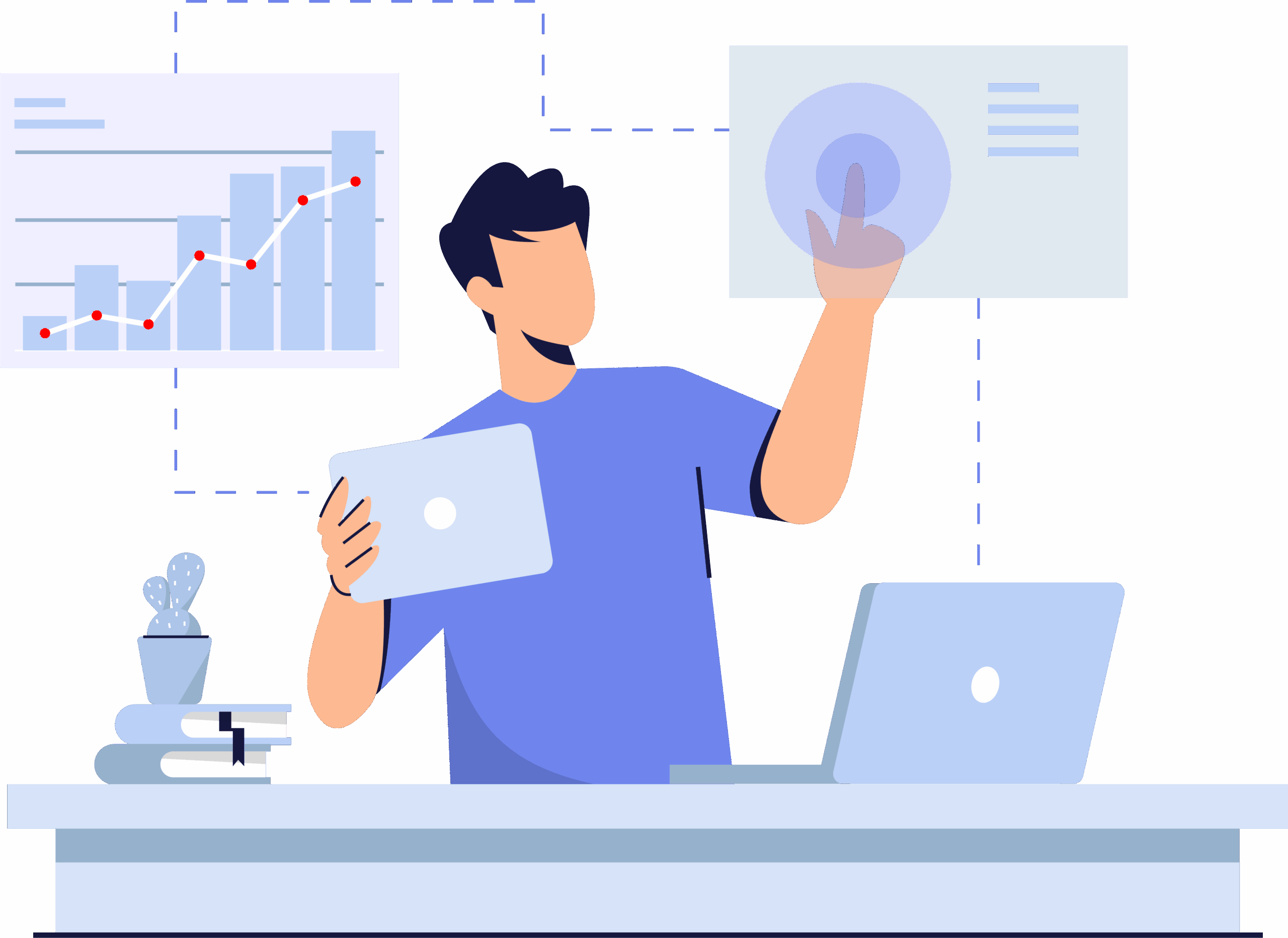
図:言葉の意味は“どの層に置かれたか”で決まる
「なぜ届かなかったのか?」を考えたとき、私はある共通点に気づきました。
アイディアが殺される理由の多くは、“戦う層”を読み違えているという構造的な問題でした。
そこで私が整理したのが、次の“三層の戦場構造”です。
- ① 言語戦:どんな語彙で語ったか。相手の脳内辞書にその単語があるか。
- ② 文化戦:そのアイディアが“そもそも許容される土壌”かどうか。
- ③ ポジション戦:誰が言うか。どの立場・関係性から放たれたか。
① 言語戦:「その単語、相手の脳内にある?」
たとえば「越境学習」「アーキテクチャ思考」「意味資本」といった言葉。
こちらが大事だと思っていても、相手の“辞書”になければ、存在しないのと同じです。
「おもしろいね」で終わる会話の多くは、言語の“互換性不全”から起きています。
② 文化戦:「その場で許されている概念か?」
「内省」「試行錯誤」「余白」。
こういった言葉が響くのは、“そういう思考様式が受け入れられている文化圏”に限られます。
たとえば、「余白が大事」と言っても、“スピードと効率が正義”の現場ではむしろ反感を買う。
教育現場で「対話重視」と言っても、“答えを早く出せる子が評価される空気”では、話が伝わらない。
③ ポジション戦:「それ、誰が言ったかで意味が変わる」
まったく同じ言葉でも、言う人が変われば刺さり方はまるで違う。
上司が言えば“指示”、同僚が言えば“共感”、部下が言えば“なまいき”に聞こえることもある。
アイディアは、言語・文化・ポジションの三重構造の上に浮かんでいる。
言葉だけを磨いても、この3つの層が合っていなければ、届かない。
そして届かない言葉は、往々にして“無視される”か、“誤って読まれる”かのどちらかになるのです。
この構造は、仕事だけでなく教育・医療・家庭など、すべての“言葉が交差する場所”に共通しています。
たとえば── ・教育の現場で「問い続けることが大事」と伝えても、テストで評価される文化では違和感になる。
・病院で「寄り添うケアが大事」と言っても、時間と回転が優先される現場では現実性を疑われる。
・家庭で「あなたらしくいてほしい」と言いながら、成績やルールに縛ってしまう矛盾もそう。
言葉が意味を持つには、必ず“置かれる地層”が必要なんです。
“通じる場所”に投げるだけで、事業は跳ねる

図:アイディアを変えずに、置き場所を変えただけ
あるプロジェクトで、私は実際に「戦場を変えるだけで跳ねる」瞬間を目の当たりにしました。
当初、そのサービスは「若手社会人向けのメンタルコーチングプログラム」として構想されていました。
共感を重視した問い、自己対話のフレーム、無理のない目標設計── 内容は非常に丁寧で、本質を突いていたと思います。
でも、まったく動かなかった。
説明会をしても、反応は「なんか良さそう」止まり。 Webページも数字が伸びず、プレゼンを重ねても、「で、それって何に効くんですか?」と切られて終わることが多かった。
私たちは、言葉を変えてみました。 訴求を変え、トンマナを整え、ロゴも変えました。 でも、結果は変わらなかった。
そこで、構造そのものを見直した。
「このサービスが“自然に通じる場所”はどこだろう?」と問い直したんです。
そして出てきた答えが、「40代管理職が部下と対話するための“問いの習慣化プログラム”」でした。
ターゲットも、文脈も、語彙も、一気に切り替わった。 でも、提供している中身は、実はほとんど変えていません。
それでも、そこから状況は一変しました。
企業の人事担当者が自ら問い合わせてきて、 現場での導入が決まり、書籍化・研修・法人契約へと連鎖的に広がっていったんです。
私たちはこのとき、ようやく理解しました。
アイディアは、「通じる場所に置かれた瞬間に、勝手に跳ねる」ということを。
アイディアの中身を変えなくても、 “語られる文脈”と“想定される相手”が合えば、言葉の意味が変わる。
マッキンゼーの調査によると、商品やサービスの「カテゴリ再設計=売り出す文脈のリポジショニング」を行った企業のうち、 平均25~30%の売上向上を記録したケースが多数あると報告されています。
※出典:McKinsey & Company『How rethinking category boundaries can drive growth』(2022)
そのままの構想を、届く人に向けて、届く場所に投げただけ。 それだけで、アイディアの“強度”が変わった。
言葉は、投げられた場所で、意味を変える。
アイディアを磨く前に、問い直してみてください。
「これは誰にとって、どの文脈で、どんな言葉として読まれるのか?」
その場所が変われば、あなたの言葉は、まだ跳ねる可能性がある。
この話を聞いて、「つまりターゲットを変えたってことですね」と思った方もいるかもしれません。
たしかに結果だけ見れば、「若手向け→管理職向け」への転換は“ターゲット変更”に見えます。
でも実際に変えたのは、ペルソナではなく“文脈”と“読み取られる立場”でした。
マーケティングは「言葉を相手に合わせていく」設計。
でも戦場論は、言葉を変えずに“そのまま読まれる場所”に置く設計です。
届かせたのではなく、通じる場所を見つけただけ。
それが、この事例の本質だったのです。
今すぐできる問い直し:あなたの言葉、どこに置かれている?
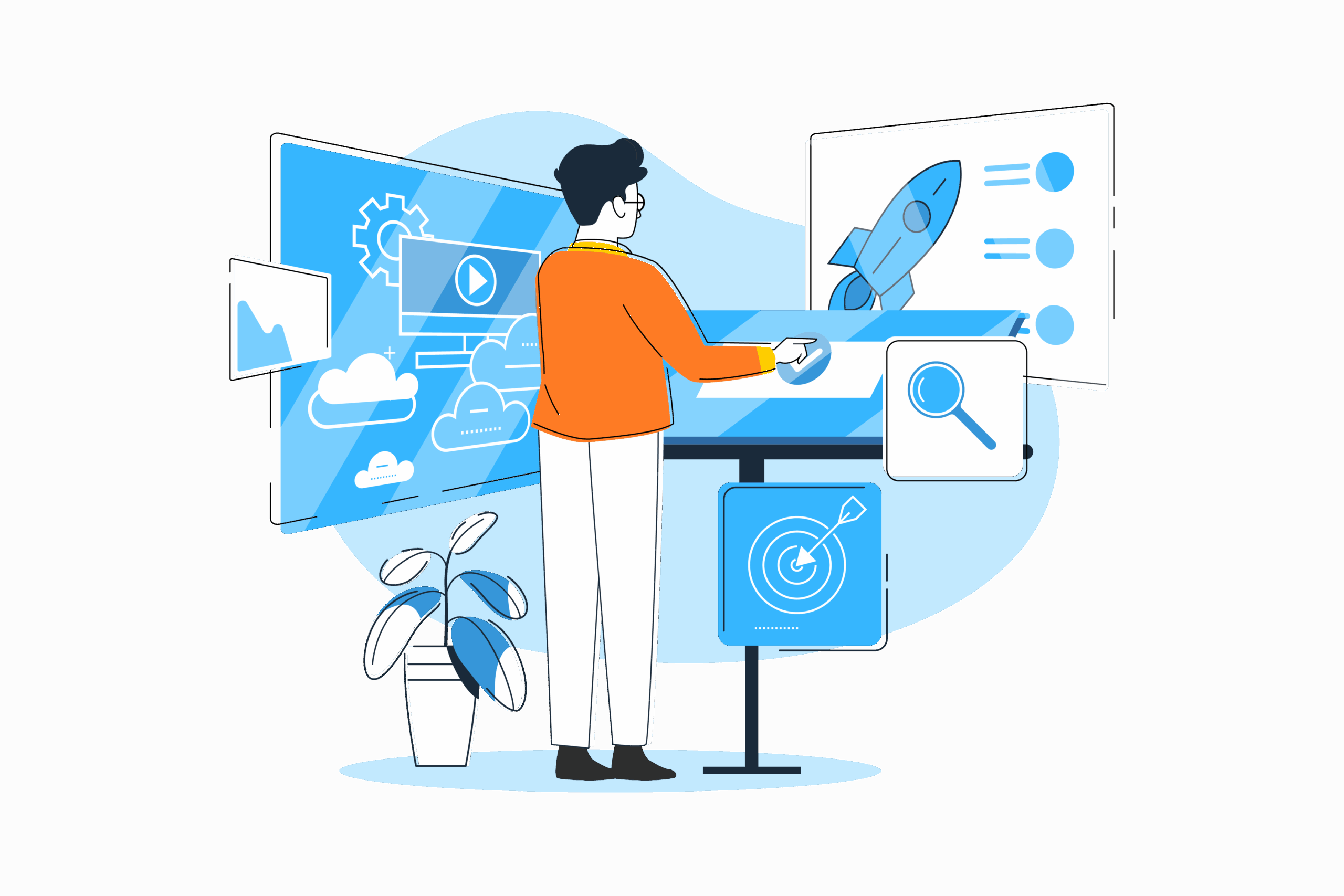
図:「文脈・誤読・再配置」の3つの問いで言葉が跳ね始める
もし今、あなたが誰かに届けたいアイディアや企画、あるいは“伝わらない感覚”を抱えているなら、 今日、たった1枚の紙でもいい。 この3つの問いを、自分に返してみてください。
- この言葉は、今どんな“文脈”に置かれているか?
(例:「新しいことが評価されにくい部署」「タイパ重視のSNS」「プレゼン資料文化の会議室」) - その文脈では、どんな“意味に読み替えられる”可能性があるか?
(例:「余白=甘え」「寄り添い=非効率」「問い=時間のムダ」) - もし場所を変えるとしたら、“どこならこの言葉は意味を失わずに届く”か?
(例:「問いが歓迎される学習コミュニティ」「理念で判断する中小企業」「副業相談が活発なSlackチャンネル」)
もっと具体的に。今日中にぜひトライしてみましょう。
- SlackやLINEの自分用ドラフトに、こう書いてみてください:
「今、自分が伝えようとしている言葉(または企画)は、◯◯な文化/チーム/空気の中に置かれている。 その文脈では、たぶん“△△”と読まれがち。 本当は“□□”として受け取ってほしい。」 - それを、Googleドキュメントの見出しにして、チーム資料の最上段にそっと書いておく。
- または、誰か1人、安心して話せる相手にだけ、「今この言葉、場所を間違えてるかもしれない」と打ち明けてみる。
書いた瞬間に、「あ、この言葉はここじゃないかも」という違和感が浮き上がります。
そしてその違和感が、“変える・残す・持ち出す”の判断軸になる。
この3つの問いに、1行ずつでもいい。
どこかに書き出してみてください。
人は、言葉を疑うより、場所を疑う方がラクに跳べる。
思考は、意外と簡単に流れを変えられる。 でも、その分“前のパターン”にも無意識で引っ張られている。
この3つの問いは、「自分の言葉がどこで鈍くなっているか」を見つけるための再配線トリガーです。
まずは、誰かに刺さらなくてもいい。
あなた自身が「通じる場所」を見つけられたら、それが次の問いの始まりです。
まとめ:言葉を変える前に、置き場所を変えてみる
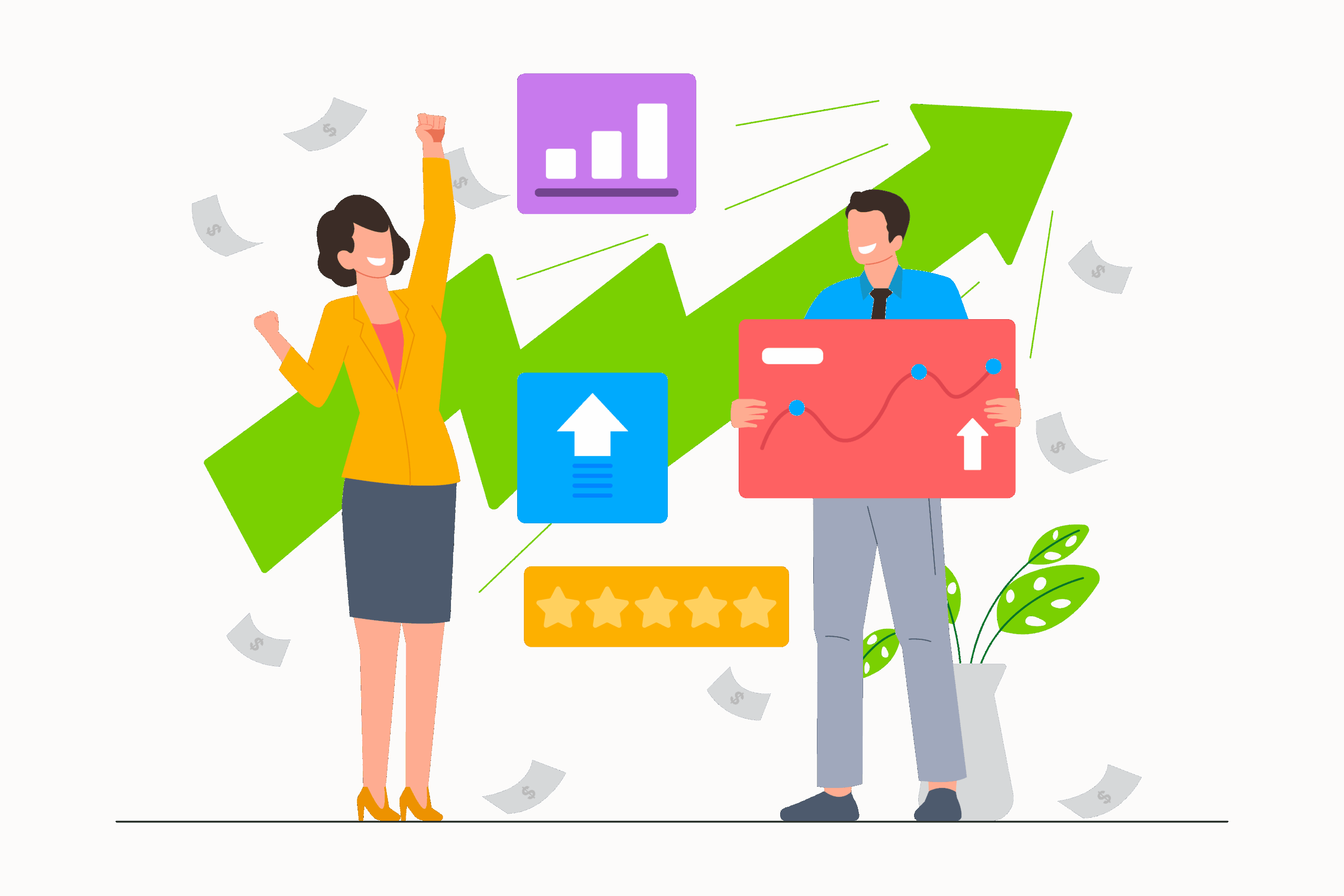
図:言葉は“どこに置かれたか”で意味を変える
「届かない」と感じたら、それはあなたの言葉が悪いのではなく、
“今いる文脈”が、その言葉の受け取りを許していない可能性があります。
言葉を変えるのは、最終手段でもいい。
まずはそのままの言葉が“自然に届く場所”を、もう一度見直してみてください。
アイディアは、通じる場所に置かれた瞬間に跳ねます。
だからこそ、戦略より前に、“戦場”を選び直す。
それが、アイディアを生かすということだと、私は思います。
📌 この記事の 3 行まとめ
・「届かない言葉」は、たいてい“置かれている文脈”に殺されている
・戦略の前に、「どこでその言葉が読まれるか」を設計する
・言葉を変えるより、“場所を変える”方が跳ねることもある
よくある質問(FAQ)
- Q1. この話って、結局マーケティングのことでは?
マーケティングは「相手に合わせて言葉を整える」思考です。
一方、このコラムは「そのままの言葉が通じる場所に置く」思考です。
両立はできますが、スタート地点がまったく異なります。 - Q2. 「通じる場所」が本当にあるかどうか不安です。
すぐには見つからないかもしれませんが、“共通語彙”や“判断の軸”が近い人や場を観察してみてください。 SNSの反応・Slackのトピックなど、思ったより近くにあることもあります。
- Q3. 会社で何度も否定されて、戦場を変える余裕がありません。
変えるのは“場所そのもの”ではなく、“投げる言葉の置き場所”でも構いません。
提案の順番を変える、別の関係性から出す、それだけで変化することもあります。 - Q4. どの言葉が“殺されていた”のか、自分では気づけません。
一番簡単なのは、「誰にも刺さらなかった言葉」を書き出して、 「その言葉が否定されたのか、無視されたのか、誤読されたのか」を分類してみることです。
無視された言葉の中に、“次の問い”が隠れています。
だから、まず文脈から疑ってみてください。
またお会いしましょう。
参考リンク・調査資料
- CB Insights『The Top 12 Reasons Startups Fail』(2021)
→ アイディアが届かない・潰される原因として「文脈の不一致」が最多理由に。 - McKinsey & Company『How rethinking category boundaries can drive growth』(2022)
→ 商品カテゴリを再構成することで“文脈が変わり、売上が跳ねた”複数の事例を紹介。