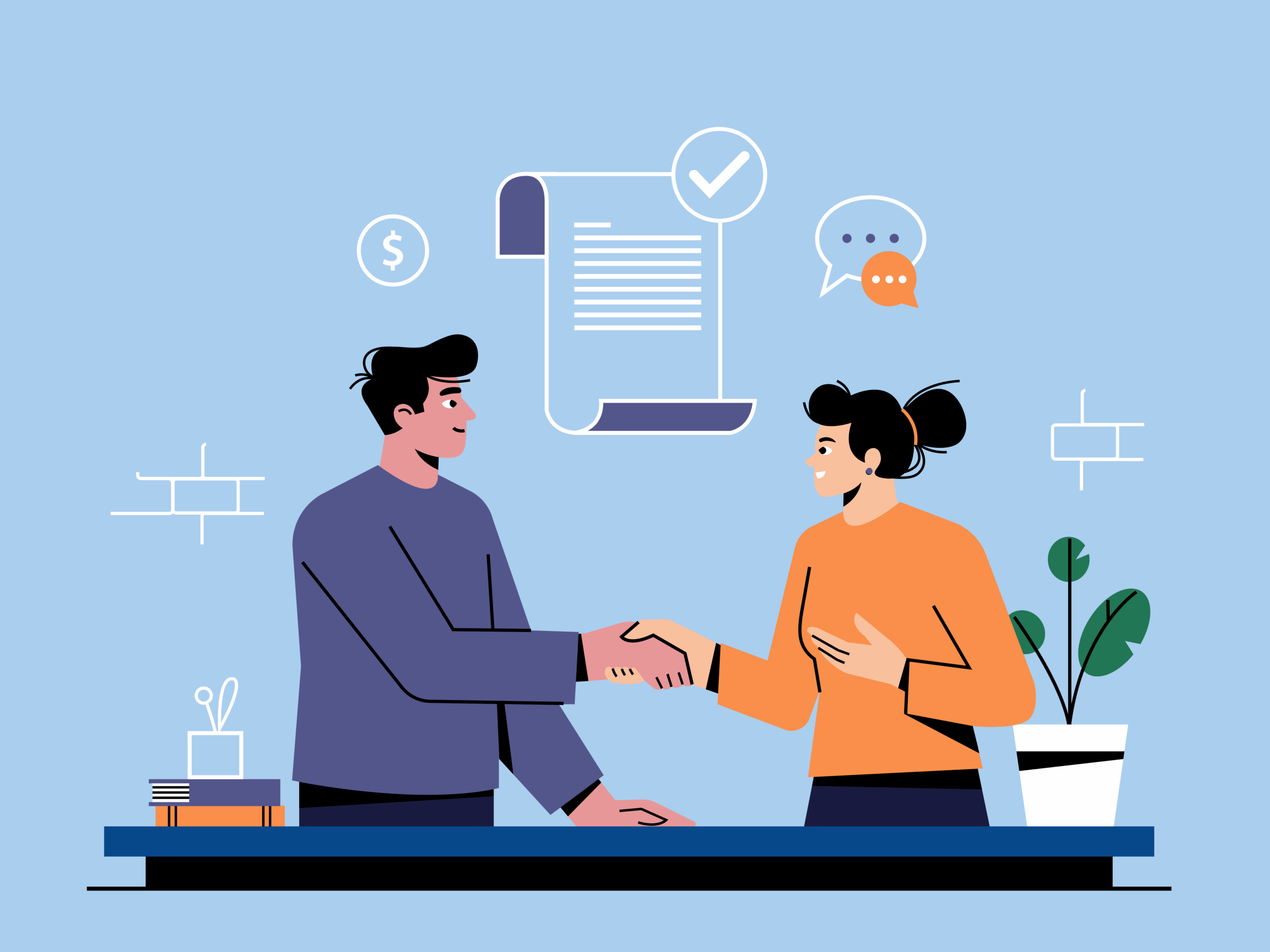“ありがとう”を翻訳すれば売上は跳ねる
こんにちは。ラプロユアコンサルティング事務所 代表の岩上です。
前回のコラムでは、「言葉は、どこに置くかで意味が変わる」という話をしました。
通じなかった言葉が、場所を変えた瞬間に届く。 言い方ではなく、置き方。伝え方ではなく、文脈。 言葉は“意味を変えた”のではなく、“意味を読まれる場所に置かれた”だけだった。
この気づきは、多くの事業と言葉を一歩前に進めてくれます。
でも、そこにはもう一段、問いが残る。
それは、「その言葉は、“誰の欲しさ”に応えていたのか?」という問いです。
言葉が通じた。それはいい。 でも、その先で──本当に“前に進めた”人がいたか?と問われると、少し足が止まります。
実際、こういう瞬間があります。
- 「これこれ、まさに私が欲しかったやつですよ」
- 「ちょうど弊社でこのようなサービスを探していたところなんです!」
- 「本当にすごいタイミングですね!なんで、いまこれを出してきたんですか?ズルいな…(笑)」
これが、言葉が通じた“その先”、心に触れたリアクションです。
ニーズ、ターゲット、ペルソナ──たしかに重要です。 でもそれだけでは、人はここまでの反応はしない。
人が動くのは、“言わなくても欲しかったこと”を、先に言われたときなんです。
今日のコラムは、マーケティングの話でありながら、言葉の“訳し方”の話でもあります。
届けるとは、機能を伝えることではない。
「ああ、それが欲しかった」と思わせる言語の輪郭を描くこと。
その設計があるかどうかで、 通じただけの言葉が、“届いた”という実感を持てるかどうかが分かれます。
今日はその“差”の正体を、一緒に問い直してみましょう。
アイディアは“できること”で止まりがち
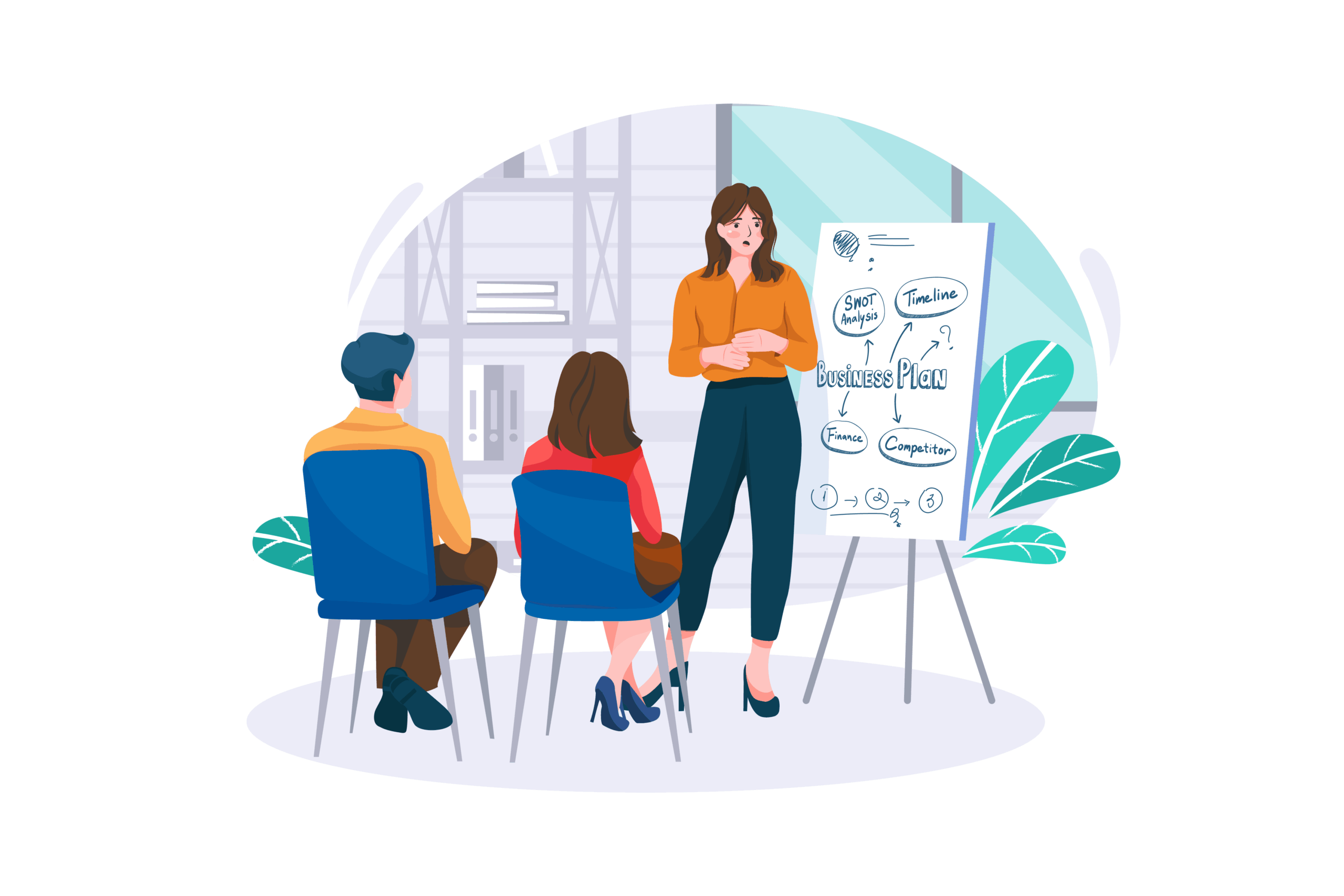
図:そのアイディア、本当に“誰かの前に届いている”か?
気づくと私たちは、「自分ができること」からアイディアを考えています。
知識があるから。スキルがあるから。仕組みが作れるから。
それ自体は素晴らしい。でも、そこに落とし穴がある。
「できるからやる」だけで止まってしまうと、言葉が自己完結してしまうんです。
たとえば、あるコンサルタントが「資料作成のスピードが武器です」と言っていたとして、 それは果たして“誰のための武器”なのか?
「私は◯◯が得意です」
「△△の資格があります」
「□□のスキルが活かせます」
この文脈では“自分が持っている能力”が主語になっていて、 “誰が前に進めるのか?”が抜け落ちてしまっていることが多い。
でも、実際に心を動かす事業は、“自分ができること”の先にある“その人が言葉にできなかった願い”に応えているものです。
以前、私は“思想性の強いライティング講座”を立ち上げたことがありました。
内容は我ながら本質的で、構成も完璧。でもまったく動かなかった。
なぜか? 誰かの“今”に刺さっていなかったんです。
“欲しさ”じゃなく、“正しさ”で語っていた。 だから、“正しいけど届かない”言葉になってしまった。
そこから私は学びました。
届く言葉とは、必要とされる瞬間に現れた言葉なんだと。
それは、「この人、たぶんこういうしんどさがあるだろうな」
「きっと、ここで止まってる気がする」
そんな相手の“見えない痛み”への想像力から始まるんです。
自分ができることだけで構成されたサービスは、“空いてる棚に自分の得意商品を並べただけの店”に似ています。
見た目は整っている。商品もきれい。 でも、お客さんからすると、「この店、自分のために設計されてないな」と感じてしまう。
「欲しいものが“結果的に揃ってる”」と、「欲しいものを“揃えてくれている”」は、まったく違うUXなんです。
「できること」はスタート地点でしかない。
本当に動く言葉は、「あなたの“こうなりたかった”に、私は応えようとしている」から始まります。
できれば今すぐ、「自分ができること」を3つ書き出してみましょう。
その横に、「これを“わざわざ欲しがってくれる人”は誰か?」を想像して書いてみてください。
例:
・Googleスプレッドシートの自動化 → 経理の人が残業1時間減らせる
・商業文のライティング → 自分の想いが言葉にできない起業家
・契約書のドラフト作成 → 自分で法務を見るしかない個人事業主
「できる」ことは、誰かにとって「前に進める」力になるかもしれない。
それを翻訳してあげるところから、言葉は“他者向け”になるのです。
“誰の『言わなくても欲しかったこと』か?”を問う
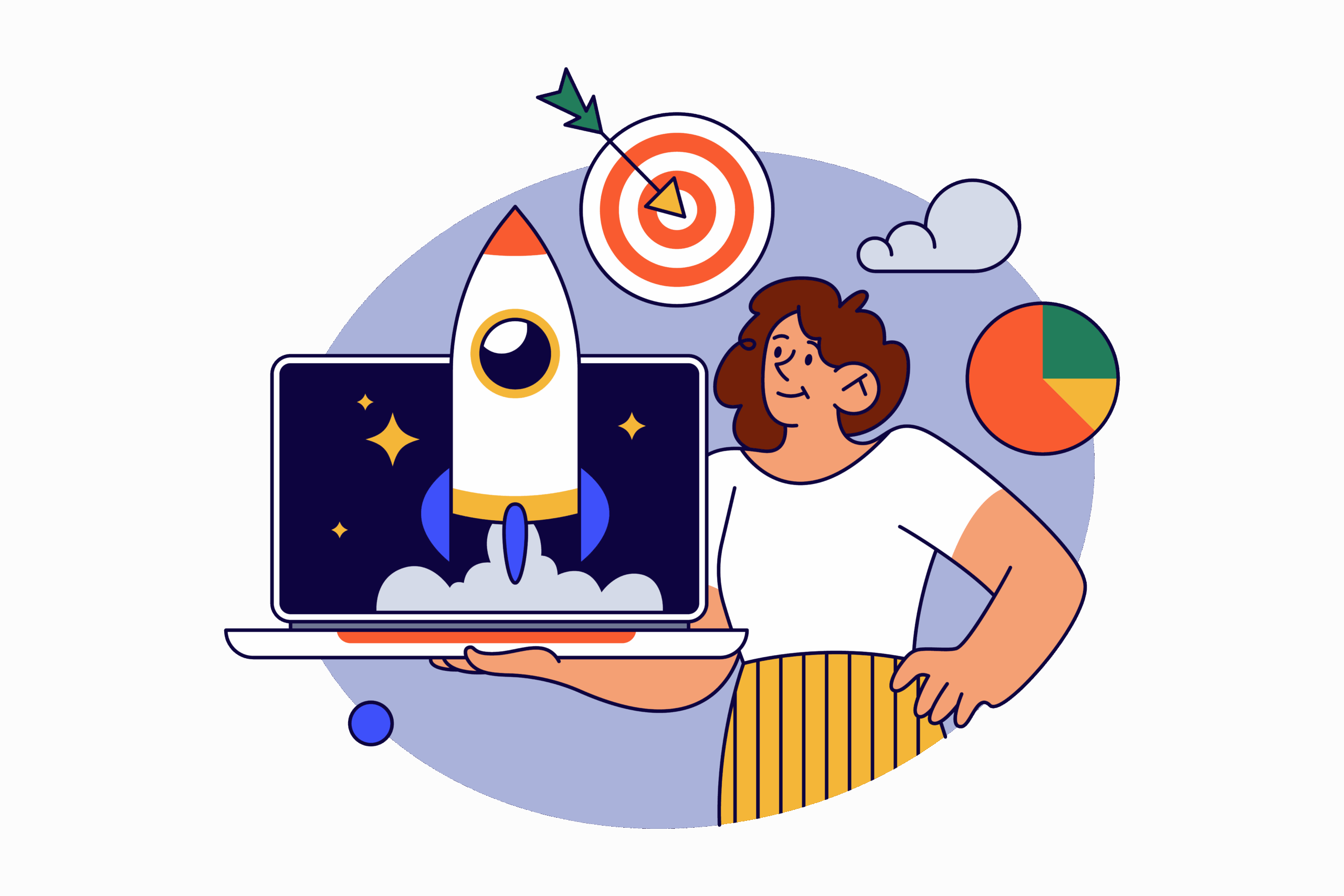
図:「あなたのためだ」と言える誰かが、そこにいるか?
本当に言葉が届いていたか? そう問い直すとき、私は必ず「ありがとう」と言われた記憶を掘り返します。
感謝の言葉って、ただのリアクションじゃない。
「この人は、きっとそれを言いたくて言ったんじゃない」
そう思える瞬間がある。
たとえば── 以前、ある法人代表の方が「岩上さんのサイトを見て、初めて“自分の悩みが正しい形で書かれてた”って思った」と言ってくれたことがありました。
それは“共感された”というより、“ようやく自分の渇きが言葉になった”という瞬間だったと思います。
だから私は、「ありがとう」の中身を疑うようにしています。
・それは何に対するありがとうだったのか?
・相手はどういう気持ちでその言葉をくれたのか?
・“どこで詰まっていたもの”が動いたから出た言葉だったのか?
ビジネスになる/ならない以前に、
“その人の中の何か”がちょっとだけ前に進んだとき、人は感謝の言葉をくれるんです。
それを、私は「言わなくても欲しかったことのカケラ」だと思っています。
事業という言葉の根本には、「誰かの欲しさ」が潜んでいる。
“届けたい人の顔”が曖昧なままだと、言葉はどこかに浮いたままになる。
たった1人でもいい。その顔を、思い出せるかどうか。
ちょっと立ち止まって考えてみてください。 昨日あの人から言われた「ありがとう」の中で、
“なんでこの人は、これを言ってくれたんだろう?”と思った瞬間を3つ思い出してください。
・その時、相手はどんな状態だった?
・自分は、何を提供した?
・その人の“言葉になっていなかった願い”を想像すると?
その瞬間に含まれていたものが、 あなたの言葉が“誰に向けて発せられたか”の原点かもしれません。
マーケティングとは、“欲しさの言語”を翻訳する営み
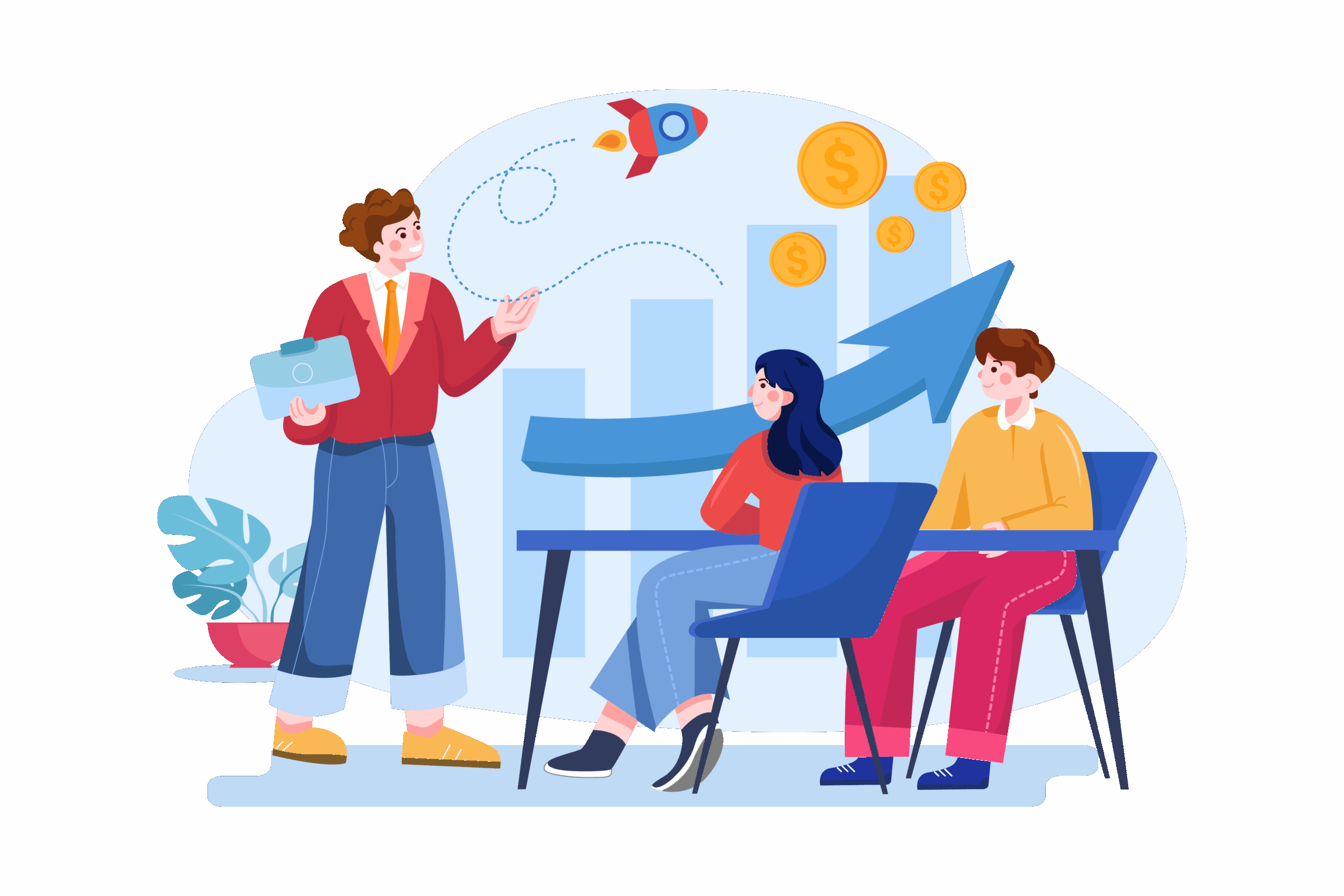
図:マーケティングは、まだ言葉になっていない欲しさを見つけ出す翻訳機構である
マーケティングという言葉には、どこか“操作の匂い”がついています。
「買わせる」「申し込ませる」「欲しがらせる」── そんな風に“人を動かす”ことが目的化された言葉として、認識されている場面が多い。
でも、本質的なマーケティングは違います。
マーケティングとは、“言わなくても欲しかったこと”を、言葉にして届ける営みです。
ピーター・ドラッカーはこう言っています。
「マーケティングの目的は、販売を不要にすることである。」
― Peter F. Drucker (出典:識学総研)
つまり、顧客の“欲しさ”にあらかじめ応えられていれば、 わざわざ“売る”という行為そのものが必要なくなる。
その人が「こうしてほしい」と言っていなくても、 実は「もうちょっとだけこうだったらいいのに」と感じている領域がある。
優れたマーケは、その領域を“探しにいく”のではなく、すでにそこにあると仮定して、言葉を差し出す。
たとえば──
- 「このボタンを押せば5秒で終わります」より、 「もう“面倒”を感じる余地がなくなります」と言われた方がラクになる
- 「スムーズなUI設計」よりも、 「“使い方を考える時間”が0になります」と言われた方が理解が早い
この違いは、“機能”を説明しているか、“状態”を言語化しているかなんです。
そして人が本当に欲しているのは、たいてい機能ではなく“こうなりたかった”という感情の収まりどころ。
つまり、人は商品そのものを求めているのではなく、“それを通して手に入る未来の状態”を欲しているということなのです。
悪いマーケティングは、この構造を“操作”にすり替えてしまいます。
「不安を煽る→安心を売る」
「欠乏を指摘する→理想像を売る」
「劣等感を刺激する→優越を売る」
行動は生まれても、共感は残らない。
そして人は後から気づくのです。
「動かされたけど、腑には落ちなかったな」と。
だからこそ私は思うのです。
マーケティングとは、商品説明ではなく、“その人がまだ言語化できていない願い”を、先に言葉にして差し出すこと。
そのとき初めて、言葉が“届いた”と呼べるのだと思います。
・ペルソナ論は「想定された誰か」への設計。でも“顔が見えた人”の言葉から出ていない。
・ジョブ理論は「課題を解決する状況」を捉える。でも“こうなりたかった”感情までは拾わない。
・カスタマージャーニーは「動線の最適化」。でも“最初の願い”が未翻訳のまま始まることもある。
このコラムで扱った“翻訳”とは、「言われなかった願いの再構成」である。
つまり、“データに映らないまま感情に残っていたもの”を、先に言葉にする作業です。
3つの問いで、言葉が“欲しさ”に変わる
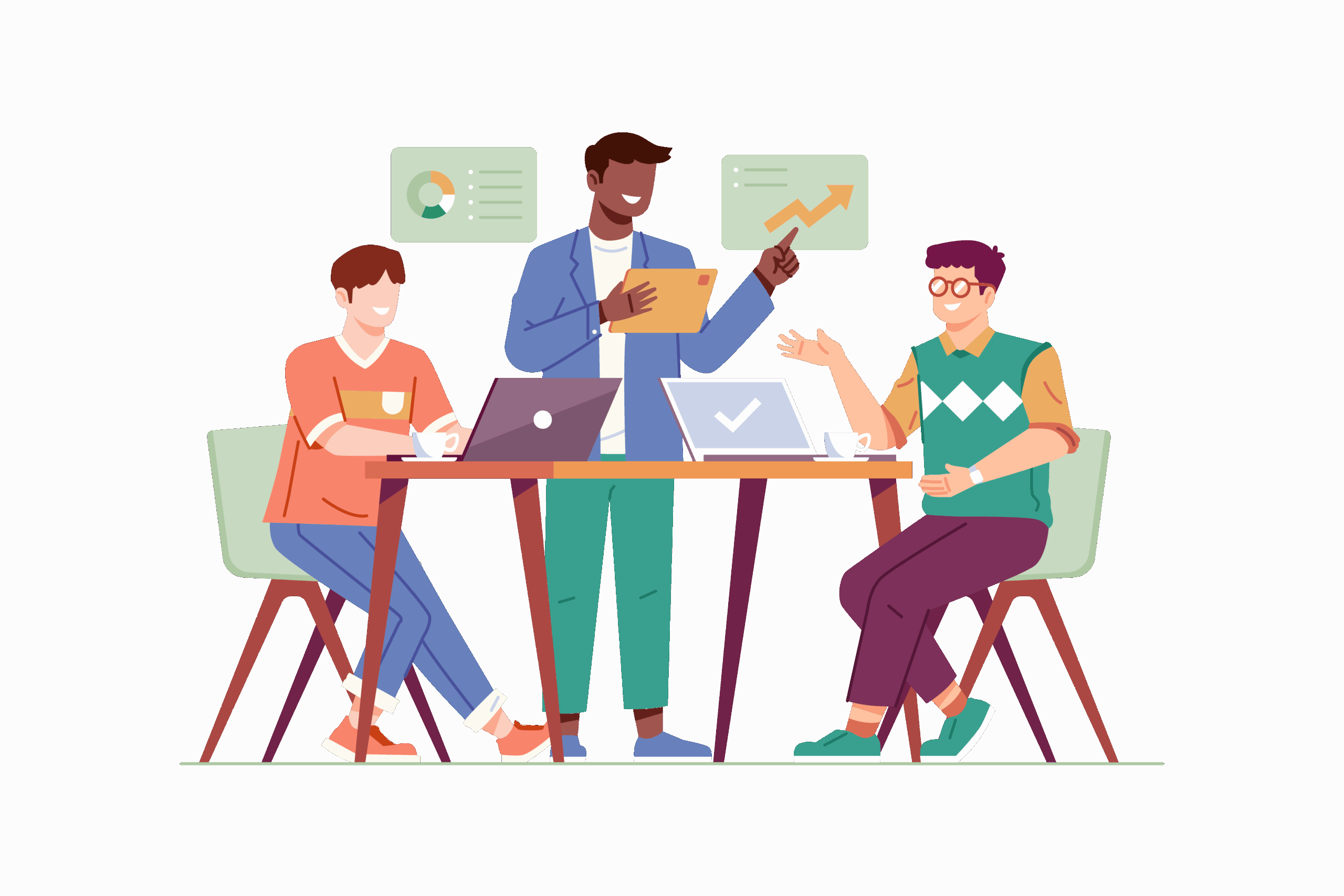
図:問いは、言葉を“欲しいもの”に変えるレンズである
ここまで読んでくれたあなたは、きっと自分のサービスや言葉について、 「何かが足りなかったのかも」と、うっすら感じ始めているかもしれません。
でも、答えはまだ出なくていい。
ここで大事なのは、自分の言葉に“問いを返す”ことです。
問いは、言葉を“翻訳するための補助線”になります。
私は普段、企画や商品開発の現場で、よくこの3つの問いを投げかけます。
- 「このサービス、誰の“こうなりたかった”を実現しようとしている?」
- 「その人は、今の言葉で“自分ごと”として受け取ってくれる?」
- 「今のままで、本当に“前に進める”ところまで行けてる?」
この3つの問いを設計するにあたって、私はいつもレビットの名言を頭に置いています。
「ドリルを買う人が欲しいのは、ドリルではなく穴である。」
― セオドア・レビット (出典:What to Eat Book)
今の言葉が“ドリルの説明”になっていないか?
“穴の話”を、ちゃんと先に語っているか?
マーケティングの本質が「顧客の欲求の翻訳」であるなら、
この3つの問いは、“翻訳の正確さ”をチェックする装置になります。
逆に、この3つの問いにちゃんと答えられていないと、 通じたようで通じていない言葉になってしまう。
たとえば、「これは誰でも使えます」は、 ①“誰のためか”が曖昧で、 ②自分ごととして受け取られず、 ③結果的に“誰にも必要とされない”言葉になりやすい。
「誰でも」は、誰のことでもないんです。
だからこそ、問い直す。
問いは、あなたの言葉を“誰かの前に届く形”に書き換えてくれます。
今日中にやろう!たった1人の“本当に届いた相手”を思い出す

図:あなたの言葉が、確かに“誰か”のためだったと気づけた瞬間
ここまで言葉と欲しさの関係について考えてきましたが、
今この瞬間からできる、とてもシンプルな問い直しワークがあります。
それは、「過去に“本当に届いたな”と思えた相手を、たった1人だけ思い出すこと」。
商品でも、投稿でも、サービスでも──
あなたの言葉や行動で、誰かが少し前に進めたと感じた瞬間を、静かに思い出してみてください。
できれば、名前や顔、声まで思い出せる人がいい。
そして、紙でもスマホでも構いません。 その人がいた“状況”と、“ありがとう”の一言に込められていた背景を、言葉にしてみてください。
・何がしんどかったのか?
・何を代わりに感じ取ってくれたのか?
・何が、“ようやくこれだ”と思わせてくれたのか?
この1人の記憶から、あなたの言葉は再び“翻訳”されはじめます。
届けるとは、届けたい人の“感情のまま”を代わりに言うこと。
そこに戻って言葉を書き直したとき、
あなたの事業は“誰かの欲しさの輪郭”を取り戻すのだと思います。
誰か1人から始めてください。 そして、その人のために、あなたの言葉を1文だけ書き直してみてください。
最初の言葉は、いつだって“小さな確かさ”の中にあるんです。
■届ける前に書き出す3問
① この言葉は、誰に届いてほしい?
② その人は、どんな“言わなくても欲しかったこと”を抱えてる?
③ 今の言葉は、“説明”になっていないか?“共鳴”してるか?
■言い換えテンプレ
「◯◯ができます」→「◯◯なあなたの□□を、今より△△にできます」
これを下書きの前に数分やるだけで、あなたの言葉は“届く言葉”に再構成され始めます。
テンプレ変換例:業界・職種別に“欲しさ翻訳”してみる
■IT系エンジニア
「バグをすぐに修正できます」 →「夜中の通知で起きなくて済みます」
■人事・採用
「候補者管理がしやすい」 →「“この人どうだったっけ?”を検索する手間が消えます」
■フリーランスライター
「構成から執筆まで一気通貫で対応します」 →「“全部言語化するの面倒”なあなたの右腕になります」
“機能→状態→欲しかったこと”の三段変換を意識するだけで、言葉は一気に他人ごとから自分ごとになります。
まとめ:届けるとは、欲しさの輪郭を翻訳すること
マーケティングとは、売ることではない。
「それ、まさに欲しかったやつです」と言われること。
その一言をもらうために、言葉を設計するのではなく、“翻訳”しなおす。
あなたのサービスは、誰の“こうなりたかった”に触れていますか?
今の言葉は、その人の“今のまま”で受け取られていますか?
届けるとは、強い言葉を放つことではなく、 その人の中にすでにある願いを、そっと言葉にすること。
だから私は、マーケティングを“欲しさの翻訳”と呼びたいと思うのです。
- マーケティングとは、「欲しさ」を“自分の言葉”に翻訳する営みである
- 誰でも使える言葉は、誰にも刺さらない言葉になりやすい
- 届けるとは、「言わなくても欲しかったこと」に応える試みである
よくある質問(FAQ)
- Q1. 「誰の欲しさか?」って、どうやって見つけるの?
過去に“ありがとう”と言われた瞬間を掘り返すのが一番早いです。
「何が前に進んだのか?」を思い出してください。 - Q2. どうして「できること」じゃダメなんですか?
“できること”はあくまで自分視点。
“必要とされたこと”は、他者視点です。
その差が、言葉の跳ね方に現れます。 - Q3. 機能を訴えるのと、欲しさを翻訳するのはどう違う?
機能は「何ができるか」、
翻訳は「なぜ、それが必要だったか」を伝えます。
人は“必要性”の方に、より深く納得します。 - Q4. それって結局、煽るマーケとどう違うの?
煽りは“不安を増やして行動を促す”構造。
翻訳は“共感と発見で行動を促す”構造です。
後者には、感謝と持続が残ります。
電通総研が全国12,000名を対象に実施した
「クオリティ・オブ・ソサエティ指標2024」によれば、
「国のデジタル化施策が進んでいると実感する」と答えた人は
わずか33.6%にとどまりました[1]。
企業メッセージや行政施策が “届いていない” ギャップは、
私たちが「言語の置き場所」を誤ると発生する典型例だと言えます。
[1] 電通総研 ヒューマノロジー創発本部 Quality of Societyセンター 「次世代への展望と地域に対する人びとの意識 〜クオリティ・オブ・ソサエティ指標2024より〜」 (2024年10月17日リリース, p.3) https://www.dentsusoken.com/news/release/2024/1017.html
「誰に“ようやく届いた”と言われたか?」
そこから、あなたの届ける言葉は、また始まります。
またお会いしましょう。