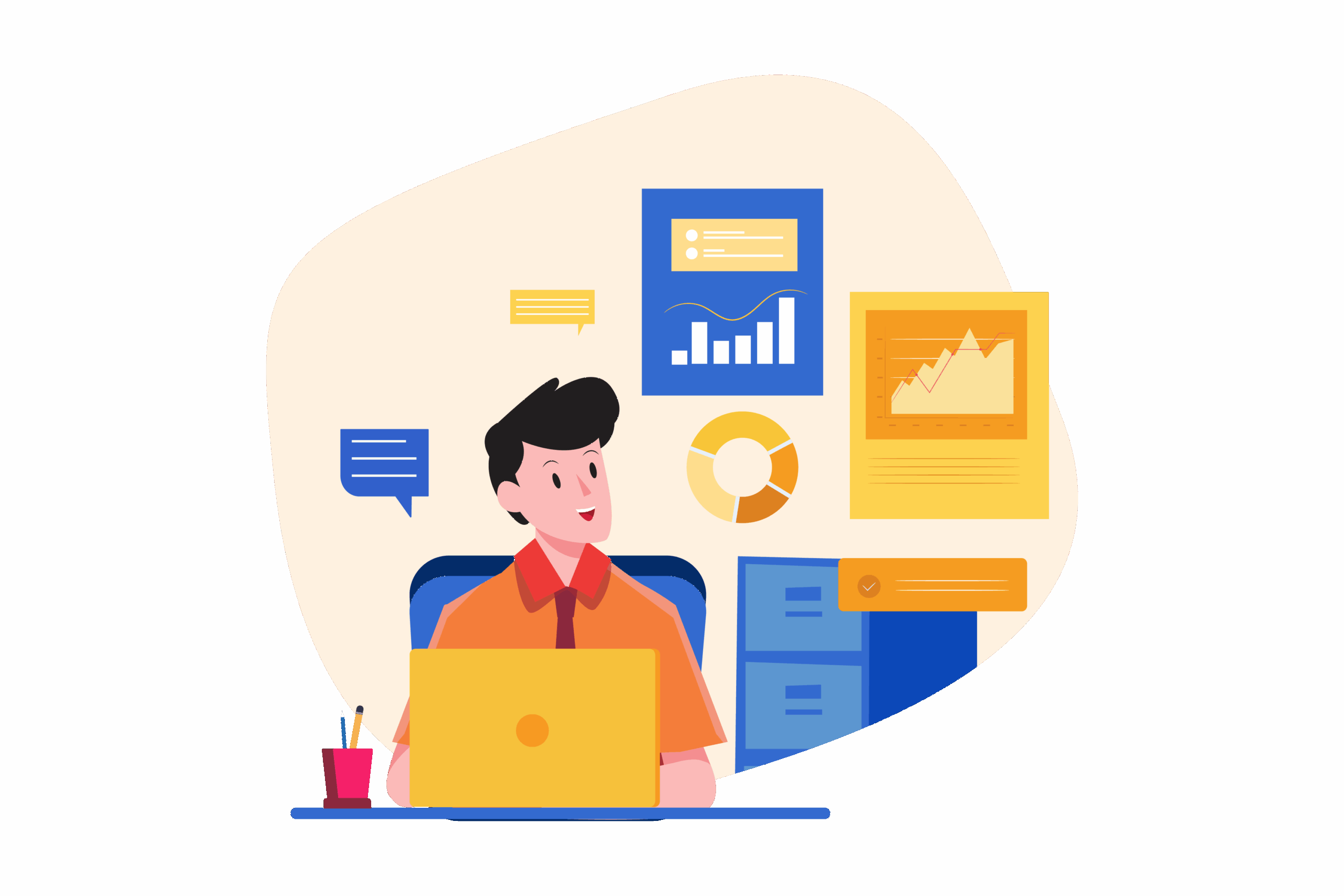「正しさ」に潰される企画書たち
こんにちは。ラプロユアコンサルティング事務所 代表の岩上です。
- ✔ 論理的に説明したのに、なぜか刺さらないことがある
- ✔ 資料も構成も悪くないのに、会議で通らなかった経験がある
- ✔ 企画の内容以前に、「聞いてもらえてない気がする」ことがある
もし1つでも当てはまるなら、このコラムが何かのヒントになるかもしれません。
資料を丁寧に作り込んだ。ロジックも整っている。構成も評価されてきた。 それにもかかわらず──
「何かずれてますね」
「いや、理屈は正しいと思うんですが…」
「これは誰の問題なんでしたっけ?」
返ってきたのは、そんなそっけない返答。 それは、あなたの企画が“間違っていた”のではなく、“潰された”のかもしれません。
なぜなら、現代の企画環境では「正しさ=通る理由」にはならないからです。
認知心理学で言う「メンタルモデルの非対称性」── “送り手と受け手で納得構造がまったく違う”状態が、あらゆる職場で起きています。
その中で“論理的構成”や“構文の美しさ”はむしろ、 「分かってる風」な資料を生み出し、現場感と乖離してしまうこともある。
私自身、何度もそれをやりました。 正しいつもりで、全部潰されました。
でも、ある時から問いを変えたんです。
「この正しさは、誰の“納得回路”に基づいてる?」
この問いを立ててから、言葉が変わり、結果が変わり、何より
“通らなかった理由”が自分の手元で分析できるようになりました。
今日のコラムは、ただのマーケティング論でもなく、資料構成ノウハウでもありません。
正しさが潰される構造そのものに目を向け、
“実務で使える問い直しの技術”としてお渡しするコラムです。
具体的には、企画書・提案・スライドなど、どのアウトプットでも応用できる 「潰されないための問い」と「納得モデルの調整法」をお届けします。
本質は、通らない資料を「もっと正しくする」ことではありません。
“誰に、どんな納得の文脈で”届くのか?
その構造から、問い直していきましょう。
「正しさ」は“構文”として整えば通る、という誤解
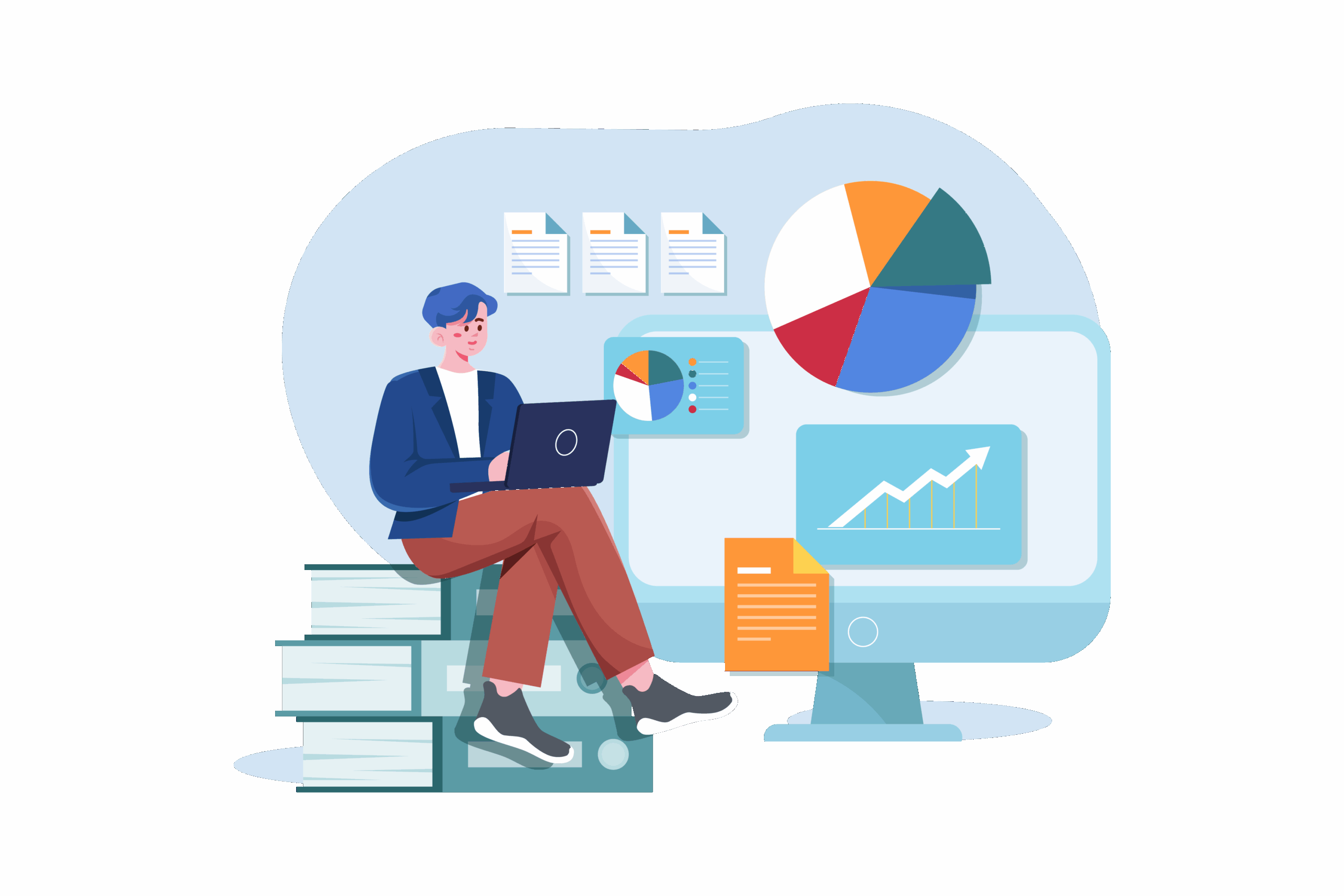
図:構文は正しくても、「誰のための構文か?」がズレると通らない
PREP法、ピラミッドストラクチャー、AIDMAモデル、ロジカルシンキング── どれも“企画を正しく伝える構文”として磨かれてきたフレームです。
私自身も長年、これらを重視してきました。 ロジックを磨き、余白をなくし、流れを整える。 「これだけ完璧なら、通らないはずがない」と。
でも現実は、何度も潰されました。
論理が通っていた。調査データも揃っていた。構成も評価されていた。 ──にも関わらず、「…で、これは誰が困ってる話ですか?」の一言で終了。
いま振り返れば、あの瞬間の私は「論理の正しさを、誰の回路にも接続せずに放っていた」んです。
心理学者ハーバート・サイモンの「限定合理性理論」では、 人間は常に「全体の正しさ」ではなく、“自分の中の納得と整合性”で判断しているとされます。
つまり、いくら正しくても── その“納得のスロット”に差し込まれなければ、ただのノイズになる。
加えて、ハイレベルな構文ほど「詰め過ぎによる認知過負荷」を引き起こします。
認知心理学の研究では、人間がプレゼンで処理できる論点は平均3.7個という統計もあり、 情報が多すぎる=伝わらないという逆説が常に付きまといます。
私が潰された資料は、まさにそれでした。 “構文として正しすぎた”せいで、誰の直感にも刺さらなかった。
ここでひとつ問いを置きたい。
あなたのその正しさ、構文は整っているけれど── “誰の頭の中の回路”に届くように設計されてますか?
■ ありがち構文例:
・「まず課題があり、その原因を特定し、施策を提案します」
・「業界の平均数値に対して御社は◯%劣っているので導入すべきです」
・「今後◯年でこの領域の市場が伸びると予測されています」
■ なぜ潰される?
・原因や比較が“自分ごと”になっていない
・数字や構成に対して“で、誰がそれを問題と感じてるの?”と問われる
・「そうですね」と思われても、「だから導入したい」とは結びつかない
論理の構文が整っていても、“感情の着地点”がなければ、企画は前に進まない。
誰の“納得回路”に沿っていたのか?を見誤る

図:構文が通っても、納得の着地点がズレていると潰される
正しさを言葉にするとき、私たちは無意識に“自分が納得できる構造”で話を組み立てています。
だから「これなら納得してもらえるはずだ」と信じて、話す。 でも、その納得構造は──相手とは違うものかもしれない。
心理学ではこれを「認知スタイル(Cognitive Style)のズレ」と呼び、 人によって情報処理の優先順位や納得の“型”が根本的に異なるとされています。
たとえば、ある人は数字で納得したい。 別の人はエピソードで共感しないと動かない。 さらに別の人は、抽象概念より具体アクションで腹落ちする。
この“納得の型の違い”を認識せずに出した言葉は── いくら正しくても、“違う言語圏”で翻訳されないまま潰されるんです。
私が自治体案件で経験した「公平性は大事です」と説いたプレゼンもそうでした。 そのチームにとっての正しさは「制度の正当性」ではなく、“現場で運用可能かどうか”だった。
同じ資料を別の市長には絶賛されたのに、その現場では通らなかった。
正しさの“モデル”が違えば、全く同じ言葉でも真逆の結論になるんです。
納得回路とは、単なる好みではなく文化・立場・経験・目的に根ざした思考モデルのこと。
だから、資料を作る時や言葉を届けるときには、 「この正しさは誰の納得モデルに沿っているか?」を、最初に設計するべきなのです。
問い直してください。
この構成、このトーン、この主張── “どの納得回路”に、どんな速度で届くように作っていますか?
共通語彙がなければ、“正しさ”は誤読される
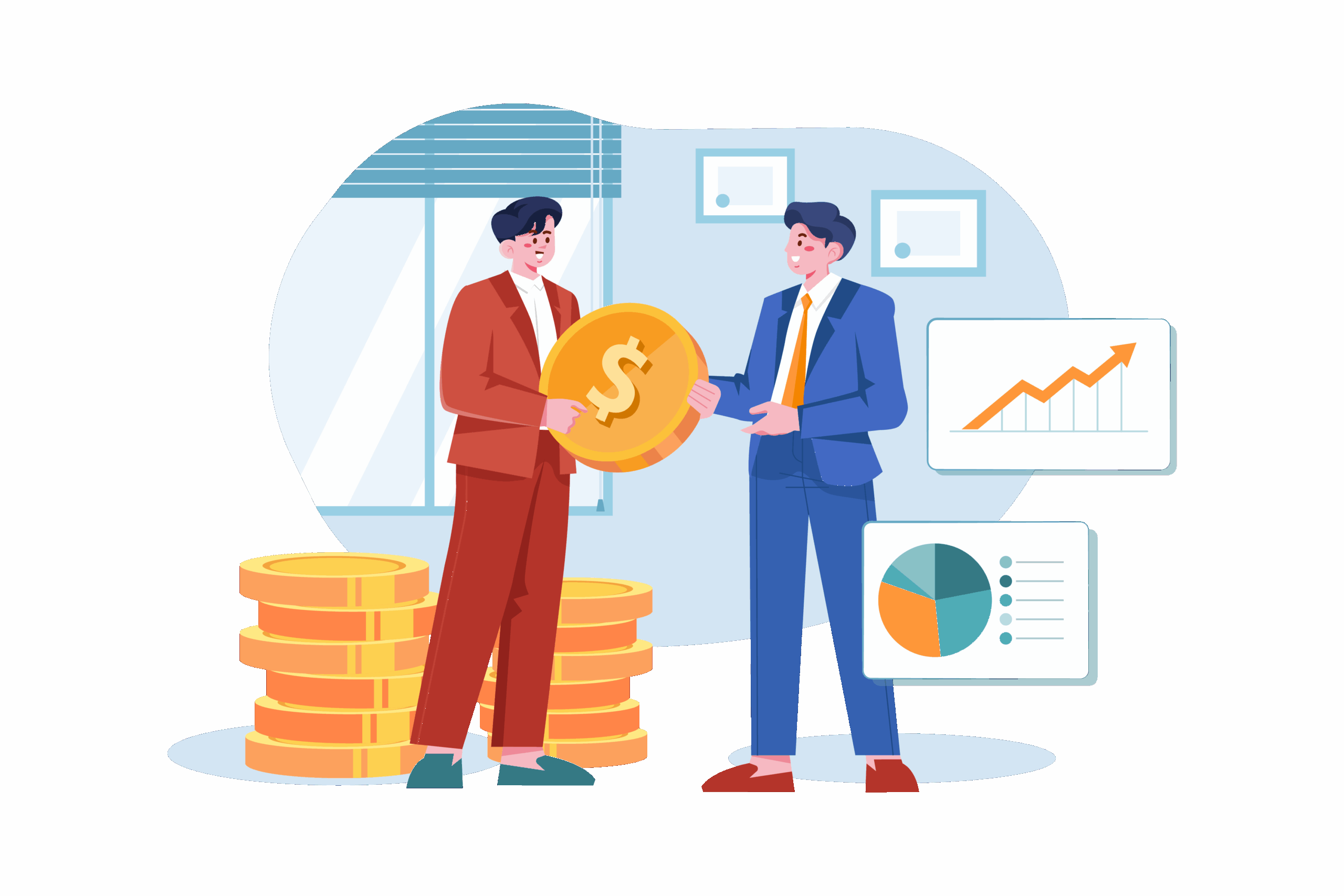
図:語彙が共通していなければ、“通じる正しさ”にはならない
正しさが潰される最大の要因のひとつが、「語彙のズレ」です。
同じ言葉を使っていても、“読み手の中に存在しない文脈”では、 その言葉は“別の意味”で解釈されてしまう。
これは心理言語学でいう「スキーマ処理理論(schema-driven comprehension)」に基づく現象です。
人は言葉を読むとき、内容そのものを理解しているのではなく、 過去の経験・文化的前提・感情記憶に基づく“意味の枠組み”に照らして理解しています。
スタンフォード大学の研究では、初見の概念語に対し、文脈共有がない場合の理解誤差は最大40%に達するとされています。 (※出典:Just & Carpenter, 1992)
たとえば、「心理的安全性」「エンゲージメント」「ナレッジ」などの言葉。
- 人事担当にとっては評価指標
- 現場社員にとっては“どうせまた社内スローガン”
- 経営者にとっては“組織の空気コスト”
同じ単語でも、“意味づけのコード”が違うと通じない。
この現象は、日常のどこでも起きます。
会議で「スケーラビリティが課題です」と言ったら、 技術部は「処理能力」と受け取り、 営業部は「横展開の体制」と読み替え、 経営は「人件費の限界」と解釈していた。
これは、“語彙は通じているけど、意味がズレている”という 最も厄介なズレのパターンです。
そしてこれは、「企画が通らない理由」でもっとも多く見逃されている。
だから私は、企画や言葉を出す前にこう問い直すようにしています。
「この言葉、相手の辞書にも“この意味”で載っているか?」
正しさを伝えるとは、言葉を載せることではなく、 “相手の意味マップに翻訳済みで届けること”なのです。
■ 例1:スケーラビリティ
・エンジニア:処理能力やサーバー構成の拡張性
・経営層:多店舗展開・横展開可能性
・営業部門:提案先に“使い回せるか”という目線
■ 例2:エンゲージメント
・人事:従業員満足度とエモーショナルな信頼
・マネジメント:離職率・目標コミット度
・現場スタッフ:監視・評価システムの別名と感じることも
単語は“意味”ではなく“文脈”とセットで流通している。 語彙を伝える前に、「どう読まれるか?」を翻訳しておこう。
「正しさ」と「通じること」の分離は、事業開発でも使える
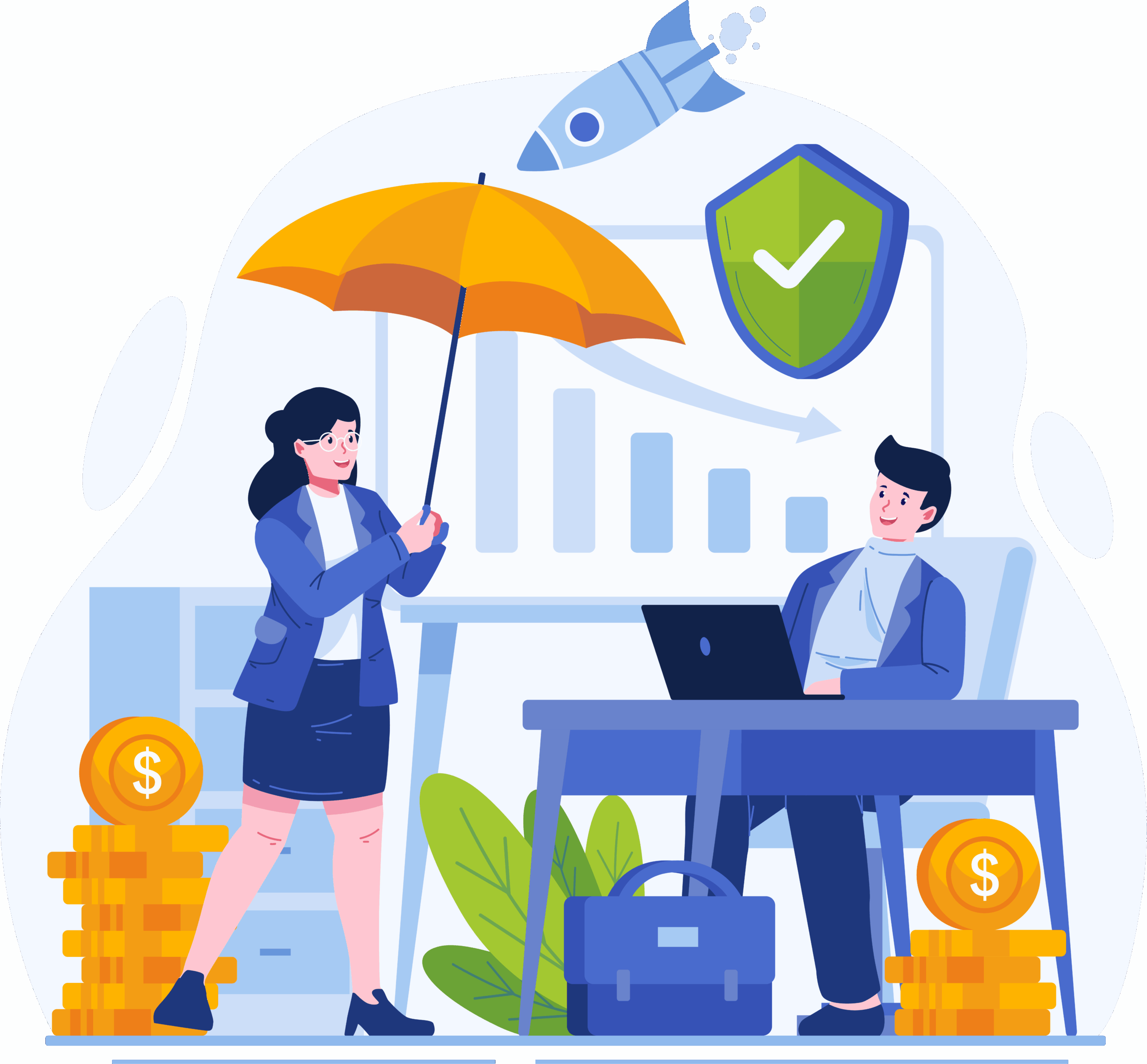
図:同じ“正しさ”でも、通じる人が違えば意味が変わる
ここまで「通らない理由」を言葉・構文・語彙の面から見てきましたが、 この構造は事業開発やサービス設計の現場でも同じです。
たとえば── ある新規SaaS事業の導入資料を作るとします。
- 社内向けには「工数削減と属人性の排除」でロジックを固める
- 顧客向けには「やりたくない業務からの開放」という言語で届ける
- 投資家向けには「スイッチングコストの優位性とARR拡張モデル」で構成する
どれも「正しい」けれど、まったく違う言葉になる。
つまり、正しさとは“共通ルール”ではなく、“届ける相手の思考モデルに合わせて調律されるもの”なのです。
この“構文分離”の視点があると、通らなかった提案も分解できます。
私の知人のUXディレクターは、同じ改善案でも
- 「NPS+12%」「LTV1.3倍」などの数字に置き換えたら経営会議が通過し、
- 一方で「ユーザーが“イライラしないで済む”設計」と書いたらCSチームが全面協力に変わった
つまり、通らなかったのは「正しさ」ではなく、「納得回路」だった。
だから私は企画の初期にこう問いかけます。
「この“正しさ”、誰の“通じる形”に翻訳されてる?」
企画とは、正しさの押し出しではなく、納得の翻訳装置の設計なのです。
■ 機能:チャット自動応答機能を提案する場合
・社内IT部門向け:
「既存システムとの互換性が高く、運用負荷が増えません」
・CSチーム向け:
「夜中の問い合わせ対応が、もう“翌朝のストレス”にならなくなります」
・経営層向け:
「カスタマーサポートのROIが◯%改善した企業事例多数」
相手が違えば、“通る文法”も変わる。
言い換えではなく、“翻訳”が必要。
明日までにやってみよう!「その正しさ、誰の言葉か?」
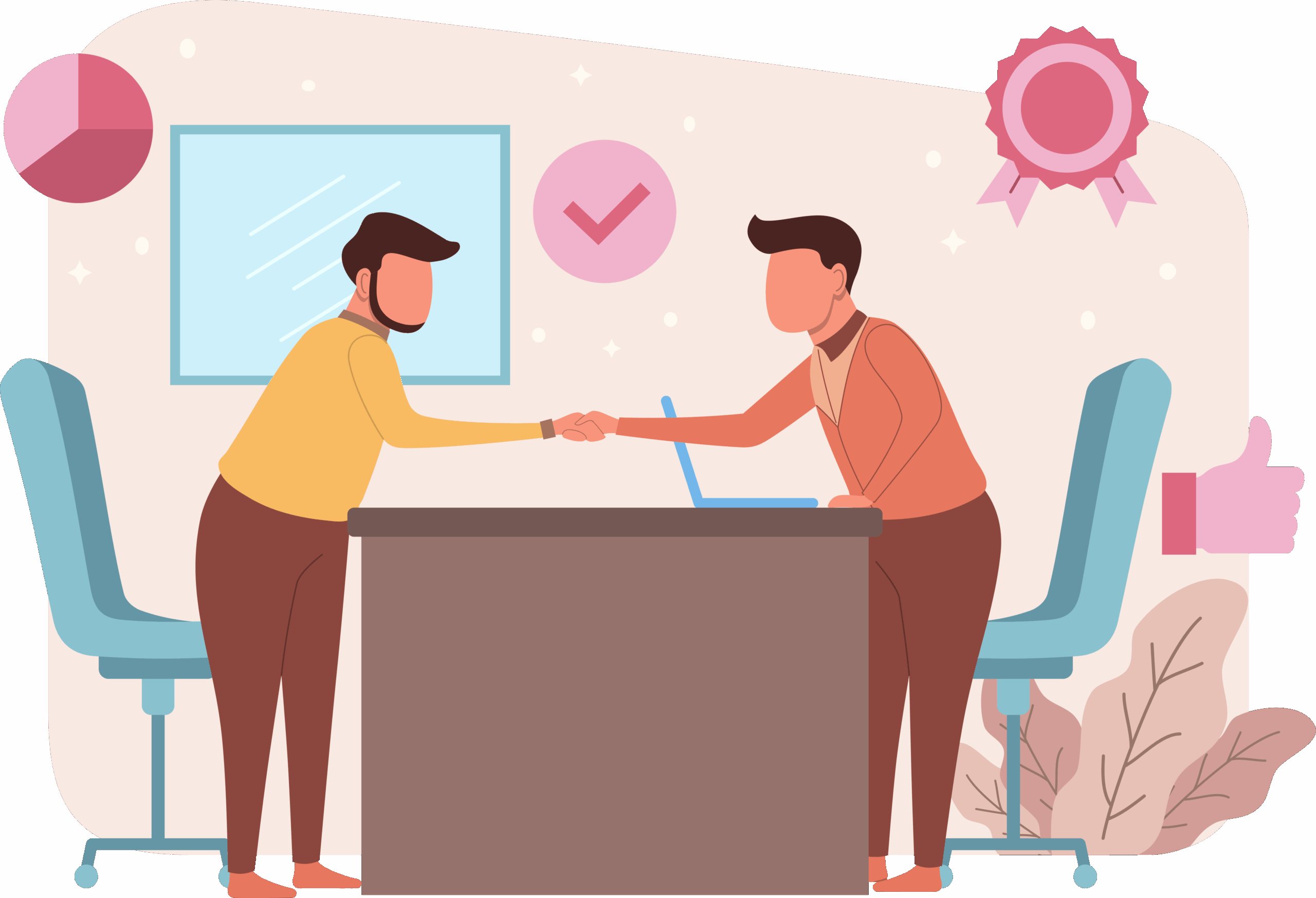
図:正しさは、誰の“意味”として届くかで決まる
ここまで、言葉が潰される構造について見てきました。
構文・納得・語彙──すべて整っていても、“誰の言葉だったか”を見誤ると届かない。
では、何から問い直せばいいか?
すぐに実務に活かせる視点として、私はこの3つの問いをおすすめしています。
- この構成・構文は、「誰の納得の型」に沿っているか?
- この言葉は、「相手の意味マップ」に翻訳済みか?
- この正しさは、「通じたあとに動いてもらえる設計」になっているか?
もし、この3つすべてに「YES」と答えられないなら──
その資料・その言葉は、通らない可能性が高い。
正しさは、届け方と翻訳形式によって“価値”が変わる。
だから私は、問い直しを「チェックリスト」ではなく“翻訳プロセス”の一部として扱っています。
■ STEP 1:誰に届けるか
→ 「◯◯部門のAさん」「採用担当の△さん」など“顔が浮かぶ1人”に絞る
■ STEP 2:その人にとっての“納得語彙”を洗い出す
→ 例:「スムーズ」より「仕事が止まらない」の方が刺さるタイプか?
■ STEP 3:構文の順序を、その人の思考リズムに並べ直す
→ データ先か共感先か? 抽象先か具体先か?
翻訳とは、「伝え方」ではなく「受け取り方」の設計である。
だから言葉は、“通したい人の地図”から書き直すべきなんです。
まとめ:正しさは、構文ではなく“届く形”に翻訳せよ
正しさは通らなかった。
それは構成や資料の出来ではなく──
“誰の納得構造に沿って書かれたか”がズレていたから。
構文が正しくても、語彙が違えば通じない。
論理が整っていても、意味が接続されなければ人は動かない。
だから、企画が潰される時に問うべきは、 「何が足りなかったか?」ではなく、 「誰の“正しさの形”を翻訳しきれてなかったか?」なんです。
届けるとは、“その人の思考フローを一度歩いてから”言葉を置くということ。
それができたとき、正しさは潰されず、“納得”という力に変わります。
- 正しさは、構文の完成度ではなく「誰に向けた翻訳か?」で決まる
- 語彙・構文・納得回路がズレると、通らず潰される
- 届けたい人の“意味の地図”を先に引くことが、届く構文の第一歩
よくある質問(FAQ)
- Q1. 「納得構造」ってどう特定すればいいの?
相手がどんな順番で判断するか(数字から? 共感から?)を観察し、過去に刺さった構文から逆算すると見えてきます。
- Q2. 全員に通じる“正しさ”の構文は作れないの?
構文の普遍化は可能ですが、「届く納得の形」は人や文脈で変わるため、調律(翻訳)は必要です。
- Q3. 翻訳しすぎて“媚びた資料”にならないか心配です
媚びるとは、信念を失うこと。翻訳とは、届け方を変えて“本質を残す”こと。軸を保てば問題ありません。
- Q4. 実際、何を直せばいいですか?
「構成」「言い回し」「語彙選定」「数字の出し方」など、伝える順番と語彙の粒度を相手の脳内順に合わせるだけで一変します。
もし明日、企画書を書くとしたら──
「この構文、誰に届くか?」「この語彙、誰が使ってるか?」「この順番、誰の思考回路と一致しているか?」
この3つを問いながら、1スライドずつ置き直してみてください。
言葉を変えるのではなく、“誰に向けて翻訳するか”が、企画を通す最短ルートです。
「どんな順番で、どんな言葉で聞きたいか」を歩いてみよう。
そのひと手間が、あなたの企画を通す構文になる。
またお会いしましょう。
参考リンク・出典一覧
関連コラム
本記事は、上記コラムと連動した【届く言葉の構文設計3部作】の第2章です。