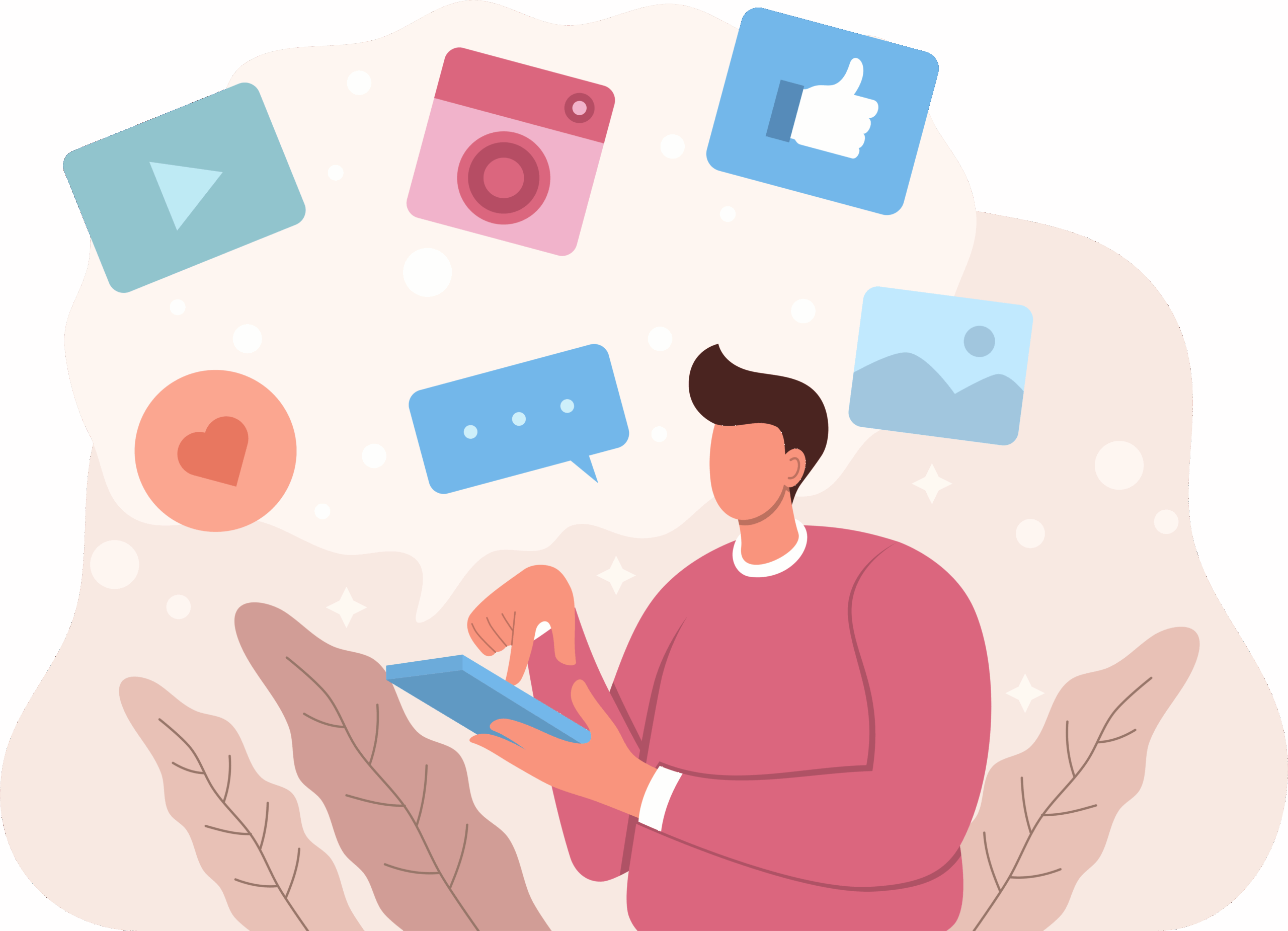こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
近年、生成AI――特にChatGPTのような自然言語処理ツールが、急速にビジネス現場へ浸透しつつあります。
会議録の自動作成、企画提案の草案、社内FAQの自動応答など、業務の効率化に寄与する反面、「もしかしたら自分の仕事がなくなるのでは」といった漠然とした不安が、現場社員の間で静かに広がっています。
ところが経営者の皆様と話をしていると、「うちはまだ関係ないよ」「AIって結局は道具だろ?」という反応も少なくありません。
実際、今は大丈夫かもしれません。しかし問題は、“現場と経営者の間にあるこの温度差”こそが、やがて組織の信頼構造を静かにむしばんでいくという事実です。
この記事では、部下がAIに対してどんな恐れや期待を抱いているのか、そして経営層がなぜ無関心になりがちなのかを紐解きながら、企業が今見直すべき“組織の未来”について、具体的な問いをお届けします。
もし、今この瞬間に部下が「AIが怖い」と口にしていないとしたら、それは“本当に不安がないから”なのでしょうか?
それとも、「言っても無駄だ」と感じているからではないでしょうか。
未来に備える経営とは、技術を追いかけることではありません。
変化の兆しに“耳を傾けること”から始まります。
部下はなぜ“黙って”AIを怖がっているのか
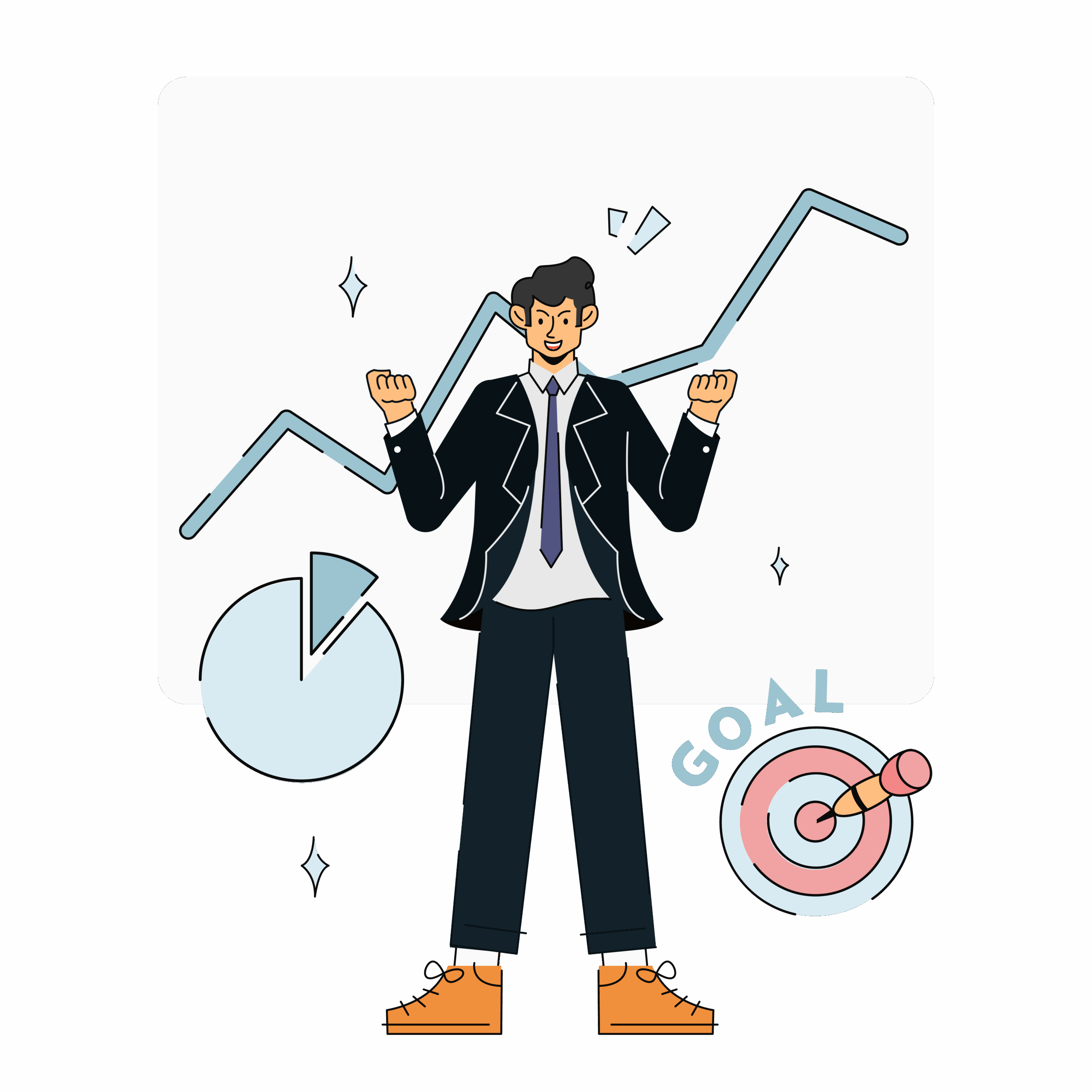
現場で働く従業員は、思っている以上に現実的です。
彼らは「AIがすべての仕事を奪う」とは考えていません。
ただ、「自分の仕事が“真っ先に”代替されるのではないか」という“局所的なリアリティ”に直面しているのです。
たとえば、経理アシスタントが伝票の入力・集計をAI OCRやRPAで自動化される流れを見たとき、そこには強烈な既視感が伴います。
カスタマーサポートの現場でも、「ChatGPTを組み込んだ自動応答」の導入検討が始まれば、誰しもが「いずれ自分の声は必要なくなるのか」と不安になります。
こうした“置き換えられる不安”は、上司には相談しにくいテーマでもあります。
なぜなら、「AIを怖がるのは変化に弱い証拠だ」と受け取られるリスクを、社員は敏感に察知しているからです。
さらに、SNSやYouTubeでは「AIが文章を書いた」「動画を作った」など、派手なデモ動画が毎日投稿されています。
これが“知識”ではなく“感情”として恐怖を植えつけているのです。
実際、PwC『2024年グローバルCXレポート』によれば、67%のビジネスパーソンが「AI導入により職務が変わる/縮小する」と感じており、そのうち38%は“将来の雇用不安”を顕在化させています※1。
部下は、AIへの不安を「合理的に言語化」できないこともあります。
無記名アンケートや雑談ベースの1on1など、感情ベースの声を拾う手段を多層化しましょう。
「AIが怖い」と口にする人は、単なる変化嫌いではありません。
むしろ、今の仕事に真面目に向き合っている人ほど、その価値を失う恐怖に敏感なのです。
経営者として必要なのは、そうした感情に「技術的知識」で答えることではありません。
「不安があるのは当然だ」と受け止める姿勢こそが、信頼を生む最初の一歩です。
経営層の“無関心”はなぜ生まれる?
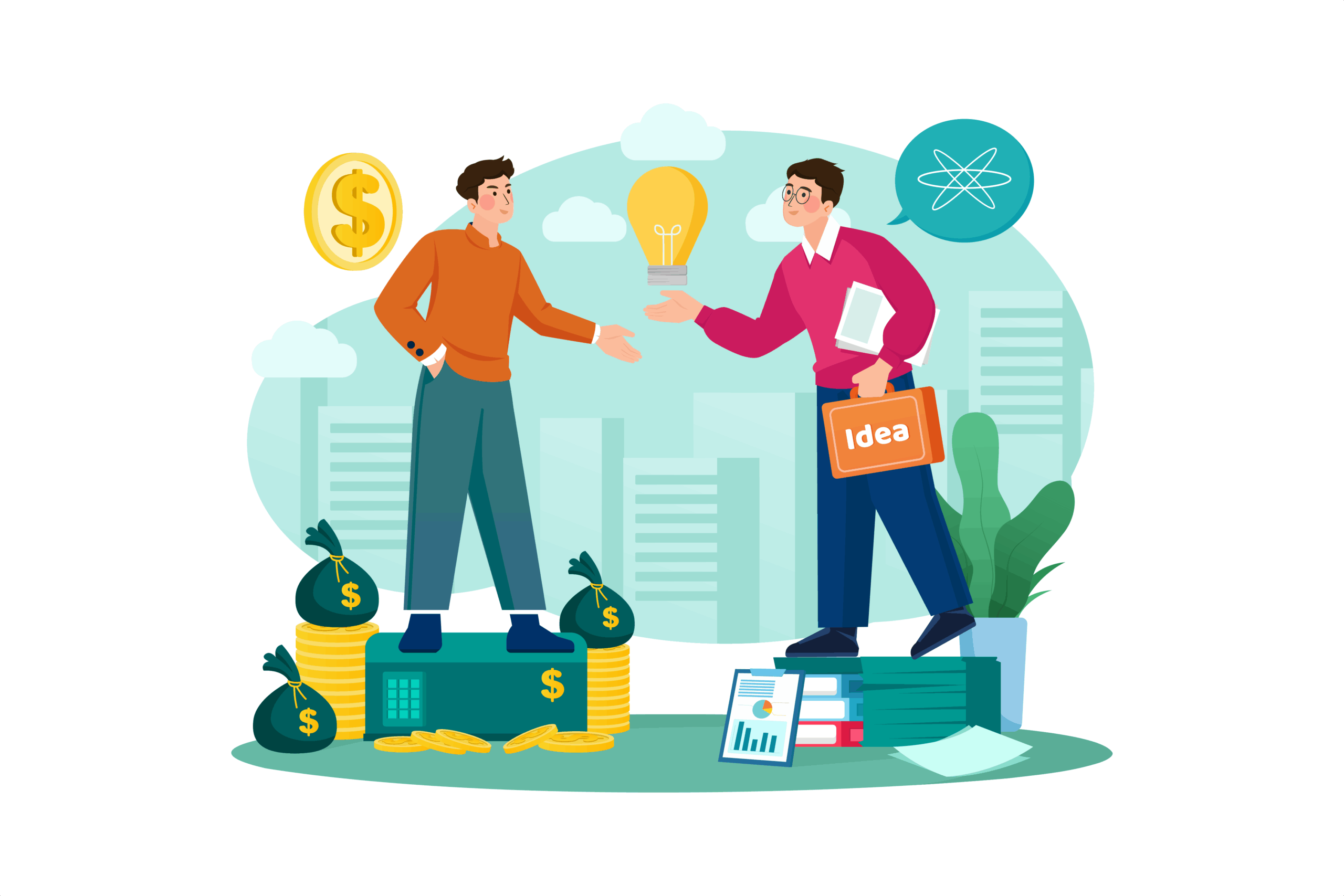
多くの経営者は、日々「人の判断」や「人間関係の機微」をもとに決断をしています。
したがってAIの進化を見ても、「自分の仕事はAIでは代替できない」という実感を持ちやすいのは自然なことかもしれません。
また、導入にかかる時間・コスト・教育などの“見えない手間”が、無意識に「今はまだいい」と思わせる心理的バリアになっていることもあります。
特に、少人数経営の現場では「それより営業が先」「資金繰りが優先」と、日々の実務が“先送りの正当化”になりがちです。
さらに問題なのは、AI導入を「ツールの話」と捉えたまま、“人の話”として考える視点を持ちにくいことです。
部下が感じているのは、ツールの性能ではなく「その導入によって、自分がどう見られるか」という評価リスクなのです。
一方で、経営者の多くは「部下のほうが若いし、ITにも詳しいから」と言ってAI対応を現場任せにする傾向もあります。
ですが、それでは“文化”として根付かせることはできません。
トップが口にしない価値観は、組織では語られない――これは組織論の鉄則です。
✔ 導入にコストがかかるという前提を持っていませんか?
✔ 現場任せにすれば自然に広まると考えていませんか?
✔ AIを“人の議題”として扱っていますか?
この3つを問い直すだけで、経営姿勢が大きく変わります。
もちろん、全ての経営者が最新技術に詳しくある必要はありません。
ただ、「関心を持ち、問い続ける姿勢」が組織の学習文化を育てるのです。
それは技術の話ではなく、経営そのものの話です。
今こそ経営者が問うべき3つの行動
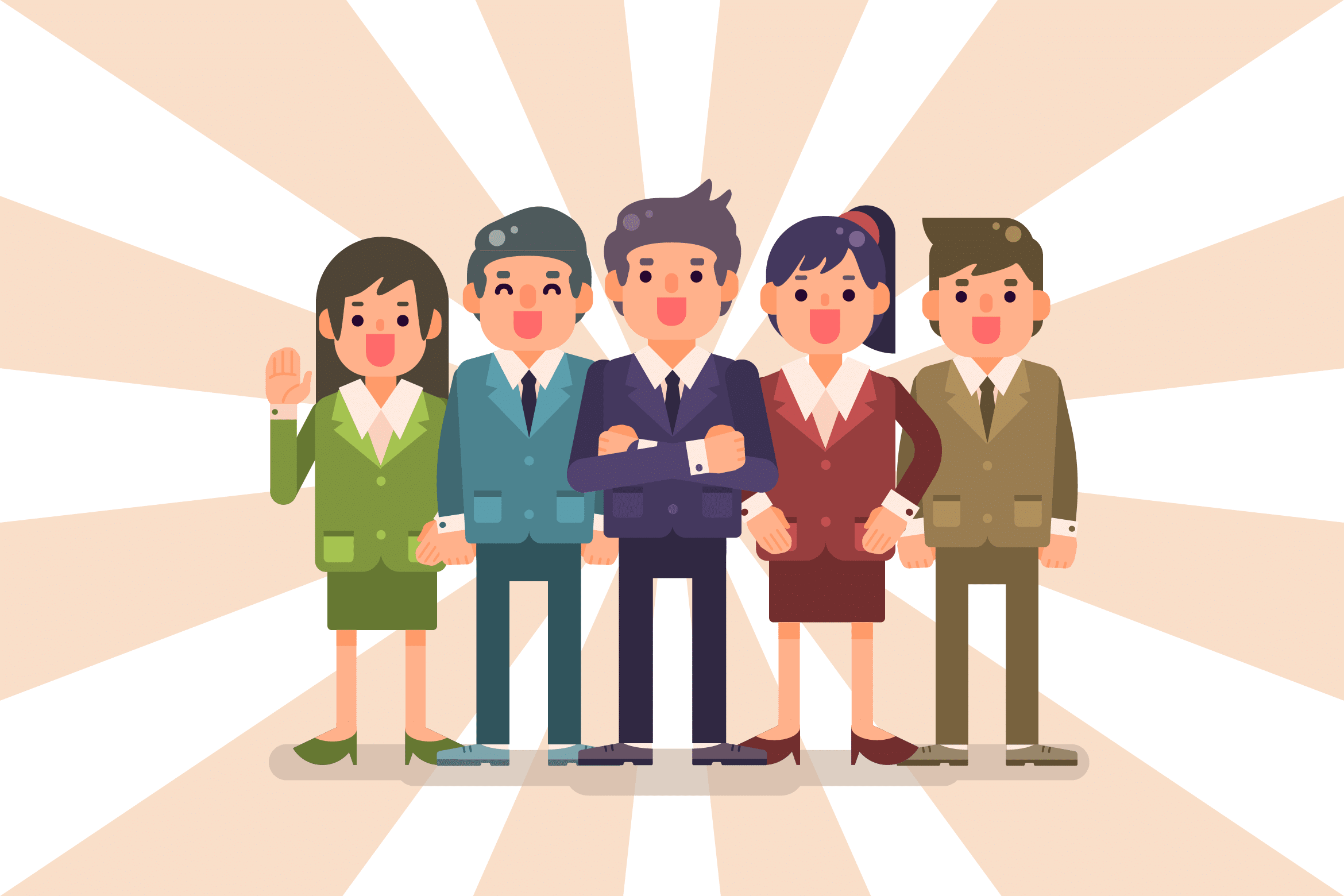
AI導入における最大の誤解は、「技術を知っている人が動けばいい」という発想です。
しかし、どれだけツールやノウハウが整備されていても、組織全体に“AIを使う空気”がなければ活用は定着しません。
その“空気”をつくる鍵こそ、経営者自身の姿勢にあります。
「どうすれば活用できるか?」と問うよりも先に、「誰が、どんな気持ちでこの変化を受け止めているのか」を聴くことが、今の経営には求められています。
まずは、対話の場を整えましょう。
定例会議や1on1では、AIに関する率直な意見を聞くための“専用の時間枠”を設けると効果的です。
あえて「不安を話すことが歓迎される空気」を演出することで、真の課題が見えてきます。
次に、経営者自身が「AIは敵ではなく、共に働くパートナーである」という明確なメッセージを出すことです。
「置き換える」ではなく「手放す」という言葉選びも重要です。
たとえば「ルーティン業務をAIに手放し、本来やりたかった仕事に集中できる組織へ」と語るだけで、意味のトーンは大きく変わります。
そして最も重要なのは、「学びが評価される風土」をつくること。
挑戦や習得が“リスク”になる職場では、変化は根づきません。
✔ 社内で「AIに関する学び・試行」を評価項目に入れてみる。
✔ 月1回、社内で“AI実験レポート共有会”を設ける。
✔ 経営者自身も「わからなかったこと」「驚いたこと」を言葉にする。
こうした小さな実践の積み重ねが、静かに文化を育てていきます。
変化の激しい時代にあって、ビジョンは静的な“旗印”ではなく、「問い続ける姿勢」そのものであるべきです。
経営者の問いが、組織の未来をつくります。
まとめ~経営者と部下、AIに向き合う温度差をどう埋めるか
- 現場は「AIで仕事を失うかも」と感じているが、声に出せていない。
- 経営層の無関心が、優秀な人材や挑戦文化の“静かな崩壊”を招いている。
- 今こそ“対話”と“ビジョンの再設計”で、学び続ける組織文化をつくるべき。
AIは“道具”であり、導入すること自体が目的ではありません。
それよりも、AIが引き起こす「組織内の心理変化」に気づけるかどうか――そこが経営者の力量の分かれ目になります。
部下が不安を語れず、変化を受け止める空気が育たない組織は、いずれ挑戦者が沈黙し、優秀な人材が静かに離れていきます。
技術を知っているかどうかよりも、“問いを持ち、耳を澄ます”姿勢が、企業の文化を決めます。
「経営者として、何を問い、どこに耳を傾けるか?」
その問い自体が、御社の未来を照らす指針になるはずです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
一見穏やかな社内でも、変化の兆しは静かに進行しているかもしれません。
この記事が、その小さな“気づき”のきっかけになれば幸いです。