AIにどこまで任せていい?“人間の仕事”を問い直す経営者の視点
こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
最近では、ChatGPTやCopilotなどの生成AIを使って、社員が自動で請求書や議事録、提案書のドラフトを作るケースが増えてきました。
確かに効率は上がりますし、「便利な時代になったな」と実感する瞬間でもあります。
しかし、経営者としてはこんな疑問も浮かびます。
「AIに、どこまで任せていいのだろう?」
AIベンダー各社の報告では、2024年時点で日本国内の中小企業のうち、35%以上が一部業務でAI活用を始めているそうです[1]。
一方で、「任せすぎてしまった結果、社員の思考力や判断力が育たなくなった」という声も、私の周囲では確実に増えてきています。
任せないと時代に遅れる。でも、任せすぎると人が動かなくなる。
このバランス感覚こそが、今の経営に求められている「問い」なのではないでしょうか。
このコラムでは、AIに任せられる仕事・任せてはいけない判断領域の違いを整理しながら、
“人間の役割”をどう再設計すべきかを、具体事例と共に考えていきます。
AIに任せる仕事・任せてはいけない仕事の違いとは?
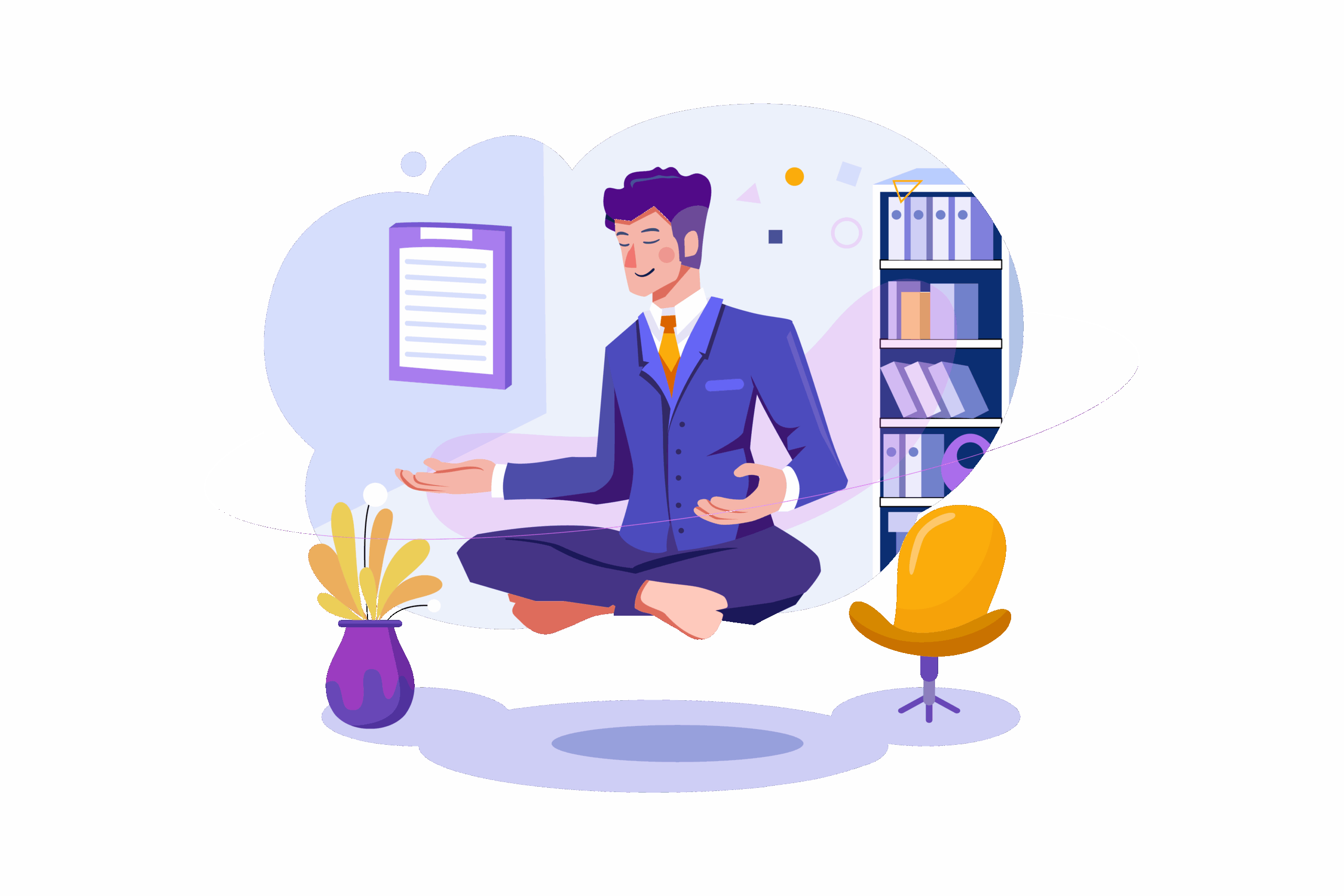
反復・構造・精度──“任せるべき”仕事の3要素
AIに任せられる仕事には明確な特徴があります。
それは「反復的で、構造化されており、正確さを求められる」という3点です。
たとえば請求書や契約書のドラフト作成、議事録の要約、定型の提案資料作成などは、すでに多くの企業でAIが活用されています。
Statistaの調査によると、米国企業の業務のうち約43%が「自動化可能な定型業務」として分類されており、これは日本の中小企業においても十分に応用可能です[1]。
こうした業務は、人間が手を動かす必要がないばかりか、むしろ人がやることでミスの温床にもなりかねないのです。
“考える”と“感じる”の分離が組織を危うくする
ただし、AIによって“作業”が代替できたとしても、“考える理由”までは省略すべきではありません。
私が関与したある企業では、提案書をChatGPTに書かせることで作業時間を半減できました。
しかしその反面、「なぜその構成なのか?」と問うと、多くの社員が答えられなくなったのです。
MITの研究でも、「AIを使って判断を効率化することで、かえって“自分の考え”を喪失するリスクがある」と報告されています[2]。
出力された文章が良ければそれでいい、という思考が続くと、“納得していない判断”が組織内に蔓延します。
✔ なぜこの出力を採用すると思ったのか?
✔ 他の候補と比べてどうだったのか?
✔ その判断に、あなた自身の経験はどう関わったか?
「責任の帰属先」が消える仕事は危険
もっとも危ういのは、「この文は誰が書いたのか分からない」という状態です。
たとえば、人事評価コメントをChatGPTで作成し、そのまま社員に渡したとしましょう。
そして、受け取った社員が「この表現は失礼じゃないか?」「本当に自分のことを理解して書いているのか?」といった疑念を感じたとします。
そうしたとき、「それはAIが書いたんです」と答えたらどうなるでしょうか。
責任の所在をAIに押しつけることは、組織の信頼を崩壊させる一歩手前です。
AIが書くことは構いません。
しかし、「なぜそう書いたのか」を説明し、「その責任を持つのは誰か」が明確でなければ、任せてはいけないのです。
AIに任せすぎる組織が抱える構造的なリスクとは?
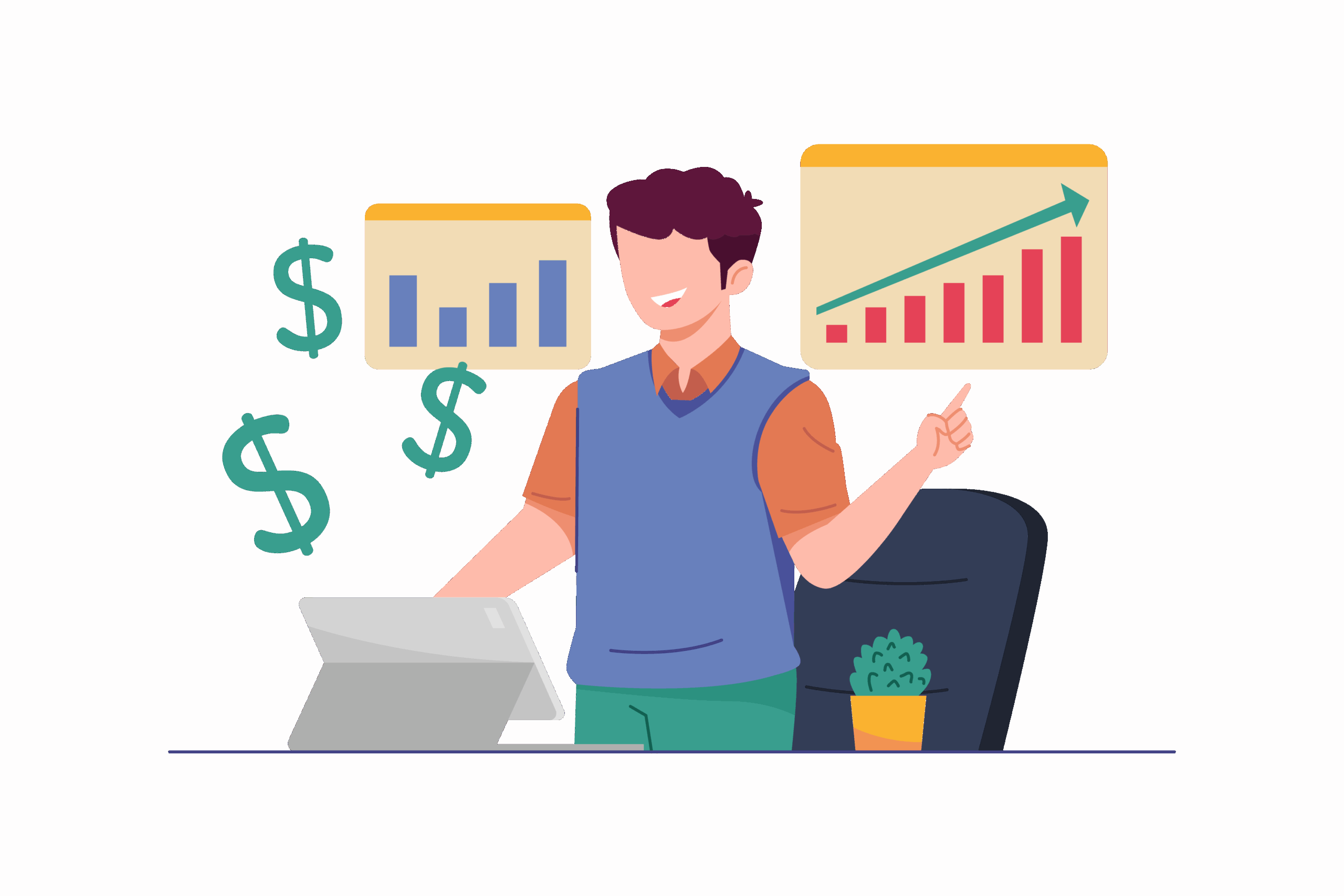
“作業速度”だけを評価する制度が引き起こす盲点
AIを使えば仕事が早く終わる。その事実自体に異論はありません。
しかし、「スピードさえ出ていれば評価される」という制度になってしまうと、本来必要だった“思考”や“比較”の工程がごっそり削られてしまいます。
ガートナーの報告によると、生成AIの導入初期段階にある企業の60%以上が「定量成果」を評価基準にしており、判断の質や倫理的整合性は後回しになっている傾向があるといいます[3]。
ある営業会社では、AIを活用してレポートの提出スピードが2倍になりました。
しかし半年後、顧客からのヒアリングで「どれもテンプレっぽくて、誰が書いたのか分からない」という声が続出しました。
スピードが上がったことで、“伝わる力”が落ちてしまったのです。
中間層が“判断しない人”になる
経営層は「使え」と言う。
現場はAIを頼る。
そのあいだにいる中間層が「判断しなくなる」という問題が顕在化し始めています。
承認だけして、内容は読まない。
数字が出ていれば深掘りしない。
──そのうちに組織全体が“判断する文化”を失っていきます。
判断しない人が増えると、組織のリスク感度が鈍化し、危機に直面したときに「なぜこうなったのか分からない」という事態に陥ります。
「上司も試してないから言えない」空気が生む沈黙
現場から「このAI使ってみたいんですが…」と声が上がっても、
上司が「ふーん、また調べておくよ」と曖昧に応じて終わる。
こうした“思考保留の会話”が組織内に増えてくると、社員は「どうせ反応がないから言わない」という結論に達します。
本質的には、上司自身が使ったことがない・分からない・試していないという不安や自信のなさが、その沈黙を生んでいるのです。
✔ 意思決定の“理由”が語られなくなる
✔ 上司がAI活用を“評価対象”に入れ始めるが、自らは試さない
✔ 若手が「聞かれないなら、説明しなくていい」と思い始める
AIが便利であるほど、“対話と判断”の価値はむしろ上がっているのかもしれません。
AI活用を問いに変える、“任せ方”経営とは?
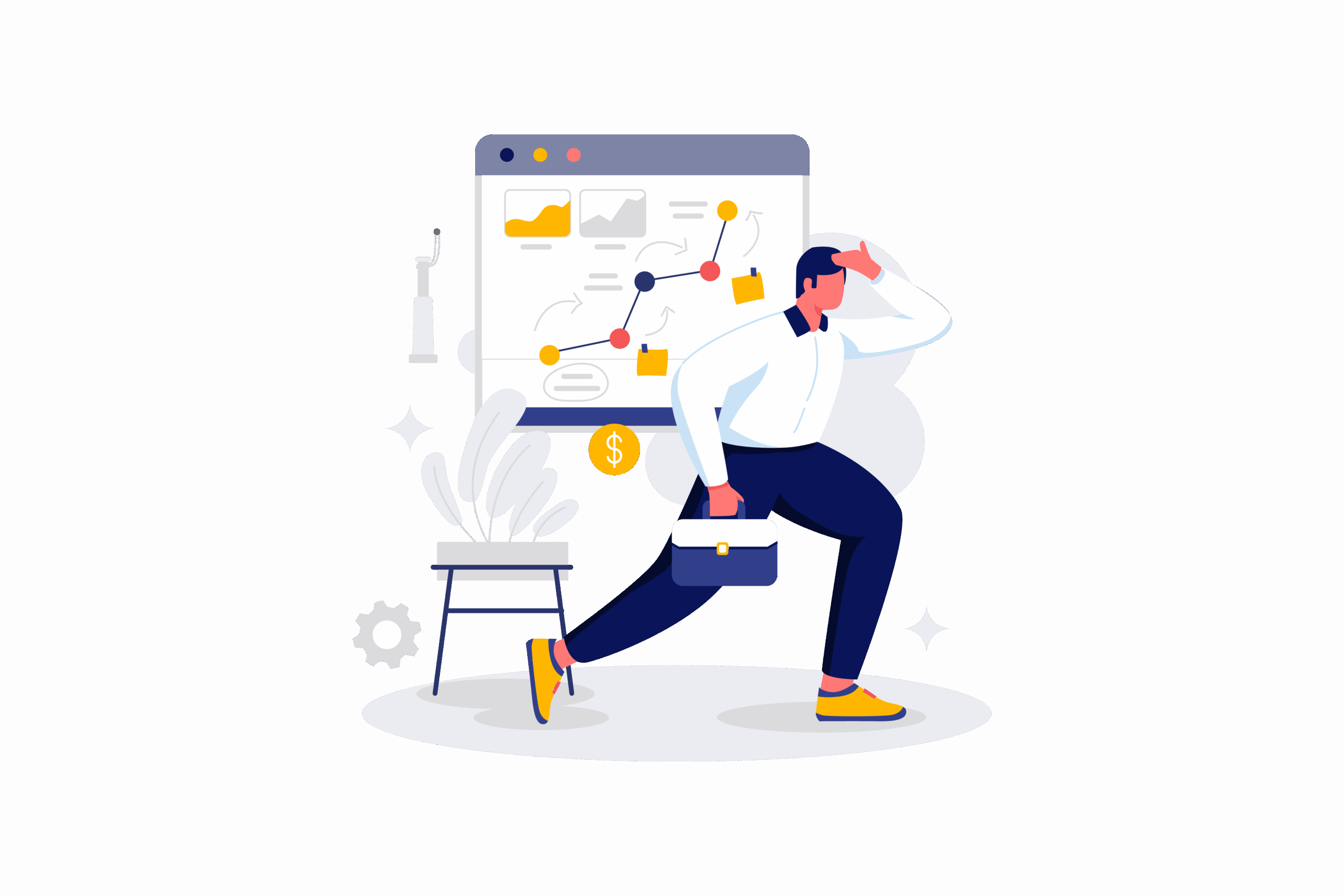
「なぜAIに任せたのか?」と問い返すことで、思考が始まる
「AIにやらせました」だけでは、思考は始まりません。
その出力を受け取ったときに、経営者としてまず返すべきは
「なぜ、それをAIに任せようと思ったのか?」という問いです。
ハーバード・ビジネス・レビューでも、「問い返しがあるとき、社員の提案の深度が平均34%向上する」というデータが示されています[4]。
ChatGPTが便利になればなるほど、「なぜこの案を採用したのか」という思考のプロセスが曖昧になります。
だからこそ、経営者が“問い返す力”を持ち続けることは、組織全体の「考え続ける文化」の保護につながります。
任せ方にも“設計”が必要だ
AIの導入とは、「使わせるか/使わせないか」の判断だけで終わる話ではありません。
実は多くの現場で起きている問題は、“使っていいとは言われたが、どこまで任せてよいか分からない”という空白なのです。
この混乱の原因は、「AIに任せること」の“設計”が曖昧だからに他なりません。
AI活用における設計とは、具体的に以下の3点を明確にすることです。
- ① 任せる範囲:AIにやらせていい作業工程/禁止する判断業務
- ② 確認の頻度:初稿段階で見るのか、最終提出前か、定期レビューか
- ③ 責任の所在:誰がそのアウトプットに責任を持つのか
この3点が抜けたまま「活用OK」としてしまうと、現場では“すべて任せていい”という解釈が広がり、意思決定がAI任せになる危険性すらあります。
実際に、ある中堅企業ではChatGPTを導入した直後、社員が生成した提案資料をマネージャーが読まずに承認するというケースが頻発し、“内容のズレ”や“トーンの不統一”による信頼低下が問題となりました。
そこで導入されたのが、次のような明文化です。
「初稿:AI / 内容確認:担当者 / 最終提出判断:マネージャー」
これにより、各レイヤーがどの段階で関与すべきかが明確になり、社員も“やっていいライン”を理解するようになりました。
任せるとは、自由にさせることではありません。
むしろ、自由を支える“構造”を設計することこそが、経営者に求められるAI時代の統治なのです。
✔ この仕事の最終責任者は誰か、はっきりしているか?
✔ AIから得た出力に対して「検証の工程」があるか?
✔ そのプロセスを社員が“説明できる状態”になっているか?
社員がAIに“背中を預けすぎた”ときのサインとは?
ある中堅メーカーで、若手社員がChatGPTで書いた企画書をそのまま出すケースが増えてきたそうです。
「なぜその構成なの?」と聞くと、「AIがそう出したからです」
「他のパターンは?」と聞いても、「見ていません」
これは“思考が省略されているサイン”です。
AIが便利になればなるほど、“なぜこうしたか”を説明できる人が減っていきます。
出力を受け取ることは誰でもできますが、それを判断するには、問いを持ち続ける力が必要です。
“AI時代の人間の仕事”を再定義する4つの視点とは?
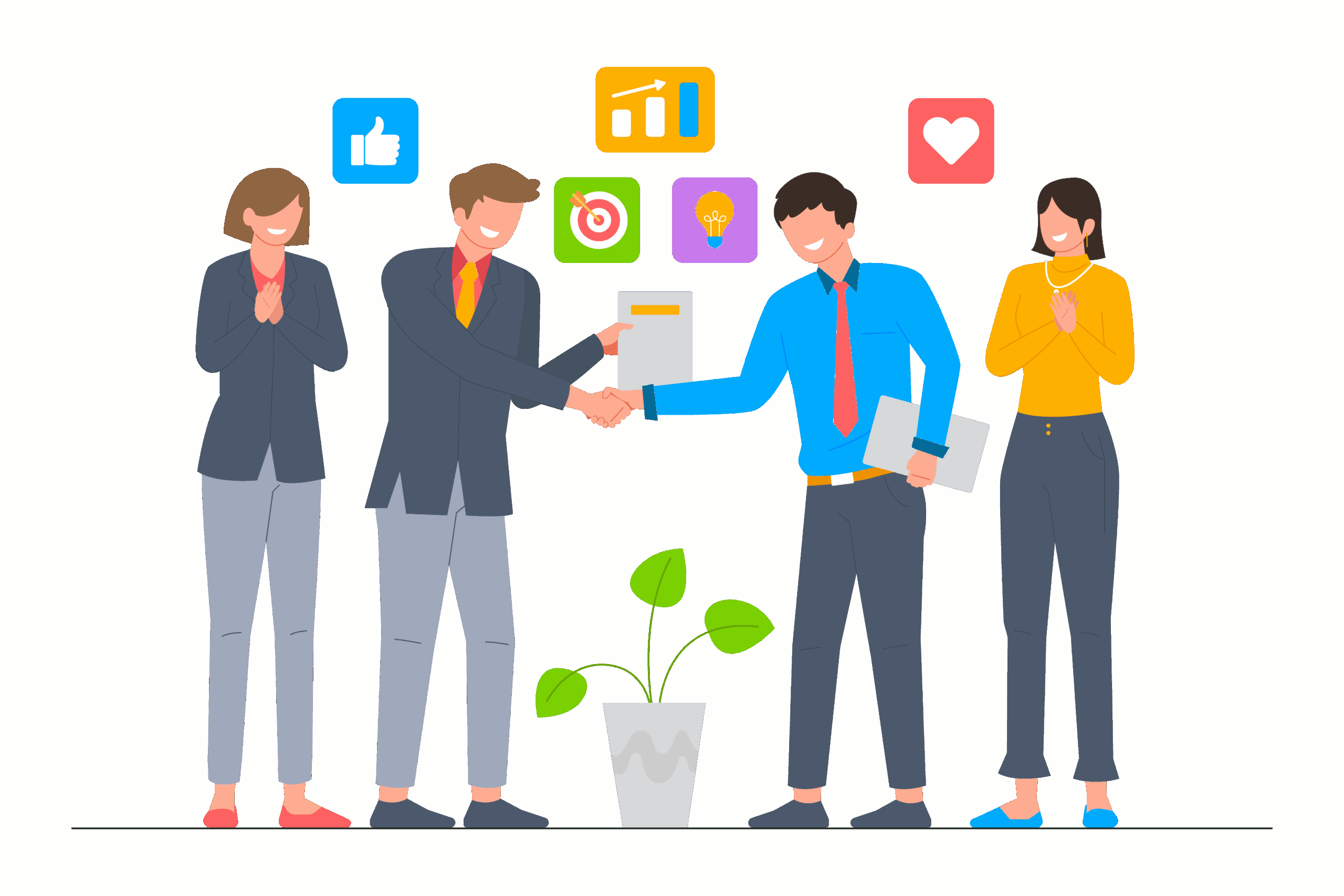
判断に“余白”があるものはAIに任せてはいけません
ビジネス現場では、数字があれば判断しやすく、データが揃えば最適解が見えると信じられがちです。
しかし、現実の意思決定の多くは「これで本当に大丈夫か?」という“違和感”や、“相手との関係性”に依存しています。
たとえば、「このメール文面で相手はどう感じるだろう?」
「このタイミングで提案するのは、戦略的に妥当か?」
──こうした判断には明確な数値では測れない“余白”があります。
この“文脈”を読む力こそ、人間にしかできない仕事です。
“問い”を探す行為が人間的である
AIは、過去のデータから正解を引き出すのが得意です。
しかし、何を問うべきかを考える行為──つまり「問題発見」は人間の仕事です。
心理学者のドナルド・キャンベルも「創造的な行動とは、“問いを発見する能力”に集約される」と述べています。
逆に言えば、問いを持たなくなった組織は、いくらAIを持っていても現状維持しかできないのです。
“考え続ける力”が、組織の温度を決めます
AIを使えば提案数は増えます。
でも、それが「考え抜かれた提案」になっているかどうかは別問題です。
世界経済フォーラム(WEF)は、2030年に必要なスキルとして「批判的思考」「創造性」「問題解決力」の3つを最重要と位置付けています[5]。
これは、逆に言えば「AIに委ねてはいけない中核スキル」が何かを示しています。
“出すこと”より“問い続けること”のほうが、はるかに難しい。
でも、そこにこそ組織の温度が宿るのだと思います。
「問いを持つ人」が減ると、会社は止まります
会社が静かに衰退していくとき、目立ったトラブルはありません。
ただ、「何のためにやってるのか分からない」と語る人が増え、「まぁAIが出したからいいか」と思考を止める人が現れます。
そのとき会社が失っているのは、業績ではなく、“問いを持ち続ける人”なのです。
経営者が「AIで便利になった」で終わらせるのではなく、
「この変化に対して、どんな問いを持つべきか?」と自らに問う姿勢こそが、組織を未来に繋げる唯一の道です。
まとめ〜AI時代の“任せ方”と“人間の問い”を再定義する
- AIに任せる仕事は、“責任”と“思考の意図”が明確なものだけ。
- 任せ方の設計と問い返しが、組織の“考える文化”を支えます。
- 「問いを持つ人」がいる限り、会社は止まりません。
AIが浸透するいま、任せられる仕事は確実に増えました。
その恩恵を受けることは素晴らしいことです。
しかし、だからこそ「AIに任せられない仕事」が、より価値を帯びてきています。
それは、感情の微細な変化を汲み取る力、
違和感に気づく直感、
問いを深め続ける知性、
──そして、答えを急がずに考え続ける姿勢です。
VUCA(不確実・複雑・曖昧・変動)な時代において、
「これが正解だ」と即答する組織よりも、「何が正解か、問い続けよう」と言える組織の方が、長く生き残っていくのではないでしょうか。
“任せ方”を設計する力と、“問い”を持ち続ける力。
この2つを両立させることが、AI時代の経営における中核だと私は考えています。
このコラムが、あなたの次の問いを生み出すきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今後も、経営の本質を一緒に問い続けていきましょう。























