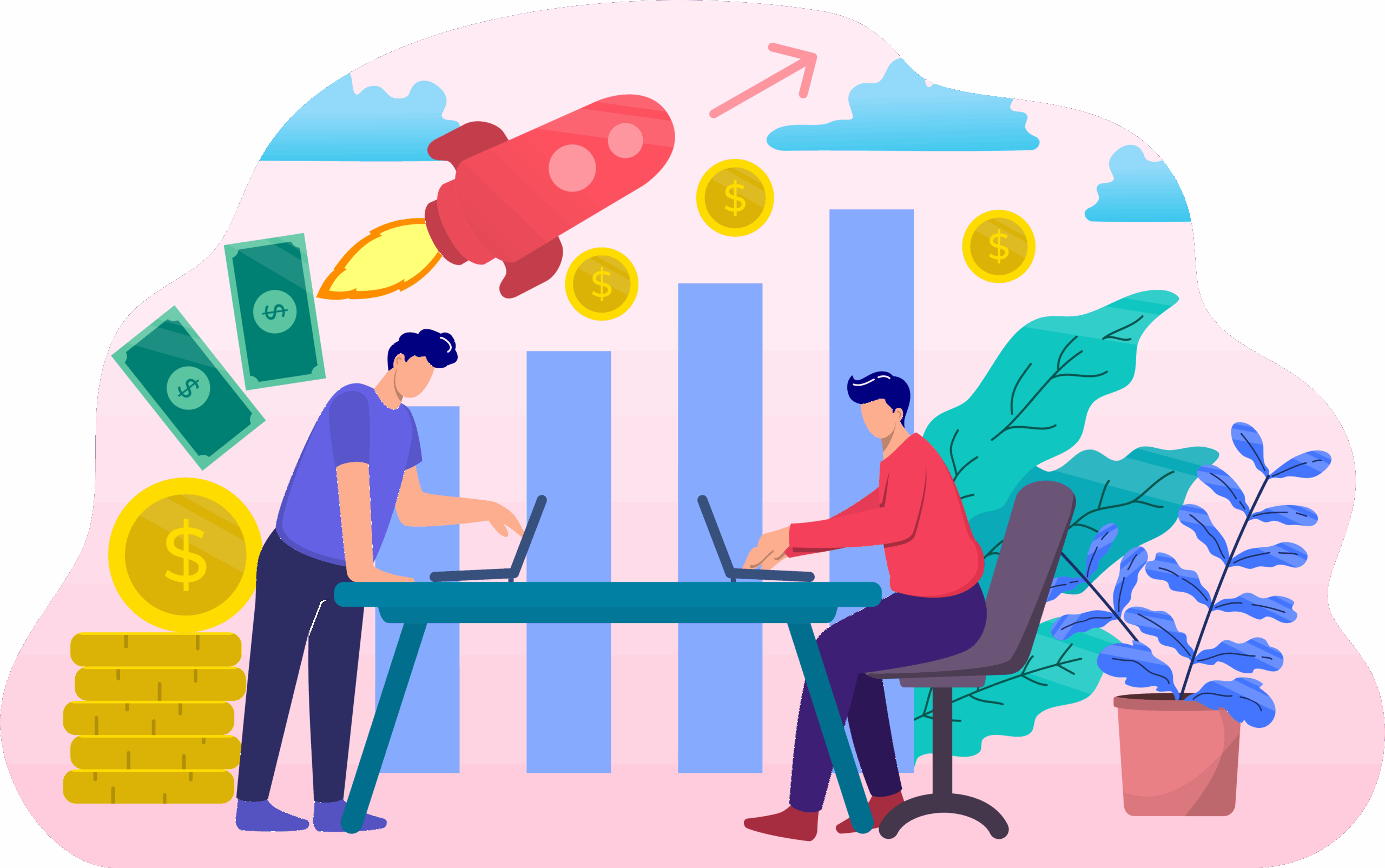“AIで新人が育たない”は本当か?人材育成と自己学習の交差点
こんにちは。ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
最近、ChatGPTなどの生成AIを使って提案書や議事録を作成する新人が増えてきました。
文章も一瞬で出力され、調べ物もすぐに済む──そんな姿を見て、「このままで本当に育つのか?」と不安になる経営者の方も多いのではないでしょうか。
「昔は苦労して覚えた」「自分で悩んで考えることが大事だった」
確かにその通りです。ただ、それは“そうしなければ学べなかった”時代の話でもあります。
では、今のAI時代において、人材育成はどう変わるべきなのか?
AIを使えば「育たない」という見方は正しいのか? それとも誤解なのか?
本コラムでは、ChatGPTと共存しながら育成を設計する方法として、
「非効率の意味」「問いを持たせる工夫」「組織知としての学びの活用」に焦点を当て、
AI時代における“新人の育て方”を問い直していきます。
AIで新人育成は失敗する?──学びの本質を問い直す
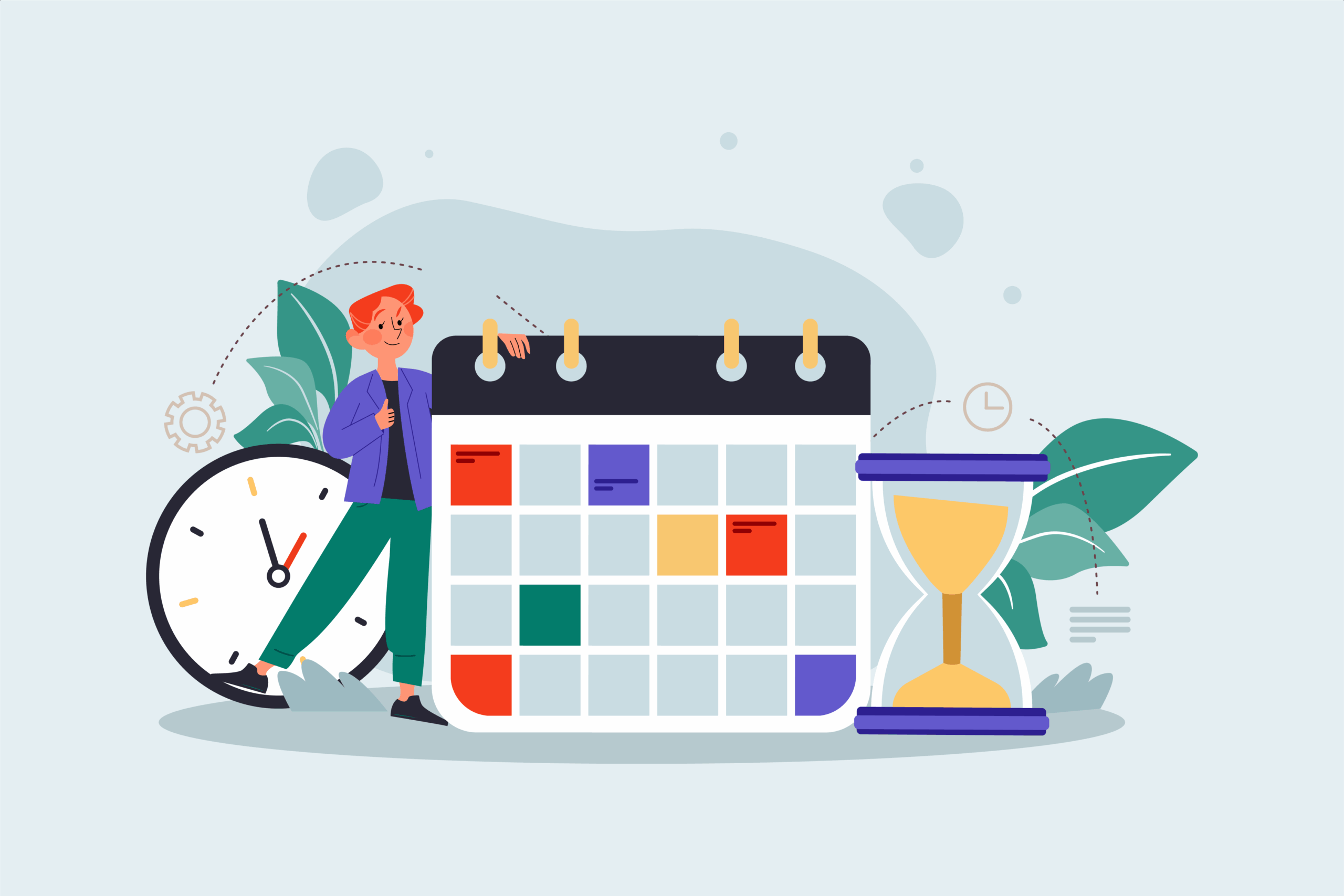
「自分で考えない」は本当か?
「ChatGPTに任せて終わりでは?」
そう感じるのは自然なことです。
しかし実際、生成AIを活用している若手の多くは、
AIの出力をそのまま使うのではなく、比較・修正・選択というプロセスを自ら行っています。
これは“考えていない”のではなく、むしろ“複雑な判断プロセスを短時間でこなしている”とも言えます。
HBRの報告によれば、「AIを使うことで情報量は増えるが、判断負荷も上がっており、むしろ“選び抜く力”が求められている」とされています[1]。
つまり、「AIを使っている=考えていない」というのは、必ずしも正しくありません。
“育つ”の定義が変わってきている
昭和・平成の育成文化では、「手を動かす」「現場で苦労する」「上司の背中を見て学ぶ」ことが重視されてきました。
しかし、時代は変わりました。
Gartnerは、「今後の学習は“経験を語る”ことより、“問いを残す”ことに価値が移る」と指摘しています[2]。
つまり、AIを使いながらも「これはどうして?」「これでいいのか?」と問いを持ち直せる新人は、
旧来の“苦労型育成”とは異なる形で、確実に“育っている”のです。
AIを“逃げ場”にしない設計とは?
AIの活用が“学ばない理由”になってしまう組織には、ある共通点があります。
それは、“問い返し”の文化がないことです。
ChatGPTが出力した文章に対して、「これでいいですか?」と聞かれたとき、
「いいよ」で終わるのではなく、「なぜそう思った?」「他の案は試した?」と返す。
この“問いの設計”があるだけで、AIは“逃げ場”ではなく“思考の補助輪”に変わります。
✔ この出力、どこが「納得できた」の?
✔ 他の提案パターンは考えた?
✔ その順番にした理由は“誰の立場”から考えたもの?
“育たない”という不安を、問いで支える。
それがAI時代の育成者に求められる姿勢です。
AI育成に“非効率”をあえて設計する理由とは?
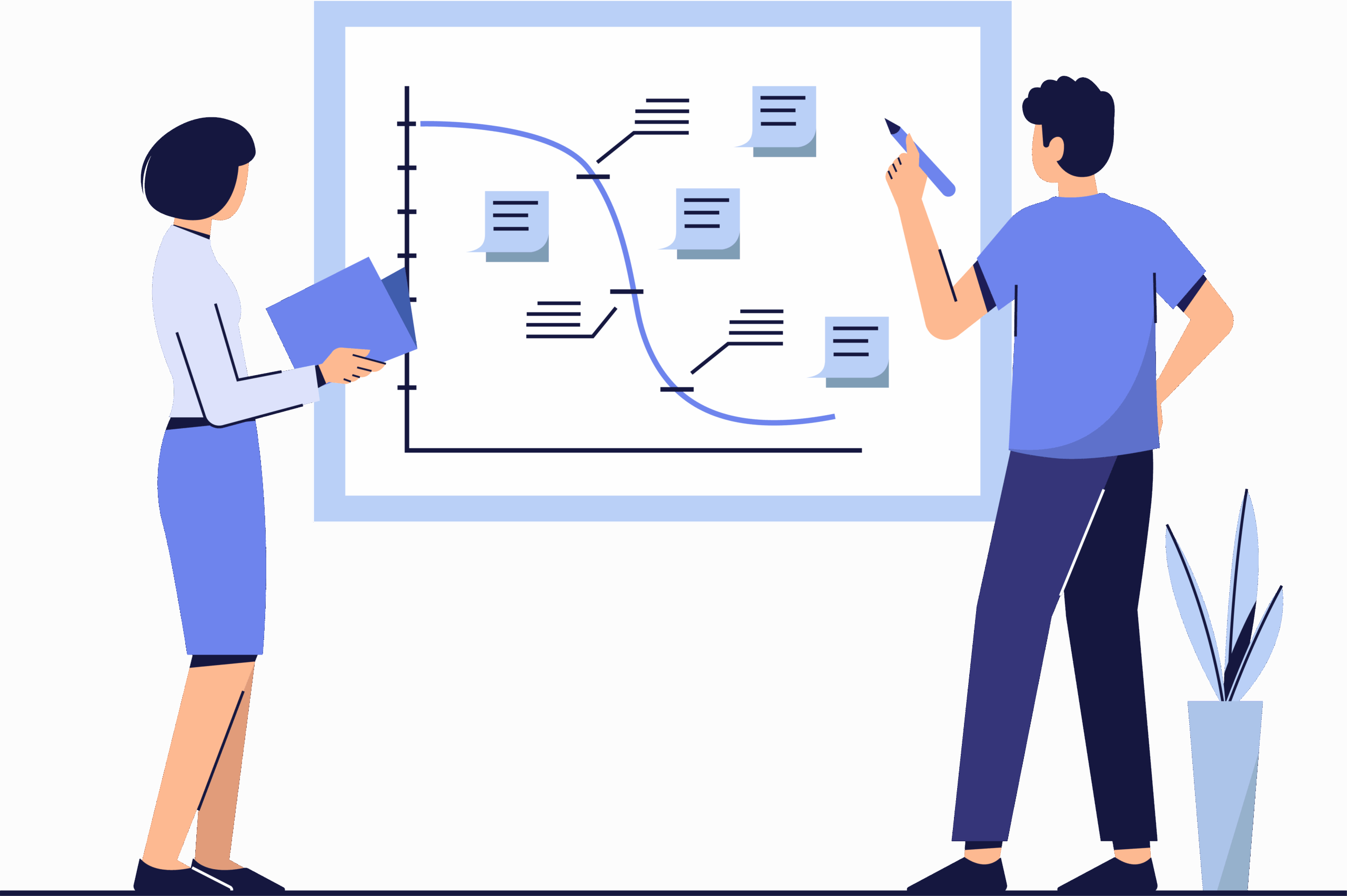
「効率の外」にしか生まれない気づきがある
AIの導入により、業務は圧倒的に効率化されました。
ただし、育成の現場においては「速くできる」=「学べている」ではないという点に注意が必要です。
McKinseyの人材戦略レポートによると、「一定の“試行錯誤”や“内省時間”がある育成プロセスの方が、結果として定着率・応用力が高くなる」という調査結果が示されています[3]。
つまり、あえて遠回りしなければ得られない“納得感”“自信”“問いの発芽”が、育成における本質的な成果なのです。
AIに頼っていい“時間帯”と“工程”を分ける
育成の過程では、「AIを使ってよいフェーズ」と「自分で考えるべきフェーズ」を明示しておくことが大切です。
以下のような工程分解が、思考の余白を確保する上で有効です:
- 初期構想・アイデア出し:AI活用OK
- 一次草案作成:AI+本人による構成調整
- レビュー前再読:自分の言葉で説明できるかを確認
- 最終提出判断:人間同士の対話・問い返しによる決定
このように「AIで効率化してよい部分」と「考える時間を守る部分」を分けることが、バランスの取れた育成設計になります。
「非効率な育成」を許容できる組織が強い理由
目の前のスピードだけを評価すると、
「AIを使いこなしてすぐ結果を出す人材」ばかりが優秀に見えてしまいます。
しかし、中長期的に強いのは、“思考プロセスを蓄積し続けられる人材”です。
成長には“時間”が必要です。
ときにミスして、ときに迷って、それでも問い直す──
その“非効率な思考”を支える組織文化が、結果的に一番強いのです。
✔ AI利用フェーズを明文化する(OK/NGを分ける)
✔ 思考ステップに問い返しを挿入する(なぜ?を2回返す)
✔ 成果より“プロセスの意味づけ”を共有する時間を取る
自己学習から“組織知”へ──AI時代の人材育成ステージ設計
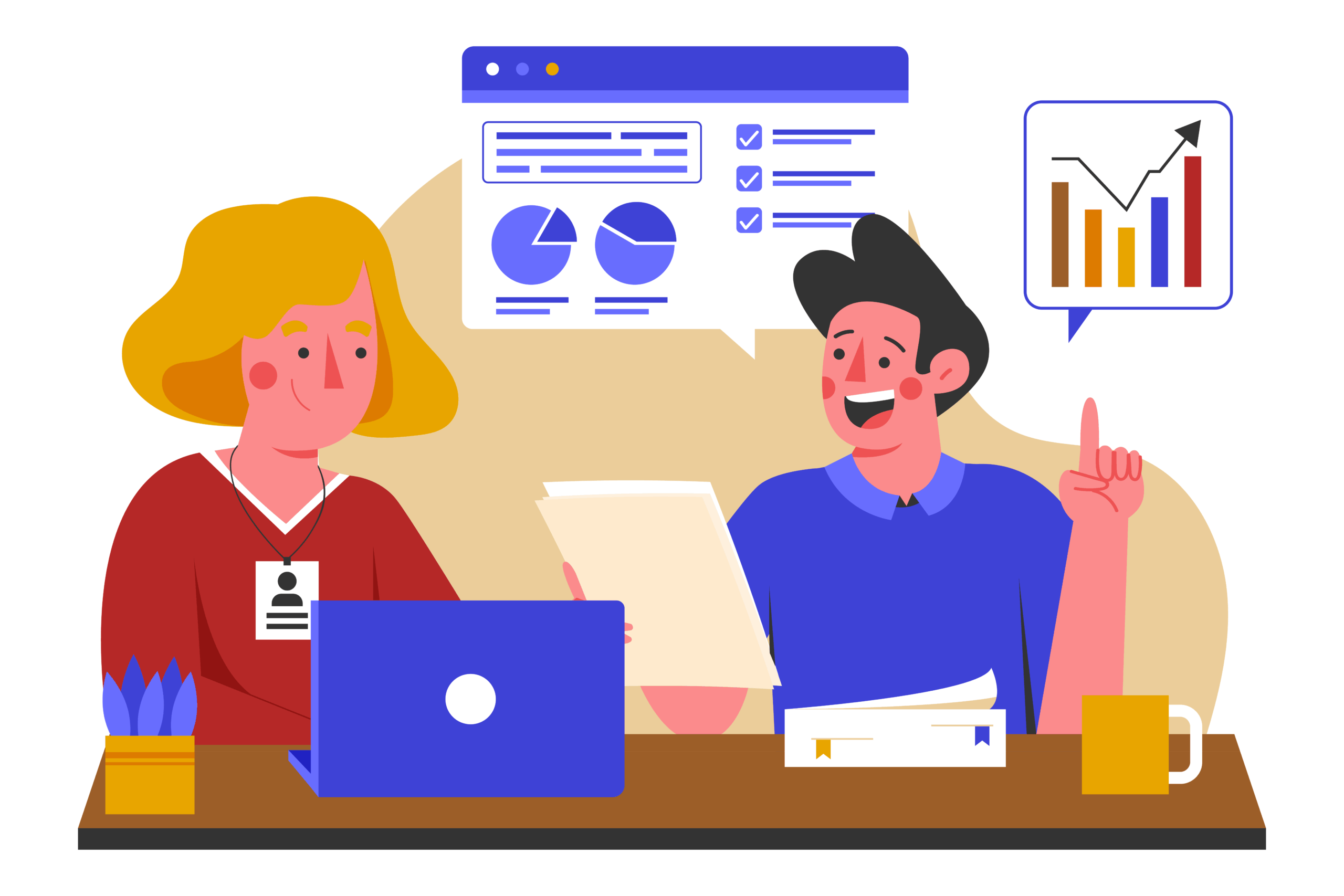
ChatGPTが“思考の外部化”を助けている
若手がChatGPTにアイデアを打ち込むとき、
そこには“思考の見える化”が自然と起こっています。
ChatGPTのプロンプトに悩んでいる姿は、まさに「自分の問いをどう表現するか」を練り上げている時間そのものです。
これは単なる“答え探し”ではなく、自分の考えを構造化する行為です。
AIは、答えを出す装置ではなく、“問いを仮設化”してくれるパートナーになりつつあるのです。
学習が「共有可能」になることで、組織が進化する
自己学習は従来、暗黙知として終わっていました。
しかし今、ChatGPTの対話ログや日々のナレッジ共有チャットは、
“成長の過程”を組織で可視化・再利用できる形に変えています。
ある企業では「AI対話日誌」を週報の一部に組み込み、
社員が「どんな思考をAIにぶつけたか」を記録・共有しています。
これにより「学びの質」が評価され、「成長の過程」が企業の資産となっています。
「答え」より「問い」を残せる人材が強い
ChatGPTを使って仕事をしている新人に、こう尋ねてみてください。
「どこがAIに任せすぎだったと思う?」
「この出力で、どこが不安だった?」
そのときに「うまく答えられなかった」「別案が浮かばなかった」と悩んでいたら、
それは“次の問い”が生まれているサインです。
育成とは、知識を満たすことではなく、
“問いが残る状態”を認識できる力を育てることなのです。
✔ ChatGPT活用記録を「学習ログ」として提出可能にする
✔ プロンプト設計や出力比較の意図を言語化させる
✔ 他者のAI活用例を「問い返しの事例集」として共有
AI時代の新人育成設計──“教える”から“問いを支える”へ
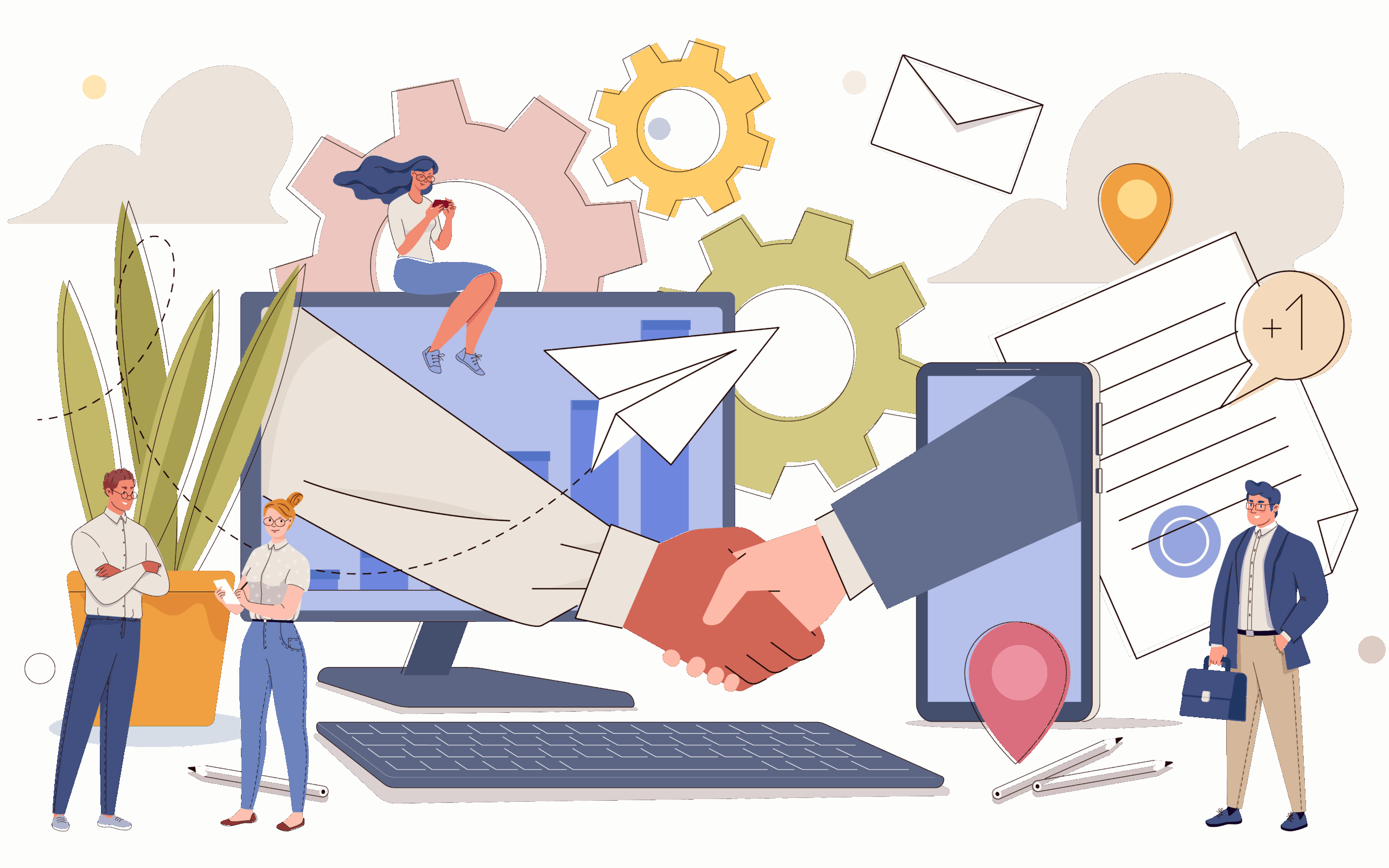
「考えなくてもできる」が育成を止めるわけではない
ChatGPTを使えば、多くの仕事が“考えずに済む”ように見えます。
しかし、それは「考える必要がない」ではなく、「考えるフェーズが変わった」というだけなのです。
たとえば、文章を書く前に「構造を考える」、出力を得た後に「読み手の立場で見直す」など、
“思考の場所”が変化しただけで、本質的な知的労力は変わっていません。
大事なのは、「考えずにできたから成長しない」と結論づけるのではなく、
“どこで思考を生んでいるか”に注目する育成姿勢です。
「教える」から「問う・気づく」への転換
教育工学では、「メタ認知」=“自分がどう考えているかを自覚する力”が、
最終的な問題解決力に大きく影響すると言われています。
育成者は「こうすればいい」と答えを教えるより、
「なんでそう思ったの?」「これは他でも応用できそう?」と“問いを投げかける役割”を担うべきなのです。
ときには間違いも許容し、
「なぜ間違えたのか」を一緒に分析する──
この“内省の時間”が、育成の核心になります。
育成における“問い返しの設計”とは?
ChatGPTが出した答えを見て「どうだった?」と返すだけでは不十分です。
育成者は、以下のように思考の深さに応じた“問いの段階”を意識する必要があります:
- STEP1:事実の確認(例:どこをそのまま使った?)
- STEP2:理由の分析(例:なぜその構成が妥当と思った?)
- STEP3:別視点の導入(例:読み手にどう伝わると思う?)
- STEP4:再適用の予測(例:次に似た仕事が来たらどう使う?)
こうした段階的問い返しによって、
育成は“知識伝達”から“思考支援”へと進化していきます。
✔ 答えではなく“問い返しスクリプト”を準備する
✔ 「なぜそうした?」を“責めずに聞く”言葉選びを磨く
✔ 出力に対する感情や違和感も、評価に含める
まとめ〜“AI育成”とは、問いを支える構造をつくること
- AIで新人が育たない、は誤解を含む問いです。
- “育てる”とは、AI活用後の「問い返し」を設計することです。
- 育成のゴールは、正解ではなく“問い続けられる力”の構築です。
AIを使えば、新人は早く仕事をこなせるようになります。
でも、そのスピードの裏で、「考える力」や「問いを持ち続ける姿勢」が失われていないか?
──それこそが、本当に問い直すべき焦点です。
育成とは、答えを詰め込むことではありません。
むしろ、「なぜそうしたのか?」「他に方法はなかったか?」といった
“問いを持つ余白”を守り続けることなのです。
ChatGPTをはじめとするAIは、考えずに使えば“逃げ道”になりますが、
問い返しを重ねれば、“考えを深める壁打ち相手”になります。
AI時代の新人育成は、“問い支援型”へと進化する。
その第一歩は、教えるのではなく、一緒に問いを考え続ける構造を作ることです。
このコラムが、あなたの次の問いを生み出すきっかけになれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
次の育成設計を考えるうえで、この視点がヒントになればうれしいです。