ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
この記事は、「途中まで」私という人間が書いています。AIによるリライトも入れていません。
「途中から」AIライティングに切り替えています。ぜひ温度差を見比べてみてください。
恐らく、当事務所の記事を読まれた方の多くはこのように感じるのではないでしょうか?
- 「え、本当にこの記事はAIが書いたの?」
- 「AIのライティング技術ってここまで進んでいるの?」
- 「AIってこんなに人間っぽく体験談や感想を書けるものなの?」
なぜ税理士事務所・行政書士事務所である当事務所が、このようなライティングAIを独自開発したのか? そこには明確な意図が存在します。
そして当事務所がなぜ生成AIによる記事を作成し、その方針を公開しているのか。また、なぜ生成AIの記事をリライトすることなく、そのまま公開しているのか。
この記事では、それらの理由について説明していきます。
2025年における生成AIのライティング能力と課題について
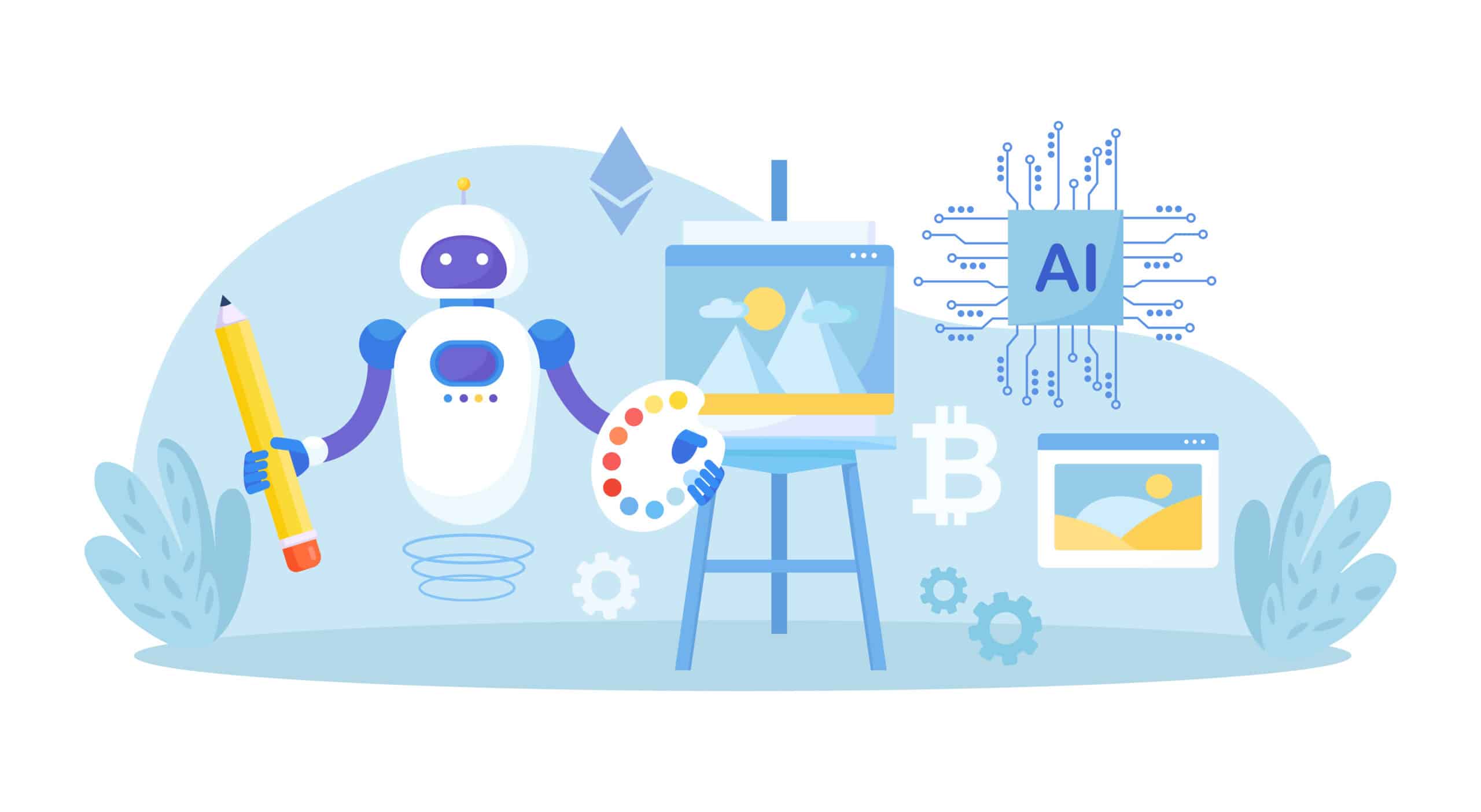
はじめに2025年現時点における、生成AIのライティング能力について触れておきましょう。
AIライティングはレベルが低い?
AIと対話をしている限りでは気が付きませんが、AIはブログ記事やコラム執筆が苦手です。
AIライティングはレベルが低い。
ライティングに携わったことがある人ほど、そう感じた経験があると思います。
AIは人間的な感情を表現することに長けておらず、テンプレ的で機械的な表現に陥りがちです。責任回避のロジックも働きますので、主語を「私」とした記事を生成することも苦手です。
繰り返しの表現・AIに見られる独特の言い回しも多数存在しますよね。
これらは生成AIによるライティングの明確な弱点として認識されています。
現状のAIをそのままの状態でウェブライティングに活用することは、まだ難しいというのが正直なところでしょう。
では、巷にあふれるAIライティングサービスを利用した記事執筆はどうでしょうか?
たしかに高品質を売りにしたAIライティングサービスもありますが、現在の生成AIが抱える根本的な問題を解決するには至りません。
やはり、人間の質感がなく、AIが生成した臭いが完全には消せないのです。
私もいくつか高額なサービスに課金して品質をチェックしました。しかし、まだまだ人間のトップライターには遠く及ばないな、というのが正直な感想です。
2025年時点でAIライティングを実務で利用することは可能ですが、AIコンテンツであることを知られたくないのであれば、かならず人間の目や手を通す必要があるのです。
AIライティングの本質的な問題
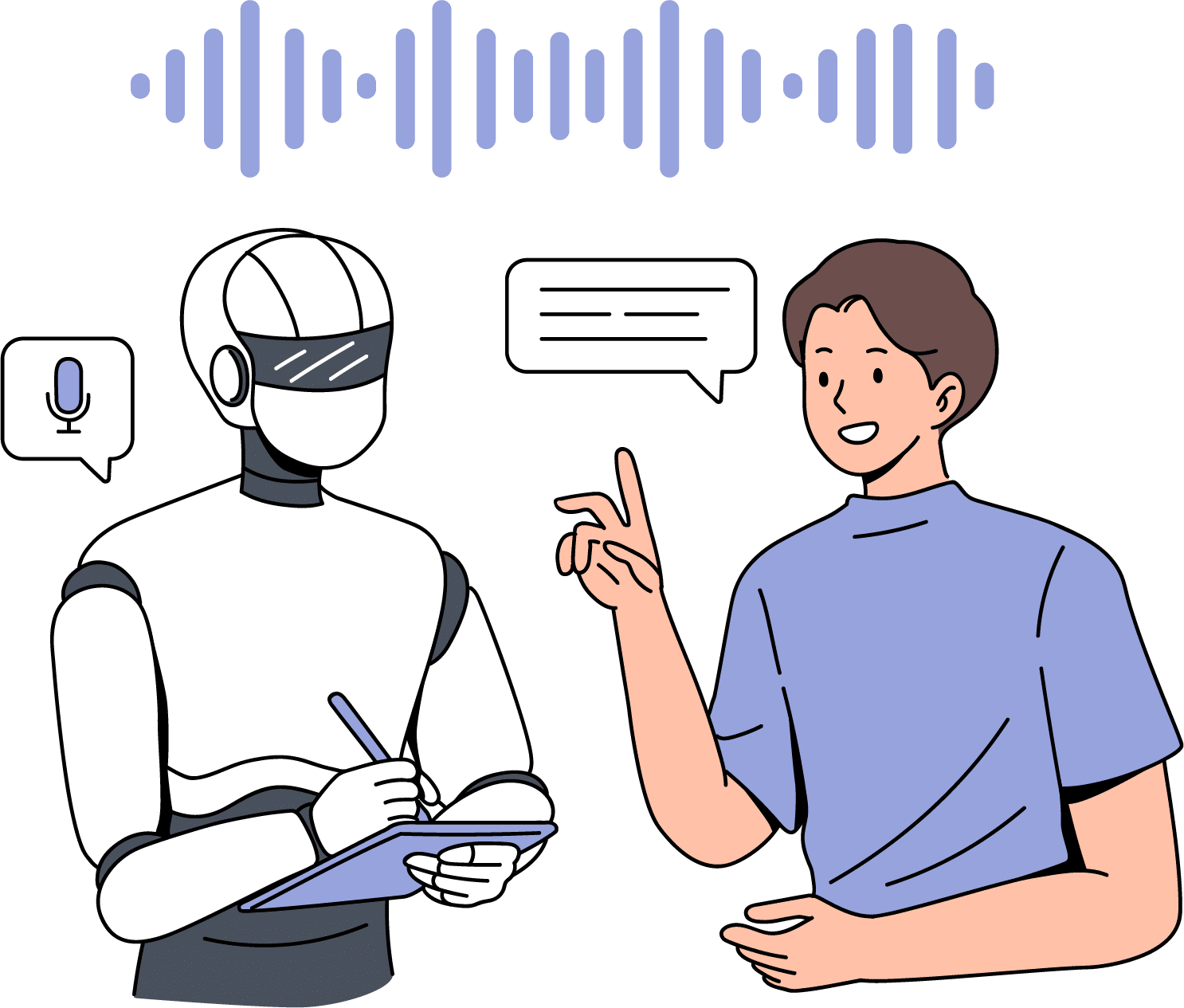
AIライティングは人間特有の色合いが薄い。「形質的な質の問題」について、ここまで確認してきました。
しかし、AIライティングにはさらに深刻な構造的問題、すなわち本質的問題点が潜んでいます。
例えば、次のようなケースを考えてみましょう
キーワードリサーチを行っていたら、競合が少なく勝ちやすい「お宝キーワード」を発見した。しかも1つや2つではなく、複数キーワードがある。これをAIライティングで記事作成したら?
このようなケースでは、競合が弱いため、AIライティングであっても上位表示が可能でしょう。収益化だけを目的として見たら、悪い事ではないかもしれません。
ただし、このようにして生み出されたコンテンツが、本当にユーザーにとって価値が高い情報コンテンツであるかは別問題です。
このAIによって完全自動生成された記事は、確かに上位表示されている。しかし、このコンテンツを見て、ユーザーが次の行動につなげたり、新しい知見・発見を得られたりする体験ができるでしょうか?
これは生成AIの構造的な部分に原因があります。
AIは過去の膨大なデータを学習することで、現在の最適解を導くツールです。
生成AIの多くがLLMの確率推論に基づく文章生成を行います。意地悪くいえば、最も当たり障りがなく、聞こえの良い回答を、それっぽい言葉をつなげてそれっぽく見せているだけ。
そもそも本質的な意味での新しい価値やビジョンの提供を行うことが困難なのです。
AIによって生成されたコンテンツを見て、ユーザーが気づきを得ることが難しい原因が、ここに集約されています。
もちろんユーザー自身が自動生成コンテンツを見て気づきを得ることはありますが、それは得てして、計算された構造設計ではないのです。
AIにとって創造性あふれるライティングは難しい
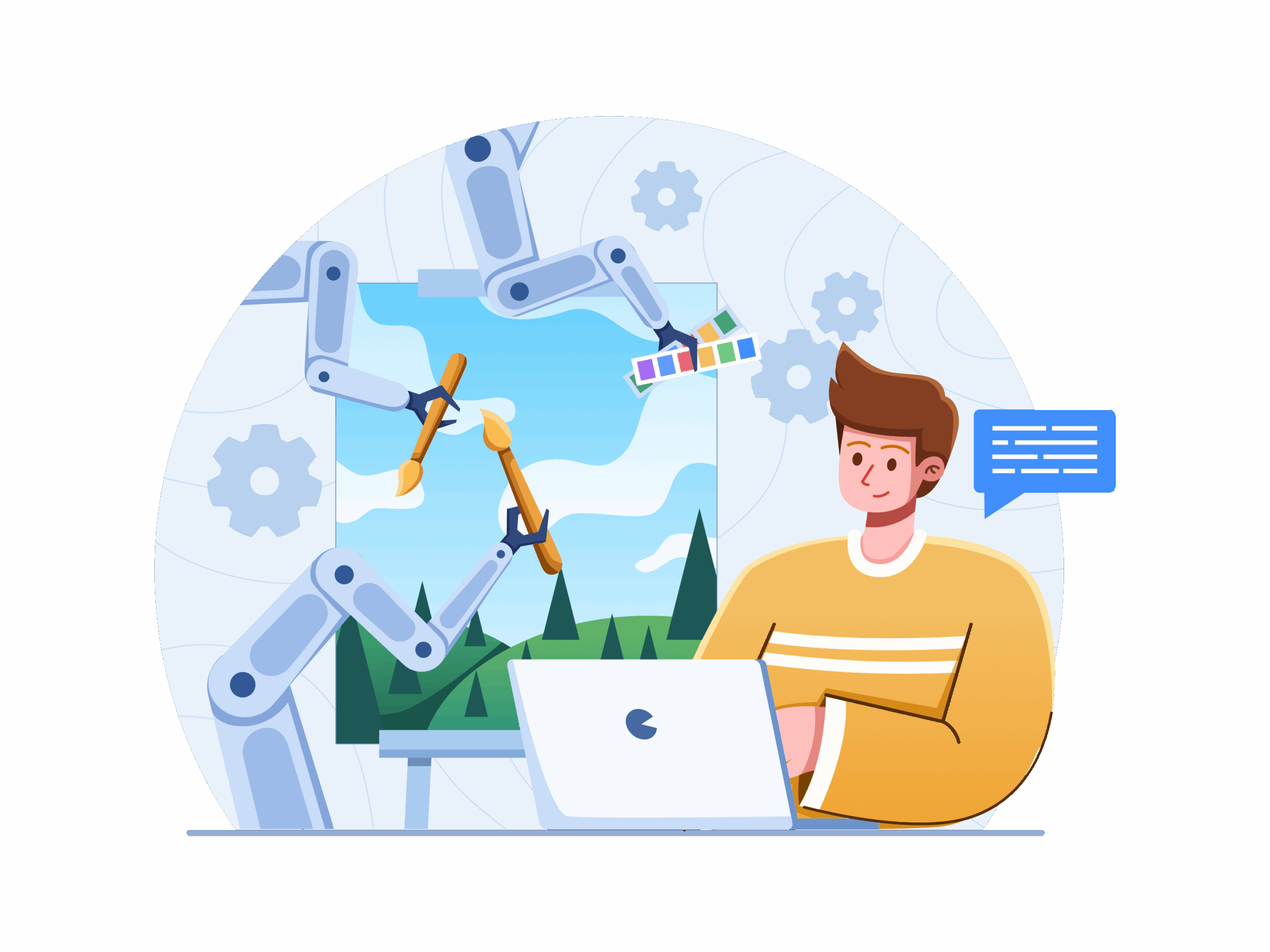
あなたは、AIによって自動生成されたコンテンツを読んで、「なんか薄っぺらいなぁ」という印象を持ったことはありませんか?
私は何度もあります。読んでいて何も引っかからない。読んだ後に何も残らない。そう感じる場面が何度もありました。
これらの問題は、AIは創造的ライティングに対応できない、という問題を我々に突き付けています。
過去の膨大なデータに基づくテーマ最適化の文章は書けるが、ユーザーに新しい発見や気づきを提供するのは難しい。人間ならではの行動を喚起するためのメッセージを込めることが難しい。未来への行動導線を担うコンテンツ生成が、AIには難しいのです。
この点は、現時点におけるAIライティングの明確な限界として認識しておく必要があります。
記事を読む読者は、「未来における価値」を記事に対して求めています。
未来にむけた創造性がない記事は、読者にとっては本質的な意味での価値を有しません。
極論ですが、記事を読んだ読者が、何かしらの違和感や気づきをその記事から受け取ることができなければ、その記事は無価値であるとも言えます(もっとも、それは人間のライターが手掛けた記事においても同様ですが)。
生成AIが普及するにつれ、ウェブ上にはAIが執筆した質の低い記事が溢れるようになりました。 ここには明確な2つの理由があります。
- ①生成AIが生成する記事は、機械感やテンプレ感が強く、そもそもの質が低いため
- ②AIモデルが自己生成したデータで繰り返し学習すると、モデルの性能が低下する傾向があるため※1
低品質コンテンツが溢れかえる未来
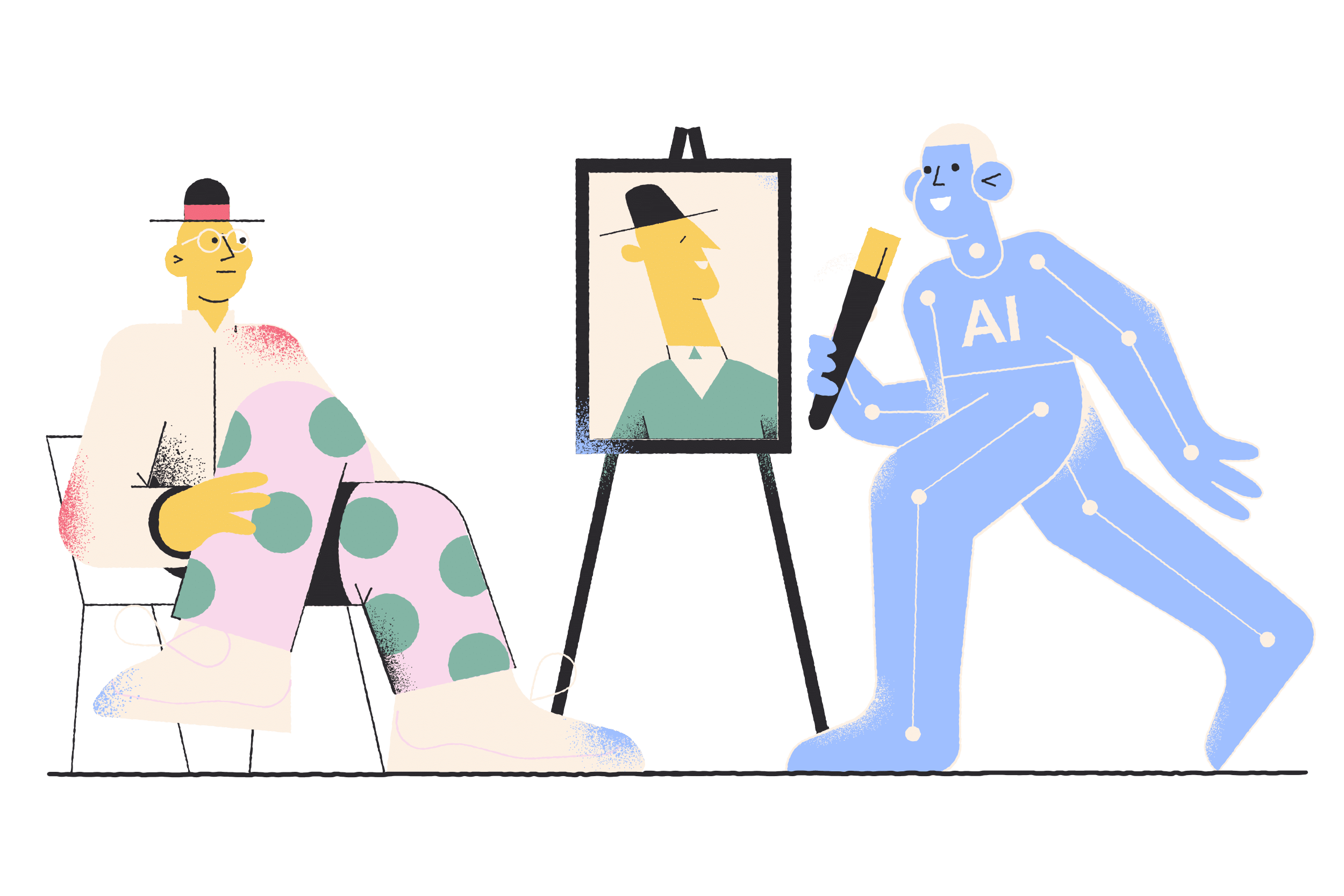
低品質なAIによるウェブライティング記事は、将来的に大きな影響を及ぼす可能性があります。
何の発見や知見も得られないような、質の低いAI生成記事が多くなればなるほど、「ウェブ上の記事全体の品質が加速度的に下落」を招くことにつながるためです。
現在の生成AIはウェブ上の知識を閲覧し、ユーザーの質問に答えるフローが確立されています。
Google検索においても検索結果の上にAIによる回答を表示するようになりました。
LLMOというAI検索を重視する動きもウェブマーケティング業界において活発になっています。
ウェブ上に低品質なコンテンツが溢れかえると、AIが生成する回答の質そのものが低くなる可能性が高まります。
もちろんAIはウェブコンテンツだけを参照に回答を生成するわけではありません。しかし、その影響は決して小さくないことが想像されます。
こうした長期的なウェブ全体の品質低下について、懸念する声はまだまだ大きくありません。
さて、現状におけるAIライティングの問題点は、以下の様に整理されます。
- ①AIライティング単体では、ユーザーに気づきを与えることは困難(ユーザーの個人体験にゆだねられてしまう)
- ②AIライティングは、体験談や私という視点から記事執筆が困難であり、質が低くなりやすい
- ③ウェブコンテンツ全体の品質劣化を招く恐れがある
これらの問題を解決する方法は2つです。
- ①人間が手を加える「ハイブリッド記事」にすることで、コンテンツの質を担保する
- ②AIに価値があるコンテンツを理解させ、ユーザーの発見につながるコンテンツ生成をさせる
当事務所は②のアプローチを採用することで、他業務や分野への利用可能性が広がるのではないか、と考えました。
現在、当事務所のビジネスコラムは、独自に開発したAIによって、すべて自動的に執筆されています。
創造的ライティングが難しいとしても、別の形で価値のあるAIコンテンツを生成するチャレンジと言い換えることもできます。
当事務所がAI記事を“リライトせずに”公開している理由
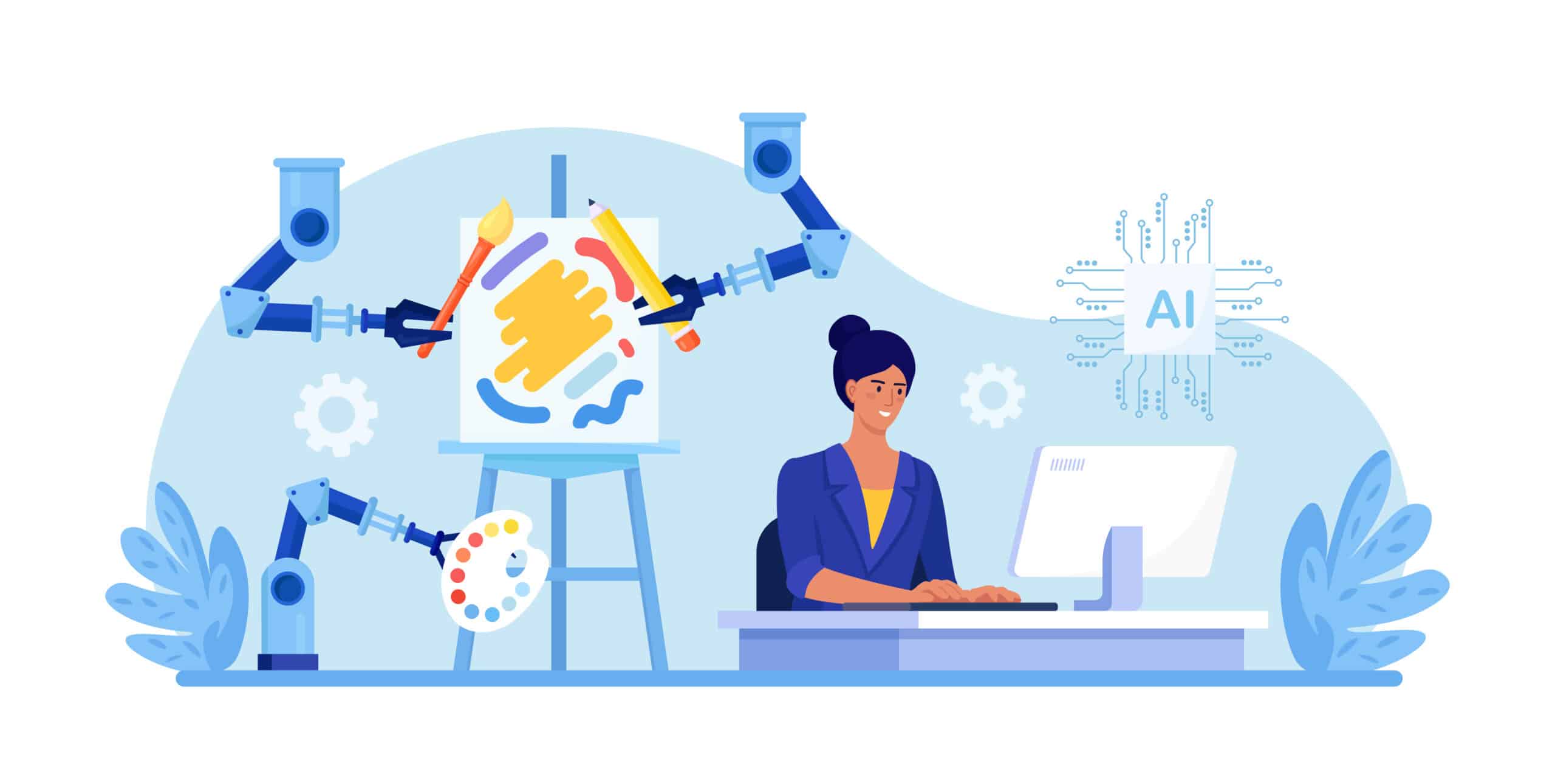
このセクションはAIライティングによって生成されています。
私たちが公開しているAI生成の記事には、一切のリライトを加えていません。
それは、決して“手抜き”ではありません。
むしろ、AIと真剣に向き合ってきたからこそ、その「まま」であることに意味を見出したのです。
多くの企業は、AIが生成した文章を“最後に人間が整える”という形を取っています。
文法や言い回し、構成を人の手で微調整することで、「違和感のない文章」に仕上げようとします。
確かに、その方が洗練されて見えるでしょう。
でも私は、そこにどこか「AIに対する諦め」や「安心を求める保守性」を感じてしまうのです。
私はむしろ、AIに対して「ここまでできる」という限界と可能性の両面を、正面から受け止めたいと思いました。
たしかに、AIはまだ創造性や情緒表現には限界があります。
でもその中でも、私たちは“人間にとっての価値とは何か”を根気強くAIに伝えてきました。
その学習プロセスには、膨大な手間と対話が必要でした。
私自身の文章構造や考え方、経営哲学、読者の感情の揺れ──
そして何より重視したのが読者(ペルソナ)の隠れた真のニーズをかぎ取る能力。
そうした要素を繰り返し、丁寧に共有していったのです。
その結果として、当事務所のAIが書く記事は、他のAI記事とは明らかに異なる“温度”や“気配”を持つようになりました。
実際に、読者の方からこういった声をいただいています:
「AIだとは思えないほど共感した」
「人が書いた記事よりも、自分に寄り添ってくれている気がした」
だからこそ私は、あえてそのままを公開するという選択をしました。
これは、私にとってAIとの“関係性”を模索するプロセスであり、
同時に、「AIの言葉がどこまで人に届くのか?」を測る実験でもあります。
もちろん、リライトという工程自体を否定しているわけではありません。
人が整えることで、文章の質が上がるのであれば、それは間違いなく“良い編集”です。
その選択肢が“プロの文章術”として成立していることも、十分理解しています。
ただ、私自身はそこに“必要性”を感じていないだけです。
当事務所で独自開発したAIは、ユーザーの心理を読み、私自身の価値観や語り口に“なり切って”執筆してくれるからです。
つまり、これは「誰が書いたか」ではなく、「何を読み取って、どう表現したか」に価値を置いたアプローチなのです。
リライトは、コンテンツの完成度を上げます。それは、ビジネス的な効果を最大化することだともいえます。
AIと人間のハイブリッド記事は間違いではないし、素晴らしい成果を出している方もたくさんいらっしゃいます。むしろそちらの方が主流でしょう。
でも、当事務所は異なるアプローチでAIと向き合っているだけなのです。
“AIのそのままの言葉が、どこまで人に届くのか?”
──そこに、私なりの実験と信念がある。
どちらが正しいという話ではありません。
ただ私は、未完成なまま、まっすぐに届けたい。
そう思っただけなのです。
まとめ:AIとのハイブリッド記事の新たな可能性

このセクションは、私という人間が書いています。
いかがでしたか?
本記事では、「AIライティングであること」をあえて公表し、さらに「リライトを行わない理由」についても率直に説明しました。
この選択には、次のような意図があります。
AIライティングの限界を、「お客様にとっての価値」の学習によってどこまで超えられるのか?
それを私自身の実験として試みたということ。そしてAIを「道具」ではなく「関係性」として捉える、そんな構築のプロセスを可視化したかったのです。
ここでご注意いただきたいのは、これは技術的な話ではなく、設計思想の話だという点です。
AIの文章から何かを感じた方がいらっしゃったとすれば、それは「深く設計すれば、AIでもここまで届く」という可能性の証です。
ちなみに、本記事では、前半の現状説明と問題提起は、人間である私が書きました。
そして、後半の当事務所の方針やAIとの関係性の説明は、AIが執筆しました。
あなたは、それぞれのパートを読んで、どのような印象を持たれたでしょうか?
私自身は以下のように感じました。
- 本記事のような「問題提起」や「問いの立て方」は、現時点のAIには難しい。これは創造性の高い領域です。
- 一方で、当事務所の方針やスタンスを語る際の“温度”については、AIのほうがむしろ中立的で、それでいて穏やかな情熱を伝えてくれたように思います。むしろ私の文章の方がAIっぽい?(笑)
- 「AI執筆 → 人間がリライト」というハイブリッド記事が主流ですが、今回のような「人間による問い立て → AIが語る」という逆のハイブリッドも、十分成立するのだと再認識しました。
このように、問題の発見や提起は、AIにとって依然として高いハードルです。
しかし一方で、思想設計が適切であれば、AIでも未来に向けた気づきや感情表現が可能である。
それもまた、この記事を通じて得られた発見です。
本記事の取り組みは、人間とAIが「ひとつの記事を共に創る」という、私にとっても初めての試みでした。
とても実験的なチャレンジではありましたが、私自身、大きな学びと可能性を感じています。
あなたは、本記事を読んで、どのようなことを感じられましたか?
この記事が、あなたにとって「小さな気づき」や「思考のきっかけ」となっていたら、 これ以上うれしいことはありません。























