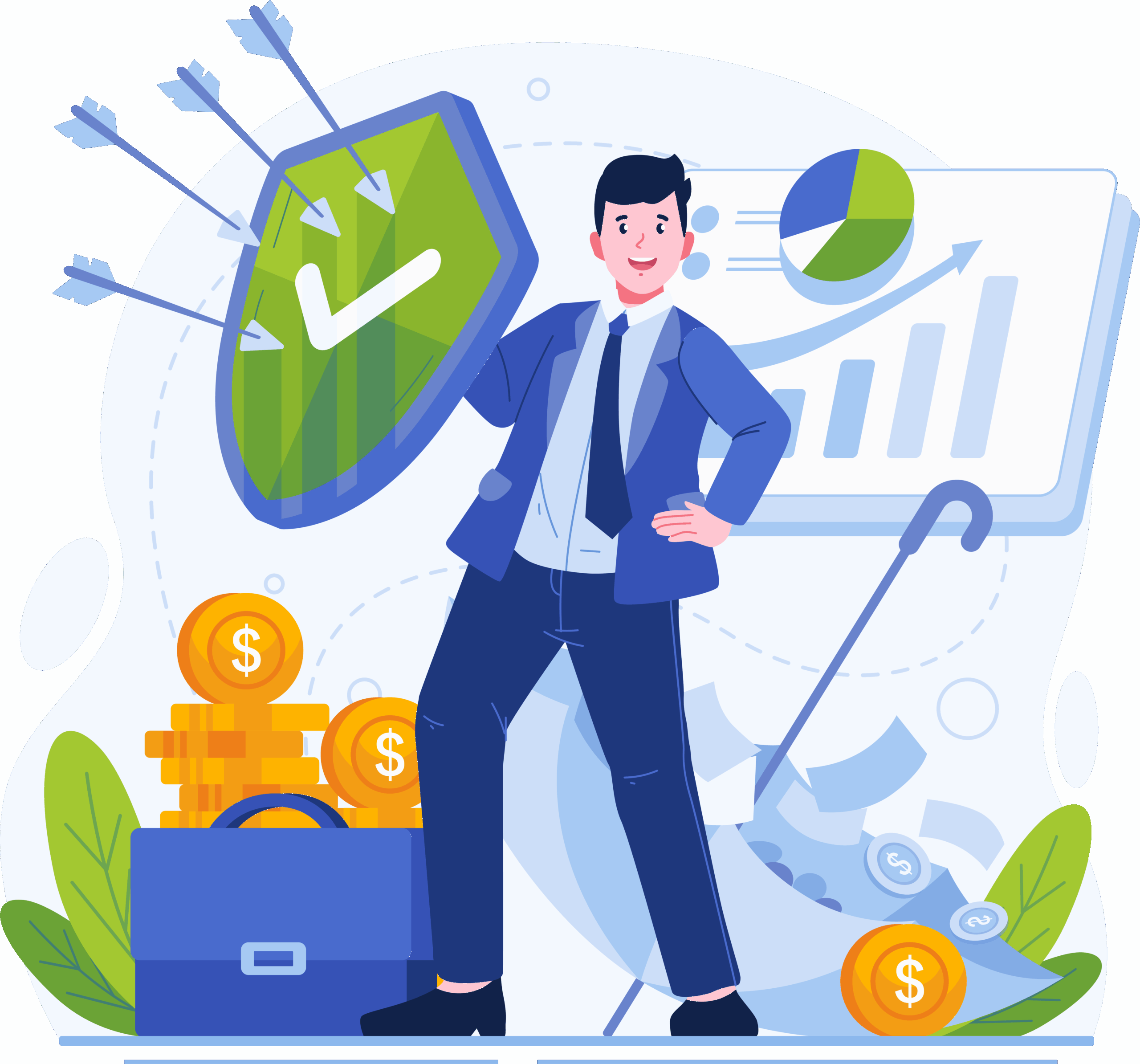こんにちは、ラプロユアコンサルティング行政書士事務所 代表の岩上です。
「評価制度を整えたはずなのに、なぜかチームの雰囲気が冷えている」 「数字は順調なのに、現場から笑顔が消え始めている」
そんな違和感を抱いたことはありませんか?
近年、KPIやMBO、OKRなど──数字で成果を測る制度が広く導入されるようになりました。 合理的で、可視化しやすく、説明責任も果たせる。たしかに便利な仕組みです。
しかしその裏側で、 “数字には映らないけれど、確かに組織を支えているもの”が見えなくなっている── そんな現実に気づき始めている経営者も増えています。
例えば、声をかけてくれる同僚、会議後のフォロー、ちょっとした気配りや笑顔。 それらは表に出てこない“見えない資本”として、組織に静かに根を張っています。
今回のコラムでは、その「数字では語れない信頼」や「空気のような貢献」を、 どう制度に取り入れていけるか──そのヒントを一緒に考えていきます。
あなたの組織にも、“まだ言葉になっていない評価軸”があるかもしれません。
なぜ“成果主義”だけでは組織が壊れるのか?

数字で見えるものだけを評価する構造的偏り
ある中堅IT企業の社長がこう語っていました。 「KPIを導入してから、数字は確かに上がったんです。でも、それと引き換えに“仲間意識”や“温かみ”が薄れていった気がします」。
成果主義は合理的です。誰が、どれだけ、何を成し遂げたか── それを明確にするために「数字」は有効な道具です。
しかしその一方で、制度が「評価しようとしない」行動は、組織から静かに消えていきます。
会議準備の支援、クレーム後のフォロー、沈黙を破る一言── そうした“支える働き”は、エクセルの行には載りません。
経営学者ジェフリー・フェファー氏はこう述べています: 「人は、自分が評価される指標に応じて行動する」※1
つまり、制度が“見ないもの”は、組織に残りません。
・数字に出ないけれど、感謝が集まっている人は誰?
・「あの人がいないと困る」と言われる存在は?
・空気が和らぐ瞬間を作っていたのは?
──見えない行動を“問い”で浮かび上がらせましょう。
成果と“関係性資本”はトレードオフになることも
ある製造業の現場では、数字を出した人だけが評価され、 チーム内の助け合いやフォロー文化が減っていったという声がありました。
成果が出る一方で、 「相談しづらい」 「遠慮が増える」 「互いに背中を向け始める」──
そんな空気の変化が、静かに組織の“関節”をきしませていくのです。
心理的安全性が損なわれれば、声は上がらず、挑戦も生まれません。 その背景には、“数字以外の働き”が見過ごされてきた制度の盲点があるのかもしれません。
「数値化できないもの」を切り捨てていないか
数字は必要です。けれど、数字だけでは語れない“空気”も、確かに存在します。
その存在を組織の中に“問い”として残す。 それが制度設計における、もう一つの責任かもしれません。
あなたの会社の評価制度── そこには「信頼」が含まれていますか?
“信頼”は資本である──組織に流れる“無形の評価軸”

信頼は再投資可能な組織資本
信頼とは、組織の“空気”をかたちづくるだけでなく、 繰り返し使える“再投資型の資本”として機能します。
一度信頼を獲得した社員は、次のプロジェクトでも早期に協働が可能になり、 確認や調整にかかるコストが減少し、関係の中に蓄積される“摩擦の少なさ”が生産性そのものになります。
これは経済学でいう「関係性資本(Relational Capital)」にも通じる概念です※2。
ある企業では、“数字に映らない信頼”が社内の技術継承やプロジェクトの継続性を支えており、 人事制度見直しの際、その存在が再評価されました。
・誰が一番、質問されているか?
・困ったときに“相談される側”は誰か?
・自発的に協力を申し出ている人は?
──これらはすべて、信頼の“観察可能な兆し”です。
“空気の良さ”は組織の戦略資源
雑談、声かけ、言葉のトーン、相談しやすさ── こうした「空気」にまつわる要素は、数値化できません。
しかし、空気の良さは、挑戦を促し、ミスの報告を早め、心理的安全性を高めるという点で、 組織の“戦略資源”そのものになります。
実際、米Google社の調査「プロジェクト・アリストテレス」でも、 “成果を生むチーム”の最重要因子は「心理的安全性」であるとされています※3。
これはつまり、「成果を支えるのは“空気”である」ことを、 データで裏付けた例でもあるのです。
測れないからこそ、設計しよう
制度が信頼を“測定対象にしない”ことで、 信頼は制度の外に追いやられてしまいます。
しかし本来、評価とは“数値で整えること”ではなく、 「組織の価値をどう見ようとするか」という問いに向き合う行為でもあるはずです。
ストーリーベースの記述、1on1の振り返り、ピアレビューの導入── そのすべてが、“信頼を言語化する場”となり得ます。
大切なのは、「信頼を正確に点数化する」ことではなく、 「制度の中に、信頼を映す余白を残す」ことなのかもしれません。
あなたの組織にある“もうひとつの評価軸”は何ですか?

問いを設計に組み込む
評価制度は「測る仕組み」ではなく、「見る構造」でもあります。
その構造に“問い”を組み込めば、 見えなかった価値が、徐々に可視化されていくのです。
例えば──
- 「あなたが今年、一番助けられたのは誰ですか?」
- 「安心して相談できたのはどんな空気でしたか?」
- 「成果の背後で支えてくれたのは誰でしたか?」
こうした問いは、数字にならない信頼や共感、感謝の感情を評価のテーブルに呼び戻します。
・「成果を出す人」ではなく、「誰かを支えていた人」は?
・「評価対象」ではなく、「チームの温度に貢献していた人」は?
・「制度の外」で、最も信頼されていた存在は?
──問いを変えると、評価される人が変わります。
未可視資本の可視化方法
すべてを数値化する必要はありません。 大切なのは、数値の“隣に言葉を置く”ことです。
ストーリー記述、振り返りノート、1on1の対話記録── これらは“点数”にはなりませんが、“関係性”を写し取る窓になります。
ある企業では、昇進面談に「感謝された場面を3つ思い出してください」という項目を追加したところ、 無意識に見落としていた“貢献の証”が浮かび上がるようになったといいます。
数値で語れないものを、あなたはどう扱っていますか?
制度は、冷たい機構ではありません。
問いを持たせることで、制度は“感度”を取り戻します。
もしあなたの中に、言葉にならないけれど確かに覚えている「誰かの働き」があるのなら、 ──それこそが、“もうひとつの評価軸”なのかもしれません※4。
よくあるご質問
Q1. 「信頼」は本当に制度に組み込めるのですか?
数値化することが難しい信頼も、“観測”や“記述”によって制度に反映させることは可能です。 ストーリー評価やピアレビュー、定性的フィードバックの導入が代表的な方法です。
Q2. 成果主義と“信頼重視”は両立できるのでしょうか?
はい。短期成果と中長期的な関係性資本は補完関係にあります。 両者を“指標と問い”として分けて設計することで、制度全体の安定性が高まります。
Q3. 評価の見直しはどのように始めれば良いですか?
まずは現行制度の“見えていない部分”を言語化するところから始めましょう。 組織内アンケートや1on1記録など、感情や共感を扱う場の設計から導入するのがおすすめです。
まとめ~成果主義”数字で語れない“信頼の設計
成果主義やKPI評価は、組織における「成果の見える化」を進める上で非常に重要です。
しかし、数字に映らない“信頼”や“支え合い”を評価制度の外に置いたままでは、 制度が組織文化を削る可能性すらあります。
今回のコラムでは、こうした“見えない資本”をどう言語化し、どう設計に取り込むか、 問いをベースに検討してきました。
信頼は測るものではなく、“気づくべきもの”。 そして制度とは、“問いを残す設計”でもあるのです。
あなたの制度設計の中に、「まだ評価されていないけれど確かにあった貢献」は、含まれていますか?
📌 この記事の 3 行まとめ
・“数字で語れないもの”が、組織の未来を左右している
・信頼・空気・つながりは“資本”であり、設計によって再評価できる
・制度に“問い”を組み込むことで、見えない貢献も可視化できる
信頼とは、制度に映らない“もうひとつの実績”なのかもしれません。
またお会いしましょう。
出典・参考文献
- ※1:ジェフリー・フェファー(Jeffrey Pfeffer)『Power: Why Some People Have It and Others Don’t』HarperBusiness, 2010年
- ※2:Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
- ※3:Google, “Project Aristotle” による社内調査
参考URL:https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/#introduction - ※4:評価制度と“問い”の関係性についての筆者経験則および複数の中小企業への制度設計支援事例より(実名非公開)