「このまま今の会社にい続けて、本当に大丈夫なのか──」
そんな不安が、ふとした瞬間に頭をよぎることはありませんか?
家族を支え、子どもの将来を考え、住宅ローンを背負って働く日々。
“自分のことは後回し”にしてきたあなたが、いま感じているその違和感。
それは、けっして気のせいではありません。
実際、40代は「会社に尽くしても報われにくい構造」の中にいます。
昇進は頭打ち、給与は横ばい、物価と社会保険料は上がり続ける──
気がつけば、“頑張っても生活は楽にならない”状態に陥っている人が、少なくありません。
でも、周囲を見渡してみてください。
いま、副業を始める人が確実に増えています。
事実、40代の副業実施率は全世代で最多の31.7%。
「もしもの備えに」「収入をもう一本増やしたい」
そんな理由で、多くの人が“動き始めている”のです。
さらにその先には、「起業」という選択肢があります。
会社に依存せず、自分のスキルや経験で収入を生み出す──
それは、構造そのものを変えるための“脱出口”でもあるのです。
「まだ何も決まってない」「とにかく動かなきゃと思ってる」
そんなあなたにこそ届けたい、“副業から始めるキャリア再設計”の戦略を、この記事にすべてまとめました。
このまま何も変えずに10年働いた自分と、
今、たった1歩動いた自分──
10年後、どちらに後悔しないか。
この記事が、その分岐点になります。
なぜ会社で努力しても報われないのか──その構造を解説した記事はこちら:
崩壊した終身雇用と、再構築するキャリア戦略──なぜ“報われる設計”が消えたのか
40代、会社にしがみつくしかないのか?
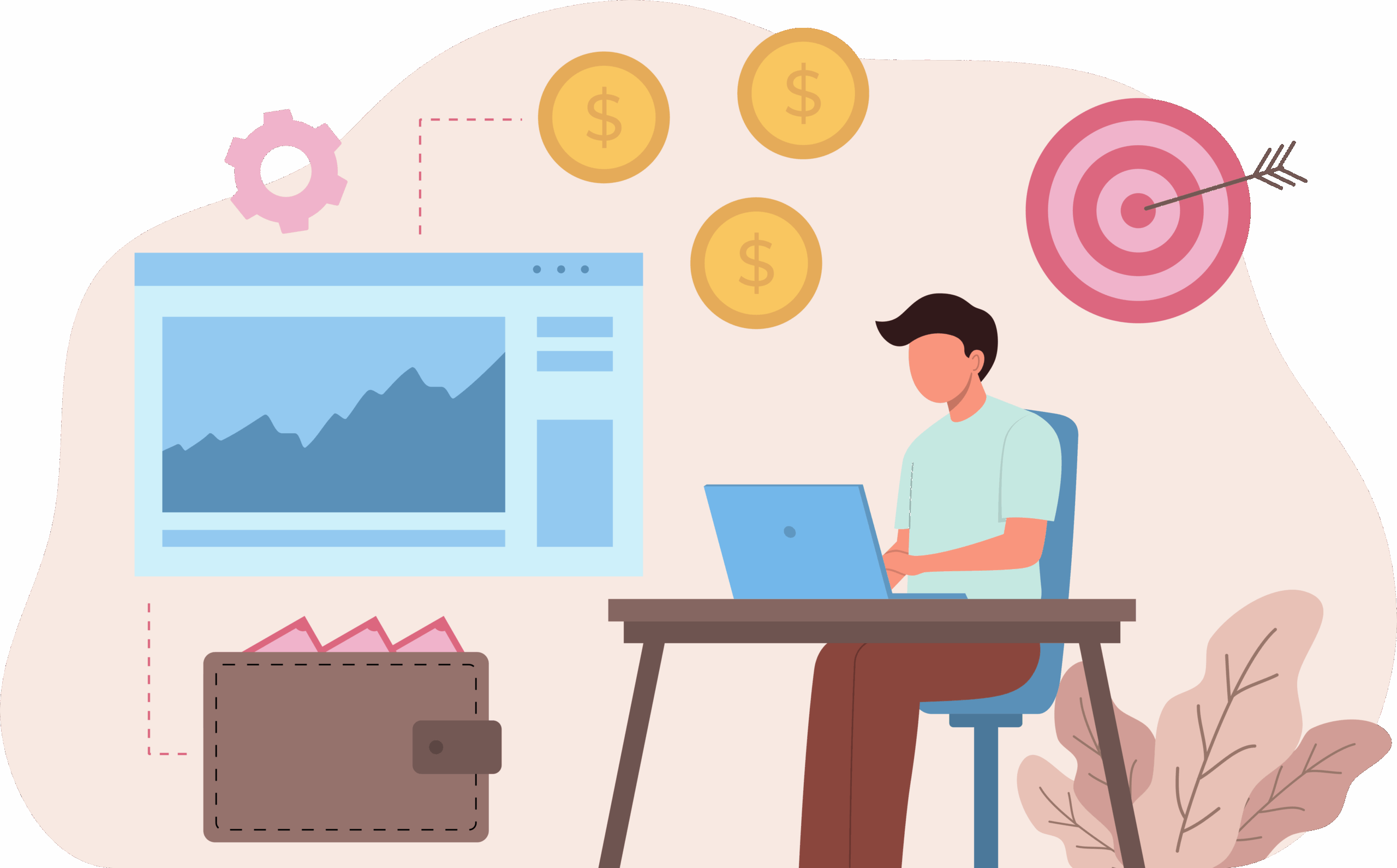
昇進は頭打ち、給与は横ばい、物価だけは上がり続ける──。
そんな現実のなかで「会社を辞めるなんて現実的じゃない」と思っていませんか?
でも、会社はもう“安全な場所”ではありません。
一見、ニュースでは「賃上げ率3%超」など明るい報道が目立ちます。
しかし実際には、社会保険料の増加・税負担の増加によって、手取りが増えた実感がある人はほとんどいません。
全国健康保険協会によると、2024年度の社会保険料(厚生年金+健康保険)は実質上昇しています[1]。
また、総務省の「家計調査年報」では、2023年度の可処分所得は前年比-1.5%という統計も出ています[2]。
つまり、名目賃金が上がっても、生活は苦しくなっているということ。
「給料が上がっているはずなのに、なぜか自由に使えるお金が減っている」
そう感じていたあなたの直感は、間違っていません。
一方、恩恵を受けているのはごく一部の大企業。
消費税の“還付”を受けるような経団連所属企業や、大規模な公共事業を請け負う法人でなければ、継続的な昇給や手厚い福利厚生は期待できません。[3]
それでも、あなたは「この会社にいるしかない」と思っていませんか?
もし、会社にいながらリスクなく“もう一つの道”を試せる方法があるとしたら──。
続くセクションでは、40代が今すぐ動ける「副業という安全装置」について詳しく解説します。
副業は“安全装置”──まずは小さく稼いでみる
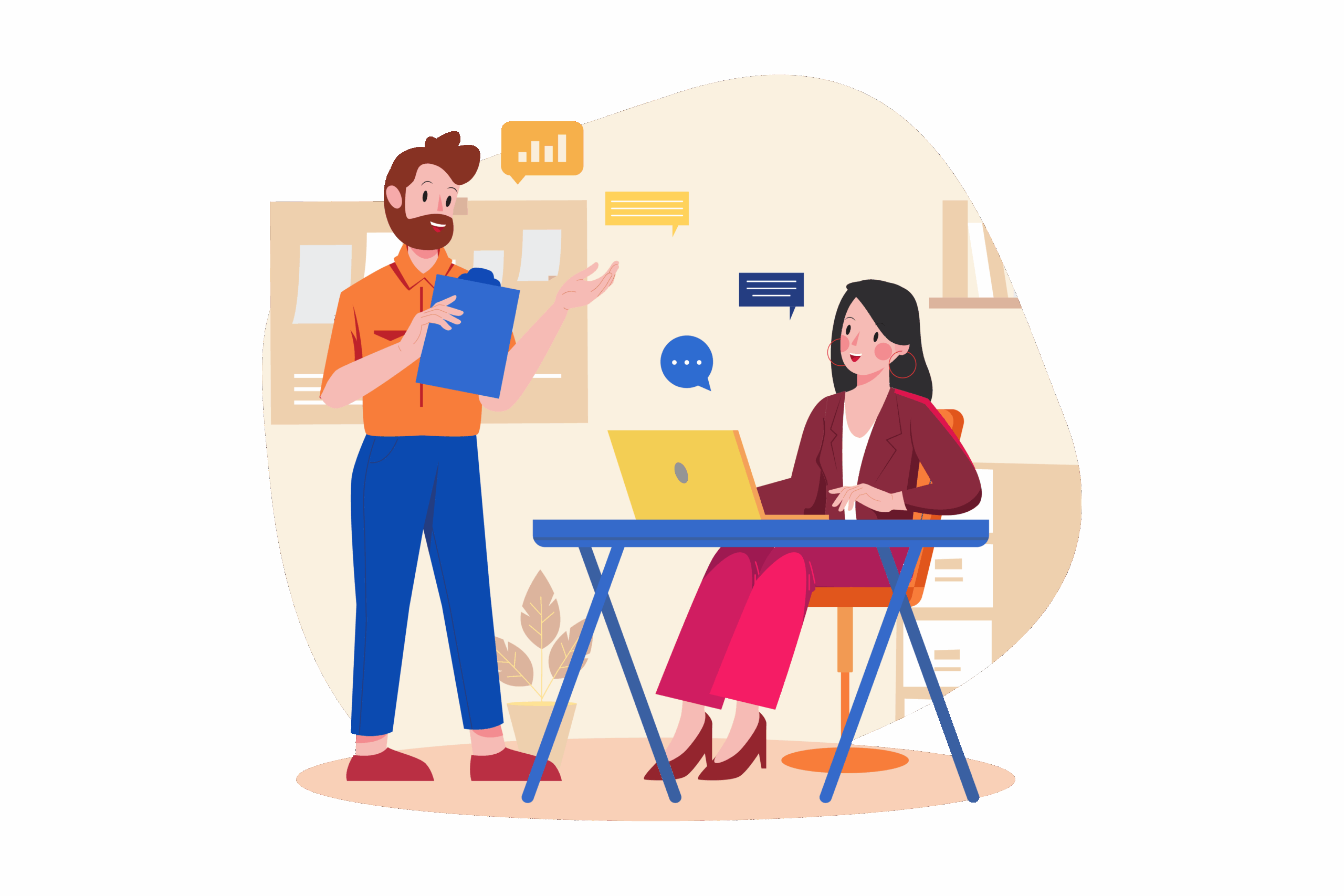
「何から始めればいいのか分からない」「起業なんてリスクが高すぎる」
そんな人にとって、副業は“最も安全な選択肢”です。
なぜなら、副業には会社を辞めずに、リスクを最小限に抑えて始められるという最大のメリットがあるからです。
実際、40代の副業実施率は31.7%と、全世代で最も高い水準[4]。
しかもその多くが、「将来への不安に備えるため」「自分の力を試したい」という理由で始めています。
副業といっても、特別なスキルや大きな初期投資は必要ありません。
今あるスキルや経験を“切り出す”ことで、すぐに現金化できるモデルはたくさんあります。
副業タイプ別:特徴と進化ステップ
| タイプ | 特徴 | メリット | リスク |
|---|---|---|---|
| 業務委託型 | ココナラ/クラウドワークスなど | 即収益化/スキル不要でも可 | 時間を切り売り/拡張性が低い |
| ストック型 | ブログ/YouTube/noteなど | 仕組みで稼ぐ/収益が継続する | 成果が出るまで時間がかかる |
| 教育・指導型 | 講座販売/コミュニティ運営など | 高単価/信頼が資産になる | 集客に工夫が必要/準備に時間 |
初期フェーズは業務委託型で「自分の商品が売れる体験」を得ることが重要。
そこからストック型に移行することで、“働き方の構造”を変えることが可能になります。
月に1万円でも、自分で稼げたとき── あなたの中にある「自信」と「構造の見え方」が確実に変わります。
副業は単なるお小遣い稼ぎではありません。
構造的に報われにくい社会の中で、自分を守る“安全装置”です。
そして同時に、それは“脱出口への前進”でもあるのです。
都内勤務の会社員(43歳・男性)は、ココナラで「Excel自動化ツール作成」の副業をスタート。
平日夜と土日を活用し、初月で1万円、3ヶ月目には5万円超の安定収益を達成。
その後、ブログ+note記事販売によるストック型収益を組み合わせ、年間売上が100万円を突破。
税負担軽減と事業拡張を見据えて、半年後に法人化。
初年度の売上は約310万円に伸び、副業から「第2の収入構造」へと成長させた。
起業は“脱出口”──会社に頼らない選択肢
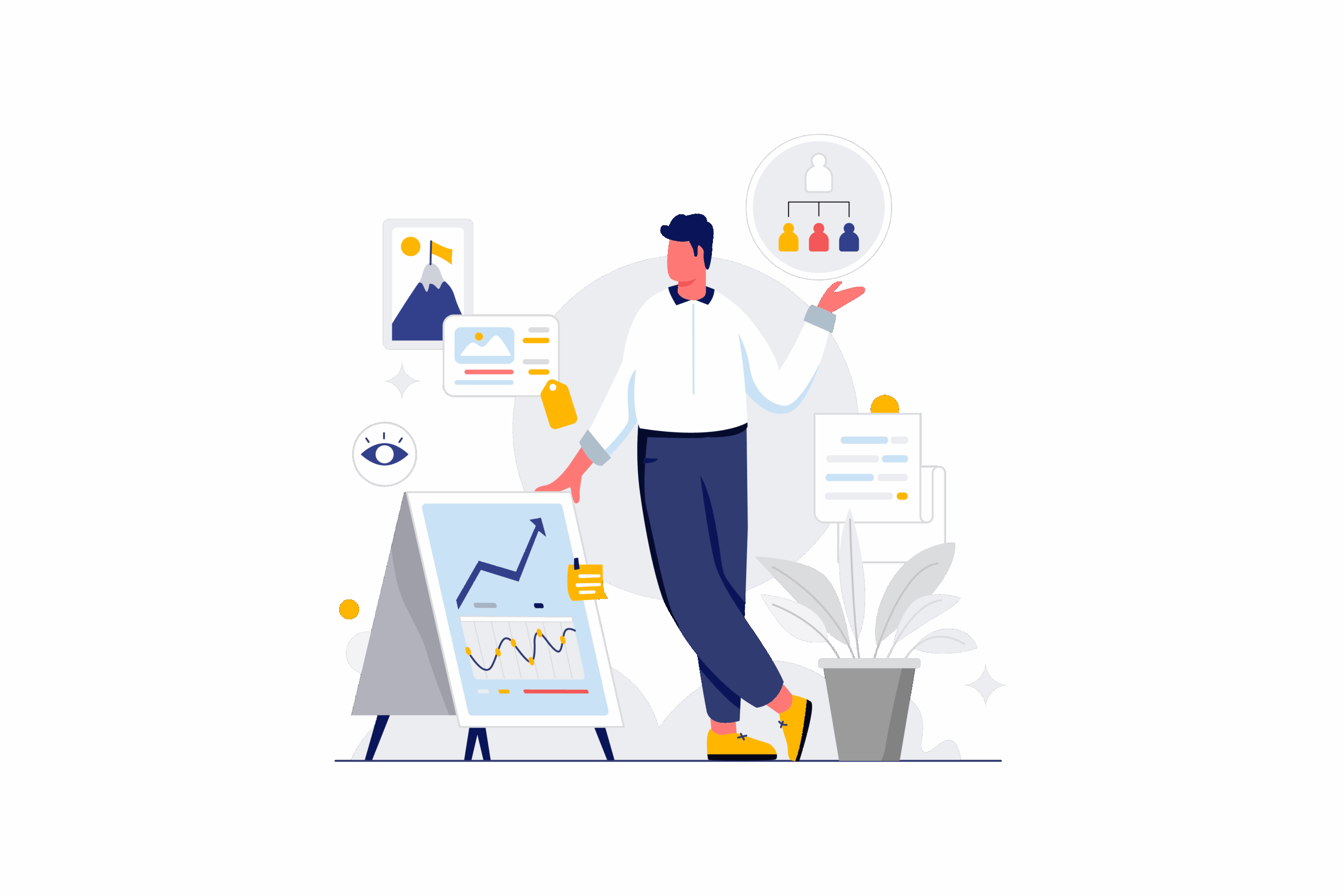
副業が“安全装置”なら、企業は”脱出口”といえます。
副業で「1円でも自分で稼げた」──その瞬間、会社に“全てを預ける”構造から抜け出せる実感が生まれるのです。
そこから次に出てくる問いが、「この力を“自分の構造”にできないだろうか?」という発想です。
つまり、起業は単なる“ビジネス”ではなく、“自分で構造を設計する”ための選択肢なのです。
起業というと大げさに聞こえるかもしれませんが、多くの人がこうしたステップを踏んでいます:
- 副業でスキル・経験を切り出す
- 個人事業主として収益源を確保する
- 必要に応じて法人化し、税制・信頼性の恩恵を受ける
ここで気になるのが、「個人事業」と「法人」の違いです。
どちらが本当に有利なのか?
以下にその違いを整理します。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社) |
|---|---|---|
| 設立費用 | ほぼ0円(開業届のみ) | 約25万円(登録免許税+定款+印紙代等) |
| 税率 | 累進課税(最大55%) | 約23.2%(法人税・住民税) |
| 社会保険 | 加入は任意(国保+国年) | 強制加入(社保+厚年) |
| 信頼性 | 個人との取引になるためやや弱い | 法人名義が使えるため強い |
| 経費の柔軟性 | 事業色が強くないと否認リスクあり | 役員報酬・福利厚生など広く活用可能 |
法人化の初期コストは確かにかかりますが、節税・信用・拡張性という“構造設計”の観点から見ると、非常に強力です。
「副業での収益が安定してきた」「年間100万円以上の利益がある」──
そんな段階での法人化は、税負担を大きく軽減し、次の展開への“投資余力”を生み出します。
法人化はゴールではありません。
“自分の働き方を、自分で設計する”という意思表明なのです。
副業禁止とどう向き合うか──現実的な壁と、突破する方法
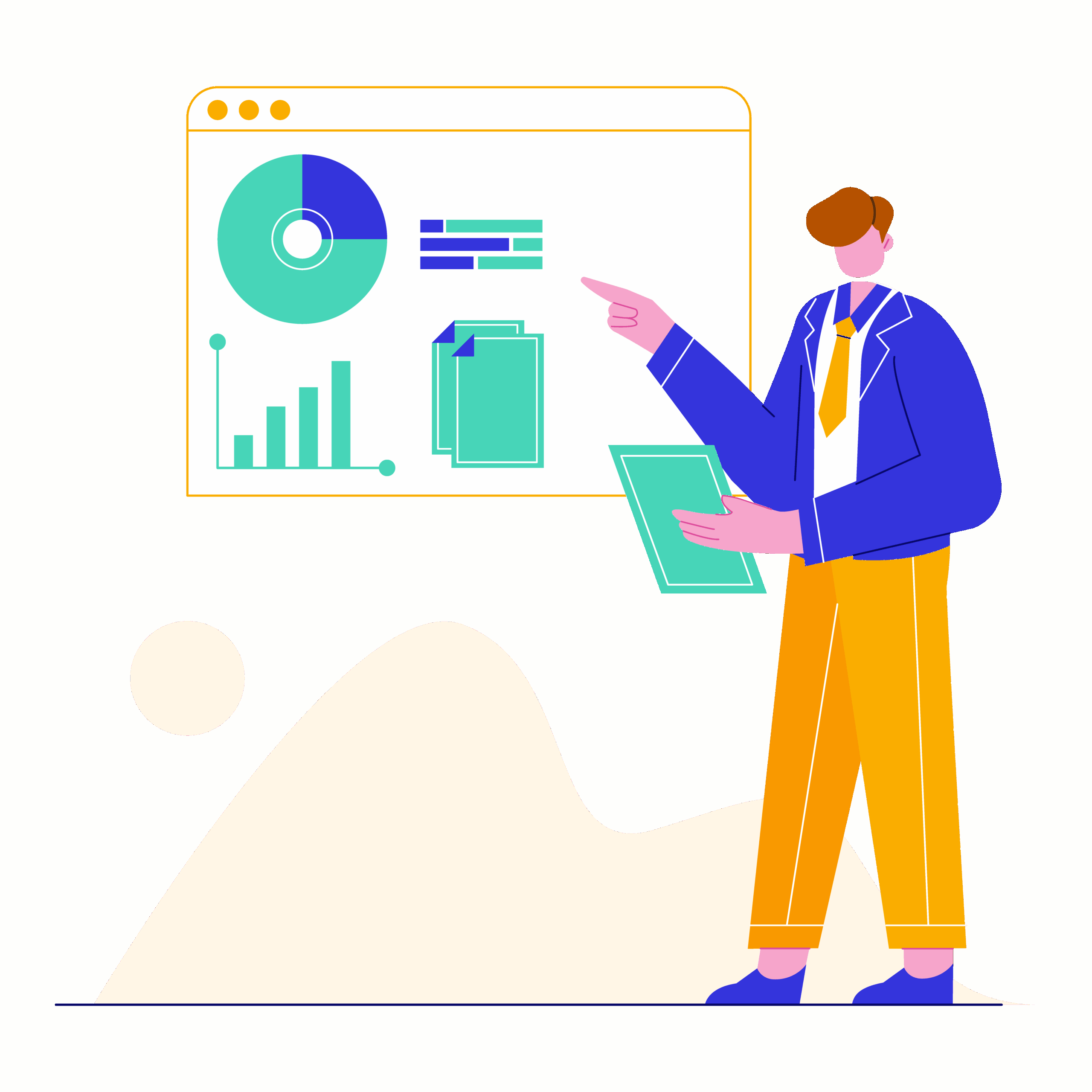
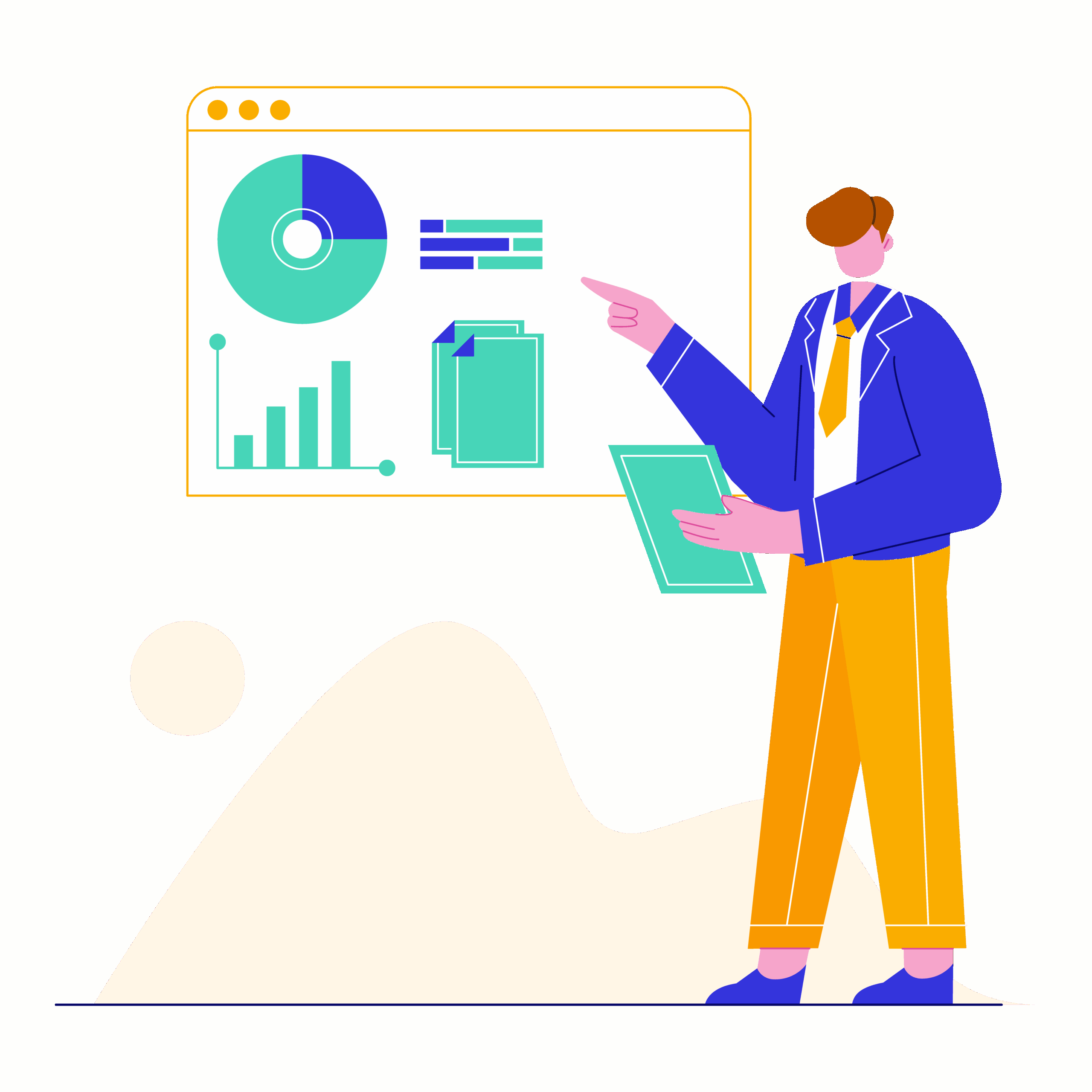
「副業したいけど、うちの会社は禁止なんだよな…」
そんな声を、私たちはこれまで何度も聞いてきました。
でも実は、“副業全面禁止”は、法的にも現実的にもグレーな領域なのです。
副業禁止は、どこまで許されるのか?
- 憲法22条により「職業選択の自由」が保障されている
- 労基法や民法に“副業全面禁止”の明文規定は存在しない
- 就業規則や忠実義務・競業避止義務により「制限」は可能
- 厚労省ガイドラインでも原則容認を明記[5]
- 東京地裁2008年判決でも「業務支障なき副業は原則自由」[6]
副業禁止に直面したら、どうすればいい?
- 就業規則を確認:「全面禁止」なのか、「許可制」なのかを把握
- 許可を得る手順を確認:非競業・情報保護・時間外活動を明示し、申請
- ガイドラインを根拠に交渉:書面で「原則容認」である制度趣旨を提示
- 交渉が難しい場合:非競業・匿名性が高く、労務時間が短い副業からスタート
会社にバレるとどうなる?
- 就業規則違反:軽微な場合は戒告〜減給程度が多く、懲戒解雇はまれ。
ただし競業・業務への著しい支障・虚偽報告などがある場合、懲戒解雇が有効とされた判例も存在します。 - 損害賠償:競業・秘密漏えい・名誉毀損がある場合に限られる
- 健康リスク:副業との通算で週80時間を超える場合は、
労働基準法第38条(労働時間通算原則)のもと、
企業側にも健康配慮義務が生じる可能性があります。
“副業禁止”の壁を越える実践ヒント
- 💡オンライン完結型でテストスタート(note/ブログ/YouTubeなど)
- 💡非競業・業務外時間に限定すれば許可が通りやすい
- 💡ガイドラインを武器に制度交渉も可能(厚労省2024年版)
- 💡社内還元を提案:副業で得たスキル・知見を本業にも活用と主張
大切なのは、“禁止”と書いてあるからといって、すぐにあきらめないこと。
ルールを正しく理解し、戦略的に動くことで道は開けます。
地方企業で勤続18年の中堅社員(41歳・女性)は、社内規則の「副業全面禁止条項」に悩みながらも、
厚労省ガイドラインと健康管理ログ、競業回避設計書をまとめて、人事部に書面申請。
業務時間外/非競業/収入上限あり の条件で、副業が条件付き容認へ。
その後、得意の文章スキルを活かしてnote・Kindle出版に挑戦。
3ヶ月で1万PV、収益3万円を達成。現在は社内でも“副業制度改訂モデル”として紹介されている。
分岐のタイミングは、いま──動かない方がリスク
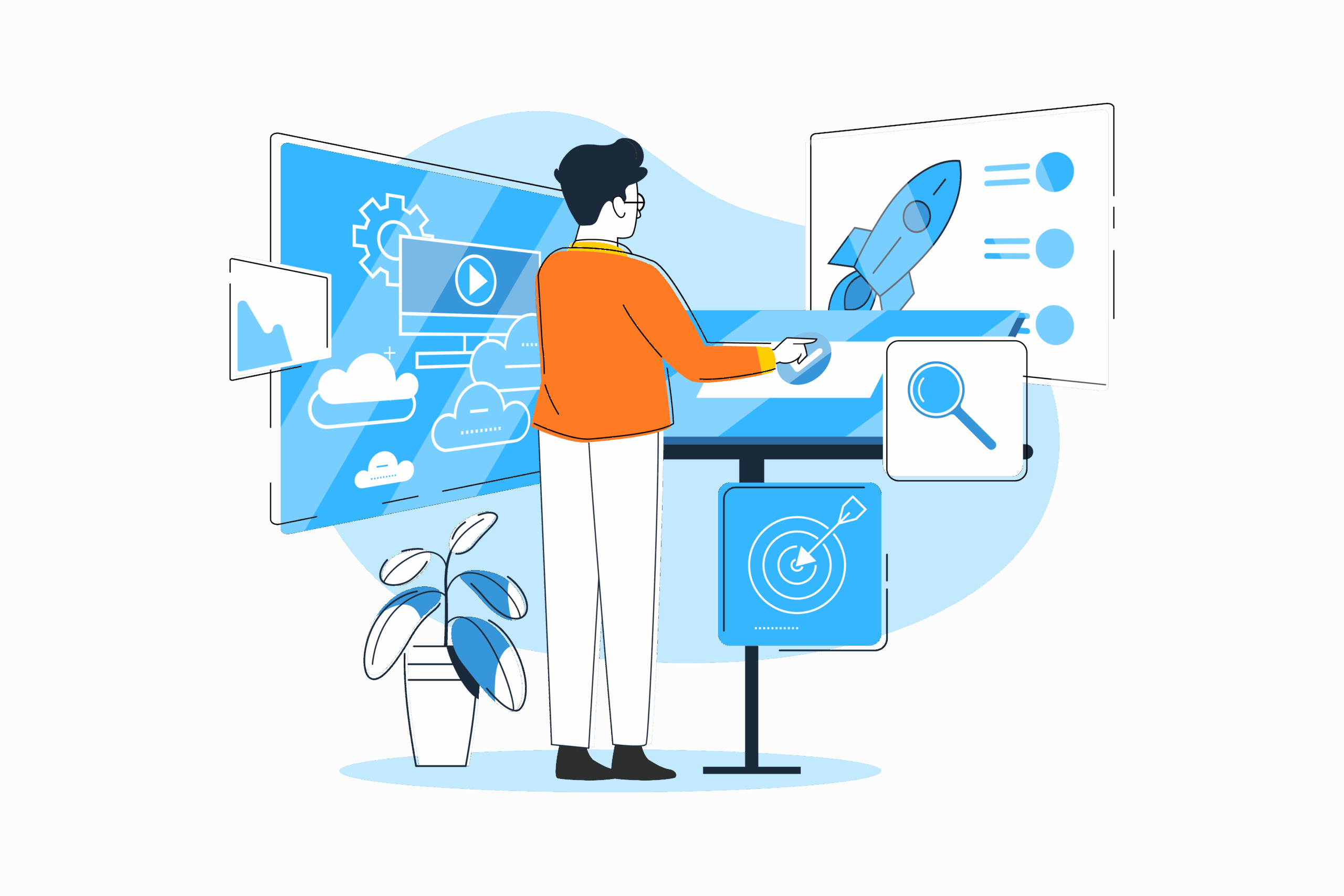
「いつか、余裕ができたら考えよう」
そう思っているうちに、気づけばもう数年が経っていた──
そんな経験、ありませんか?
40代は、人生において最も“静かに崩れていくリスク”が潜む時期です。
子どもの教育費、住宅ローン、親の介護、自分の健康不安…
何も変わらなくても、支出と負担だけは確実に増えていきます。
そのときに「会社しか選択肢がない」という状態だと、選べる未来が急激に狭まっていきます。
だからこそ、“会社を辞めなくてもいい今のうちに”、次の柱を立てておくことが、もっとも堅実なリスクヘッジになるのです。
副業は、人生の“キャリアセーフティネット”です。
1円でも自分の力で収益が出た瞬間、「会社だけに依存しない自分」が生まれます。
起業は、“構造を作る側”に立つための選択です。
法人を持ち、ルールを理解し、自分の意思で仕組みをつくれるようになったとき、
あなたはもう、未来を“選ばされる”側ではありません。
あなたの中には、もう“構造を変える力”が眠っています。
あとは、それを「試すか/試さないか」──たったそれだけの違いです。
もし、この記事をここまで読んでくれたなら、あなたの中ではもう何かが始まっているはずです。
小さな一歩でも構いません。
今日、その一歩を踏み出してみませんか?
よくある質問(FAQ)
Q. 副業って会社にバレませんか?
住民税の特別徴収やSNS発信などで判明する可能性はありますが、申告方法を工夫すれば防げます。事前の相談や非競業型モデルを選ぶことで、会社に認められながら副業することも可能です。
Q. 自分のスキルで本当に稼げますか?
はい。最初はスキルに自信がなくても、知識や経験を“誰かの役に立つ形”に変えることで現金化できます。実際に40代の副業実施率は30%を超えており、誰でも始められる環境が整っています。
Q. 副業から起業に移るタイミングっていつですか?
月5〜10万円の収益が安定して出るようになったら、起業や法人化の検討タイミングです。税制・信頼性・事業展開の広がりなどを踏まえ、法人化するとメリットが大きくなります。
Q. 法人化するメリットって何ですか?
節税・社会的信用・資金調達のしやすさ・経費の柔軟性など、事業を広げる上で大きなメリットがあります。法人を持つことは、構造を“自分の手に取り戻す”手段でもあります。
Q. ラプロユアコンサルティングでは何をサポートしてくれるの?
会社設立の手続きから、ビジネスモデル設計、補助金・税務連携まで、法人化に必要な“設計支援”を一括でお手伝いしています。会社を辞めずにチャレンジしたいという方もご相談ください。

最後に:あなたにも“選べる構造”がある
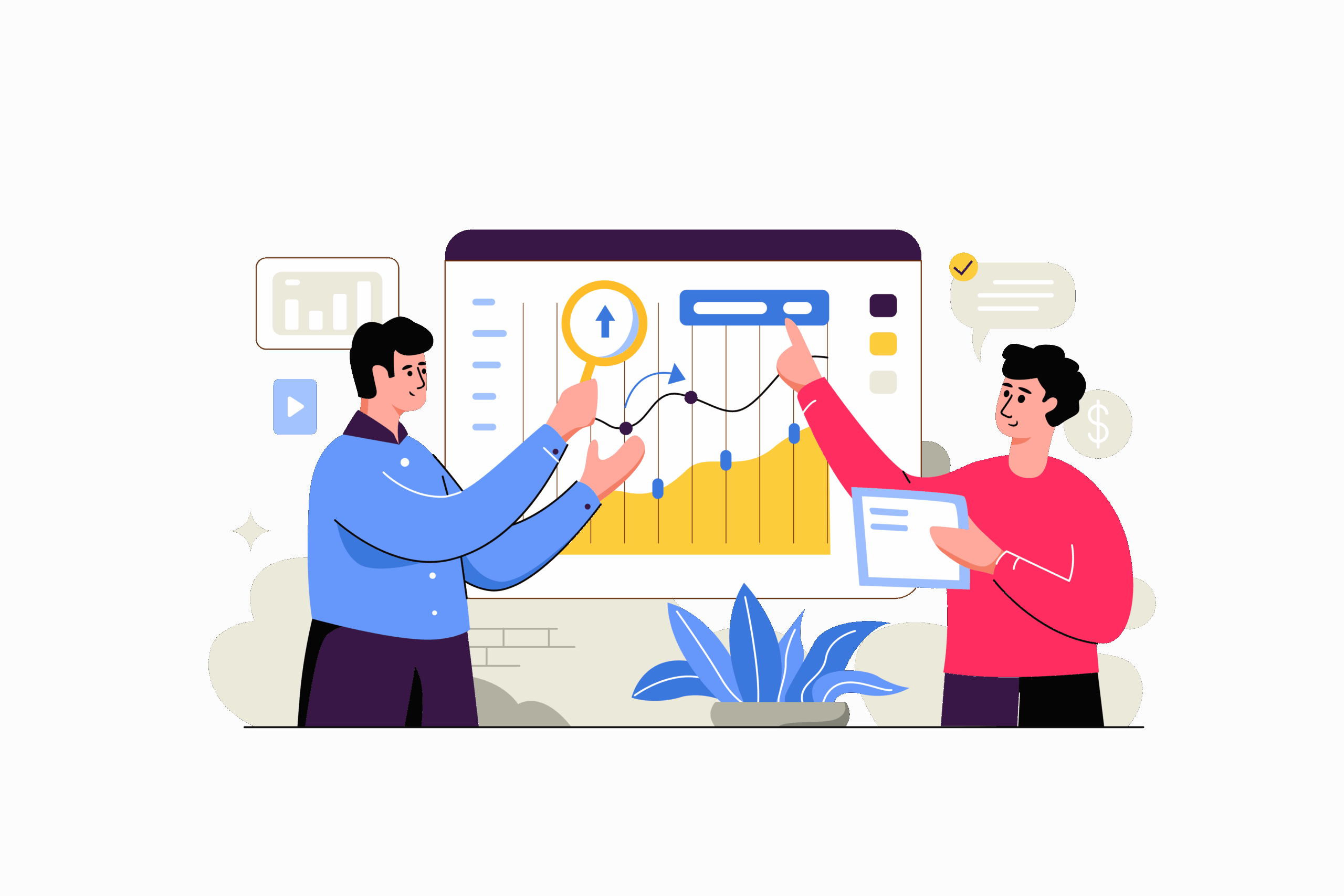
- 40代のキャリアは“会社だけ”に依存しない設計が必要
- 副業は安全に動ける最初の選択肢、起業は構造を変える手段
- 未来を選ぶ力は、すでに“あなたの中”にある
「このままで本当に大丈夫なのか」── そう思ったときが、キャリアを再設計するチャンスです。
会社にいながら副業で一歩を踏み出し、自分の価値を試す。
そこで得た実感をもとに、自分で構造を設計し、法人として未来を選ぶ。
それは決して、一部の特別な人にだけ許された選択ではありません。
副業は「安全装置」。
起業は「脱出口」。
そのどちらも、あなた自身が持ちうる“選択の力”です。
私たちは、会社を辞めずに動き出す人の味方です。
副業の始め方、法人化の判断、節税・信頼性・設計支援まで──
あなたの“構造設計”を、ゼロから全力でサポートします。
このまま10年働いた未来と、今日たった1歩踏み出した未来。
その差は、想像よりもずっと大きい。
あなたの未来は、いまここから選べます。
📘 無料で始める“キャリア構造の再設計”
副業を「収入の手段」ではなく、
“構造を選び直すきっかけ”として考えてみませんか?
- ✅ 今すぐ使える「副業から起業までのキャリア分岐ロードマップ(無料PDF)」をご用意しました。
- ✅ 40代の副業事情・法人化の判断基準・心理設計の流れまで、実例とデータに基づき体系化。
- ✅ あなたの“動ける構造”をつくる第一歩に。
参考資料・出典一覧
-
全国健康保険協会「令和6年度 社会保険料率一覧」
https://www.mhlw.go.jp/content/000971188.pdf -
総務省統計局「家計調査年報(2023年)」─ 実質可処分所得の推移
https://www.stat.go.jp/data/kakei/2023np/pdf/youyaku.pdf -
財務省「消費税の仕組みと輸出企業の還付制度に関する解説」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/063.htm -
総務省「令和4年 就業構造基本調査」─ 副業実施率と年齢別傾向
https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/index.html -
厚生労働省『副業・兼業の促進に関するガイドライン(2024年7月改定版)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html -
契約ウォッチ「東京地裁2008年12月5日判決(私大教授兼職事件)解説」
https://www.keiyaku-watch.jp/articles/137






















