「4Pを学んで、ちゃんと整理して取り組んできたはずなんです。
でも…なんか、“うまく回らない”んですよね」
これは、実際に当事務所の顧問先の社長様から耳にした言葉です。
商品設計も、価格設定も、販路も、広告も──
ひとつひとつ真面目にやってきた経営者ほど、
この“モヤモヤ”にぶつかりやすいのかもしれません。
確かに、4Pは古典的かつ有効なフレームワークです。
でも現実には、それだけでは届かない、伝わらない、選ばれない。
そんな“届かない努力”が現場では増えています。
今回ご紹介するのは、その4Pを「演算構造」へと再設計したモデル──
Product × Translation × Access × Framing(PTAFモデル)です。
この構造を使えば、あなたのビジネスが「どこで止まっているか」「どこが伝わっていないか」を、
数式レベルで診断・改善できるようになります。
商品を変える前に、売り方を変える前に──
まずは構造を、掛け算で見直してみませんか?
4Pモデルを整えただけでは売れない

「4Pはすべて整っているはずなのに、選ばれない」──
この違和感を経験した人は、少なくないはずです。
4Pとは、マーケティングにおける“古典的かつ普遍的な整理法”です。
Product(商品)・Price(価格)・Place(販路)・Promotion(販促)の4つの要素をバランスよく設計することで、市場に適応し、売上を最大化できる。
フィリップ・コトラーをはじめ、名だたるマーケターがこれを基盤に理論を構築してきました。
しかし現代では、「4Pを整えただけでは選ばれない」という現象が増えています。
たとえば──
- ✔ 商品はきちんと設計されている(Product)
- ✔ 価格は妥当で、競合より安いこともある(Price)
- ✔ ネットでも買えるし、リアル店舗もある(Place)
- ✔ SNSも広告もまめに更新している(Promotion)
それなのに、なぜか売れない。紹介もされない。リピートも起きない。
こうした現象は、4Pという“分類”のフレームワークでは説明できない領域に入り始めているのです。
本記事では、従来のマーケティング理論「4P」に代わり、
小規模ビジネスでも実践できる、選ばれる構造=PTAFモデルを解説します。
売上 = Product × Translation × Access × Framing
→ 商品(Product)を軸に、「語られ」「届き」「納得される」構造をつくる。
→ どれかひとつでも“0”に近ければ、売上も限りなく0に近づいてしまう。
「構造が整えば、紹介される」
「構造が整えば、価格に納得される」
「構造が整えば、売上は動き出す」
この視点を手に入れることで、あなたのビジネスは
“がんばり続ける状態”から、“選ばれる構造で回る状態”へと変わっていきます。
Productが“0”なら、何をかけても売れない
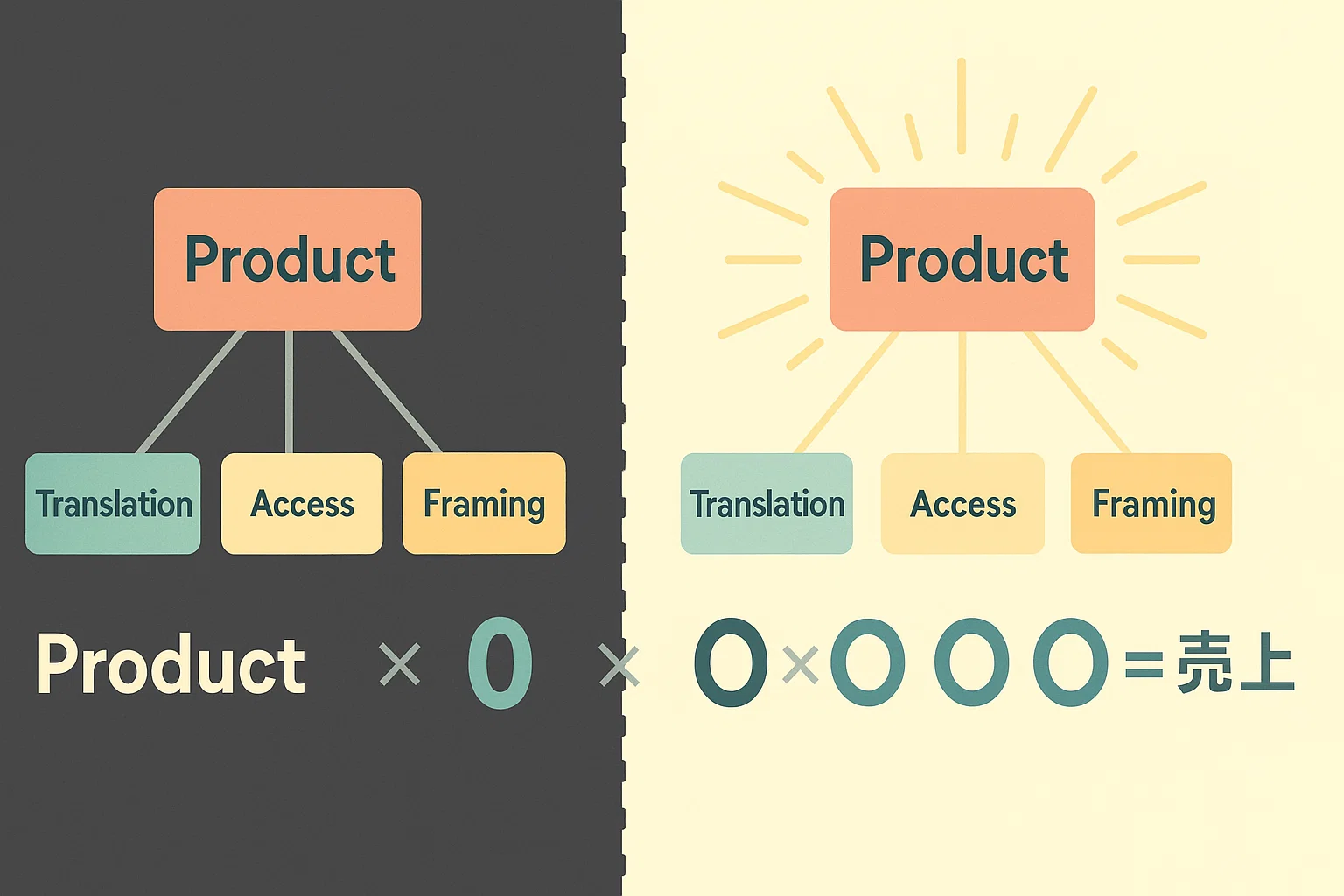
前章でお伝えしたように──
現代のビジネスでは「努力しているのに売れない」という現象が頻発しています。
原因のひとつが、「構造としての連携」が断絶していること。
いわば、各施策が“掛け算になっていない”状態です。
売上 = Product × Translation × Access × Framing
→ 各係数は互いに“掛け算”で連動。
→ どれかが「0」に近づけば、売上も限りなく0になる。
これは単なる比喩ではありません。現場では、
「SNSは動かしている」「広告も出している」「接客も丁寧」──
にもかかわらず、まったく反応がないという事例が後を絶ちません。
よくよく分析してみると、“選ばれる理由”があいまいで、
そもそもProductの中核が語られていなかった。
つまり、Productという係数がゼロに近い状態だったのです。
特に重要なのは、Productの絶対性です。
- ✔ Productが“0”なら、他がいくら整っていても結果は出ません
- ✔ 逆に、Productが“圧倒的”であれば、他が弱くても売れる可能性があります
つまりこの構造は、単なる均等な4つのPではなく、
Productを中核に、他3つが“増幅装置”として機能する非対称構造なのです。
あなたのビジネスは、今「どの係数」が止まっているでしょうか?
翻訳できていない? 届いていない? 選ばれない? それとも──
Productそのものが語られていない?
次章では、このProduct=“選ばれる理由の本体”について、
信頼・体験・言語の3層構造から深掘りしていきます。
Productが持つ“本質力”とは何か?
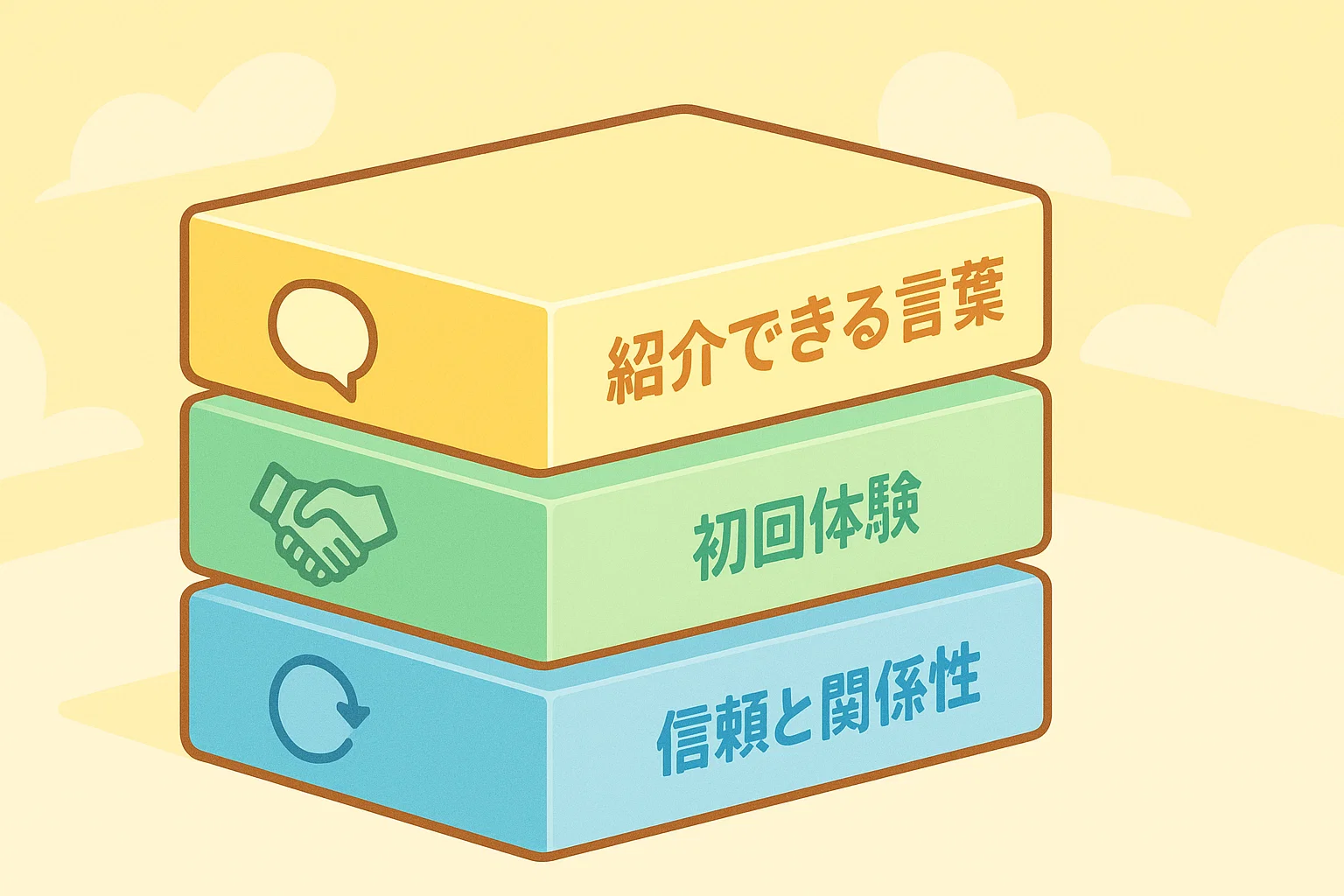
Product=売るもの──そう思っていませんか?
たしかに、従来の4P理論ではそう定義されています。
しかしPTAFにおけるProductとは、もっと深く、もっと構造的な意味を持っています。
Product=“選ばれる理由の本体”
単なるモノやサービスではなく、
「誰に」「なぜ」選ばれ続けるのかを構造的に備えた中核。
機能・価格・対応・信頼・価値──それらを“まとめて宿す存在”が、Productです。
特に小さなビジネスにおいては、
商品の中に「再選択される理由」が組み込まれているかが、成功と失速の分かれ目です。
ではその「Productの本質力」は、どのように分解できるのか?
本記事では以下の3層構造として定義します。
- ① 言語構造:誰かに紹介できる「一言」があるか?
└ 「あなたの商品を紹介するとしたら、何と言って紹介されたいですか?」 - ② 体験構造:初回体験で“信頼”が生まれる流れがあるか?
└ 「初回の接点で“これなら安心だ”と伝わる要素、ありますか?」 - ③ 信頼構造:対応・人柄・姿勢が“理由になる”一貫性を持っているか?
└ 「サービス以外の“人としての信頼”が伝わる場面、設計されていますか?」
これら3つが機能していれば、
商品はただの“売るもの”から、「誰かが誰かに語りたくなる存在」へと進化します。
- 1. 「なぜ選ばれているか?」をお客様の言葉で書き出す
- 2. 体験の入口(初回接点)を点検し、“信頼が生まれる瞬間”を明文化
- 3. 紹介・リピートが起きた顧客の理由をヒアリングし、構造に反映
📝 関連記事:
-
【完全版】選ばれるブランドを育てる3層設計と伝え方
└ ブランドとは、Productの“再選択される力”を構造として育てること
次章では、Productという“選ばれる理由”が、
どのように「Translation=語られる構造」へと変換されるのかを解説します。
PromotionからTranslationへ:語られる構造をどう設計するか?
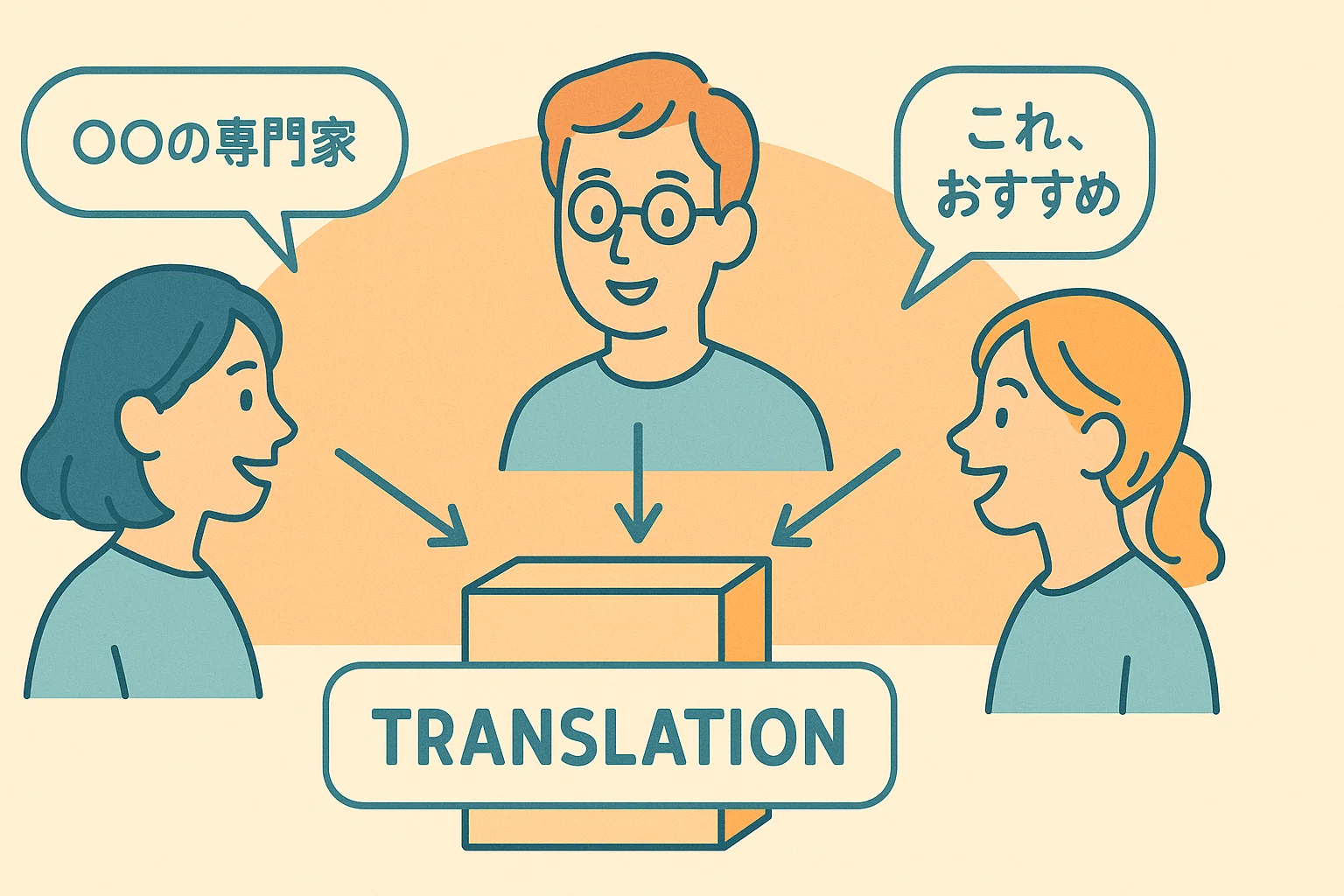
従来の4Pでは「Promotion=告知・広告・発信」と定義されてきました。
しかし現代では、「何をどんなに伝えても、誰も紹介してくれない」という現象が増えています。
商品が魅力的であっても、それが“他人に語れる形”になっていなければ、存在しないのと同じ──
今求められているのは、「伝える」ではなく「語られる」構造です。
それが、Translationの本質です。
Translation = 商品の価値が“再翻訳”され、誰かの言葉で他者に届く構造
→ 「伝える」でも「伝わる」でもなく、「語られる」ことがTranslationの目的。
→ 紹介・口コミ・SNS・推薦が自然発生する構造はここから生まれる。
紹介が発生しないサービスには、以下のような共通点があります。
- ✔ 名前が覚えにくい/言語化しづらい
- ✔ 問題解決の範囲が曖昧で「何が得意か」が伝えにくい
- ✔ サービス全体を説明しようとして、説明が長くなる
逆に、紹介されるサービスは「紹介される前提」で設計されています。
たとえば──
「あの人、“外国人起業支援”の専門家だよ」
「“ビザと会社設立のワンストップ”なら、ここ」
こうした紹介が成立するのは、Productの魅力がTranslationによって
「一言で語られる構造」に変換されているからです。
Translationを支えるのは、以下の3要素です。
- ① タグライン構造:一言で語れるラベルがあるか?(◯◯の専門家)
└ 「あなたが紹介されるなら、どう紹介されたいですか?」 - ② FAQ構造:「誰が/どんな時に/何を頼めるか」が想像できるQ&Aが整備されているか?
- ③ 紹介フレーズ設計:「どう紹介されたいか?」から逆算して言葉を用意しているか?
- 1. タグラインを整える(例:「日本で起業したい外国人の味方」)
- 2. よくある質問を3〜5つ書き出す(検索されそうな表現で)
- 3. 紹介者が“口に出しやすい”短い紹介例を決めておく
📝 関連記事:
-
【完全保存版】売上が激変する“4つの構造エラー”と改善術
└ Translation構造が弱いと「紹介されない・伝わらない」状況に陥る実例と改善法を解説
Translationが機能していれば、あなたがいなくても、誰かがあなたを紹介してくれます。
それは単なる営業活動ではなく、“語られる前提で設計された構造”によって起きるのです。
次章では、その語られた価値が“届く”ために必要な、Access(接触構造)について解説します。
PlaceからAccessへ:知られていなければ、存在していないのと同じ

Translationで「語られる構造」が整っていたとしても──
そもそもその情報に“たどり着けなければ”、顧客は存在すら知りません。
Accessとは、単なる導線やチャネルの話ではありません。
「必要な人が、必要なときに、安心して出会える構造」があるかどうか。
それが、Accessの本質です。
Access = 顧客が「出会える」「探せる」「安心して選べる」構造
→ SNS・検索・比較・UI・リンク構造など、すべてが“接触点”。
→ 「選ばれない」のではなく「知られてすらいない」状態が、最大の売上ロス要因になる。
たとえば次のような状態に、心当たりはありませんか?
- ✔ SNSプロフィールにサービスページのリンクがない/分かりづらい
- ✔ 問い合わせフォームが見つからない・途中で離脱される
- ✔ 比較できる情報がなく、判断ポイントが示されていない
- ✔ スマホで“次に何すればいいか”が示されていない
これらはすべて、「接触構造が壊れている」状態です。
商品力やTranslationが優れていても、この“0乗算”が発生すれば売上はゼロになります。
どれだけ素晴らしい商品でも──
地下室に展示されていれば、誰の目にも触れない。
なぜそうなるか?
それは、「発信されていても、届く状態になっていない」からです。
情報が過剰な現代では、“届く準備”がなければ、発信は素通りされてしまうのです。
Accessは、以下の3つの視点で設計します。
- ① 入口設計:検索・SNS・紹介リンクから迷わずたどり着けるか?
- ② 接点設計:たどり着いた瞬間に「ここで解決できる」とわかる構成になっているか?
- ③ 比較設計:他との違いや選ぶ理由が“自分で比較できる形”になっているか?
- 1. SNSやプロフィールに“今すぐ飛べる”リンクを明示する
- 2. スマホで3クリック以内に申込み・問い合わせにたどり着ける導線を設計
- 3. サービス比較表・料金説明・事例・FAQなどを使って選ぶ判断軸を提示
📝 関連記事:
-
【9割が知らない】売れない会社の共通点「選ばせすぎ」から抜け出す方法
└ Access設計が弱いと、選ばれる前に“脱落される構造”が生まれる
次章では、“気づかれた後”に、なぜ選ばれるのかを支える構造──
Framing(価値の枠組み)について深掘りしていきます。
PriceからFramingへ:価格は“数字”ではなく“構造”で納得される
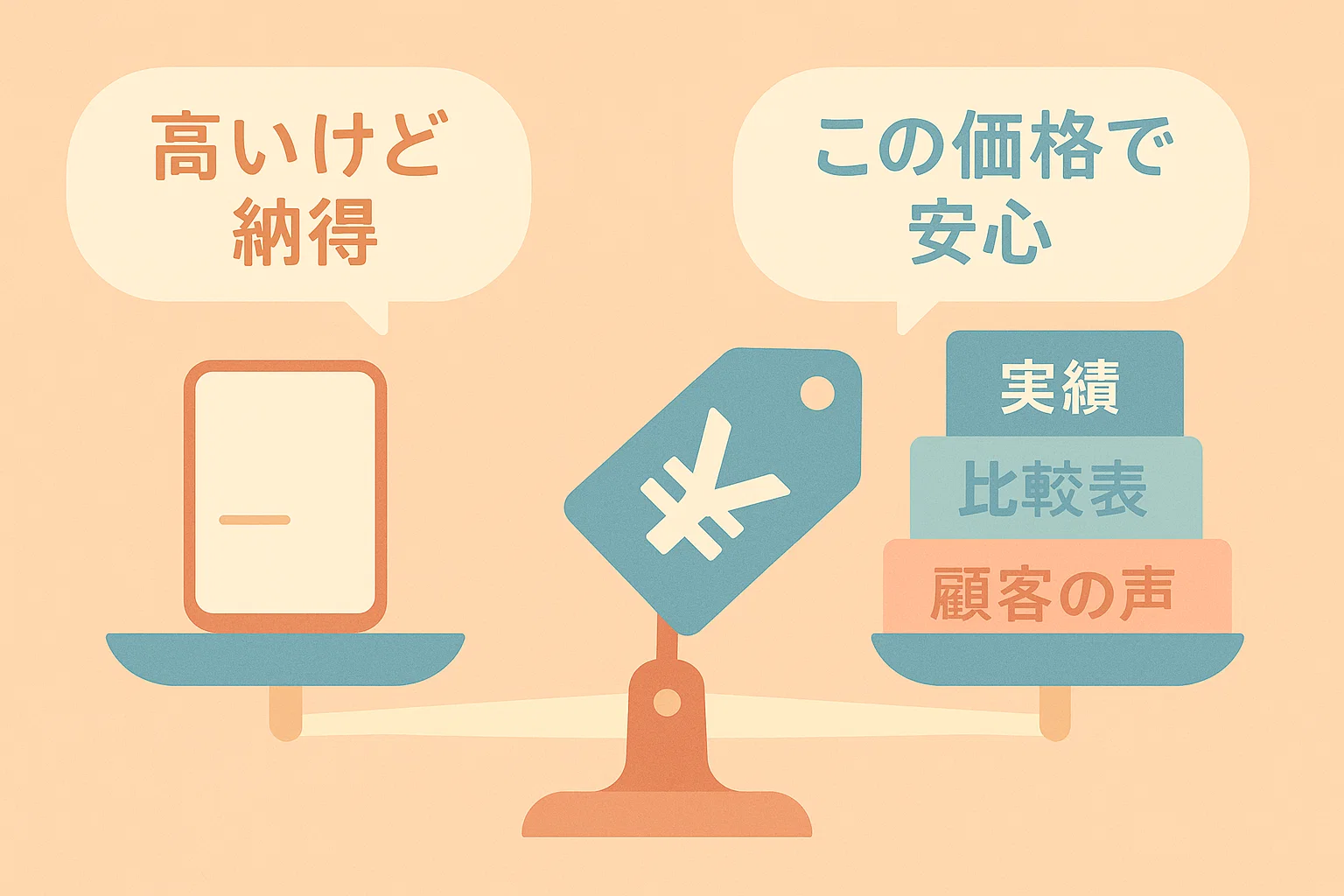
顧客が最後に判断を下すポイント──それがFraming(価値の枠組み)です。
Translationで語られ、Accessで届いた商品が、
「最終的に選ばれるかどうか」は、このFramingにかかっています。
従来の4Pで言えば「Price」の領域に見えるかもしれません。
しかしPTAFにおけるFramingは、価格そのものではなく、価格が“納得される理由”の設計です。
Framing = 価格・価値・納得・比較軸の“文脈”を設計する構造
→ 数字ではなく「なぜこの価格か」が語られているか?
→ 他と比較されたときに“納得して選ばれる理由”を提示できているか?
Framingが不在のまま価格を提示してしまうと、こんな疑問が発生します。
- ✔ 「この価格の根拠が分からない…」
- ✔ 「他社と何が違うの?」
- ✔ 「それって高くない?」
これらの疑問に“構造的に答えられる”設計があるかどうか。
顧客は「価格」そのものではなく、「価格に説得力があるかどうか」で判断しています。
Framingを構成するのは、以下の3つの視点です。
- ① 価格の背景設計:工程・品質・対応など、価格の“理由”が語られているか?
- ② 比較軸の提示:他社との違いや判断ポイントが“自分で比較できる形”になっているか?
- ③ 安心・信頼を支える声:「高いけど、ここにお願いしたい」と言わせる実績や声があるか?
- 1. 価格に対して「なぜ?」と問われたとき、工程やリスクを語れるようにする
- 2. 比較できる“軸”を用意する(例:対応スピード/サポート有無/納品形式)
- 3. 実際の顧客の声・体験談・成果データを示し、“安心感の根拠”を設ける
📝 関連記事:
-
「頑張ってるのに売れない」を完全解決!売れない原因は「構造」と「質」のズレでした
└ Framing構造が弱いと、価格・信頼・満足がズレ、購買の最終判断で“脱落”される
Framingは、「価格に説得力を持たせる力」です。
値下げや比較競争に巻き込まれず、“この価格だからお願いしたい”と選ばれる構造を設計しておきましょう。
次章では、これまでの4つの係数(Product・Translation・Access・Framing)を
どのように自己診断し、どこを優先的に改善していくべきか──
全体を俯瞰しながら整理していきます。
あなたの“構造係数”はどこで止まっている?──診断から戦略へ
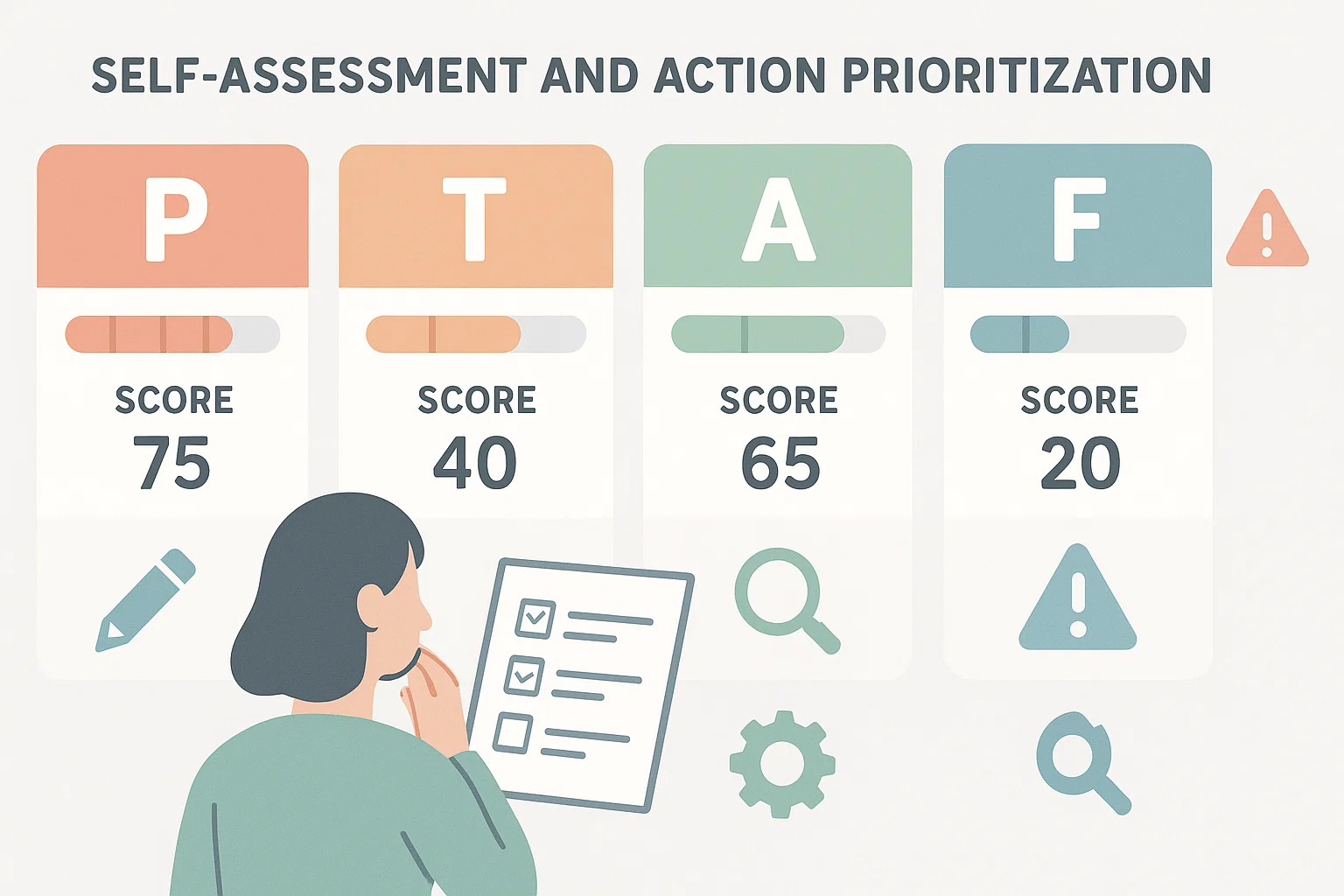
ここまで読んで、「うちはどこが弱いんだろう?」と感じた方へ──
自分のビジネスのどの構造係数が“0に近い”のかを可視化するチェックシートを用意しました。
売上を生む4つの構造係数:
Product × Translation × Access × Framing
このうち、ひとつでも“0”に近ければ、売上は0に限りなく近づいてしまう。
以下の質問に、直感で答えてみてください。
各項目が「1.0以上」であれば機能しており、“0.5未満”であれば構造的に危険信号です。
- ✔ 商品が「誰に」「なぜ」選ばれているかを一言で言語化できる(Product)
- ✔ 紹介や口コミが自然に発生している(Translation)
- ✔ SNS・検索・LPなど“気づかれる導線”が整っている(Access)
- ✔ 顧客は価格や内容に「納得したうえで選んでいる」と実感できる(Framing)
📩 無料配布中:「構造係数セルフ診断シート(PDF)」
PDFをダウンロードする構造別アクションマップ:どこをどう直す?
- Productが弱い: 「誰に」「何を」「なぜ選ばれるか」を再定義。タグライン再設計が有効。
- Translationが弱い: FAQ・紹介文・“語られる”一言を整備。紹介スクリプトも有効。
- Accessが弱い: SNS・検索・リンク・スマホUIを整備。3クリック以内に申込導線を。
- Framingが弱い: 比較表・価格の理由・お客様の声を提示。「この価格で選ばれる理由」を明示。
どこから着手するべきか?優先順位の考え方
- ✔ Productが“曖昧”なら最優先。 すべての掛け算はここから始まる。
- ✔ TranslationとAccess両方が弱ければ、言語設計が原因の可能性あり。
- ✔ Framingが低ければ、価格以外の“価値の理由”を再構築。
チェックが終わったら、「よし、全部やろう!」ではなく──
“止まっている係数から順に”構造を立て直すことが、改善の鉄則です。
小手先のLP改善やSNS更新ではなく、構造の再設計に着手する。
これこそが、「ちゃんと努力が届く」状態への第一歩なのです。
次章では、これまでの内容を振り返りながら、
あなたのビジネスに「構造の目線」を宿す最終まとめをお届けします。
まとめ~構造を変えれば、結果は変わる

- 売上が止まっているのは、努力不足ではなく「構造不全」が原因かもしれない
- 売上は Product × Translation × Access × Framing の掛け算で決まる
- まずは“ゼロに近い係数”を見つけて、そこから優先的に構造を立て直そう
商品の魅力、伝え方、導線、価格。
そのどれもが“整っているはずなのに売れない”…。
そんなときは、「構造」の視点を持ってみてください。
あなたのビジネスには、選ばれる理由の“欠けた係数”があるのかもしれません。
逆に言えば──そこさえ整えば、信じられないくらい、売上が自然に動き出します。
自分の構造係数がどこで止まっているのか。
どうすればTranslationが生まれるのか。
顧客が納得して選べる導線になっているのか。
どれだけ努力を重ねても、「構造のゼロ」は成果をすべて消してしまいます。
でも逆に──構造を0→1に変えるだけで、努力が“ちゃんと届く”ようになるんです。
ぜひこの構造を、あなたのビジネスに組み込んでみてください。
そしてまずは、あなたのProductが“語られる準備”ができているか──
今日、見直してみてください。
📄 PDFで手元に残したい方へ:「構造係数チェックシート」無料配布中
PDFをダウンロードするよくある質問(FAQ)
Q1. PTAF構造は4Pとは別の概念ですか?
従来の「並列チェック」から「連携と乗算の構造」へ進化させたものです。
Q2. どの係数から改善するのが最も効果的ですか?
Translation・Access・FramingはProductの“媒介構造”であるため、Productが0では何も届きません。
Q3. TranslationとPromotion(発信)の違いがよくわかりません
“語られる構造”を設計することがTranslationの本質です。
Q4. この構造は士業・コンサル以外の業種にも使えますか?
「選ばれる構造をどうつくるか」は業種を問わず普遍的なテーマです。
Q5. 構造が整っても紹介や売上が増えないときはどうすれば?
構造が整っている状態で初めて“改善PDCA”が回りはじめるのが通常です。
脚注・参考文献
- 中小企業庁(2023)『2023年版中小企業白書』
└ 創業後3年以内の事業継続率 約50.2%に言及。小規模法人における構造設計の重要性の統計根拠。 - Philip Kotler(2022)『マーケティング・マネジメント(第16版)』
└ 従来の4P理論の定義およびマーケティングの基本フレームとして引用。 - Robert Cialdini(2001)『影響力の武器』
└ 紹介・信頼・再選択における行動心理メカニズムの土台として参照。 - 小阪裕司(2012)『価値創造の思考法』
└ 「価値は文脈で認知される」というFraming設計との関連性に基づき参照。 - ラプロユアコンサルティング行政書士事務所(2024)『商品開発・構造設計に関する内部理論資料』
└ PTAFモデル(Product・Translation・Access・Framing)とその係数構造理論の出典。
本稿はPTAFモデル(©2025 Lapro your Consulting)を基盤として、4P戦略論の拡張概念を解説しています。






















