商品はしっかり揃えた。
LPもきちんと作った。
広告もSNS発信も、やれることは一通りやってきた──
それなのに、なぜか売上が伸びない。
このような経験、心当たりはありませんか?
もちろん、サービスの質や伝え方に課題があるケースもあるでしょう。
ですが、多くの中小企業や個人事業では──
「商品も悪くない」「発信もしている」のに売れないという現象が起きています。
実はその背景には、“選ばせすぎている構造”があることが少なくありません。
商品数が多すぎる。
LPで伝えたいことが渋滞している。
メニューやサイトの誘導が複雑で、お客さまがどこから見ていいか分からない状態になっている。
私自身も、かつて「商品を増やせば売れる」と思い込んで、 メニューを細かく足していった結果、逆に成約率が下がった経験があります。
本記事では、売れない原因を「選ばれない」から「選べない」へと視点転換し、
小さな会社でも実行できる「選ばせない構造の作り方」を、具体的に解説していきます。
読み終える頃には、「どこを減らせば売上が伸びるか」が明確になっているはずです。
情報を増やしても、選ばれない理由
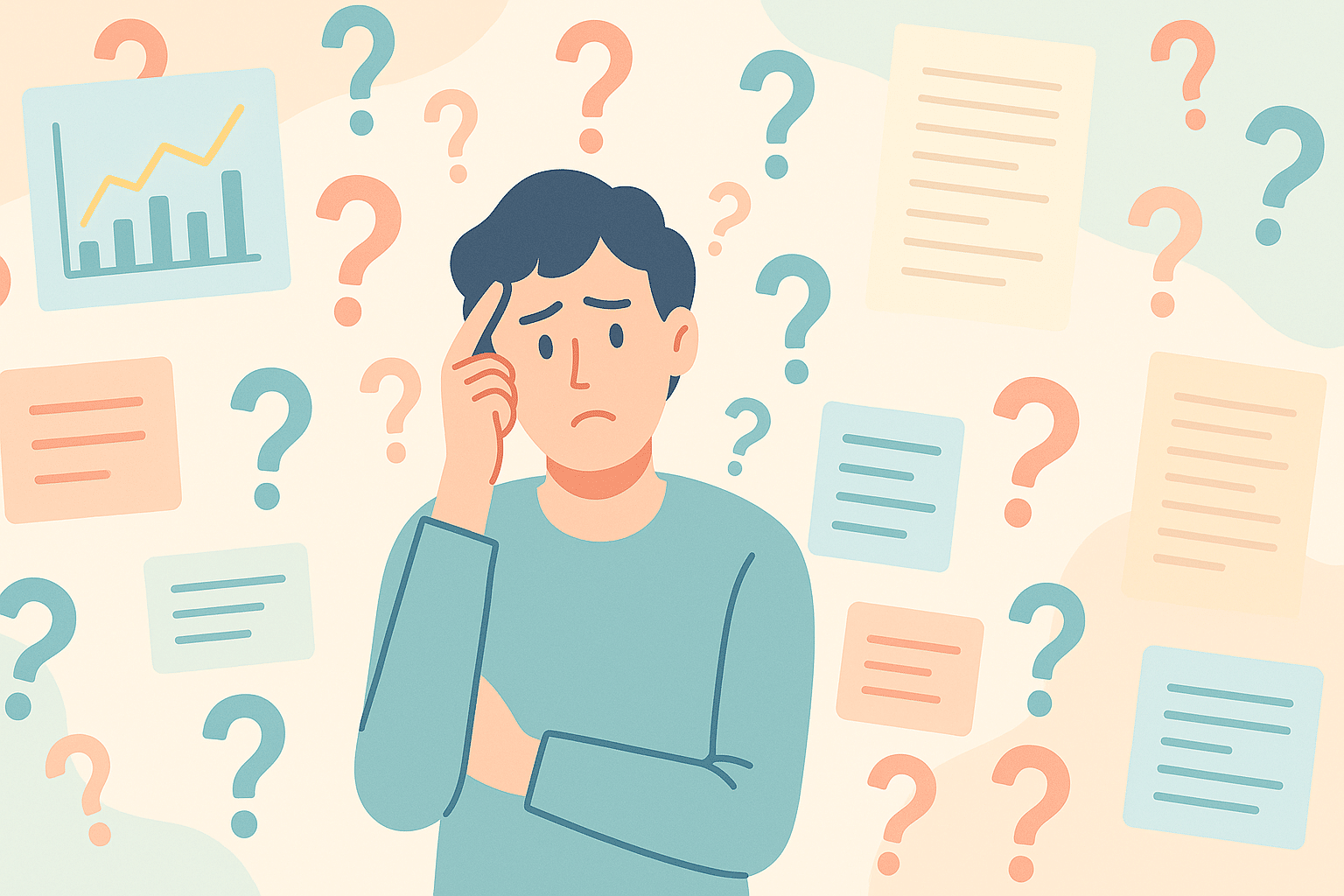
サービスを充実させ、説明文を丁寧に書き、Q&AもFAQも完備── それでも「思ったより申し込みが来ない」と悩むこと、ありませんか?
実はその原因は、情報の“不足”ではなく、“過剰”にあるかもしれません。
行動心理学には、「選択肢が多すぎると人は動けなくなる」という原理があります。 これは 「選択回避(choice overload)」 と呼ばれ、販売・購買・教育・行政などあらゆる分野で確認されています。
有名な研究では、24種類のジャムを並べた売場と、6種類だけの売場を比較したところ── 実際に購入に至った割合は、“選択肢が少ない方”が6倍以上も高かったのです[1]。
人は「選びたい」生き物ではありません。
むしろ、「迷いたくない」「失敗したくない」と思っている人が多いのです。
サービスメニューが多い、選択フローが長い、LPに情報が渋滞している── これらはすべて、「選ばれる前に、疲れて離脱される構造」なのです。
だからこそ必要なのは、たくさん伝えることではなく、
「選ばせない構造」によって、迷わせないこと。
商品やサービスの魅力をきちんと伝えるために、 まずは「絞ることで選ばれやすくなる」という考え方を意識してみてください。
売れる構造は“選ばせない導線”でできている

「売れる仕組み」は、意外なほどシンプルです。 それは、「お客様に選ばせない=迷わせない」こと。
たとえばスターバックスでは、サイズやカスタムは存在しますが、 店頭に並ぶメニューは非常に絞られています。 「本日のおすすめ」など、お客さまの視線や行動を誘導する工夫が随所に仕込まれています。
Appleの販売構造も同じです。
iPhoneは毎年数モデルしか展開されず、選択肢は限定的。
「これを選べば間違いない」と伝わるシンプルな構成と訴求で、選択の負荷を最小限に抑えているのです。
では、なぜ「選ばせないこと」が売上につながるのでしょうか?
人は、選択肢が与えられたときに3つの“見えないコスト”を払っています。
それは、認知コスト・比較コスト・決断コストです。
まず「何があるのか?」を認識するだけで脳はエネルギーを使い(認知コスト)、
次に「どれがいいか?」を比較して(比較コスト)、
最後に「本当にこれでいいのか?」と決断を迷います(決断コスト)。
この3ステップが“無意識の疲労”を生み、「やめておこう」に直結するのです。
選択肢が多い方が「親切」に見えるかもしれませんが、人は「選ばない自由」よりも「迷わず進める道」を好む傾向があるということです。
レストランでメニューが20ページもあると、疲れて「いつもの」で済ませたくなる。 Amazonで同じ商品が何十個も並んでいたら、レビュー数の多いものを“なんとなく”選ぶ── そんな経験、ありませんか?
これがヒューリスティック(直感判断)です。
人は比較を回避し、「よさそう」「おすすめされている」「選びやすい」ものを無意識に選びます。
つまり、“選ばれる仕組み”とは、比較をさせずに決断を生む設計なのです。
一方で、商品が横並びで並んでいたり、情報が分散していたりすると、
「自分に合ってるのはどれだろう…」と迷いが生まれ、そのまま離脱されることも多くなります。
だからこそ、売れる構造には“選ばせない工夫”があるのです。
スタバのように、おすすめが目に入る。Appleのように、迷う余地がない。
それはすべて「決断させる前に、流れに乗せている」構造の力なのです。
中小企業や個人事業でも、この考え方は同じ。 大事なのは、商品のクオリティや情報量ではなく、 「選ばれやすくする仕掛け」=“導線設計”、すなわち“誘導”が大切なのです。
つまり「何を伝えるか」より、「何を選ばせないか」こそが、売れる設計の第一歩なのです。
小さな会社ほど「絞る勇気」が武器になる

「もっと売上を上げたい」
「多くの人にサービスを届けたい」
そんな思いから、「商品を増やす」「オプションを追加する」経営判断をとるケースは少なくありません。
でも、小さな会社ほど、その拡張はリソースの分散と訴求のぼやけを生みやすくなります。
たとえば、コンサルティングを提供していたある個人事業主は、 メニューを「創業支援」「SNS活用」「売上アップ」「人材育成」と次々に追加していきました。
その結果── 「何をしている人か分からない」「自分に関係あるのか判断しづらい」という理由で、 問い合わせ数が激減してしまったのです。
そこで思い切って、“創業支援1本”に絞ったところ、
メッセージがクリアになり、「まさにそれが必要だった」と言ってもらえる機会が激増。
売上も月単位で安定し始めたのです。
小さな会社には、大企業のように商品開発や広告費にかけられる資源が限られています。
だからこそ、「伝える力」ではなく「絞る力」こそが武器になるのです。
誰に届けたいのか。何を軸に据えるのか。 「誰も取りこぼしたくない」と考えるほど、誰の心にも届かなくなることがあります。
絞るとは、捨てることではありません。 絞るとは、“伝わる構造”をつくることなのです。
選ばれるための第一歩は、「何を選ばせないか」を決めること。 そしてその決断こそが、小さな会社を動かす経営の構造選択なのです。
まず削るべきは「商品数」「言葉」「選択肢」

「選ばれないのは、選ばせすぎているから」── そう考えるとき、では何から削っていけばいいのか?という疑問が出てきます。
このセクションでは、特に小規模事業・個人経営でありがちな「迷わせる要素」を3つに絞ってお伝えします。
1. 商品・サービス数を減らす
人気がないもの、説明に時間がかかるものは、
まず“非表示”にするだけでも選ばれやすくなります。
商品ラインナップが多ければ多いほど「選べない」リスクが高まります。
特にスマホで見たとき、数十件の商品がずらっと並ぶだけで、ユーザーの認知負荷は一気に跳ね上がります。
また、販売実績がほとんどない商品は、思い切って一度“隠す”ことで、 メイン商品が引き立ち、選ばれやすくなるケースも少なくありません。
まずはこれをやってみよう:
- この1ヶ月で売れていない商品を3つピックアップ
- LPやカート画面から“非表示設定”だけしてみる
- 削ったあと、主力商品のクリック率をチェック
2. 言葉を減らす・統一する
同じサービスに複数の呼び名があると、それだけで迷いが生まれます。
言葉は“削る”よりも“揃える”ことが重要です。
「起業サポート」「創業支援」「法人化コンサル」──これらが同じ内容を指していたとしても、 顧客は「どれが何なのか、何が違うのか?」と混乱します。
言葉の揃っていない発信は、“伝える”のではなく“濁す”という結果を招いてしまうのです。
専門用語やかっこいい横文字を並べる前に、 「読み手に一発で伝わるか?」という基準で表現を見直しましょう。
すぐにできるチェック法:
- 同じサービスに複数の名称があるか洗い出す
- SNS投稿/LP/資料で使用されている語句を一覧に
- 1語に統一し、全メディアで言い換えを避ける
3. 決済導線を絞る
「無料相談」「資料DL」「サービス申込」などの選択肢を並列に提示すると、
かえって行動が止まってしまいます。
実際、CTA(行動喚起)を3種類以上並べると、 クリック率が20〜30%下がるという調査も存在します[2]。
これは「どれを選べばいいのか分からない」という、選択疲れの典型例です。
最も取ってほしいアクションを1つに絞ることで、 反射的に行動できる“一本道”を作ることができるのです。
少し乱暴に聞こえるかもしれませんが── 今のあなたの導線、「親切すぎて、売れていない」状態かもしれません。
今日できる小さな一歩:
- 自社サイトのCTAをすべてリストアップ
- 「一番取ってほしいアクション」を1つ選ぶ
- それ以外のCTAを一時的に“下に移す/減らす”
最後に、こう問い直してみてください。 「それ、本当に“見せる必要”があるのか?」
“選ばない構造”が、売上の安定と再現性をつくる

売上が不安定な会社の多くは、構造が存在しないか、常に変更されている状態にあります。
一方、安定して成果を出している企業には、共通して“選ばせない導線”が存在しています。
たとえば、人気がある商品が毎回違うという状態。
一見、幅広くニーズを取れているように見えますが、これは顧客に“選ばせすぎている”サインです。
選ばせない構造では、「この商品を選べば間違いない」と伝わるよう設計されています。 その結果、顧客の購買行動に“迷い”がなくなり、「毎回同じものが売れる」再現性が生まれます。
実際、売上が安定している企業の多くは── 商品数が少ない/価格が明快/言葉が統一されている/導線が一本道になっている、といった特徴を備えています。
逆に、商品数が多すぎて、導線もLPもSNSもバラバラに散っている状態では、 「何が主軸か分からない」「買いにくい」という構造的課題が浮き彫りになります。
売上とは、商品力でも広告力でもなく、“選ばれやすい構造”の結果なのです。
つまり──「なぜ売れないか」ではなく、
「なぜ迷われているか?」を構造から見直すことが、売上改善の本質になります。
ビジネスの再現性は、構造によってつくられます。
運や一発勝負に頼らず、“選ばせない”という静かな設計が、安定した売上と安心感を生み出すのです。
よくある質問(FAQ)

- Q1. 商品数を減らすと、売上も減ってしまいませんか?
- 一時的な売上減の不安はありますが、集中によって選ばれやすくなり、むしろ売上は安定します。データでも証明されています。
- Q2. サービスの特徴を伝えるには情報量が必要では?
- もちろんですが、「絞られた構造の中で」伝えるのがポイントです。選ばれた後に詳しく伝える設計が効果的です。
- Q3. SNSやLPでいろんな表現を試しているのは悪いこと?
- 試すこと自体は悪くありません。ただ“言葉の統一”がされていないと、認知→行動に繋がりません。
- Q4. 選択肢を絞ると、顧客を限定してしまいませんか?
- むしろ逆です。「このサービスは自分のことだ」と思わせる明確な訴求が、より広い層に響きます。
- Q5. どこから手をつければいいか分かりません。
- まずは、商品一覧・導線・言葉の整理から。“減らすべきもの”を1つ可視化するだけで流れが変わります。
まとめ~売れない会社の共通点「選ばせすぎ」から抜け出す方法~

- 売上が伸びない理由は、商品の質や努力不足ではなく“構造の問題”かもしれない。
- 小さな会社ほど、絞ることで選ばれやすくなり、再現性が生まれる。
- 「何を減らすか」「何を選ばせないか」が、売れるビジネスをつくる設計条件になる。
たくさんの商品、丁寧なLP、複数の導線──
それらは「届けたい」という善意の表れでもあります。
でも、売れない理由は、努力や魅力ではないこともあります。
「選べない構造」そのものが、購買行動を止めてしまっている──
その可能性に、一度目を向けてみてください。
売上は、運ではなく構造の結果です。
そして構造は、明日からでも変えられます。
まずはひとつ、減らしてみる。揃えてみる。絞ってみる。
小さな選択から、構造は動き出します。
📖参考・出典
-
Iyengar, S. S., & Lepper, M. R. (2000). When choice is demotivating: Can one desire too much of a good thing?
Journal of Personality and Social Psychology, 79(6), 995–1006.
https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.6.995 -
HubSpot(2022年)“How Many CTAs Should You Include on a Page?”
https://blog.hubspot.com/marketing/how-many-ctas-on-a-page






















